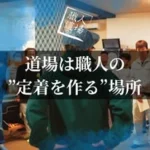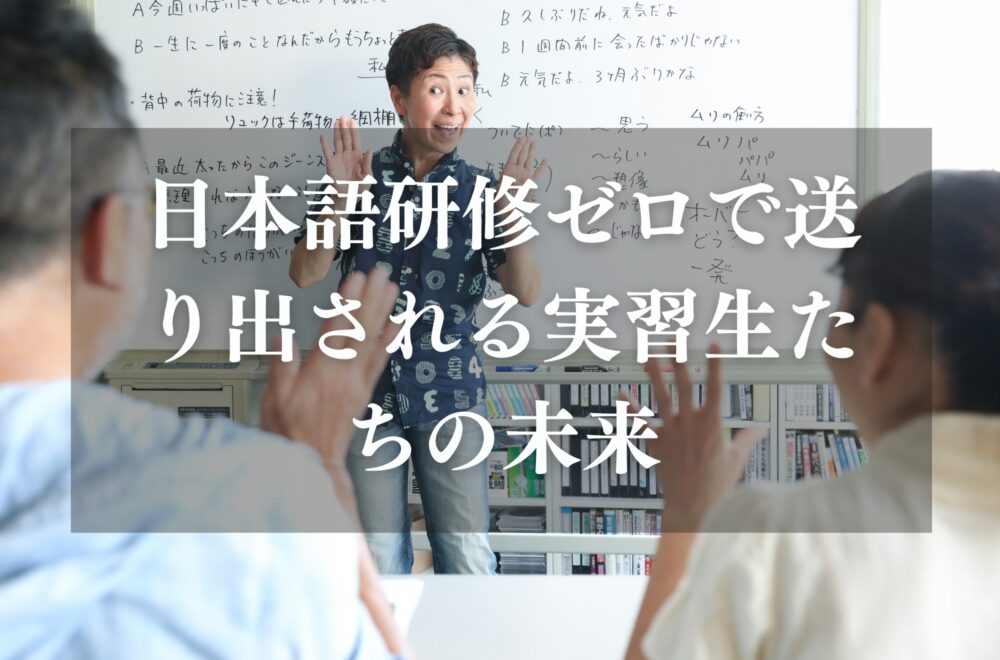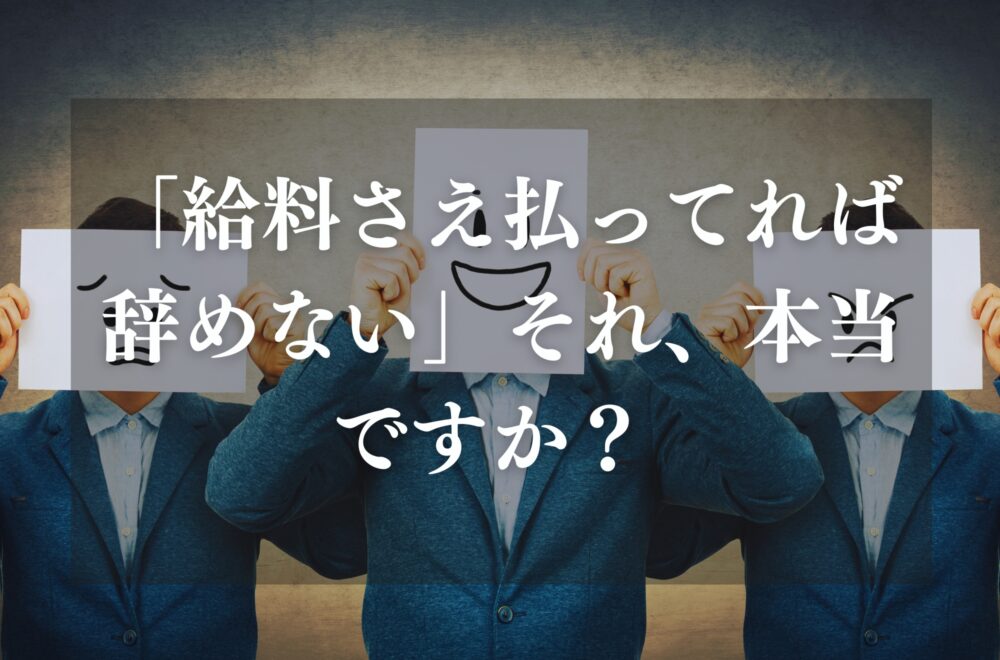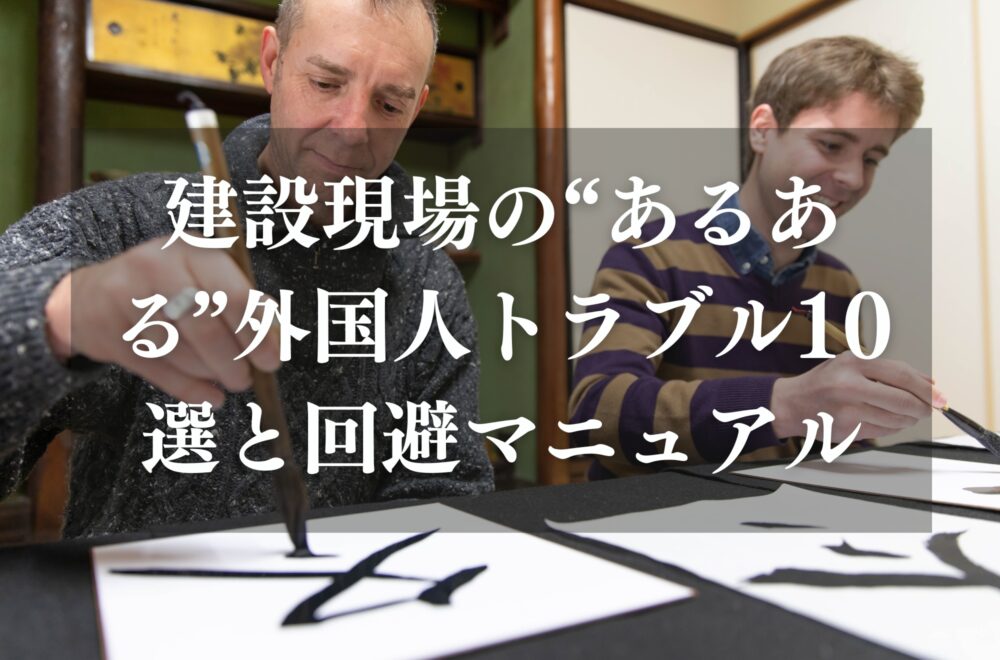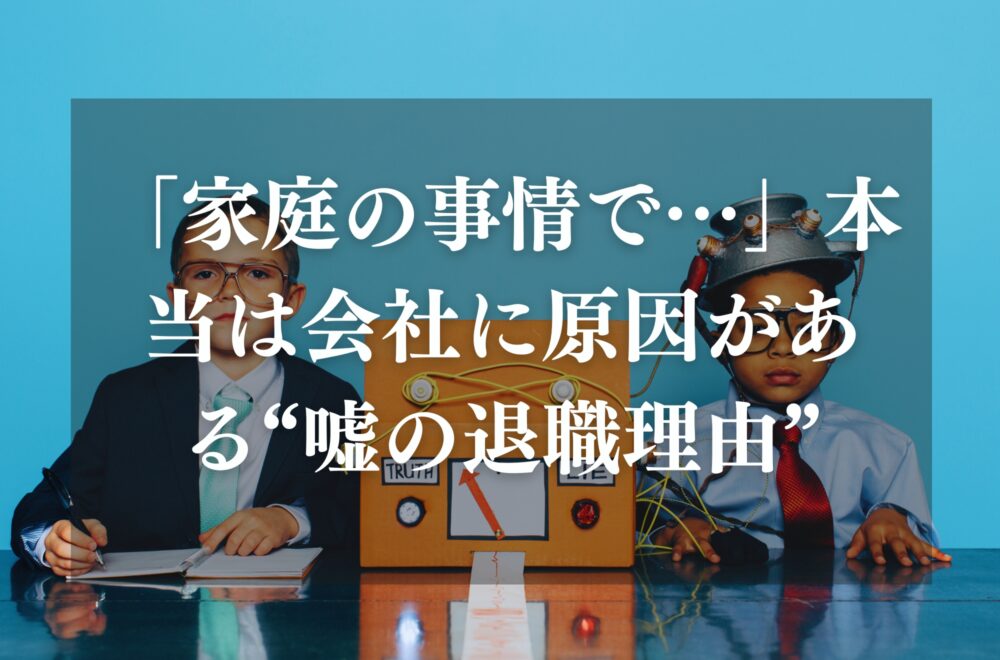外国人特定技能職人は本当に使える?建設業の現場での実態とは
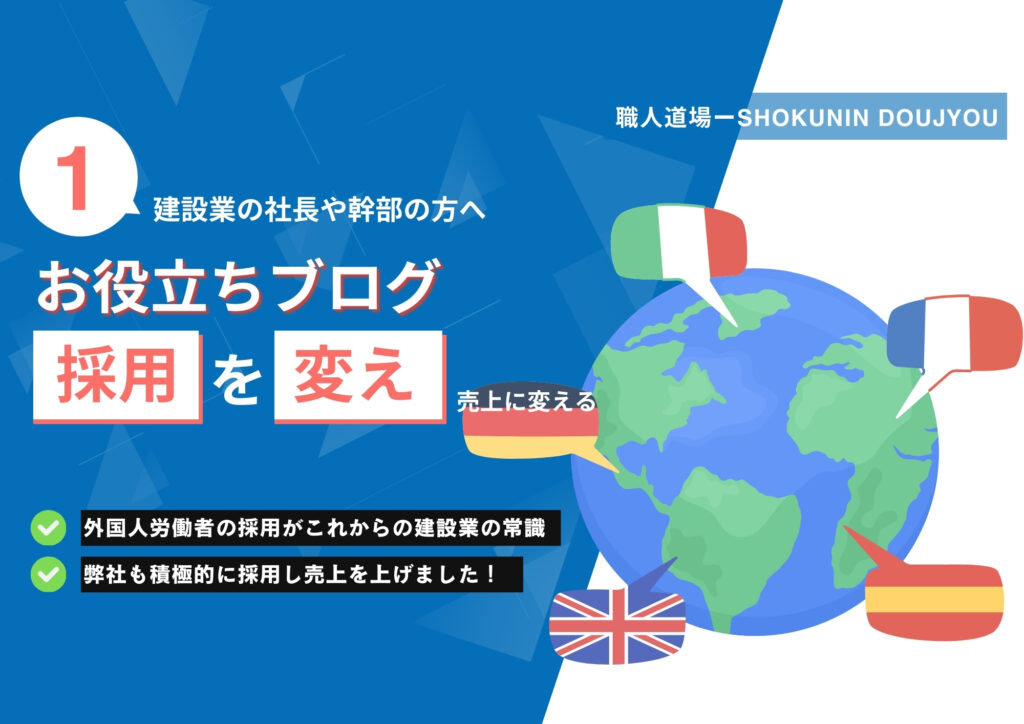
1. 外国人特定技能職人とは?建設業での活用が注目される理由
日本の建設業界は深刻な人手不足に直面しています。特に、少子高齢化が進み、若者の職人離れが顕著になっている今、外国人労働者への依存度が高まっています。その中で注目されているのが「特定技能」制度。この制度は、技能実習制度とは異なり、一定のスキルを持つ外国人が即戦力として働くことができることを目的としています。
特定技能外国人の受け入れが進む背景には、次のような理由があります。
- 日本人職人の減少
建設業界の就業者の高齢化が進み、若手の担い手が不足しているため、新たな労働力の確保が急務となっています。 - 技能実習制度の限界
技能実習制度は「育成」が目的であり、長期間の戦力確保が難しいのに対し、特定技能外国人は熟練労働者としての長期雇用が可能です。 - 即戦力となる人材確保
特定技能外国人は、一定の試験に合格することで日本での就労が認められるため、技能実習生よりも即戦力として期待できる点が大きな魅力です。
しかし、実際に外国人職人を受け入れるとなると、「本当に戦力になるのか?」「仕事の質は大丈夫なのか?」といった疑問を持つ建設業の経営者も少なくありません。そこで、次の章では「技能実習制度と特定技能の違い」を明確にし、建設業でどちらが適しているのかを解説していきます。
2. 特定技能制度と技能実習制度の違いを理解しよう
外国人労働者を受け入れる際、多くの経営者が「技能実習生と特定技能外国人の違い」を正しく理解していません。しかし、この違いを把握しておくことで、会社に最適な人材の確保が可能になります。
🔹 技能実習制度とは?
- 目的:発展途上国の人材育成(国際貢献が主目的)
- 期間:最長5年間(原則3年+延長2年)
- 就労可能職種:限定的(建設業の一部職種のみ)
- 制限:転職不可(受け入れ企業に固定)
- 即戦力性:基本的に初心者から育成する
🔹 特定技能制度とは?
- 目的:日本の人手不足解消(戦力としての雇用が目的)
- 期間:最長5年間(更新可能)
- 就労可能職種:建設業全般
- 制限:転職可能(同業種内での移動は自由)
- 即戦力性:試験に合格した人材のみ受け入れ
要するに、技能実習制度は「育成」が目的であり、特定技能制度は「即戦力としての活用」が目的という違いがあります。建設業で外国人労働者を受け入れるなら、特定技能のほうが実用的であり、長期的な戦力として期待できるといえるでしょう。
3. 建設業界の人手不足を外国人特定技能職人で解決できるのか?
特定技能外国人を受け入れることで、本当に建設業界の人手不足を解決できるのか?この疑問について、具体的なデータをもとに考察していきます。
🔹 建設業界の人手不足の現状
- 建設業従事者の平均年齢は47.6歳(他業種と比べて高齢化が進行)
- 29歳以下の若手職人は全体の約11%
- 2030年までに約100万人の建設労働者が不足する見込み
このデータからも分かる通り、日本人職人だけで業界を維持するのは限界に達しています。
🔹 外国人特定技能職人の受け入れ実績
国土交通省のデータによると、2023年時点で特定技能の外国人職人は約35,000人が建設業に従事しており、この数は年々増加傾向にあります。つまり、多くの建設会社が「外国人職人なしでは回らない」という状況になりつつあるのです。
また、外国人職人の活用が進んでいる企業では、次のようなメリットが挙げられています。
- 人手不足の解消:日本人職人の減少をカバーできる
- 人件費の最適化:日本人職人よりも低コストで雇用可能
- 技能向上への期待:技術習得意欲が高い外国人が多い
一方で、「本当に戦力になるのか?」「仕事のクオリティは大丈夫なのか?」という不安を持つ経営者も少なくありません。そこで、次の章では「外国人職人の実際の評価」について深掘りしていきます。
4. 外国人職人は本当に戦力になる?現場での実際の評価
「外国人職人は使えない」と思っている経営者が一定数いるのも事実です。しかし、実際に受け入れを進めている企業では、外国人職人の働きぶりに満足しているケースが多いのも現実です。
🔹 現場でのリアルな評価
特定技能外国人職人に対する評価は、以下のように二極化しています。
✅ 評価が高いケース
- 基本的な技術を持っており、すぐに現場で活躍できる
- 指示を忠実に守り、手を抜かない
- 仕事に対する意欲が高く、責任感を持って働く
❌ 評価が低いケース
- 言語の壁があり、細かい指示が伝わりにくい
- 日本の職人文化に馴染むまでに時間がかかる
- 最初の教育・指導に手間がかかる
このように、外国人職人の戦力化には「受け入れ側の準備と教育」が大きく影響することが分かります。つまり、適切な教育体制を整えれば、特定技能外国人は十分に戦力になるのです。
5. 「日本人職人 VS 外国人職人」スキルと仕事の質を比較
建設業界において、「日本人職人と外国人職人の違いは何か?」という疑問を持つ経営者は多いでしょう。特に、「仕事の質は大丈夫なのか?」という懸念があるかもしれません。しかし、実際の現場では日本人職人と外国人職人には、それぞれ異なる強みと課題があるのです。
🔹 日本人職人の強み
✅ 長年の経験に基づく高度な技術
✅ 現場での応用力や即時対応能力
✅ 細かい作業や仕上げの精度が高い
✅ 日本の建設文化や安全基準を熟知
🔹 外国人職人の強み
✅ 意欲が高く、指示を忠実に守る
✅ 基本的な作業の習得が早い
✅ 肉体的にタフで労働時間を厭わない
✅ 若年層が多く、持続的な労働力の確保が可能
🔹 日本人職人と外国人職人の比較(一覧表)
| 比較項目 | 日本人職人 | 外国人職人(特定技能) |
|---|---|---|
| 技術レベル | 高い(経験豊富) | 基本技術はあるが応用は弱い |
| 仕事の正確性 | 仕上げが細かい | 指示を忠実に実行 |
| 作業スピード | 高速(熟練度が高い) | 習得後は早いが、慣れるまで時間が必要 |
| 言語能力 | 問題なし | 言語の壁がある |
| 労働意欲 | 個人差が大きい | 労働意欲が高い |
| コスト | 高め | 日本人より安い |
この比較から分かるように、「どちらが優れているか」ではなく、日本人職人と外国人職人を適材適所で活用することが重要だと言えます。例えば、仕上げの精度が求められる作業は日本人職人に任せ、反復作業や力仕事は外国人職人に担当させると、現場の効率が大幅に向上します。
6. 外国人職人を受け入れる建設会社の成功例と失敗例
✅ 成功している建設会社の特徴
🔹 外国人職人専用の教育プログラムを導入
🔹 言語の壁を考慮し、簡単な日本語で指示を出す
🔹 日本人職人とのチームワークを重視
🔹 特定技能外国人のキャリアプランを考えている
✅ 事例:A社(東京都)
A社は外国人職人向けに、日本語の建設用語を覚える研修を実施。その結果、コミュニケーションがスムーズになり、外国人職人の定着率が大幅に向上。
❌ 失敗する建設会社の特徴
❌ 指導方法が曖昧で、日本人職人任せになっている
❌ 日本語の指導をしないため、意思疎通ができない
❌ 外国人職人を「安い労働力」として扱い、育成を怠る
❌ 職人間の文化の違いを無視し、対立を生む
⚠ 事例:B社(大阪府)
B社は外国人職人を雇用したが、「言葉が通じない」という理由で現場監督が彼らに指示を出さず、結局使えないまま退職してしまった。
外国人職人を活用するには、単に雇うだけでなく、育成と環境整備が不可欠です。
7. 特定技能外国人を雇う際に活用できる助成金・補助金とは?
特定技能外国人を受け入れる際、企業は様々な助成金や補助金を活用することができます。これを知っているかどうかで、採用コストが大きく変わるため、経営者は必ずチェックすべきポイントです。
✅ 活用できる助成金・補助金の例
| 助成金・補助金 | 概要 | 支給額 |
|---|---|---|
| 外国人技能実習生・特定技能外国人受入助成金 | 外国人労働者の受け入れ企業向け補助 | 50万円~100万円 |
| 雇用調整助成金 | 一時的に仕事が減った際の給与補助 | 給与の最大90%補助 |
| キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 外国人職人を正社員にした場合の助成金 | 最大72万円/人 |
特に外国人職人を受け入れる建設会社の経営者は、助成金制度を活用することで大幅にコストを削減できるため、事前に調べておくことが重要です。
8. 外国人職人の「定着率」を高めるために必要なポイント
外国人職人は「採用したら終わり」ではありません。定着させる仕組みを作らなければ、人材流出が起こり、再び人手不足に陥ってしまいます。
✅ 外国人職人を定着させるポイント
✅ 定期的な日本語研修を実施する
✅ 現場でのトラブルを減らすため、文化の違いを理解する
✅ キャリアパスを示し、成長の機会を与える
✅ 給与や待遇面での不満を解消する
外国人職人は「成長できる環境」を求めているため、単に作業員として雇うのではなく、長期的な雇用を考えることが大切です。
9. 建設現場での外国人職人とのコミュニケーション問題を解決する方法
外国人職人を現場で活用する上で、大きな壁となるのが「言語の問題」です。特に、日本の建設現場では専門用語や職人独特の言い回しが多く、言葉が通じないと作業の指示が正しく伝わらないことがあります。
✅ 外国人職人とのコミュニケーションで発生しやすい課題
❌ 指示を出しても理解されない → 日本語が分からず、間違った作業をしてしまう
❌ 細かいニュアンスが伝わらない → 日本人特有の「空気を読む」文化がないため、指示待ちになりやすい
❌ 職人間の関係が築きにくい → 日本人職人との会話が少なく、孤立してしまう
✅ 解決策:現場で使える簡単なコミュニケーション手法
✅ 単純な言葉で指示を出す
👉 「ここを○○して」ではなく、「コンクリートをここに流して」など、具体的な動作を伝える
✅ ジェスチャーを活用する
👉 日本語が分からない外国人に対しては、身振り手振りで伝えると理解しやすい
✅ 建設業専用の「やさしい日本語」を使う
👉 「荷揚げする」ではなく「荷物を上に運ぶ」、「コテで仕上げる」ではなく「この道具でならす」と言い換える
✅ 現場で使う日本語リストを作成する
👉 例:「運ぶ=carry」「塗る=paint」「削る=scrape」など、基本単語を覚えさせる
これらの工夫を取り入れることで、外国人職人とのコミュニケーションの問題を解消し、作業の効率を高めることが可能になります。
10. 特定技能外国人を雇う際に気を付けるべき法的リスク
外国人特定技能職人を雇用する際、建設会社の経営者が最も注意すべきなのは「法的リスク」です。知らずに雇用すると、労働基準法違反や不法就労のリスクを負う可能性があります。
✅ 外国人労働者を雇用する際の主な法的リスク
❌ 特定技能の在留資格を正しく取得していない
👉 特定技能ビザがない状態で雇うと、「不法就労助長罪」となり、企業側が罰則を受ける可能性がある
❌ 労働時間や賃金のルールを守っていない
👉 外国人労働者にも日本の労働基準法が適用されるため、適正な賃金を支払う必要がある
❌ 適切な管理をせず、外国人職人が転職・離脱してしまう
👉 特定技能職人は「転職可能」なため、待遇が悪いとすぐに他社へ移ってしまう
✅ 法的リスクを回避するための対策
✅ 特定技能ビザの取得をしっかり確認する
👉 特定技能1号は「最長5年」、特定技能2号は「更新可能」となるため、ビザの更新を怠らない
✅ 外国人向けの労働契約を明確にする
👉 日本語と外国語の両方で契約書を作成し、労働条件を明確に伝える
✅ 専門家(行政書士・社会保険労務士)に相談する
👉 法的なリスクを回避するため、定期的に専門家のアドバイスを受けることが重要
法的リスクを回避しながら、外国人職人を適切に雇用することで、長期的な戦力として活躍してもらうことができるのです。
11. 実際どうなの?外国人職人が現場で抱えるリアルな悩みとは
特定技能外国人職人は、日本の建設業界で重要な役割を果たしつつありますが、彼ら自身にも多くの悩みがあります。
✅ 外国人職人が抱える代表的な悩み
❌ 言葉の壁があり、日本人職人とコミュニケーションが取れない
❌ 給与が低く、生活が苦しい
❌ 日本の労働文化(長時間労働など)に適応できない
❌ 日本の建設現場の安全基準やルールに戸惑う
このような悩みを解決することで、外国人職人の定着率を上げ、より良い職場環境を作ることができます。
12. 外国人職人を即戦力化するための教育・トレーニングの工夫
外国人職人を「即戦力」にするためには、教育とトレーニングが欠かせません。初期の教育に力を入れることで、現場でのスムーズな戦力化が可能になります。
✅ 即戦力化のための教育プログラム
✅ 現場で使う日本語を教える(建設用語リストの活用)
✅ 作業の基本を徹底的に指導(動画や図解を活用)
✅ OJT(実地訓練)を積極的に行う
✅ 日本の建設業界の安全基準やルールを徹底させる
例えば、職人道場のような研修施設を活用することで、短期間で即戦力化できる外国人職人を育成することが可能です。
13. 外国人職人の労働環境を整えることで生産性を向上させる方法
外国人職人を長期的な戦力として活用するには、労働環境を整備し、働きやすい職場を作ることが不可欠です。
多くの建設会社が「外国人はすぐに辞める」と悩んでいますが、その原因は環境の未整備にあることが多いのです。
✅ 外国人職人が働きにくいと感じる主な要因
❌ 言葉の壁(指示がうまく伝わらない)
❌ 劣悪な住環境(寮が狭い・汚い・設備が古い)
❌ 給与が低い・残業代が適切に支払われない
❌ パワハラ・差別的な扱いを受ける
❌ 日本人職人との関係がうまくいかない
✅ 労働環境を改善し、生産性を向上させるためのポイント
✅ 外国人職人向けの「やさしい日本語マニュアル」を作る
👉 建設業に特化した日本語教材を作り、現場での意思疎通を円滑にする
✅ 外国人専用の相談窓口を設ける
👉 仕事の悩みを気軽に相談できる体制を整える
✅ 住環境を整備する(寮の設備改善・清潔な環境を提供)
👉 寮の環境を快適にすることで、長期的な定着を促進
✅ 給与・待遇を見直し、日本人職人との格差をなくす
👉 「外国人だから安い」という扱いではなく、公平な待遇を保証する
これらの施策を実行することで、外国人職人の定着率が向上し、結果的に企業の生産性も上がるのです。
14. 建設業の未来は「外国人特定技能職人」と共にあるのか?
今後の建設業界では、外国人職人の活用が不可欠な要素となることは間違いありません。
日本人職人の減少が進む一方で、特定技能外国人の数は年々増加しています。
✅ 建設業における外国人職人の重要性
📌 2030年には約100万人の職人不足が見込まれる
📌 外国人特定技能職人の数は今後さらに増加する見込み
📌 技能向上・教育制度の充実により、外国人職人の技術力も向上
✅ 未来の建設業界で求められること
✅ 外国人と日本人が共存できる職場環境の整備
✅ 特定技能外国人のさらなる活用と育成
✅ テクノロジー(AI・ロボット)の活用と併用した外国人労働力の最適化
外国人職人は「一時的な労働力」ではなく、建設業界の未来を支える存在になる可能性が高いのです。
15. 外国人職人を雇っても「単価が下がらない」理由とは?
「外国人職人を雇えば、建設業の単価が下がるのでは?」と考える経営者は多いですが、実はそれほど単純ではありません。
外国人職人の雇用が増えても、建設業のコストが劇的に下がることはないのです。
✅ なぜ単価が下がらないのか?
📌 外国人職人を雇うための管理コストが発生する
📌 適切な教育・トレーニングの費用がかかる
📌 外国人職人の賃金が年々上昇している
📌 建設業界全体の人手不足により、職人単価はむしろ上昇傾向
✅ 企業が考えるべきこと
✅ 外国人職人を単なる「安い労働力」としてではなく、長期的な戦力として考える
✅ 生産性を向上させ、労働時間ではなく成果で評価する体制を整える
✅ 教育・育成に投資し、高スキルの外国人職人を育てる
単価を下げるのではなく、生産性を向上させることが本質的な解決策となるのです。
16. 外国人職人を雇用するなら避けて通れない「管理体制」の問題
外国人職人を雇用するには、適切な管理体制が必要です。
特に、法的な管理・労務管理を怠ると、重大なトラブルに発展することがあります。
✅ 外国人職人の管理で発生しやすい問題
❌ 在留資格の管理ミス(ビザの更新忘れなど)
❌ 労働時間・残業代の未払いトラブル
❌ 現場での安全管理が不十分
❌ 労働環境の悪化による離職増加
✅ 適切な管理体制を作るためのポイント
✅ 在留資格・ビザの管理を専門家に依頼する
✅ 労務管理を適切に行い、法令を遵守する
✅ 外国人向けの安全教育を徹底し、現場トラブルを防ぐ
✅ 労働環境を整備し、定着率を向上させる
管理体制をしっかりと整えることで、外国人職人のトラブルを未然に防ぎ、企業としての信頼性を高めることができます。
17. 外国人職人が活躍できる現場と、すぐに辞めてしまう現場の違い
外国人職人を雇用しても、「すぐに辞めてしまう」という問題が発生することがあります。
定着率が高い現場と低い現場では、決定的な違いがあるのです。
✅ 外国人職人が定着する現場の特徴
✅ 日本人職人との関係が良好(チームワークがある)
✅ 外国人専用の教育・研修制度が整っている
✅ 待遇・給与が適切で、モチベーションが維持できる
✅ 企業全体が外国人職人を受け入れる文化を持っている
❌ 外国人職人がすぐに辞める現場の特徴
❌ 言葉の壁があり、孤立してしまう
❌ 日本人職人との関係が悪く、差別的な扱いを受ける
❌ 給与が低く、他の企業に転職する
❌ 仕事のやりがいを感じられない
外国人職人の定着率を上げるためには、人間関係・教育・待遇の3つを改善することがカギとなります。
18. 建設業界の人材不足は外国人で解決できるのか?長期的な視点で考える
現在の建設業界は深刻な人手不足に直面しており、多くの企業が外国人職人の採用を進めています。しかし、外国人職人を雇用することで本当に人材不足は解決できるのか? という疑問が残ります。
✅ 建設業の人材不足の現状
📌 2023年時点で建設業就業者の平均年齢は約50歳
📌 29歳以下の若年層は全体の11%に過ぎない
📌 2030年には約100万人の職人不足が予測されている
このデータからも分かるように、日本人だけでは建設業を支え続けるのが難しい状況です。
では、外国人職人を雇うことでこの問題は解決できるのでしょうか?
✅ 外国人職人による人材不足解消の可能性
✅ 外国人職人の採用枠が拡大し、建設業の人手不足を補える
✅ 若い労働力が増えることで、業界の活性化につながる
✅ 外国人職人が技術を習得すれば、日本人職人と同等の戦力になる
❌ しかし、外国人職人だけでは解決できない課題も
❌ 教育・育成が追いつかないと即戦力にならない
❌ 言語の壁や文化の違いによるトラブルが発生しやすい
❌ 企業が外国人職人を受け入れる準備をしないと定着率が低い
つまり、外国人職人を活用することは人材不足解消の「一つの手段」ではあるが、それだけでは根本的な解決にはならないということです。
解決策としては、外国人職人を「育成」し、長期的に戦力化する仕組みを整えることが重要になります。
19. 今すぐ動くべき?外国人職人の雇用を後回しにすると起こるリスク
「外国人職人の雇用は、もう少し様子を見てから…」と考えている企業も少なくありません。
しかし、今すぐ動かないと、後々大きなリスクを抱える可能性があります。
✅ 外国人職人の雇用を後回しにすることで起こるリスク
❌ 優秀な外国人職人の確保が難しくなる
👉 早めに動いた企業は、既に外国人職人の採用を進めており、後から参入すると優秀な人材が残っていない可能性がある。
❌ 日本人職人の減少が加速し、競争力が低下する
👉 日本人職人の高齢化が進む中、新たな労働力を確保しないと、将来的に仕事を受注する能力が低下するリスクがある。
❌ 制度変更の影響を受け、採用が難しくなる可能性がある
👉 特定技能制度は、政府の政策変更によってルールが変わる可能性がある。今のうちに受け入れ体制を整えておく方が安心。
✅ 今すぐ動くべき理由
✅ 今なら助成金や補助金を活用できるため、採用コストを抑えられる
✅ 外国人職人を育成する時間を確保し、長期的な戦力化が可能になる
✅ 早めに外国人職人を受け入れることで、日本人職人との協力体制を構築しやすい
「まだ早い」と思っている間に、他社はすでに外国人職人を受け入れ、競争力を高めています。
外国人職人の活用を検討しているなら、できるだけ早めに行動することが重要です。
20. 建設業経営者が知っておくべき、外国人職人採用のリアルなコスト
外国人職人を採用する際、多くの経営者が「コストがどれくらいかかるのか?」と疑問を持ちます。
ここでは、実際にかかるコストを具体的に解説します。
✅ 外国人職人を雇用する際の主なコスト
| 費用項目 | 概要 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 在留資格申請費用 | ビザ取得に必要な手続き費用 | 5万円~10万円 |
| 人材紹介手数料 | 人材派遣会社や仲介業者への支払い | 30万円~50万円 |
| 教育・研修費用 | 日本語教育、建設技術指導 | 10万円~20万円 |
| 住居・寮の整備費用 | 寮の準備、家具・家電の購入など | 10万円~30万円 |
| 労働保険・社会保険 | 外国人労働者向けの保険加入 | 毎月数万円 |
このように、外国人職人を採用するには、一定の初期費用がかかります。しかし、助成金や補助金を活用することで、実質的な負担を軽減することが可能です。
✅ 外国人職人採用のコストを最小限に抑える方法
✅ 国や自治体の助成金・補助金を活用する
✅ 複数の外国人職人を同時に受け入れ、教育コストを分散する
✅ 日本人職人とのチーム作りを強化し、教育の負担を軽減する
外国人職人を「コスト」と考えるのではなく、「未来の投資」と捉えることが大切です。
まとめ|建設業の未来は、外国人職人と共に成長する!
本記事では、特定技能外国人職人の活用方法とその現実について詳しく解説しました。
改めて重要なポイントを整理すると、以下のようになります。
✅ 外国人職人は、日本の建設業において不可欠な存在になりつつある
✅ 技能実習制度と特定技能制度の違いを理解し、適切に活用することが重要
✅ 日本人職人と外国人職人は、それぞれ異なる強みを持っており、適材適所で活用するべき
✅ 助成金や補助金を活用し、採用コストを抑えることができる
✅ 外国人職人を受け入れるなら、早めに動くことが競争力強化につながる
外国人職人の雇用は、ただの「人手不足対策」ではなく、建設業界の未来を支える重要な戦略です。
これからの時代に向けて、外国人職人を適切に活用し、企業の競争力を高めていきましょう!
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武