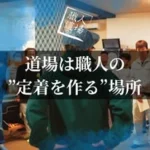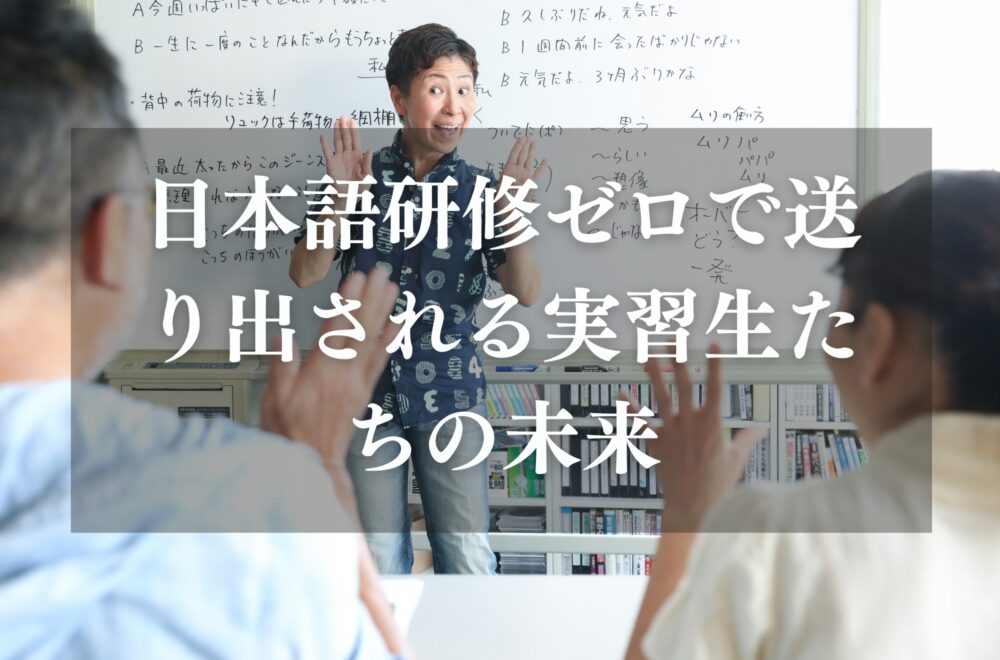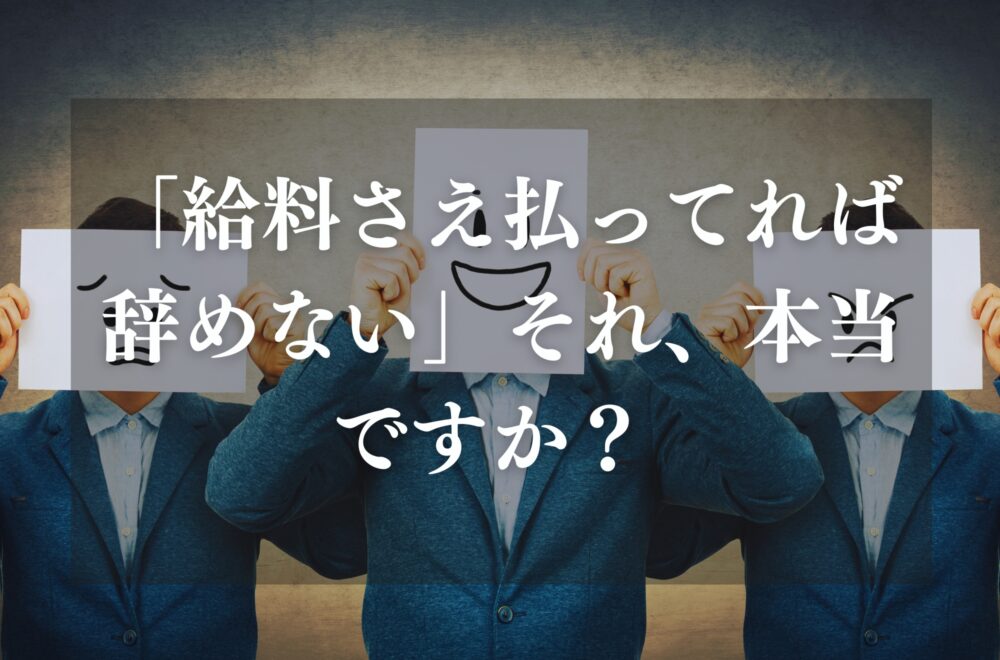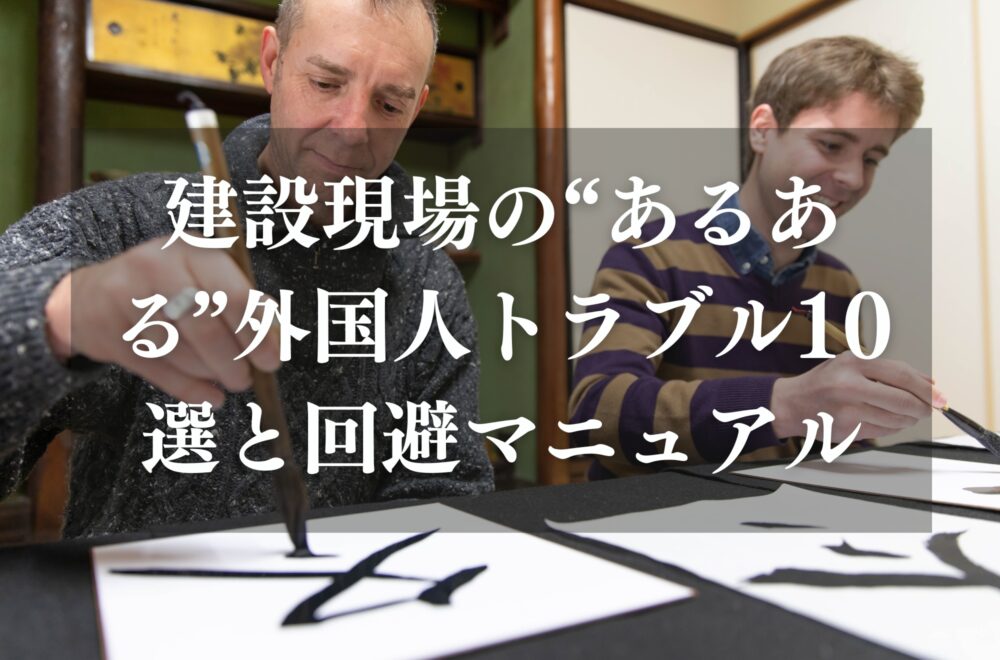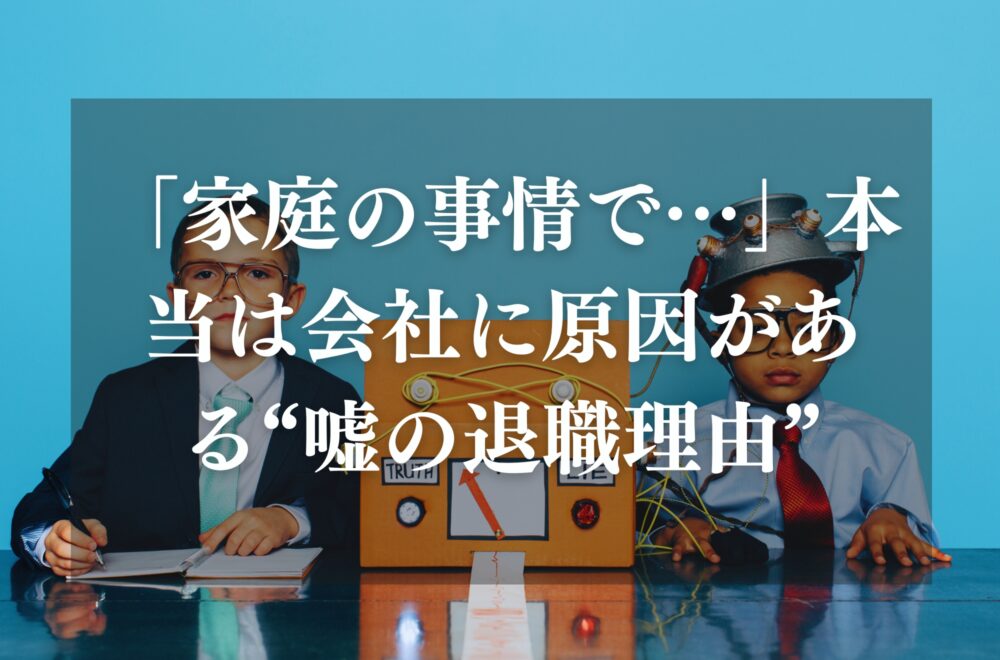建設会社社長の本音「正直、外国人職人の教育って限界がある」物語り

※この物語はフィクションですが実際に弊社の利用企業様の声を参考に作成しています。
>目次(気になる記事のリンクをクリック下さい)
- ① 「正直、育たない…」社長の愚痴は本音か、それとも現実か?
- ② うちのやり方が悪い?それとも彼らが悪い?モヤモヤが止まらない現場
- ③ 「伝わらない」「動かない」「すぐ辞める」—これ全部うちの話
- ④ 真面目でやる気はあるのに…なぜ外国人職人は空回りしてしまうのか
- ⑤ 日本人と同じ育て方でいいわけないって、誰か早く教えてよ
- ⑥ 「3年育てて辞められた」って、さすがに心折れるわ
- ⑦ 通訳つけてもイライラ、教えてもミス連発…現場監督も限界!
- ⑧ 助成金で採用はしたけど…結局、現場が回らないってどういうこと?
- ⑨ あの研修、意味あった?現場とのギャップがエグすぎる問題
- ⑩ 「限界がある」は言い訳じゃない。けど、もう一度だけ希望を持ってみようか
- 【まとめ】「限界」から始まる、建設現場の未来づくり
- この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武
- 多能工職人育成学校・技術研修所「職人道場紹介動画」
① 「正直、育たない…」社長の愚痴は本音か、それとも現実か?

「正直、うちで外国人を育てるのはもう無理かもしれん」
こんな言葉を、あなたもどこかで聞いたことがあるかもしれません。いや、もしかしたら、自分がつぶやいたことがあるかもしれませんね。最近、建設会社の社長さんたちと話していると、こんな“本音”がポロッと出てくる機会が増えました。
「ちゃんと教えてるんだけどさ、全然育たないんだよね」
「最初はニコニコしてたのに、1ヶ月で辞めちゃったよ」
「結局、通訳使っても全然通じない。もうどうすりゃいいの?」
——これ、決して特殊な例じゃありません。多くの中小建設会社が、同じような問題に直面しています。
なんで“育たない”って思っちゃうのか
そもそも、なぜ社長たちは「育たない」と感じてしまうのか。
その背景には、いくつかの“ズレ”があります。
まず一つ目は、「日本人を育てた感覚で、外国人も育つはず」という思い込み。
昔ながらの職人文化では、「見て覚えろ」「言われなくても察しろ」が当たり前でしたよね。でもこれ、文化的にまったく違う背景を持つ外国人にとっては、ただの無理ゲーです。
それに加えて、「教える時間がない」「そもそも誰が教えるの?」という育成のリソース問題。現場は常にカツカツ。新人に手取り足取り教える余裕なんて、正直ない。でも、やらないと育たない。……だから、「やっぱり限界だわ」ってなるんです。
本当に“育たない”のか? それとも“育てられてない”のか?
ここが、このテーマの核心かもしれません。
たしかに育たない外国人職人もいる。けれど、「全員がそうか?」と問われたら、実はそうでもない。ちゃんと育って、現場で頼られてる外国人職人だっているんです。
じゃあ、何が違うのか?
答えはシンプルで、「育て方」と「受け入れの仕組み」が違うんです。
たとえば、ある建設会社では、外国人職人に対して1日5分でも「振り返りの時間」をつくってる。今日やった作業の中で、何ができて、何ができなかったか。翌日はどうするか。通訳を交えてしっかり言語化してるんです。
たったそれだけでも、職人の成長スピードはまるで違う。
社長の本音は、現場の“叫び”でもある
ここまで話してきて、「いや、そんな理想論じゃどうにもならんのよ」って思った方もいるかもしれません。
でもね、「育たない」「限界だ」っていうその言葉の裏には、現場のリアルな叫びがあるんです。
いつも通訳を呼べるわけじゃない
日本語マニュアルを渡しても読めない
教えても教えても同じミスをされる
注意したら“怒られた”と勘違いして辞めていく
そうなると、社長の頭の中にはこういう考えがよぎります。
「だったら最初から採らない方がいいんじゃないか?」
「助成金があっても、割に合わないよな…」
「育つ前に辞める。これじゃ意味がないよな…」
このモヤモヤ、本当に多くの現場で渦巻いています。
愚痴でも弱音でもいい。でも「やめる前に一度立ち止まる」
ここまで本音で書いてきました。でも、一つだけ忘れないでほしいのは、「限界」って言葉は、終わりじゃなくて“変わり目”かもしれないってことです。
「もう無理だ」と思ったら、それは“今のやり方”が合ってないサインかもしれません。
そして、変えられるのは制度じゃなくて、現場の教育設計です。
育てる人が育て方を学ぶ
通じないなら伝え方を変える
やる気があるなら仕組みを用意する
この積み重ねが、じつは「限界だと思っていた壁」を超える突破口になります。
次へつなぐための“第一声”としての本音
「育たない」「無理だ」と言っていいんです。愚痴っていいんです。
大事なのは、それを「だから、もうやめよう」ではなく、
「じゃあ、次はどうするか?」につなげること。
社長の本音には、現場をどうにかしたいっていう“責任感”が詰まっている。
だからこそ、あきらめる前に、もう一度だけ可能性を探してみましょう。
② うちのやり方が悪い?それとも彼らが悪い?モヤモヤが止まらない現場

「言った通りにやらない」
「何度教えても同じミス」
「こっちの空気、まったく読まない」
——そんなとき、ふと頭をよぎるのがこの疑問。
「うちの教え方が悪いのか?それとも彼らが悪いのか?」
この“どっちなんだ論争”、正直どこの建設会社でも1度はあるんじゃないでしょうか。そして、たいていの現場では答えが出ないまま、イライラと疲労だけが積み重なっていく。
教えてる“つもり” VS 理解してない“現実”
たとえば、こんな場面を想像してください。
監督「この作業は、次にこれやって、それからこれね」
外国人職人「はい、わかりました」
——数分後、まったく違う作業を始める。
よくある話ですよね。で、こっちは「なんで!?」ってなる。
でも当の本人は、「言われた通りやったつもりです」と言う。
ここで発生しているのは、「指示のズレ」じゃないんです。
“理解の確認”をしてないまま、次に進んでしまっていることなんですよ。
文化の違い?それとも「見えない前提」の罠?
日本の現場って、正直“言わなくても察しろ文化”が強いですよね。
「普通こうやるだろう」
「前回見たよね?」
「言わせんなよ、って話」
でも、外国人職人にとっては、その“普通”がわからないし、そもそも前回のことも曖昧にしか覚えてないことが多い。
たとえば、日本人なら「仕上げって言われたら、キレイに丁寧に」が頭に浮かぶけど、別の文化では「仕上げ=終わらせること」って捉えたりする。だから、「雑に終わらせたつもり」で、「お前、何やってんだ!」って怒られることになる。
これって、「彼らが悪い」というよりも、前提を共有できていないという話なんですよ。
指示も確認も“前提ゼロ”でやってみると見えること
ある企業の例ですが、外国人職人とのやりとりを“ゼロベースでやってみる”実験をしたんです。
つまり、「普通こうするでしょ」を全部捨てて、
使う道具の名前を毎回確認
作業順をホワイトボードで絵にして共有
どこまで終わったら次に進んでいいかを“視覚”で示す
するとどうでしょう?
これまで「何度言っても分からない」とされてた職人たちが、スムーズに作業できるようになったんです。
つまり、「うちのやり方が悪いのか?彼らが悪いのか?」じゃなくて、
「そもそも、共通のやり方がなかった」ということだったんです。
「悪い」のじゃなく「合ってない」だけかもしれない
この“モヤモヤ”を解決する最大のヒントは、「正しい・間違い」ではなく「合う・合わない」という視点に切り替えることです。
うちの現場に合った教育方法って何だろう?
この国の人には、どう伝えたら伝わる?
誰に教えさせるのが一番うまくいく?
こう考えるだけで、ずいぶん見える景色が変わってきます。
結局、育成は「共通言語」を作る作業
「言葉が通じない」ってよく言うけど、本当に通じないのは言葉じゃなくて“共通の考え方”や“共通の行動ルール”だったりします。
たとえば職人道場では、「作業手順を5ステップに分ける」「完成形の写真を見せる」「毎日“できたこと”を報告させる」といったシンプルな“共通言語”を作ってから教育に入る。
そうすると、指導する側もされる側も、“何を目指しているのか”がブレなくなる。だからミスが減るし、育つスピードも一気に上がる。
「モヤモヤしたら、やり方を見直す」が新常識
もし今あなたの現場で、「どうして育たないんだ?」というモヤモヤが続いているなら、いったん問いを変えてみましょう。
「うちのやり方、彼らに合ってるかな?」
それは負けでも敗北でもなく、“より良い育成の第一歩”です。
③ 「伝わらない」「動かない」「すぐ辞める」—これ全部うちの話

「なあ、俺の言ってること、分かってんのか?」
「これ、もう3回目だぞ?」
「昨日まで元気だったのに、今日いきなり来なくなった…」
——こんなセリフ、うちの現場では日常茶飯事。いや、正直に言おう。
「伝わらない」「動かない」「すぐ辞める」って、これ全部、うちの話です。
現場を回してる社長や監督なら、一度はこの状況に頭を抱えたことがあるはず。
外国人職人を受け入れたはいいけど、実際には想像以上に“かみ合わない”ことが多すぎる。まるで、お互い違う星の住人みたいだ。
「伝えた」と「伝わった」の間には深い谷がある
何が一番つらいかって、「ちゃんと説明したのに、なんで伝わってないの!?」っていう瞬間ですよね。
言葉の問題もある。
でもそれ以上に大きいのは、「前提」が違いすぎるってこと。
たとえば、「養生を先にしといて」と言ったとする。
日本人職人なら、どこまでやるべきか、何を使うか、どの順番かなんとなく分かる。
でも外国人職人は、「養生って何?」「どこから?」「テープはどれ使うの?」ってなる。
で、「あー、もういいよ!俺がやるから!」ってなる。
はい、これが教育の崩壊第一歩です。
「動かない」のはやる気がないから?
もう一つのよくある誤解がこれ。
「動かない=やる気がない」って、決めつけてませんか?
実際には、動かない理由っていっぱいあるんです。
何をすればいいか分からない(指示が抽象的)
失敗が怖くて手を出せない(叱られる前提)
一回ミスして、気まずくなっている
他の職人に何か言われて、萎縮している
これ、全部“やる気がない”んじゃなくて、“動けない環境に追い込まれてる”だけなんですよね。
「すぐ辞める」理由は、給料より“孤立感”
そして最後、「すぐ辞める」問題。
「最近の若い外国人は、根性がない」とか、「昔の実習生の方が我慢強かった」なんて声も聞こえてきますが、ちょっと待って。
そもそも、今の現場って“孤立しやすい空気”になってませんか?
休憩中も誰も話しかけない
困ってるのに誰もフォローしない
注意された後、フォローがない
毎日が“やらかさないようにする”プレッシャー
これ、本人からしたら相当キツイ。日本語も完璧じゃない、文化も違う、だけど周囲は淡々と仕事をしている。
「ここ、自分の居場所じゃないかも…」って思ったら、そりゃ辞めたくもなります。
結局、「伝わらない・動かない・辞める」って連鎖してる
これって、バラバラの問題に見えるけど、全部つながってるんですよ。
指示が伝わらない
だから動けない
だから怒られる
だから怖くなって、話せなくなる
だからまたミスする
で、限界になって辞める
これ、現場では本当にリアルな負の連鎖として起きてます。
「うちの話」で終わらせないために
「これ全部うちの話だよ…」って感じたなら、ちょっとだけ視点を変えてみましょう。
伝える方法、増やしてみる(図、写真、動画)
やる前に「これで合ってる?」と確認させてみる
失敗しても、「OK、ここ直せば大丈夫だよ」と言ってみる
一緒に昼飯食ってみる(←これ意外と効く)
大きな仕組みじゃなくても、日常のちょっとした工夫が“伝わる・動ける・続けられる”を生み出します。
うちの現場も、変われるかもしれない
「うちには無理だ」「うちは特殊だから」って思いがちだけど、
実はどの現場も似たような悩みを抱えてる。
そして、どの現場も、ちょっとした“理解と仕組み”で変わっていける。
その第一歩は、「うちの話」で終わらせず、「次はどうしようか」と考えること。
④ 真面目でやる気はあるのに…なぜ外国人職人は空回りしてしまうのか

「すごく真面目で、人柄もいいんだよ」
「遅刻もないし、黙々と働いてくれる」
「でも、なんか…育たないんだよなぁ」
——これ、よくある話です。
外国人職人の中には、誰が見ても“性格がいい”“まじめに取り組んでいる”タイプがいる。なのに、どうにも現場で評価されない。結果、任せる仕事も限られて、本人もやる気を失っていく…。
これ、実力がないからじゃないんです。むしろ、頑張りすぎて空回っていることが多いんです。
空回るのは「ミスを恐れている」から
外国人職人に多い傾向。それが、「とにかくミスをしたくない」という思い。
文化的に、上司から怒られる=信用を失う、という強い感覚を持っている人も多く、間違いを極端に恐れてしまう。その結果、どうなるか?
やったことがない作業は手を出さない
指示が曖昧なときは固まって動けない
判断ミスを恐れて、逐一確認してくる
つまり、「チャレンジしない→仕事が増えない→スキルが伸びない→周りから“できない”と思われる」
という悪循環にハマってしまうわけです。
本人は一生懸命。でも現場には「指示待ち」に見える
これが一番もったいないところ。
外国人職人が丁寧に指示を待っているとき、日本人の目からは「ボーッとしてる」「自分で考えてない」と映ってしまう。
でも、本人は「間違えたくない」「正しくやりたい」って思ってるんですよ。
この“意図のズレ”が、信頼関係を壊す原因になっていることもある。
「指示してるのにできない」は、実は“解釈”のズレ
たとえば、こんなやりとり。
監督:「その材料、先に運んどいて」
外国人職人:「はい(と答えるが、動かない)」
監督:「あれ?やらないの?」
外国人職人:「“今すぐ”って意味じゃなかったと思って…」
これ、よくあるんです。日本語って“指示”が曖昧なんですよね。
「あとで」→ いつ?
「適当に」→ どの程度?
「様子を見て」→ 何を見ればいい?
つまり、“言ったつもり”と“理解されたつもり”の間に、見えないギャップがある。
空回りさせないための一番の方法は「成功体験」
実は、一度でも「できた!」「褒められた!」という経験をすると、外国人職人は劇的に変わります。
自信がつく
判断に迷わなくなる
自発的に動けるようになる
仲間とコミュニケーションを取り始める
でも、問題はここ。
「成功体験を作る仕組み」が、現場にほとんどない。
職人道場でやっている“成功のしかけ”
職人道場では、外国人職人が空回りしないよう、あえて「できそうなことから始める」仕組みをつくっています。
まず簡単な作業で“成功の感覚”を掴ませる
できたらすぐにフィードバック、「Good Job!」と声をかける
チームで達成感を共有し、「自分は役に立ってる」と実感させる
この“成功→自信→挑戦→成長”の流れをつくることで、たった20日間でも即戦力に近づけるのです。
「まじめ」は伸びしろ。空回りは環境の責任
真面目な人が空回りするって、ものすごくもったいないことです。
だって、まじめってことは「手を抜かない」「サボらない」「やる気がある」ってこと。
育てる側からしたら、これほど伸ばしがいのある人材はいないはず。
でもそれが活かされてないとしたら、
それはその人が悪いのではなく、「伸ばす仕組み」が足りないだけなんです。
最後に:空回ってる人には、「できること」から始めさせよう
何でもできる人を求めるんじゃなくて、
まず“1つだけでもちゃんとできる人”を育てる。
その小さな成功が、次のチャレンジを引き出し、現場で動ける人材へと変えていきます。
真面目な外国人職人を「宝」に変えるか、「残念」で終わらせるかは、現場の仕組み次第です。
⑤ 日本人と同じ育て方でいいわけないって、誰か早く教えてよ

「新人教育なんて、昔からのやり方でいいだろ」
「俺たちも、現場で怒られながら覚えてきたんだし」
——そう思って、外国人職人にも同じように接していませんか?
その結果、どうなったか?
「何度言ってもできない」「辞めた」「伝わらない」——そう、うちの現場が今まさにそうなんです。
正直、最初は「なんでこんな簡単なこともできないんだ?」ってイラっとしてました。
でも、あるときふと気づいたんです。
あれ?これって、育て方のせいなんじゃないか?
「見て覚えろ」が通じない相手に、どう教える?
昔ながらの職人文化。
それは「背中を見て学べ」「言われる前に動け」「間違ったら怒られるのが当たり前」。
でも、それは日本人同士だから成立していた“共通言語”があったから。
外国人職人に同じ方法を適用したら、ただの**“意味不明なスパルタ”**になることも。
たとえば、
- 道具の名前を知らない(だから指示が分からない)
- 曖昧な表現が理解できない(「ちょっと」「適当に」が通じない)
- 叱られると「自分は嫌われた」と感じて黙り込む
これ、決して能力の問題じゃない。
育て方が違うだけ。学び方が違うだけ。
誰も教えてくれなかった“外国人職人の育て方”
制度はある。助成金もある。
でも、「どう育てるか」って、誰も教えてくれないんですよね。
結果として、現場では「とりあえずうちのやり方でやらせてみよう」→「なんか全然うまくいかない」→「もう無理だわ」のループが起きる。
この“育て方の空白”こそが、今一番の問題なんです。
職人道場が最初にやるのは「育てる側の意識改革」
職人道場では、いきなり外国人職人に技術を教えるんじゃありません。
まずは育てる側(講師や現場リーダー)のマインドを変えるところから始めます。
- 「察して」はNG、「明確に伝える」が基本
- 説明+実演+再現の3ステップを使う
- NG例を見せてからOK例を教える
- 分からないのは“やる気”ではなく“構造”の問題と考える
こういった教育の“原則”を先に押さえることで、指導の効率と納得度がまったく変わってくるんです。
「同じじゃないからこそ、通じ合える」育て方がある
文化、言葉、働き方、価値観。
そりゃ違いますよ、当たり前です。
でも、その違いを「やっかいだな」と思うか、
「面白いな」「工夫しがいがあるな」と思えるかで、現場の空気はガラッと変わります。
ある会社では、ベトナム人職人を指導するときに、
- 毎朝“昨日の復習”を10分だけやる
- 「これ、どう思う?」と質問して自分の意見を言わせる
- 小さな成功を“見える化”してホワイトボードに貼り出す
たったこれだけで、「何もできなかった彼」が、3ヶ月後には若手のリーダー格に育っていました。
「昔からのやり方」は誇り。でも“今に合う”育て方も必要
古いやり方が全部ダメだとは言いません。
でも、それだけじゃ足りない時代になったのも確かです。
職人の技術は、現場でこそ光る。
でもその技術を“受け取る側”が変わってきてるなら、教える側もアップデートしなきゃいけない。
その変化に早く気づいた人から、次の世代を育てていけるんです。
最後に:自分たちの“当たり前”を疑ってみる
- 教えてるのに伝わらない
- やる気はあるのに育たない
- 辞める理由が分からない
もし、そんなモヤモヤがあるなら、
まず「日本人と同じ育て方でいいわけない」って、口に出して言ってみてください。
そこから、きっと何かが変わります。
⑥ 「3年育てて辞められた」って、さすがに心折れるわ

「やっと現場で通用するようになったのに、帰国したいって言われた」
「3年かけて教えて、やっと一人前になった矢先に辞められた」
「次の子?いや、もう育てる気力がないよ…」
—これ、建設業界の社長や現場責任者の“リアルな嘆き”です。
そしてその気持ち、正直、めちゃくちゃ分かる。
時間も労力も使って、汗だくで教えて、「お、やっと自分の右腕になるかも」と思ったところで離脱。
この脱力感、誰かに聞いてほしいぐらいですよね。
教育には「時間投資」という痛みがある
職人を育てるって、言ってしまえば“先行投資”です。
すぐに回収できるもんじゃない。だけど、いつか現場の中心になってくれるって信じて、歯を食いしばって続ける。
でも、その回収前に辞められたら?
正直、「もう次はいいや…」って気持ちになりますよね。
しかも外国人の場合、技能実習制度の“3年満了”がある。本人に悪気がなくても、「帰国します」の一言で全部リセット。
それ、こっちは気持ちの整理がつかないっすよ…!
「裏切られた」わけじゃない。でも、そう感じてしまう
辞める理由が本人の都合なのは分かってる。
- 家族の事情
- 他の仕事にチャレンジしたい
- 日本での生活に疲れた
全部理解できます。
でも、だからといって「そうか、頑張ってな」って簡単に言えるか?って話なんですよ。
3年間、言葉の壁にイラついて、何度も同じミスに頭を抱えて、時にぶつかり合って、それでも信じて育てた。
その努力が、まるで“消えたような感覚”になってしまう。
それが、つらいんです。
定着率の低さは“構造の問題”でもある
実は、「外国人職人が辞める」のって、本人の問題だけじゃなくて、“制度と企業側の体制”にも課題があるんです。
- 技能実習制度は“育成”が目的。だから3年で終わる前提。
- 特定技能に移行する仕組みもあるけど、企業側の手続きが面倒で進まない。
- 育てる側はリターンを期待するが、制度側は“サイクル”を想定してる。
つまり、長く働いてもらいたい側と、短期育成を想定した制度設計の間にギャップがあるんです。
職人道場では「短期で戦力化」「中期で定着」をセットで考える
この問題に対して、職人道場が出した答えが、**“短期育成+中期定着支援”**というモデルです。
- 最初の20日間で、現場で動けるスキルを叩き込む(これで即戦力)
- その後は、現場の管理者と連携して、3ヶ月・6ヶ月・1年での“定着プラン”を一緒に設計する
- 特定技能への移行サポートや、本人との定期ヒアリングも実施
これにより、「3年経つ前に辞める」ことを防ぎ、**“気づけばもう5年働いてる”**という状態を目指しているんです。
「心折れた」その気持ちを、どう扱うか
ここで大事なのは、「もう育てるのやめよう」じゃなくて、**「もう同じ失敗は繰り返さないようにしよう」**と気持ちを切り替えること。
そのためには、
- 育成プランを“見える化”する
- 本人のキャリアプランも最初に共有しておく
- 定期的にモチベーションを聞く機会を作る
- 「戻ってくる道」を用意する(再来日や再雇用)
こういうちょっとした“未来への工夫”が、次の育成に前向きになる鍵になります。
最後に:育てた時間は、決してムダじゃない
辞められると、「全部ムダだった…」って感じてしまうかもしれません。
でも、実はそうじゃない。
その職人が別の場所で活躍するたびに、「あの人、うちで育ったんだよ」って言えること。
それって、めちゃくちゃ誇らしいことじゃないですか?
“心折れた”経験は、次にもっといい育成をするための土台にもなる。
だから、今は無理でも、いつかまた「よし、次も育ててみるか」と思える日が来るはずです。
⑦ 通訳つけてもイライラ、教えてもミス連発…現場監督も限界!

「もう無理…正直、もう教えたくない」
「何度言っても通じない、何度やらせても間違える」
「通訳がいても、思ってることの半分も伝わらない!」
——これ、現場監督の“リアルな悲鳴”です。
外国人職人の育成を任されたはいいけれど、気がつけば“ストレスのはけ口”になってる。
上からは「育てろ」、現場では「進めろ」、本人は「分かってない」——もう、パンク寸前です。
通訳がいても“心の翻訳”まではしてくれない
よく言われますよね、「通訳つければ何とかなるでしょ?」って。
……なりません。
なぜなら、通訳が訳すのは“言葉”であって、“ニュアンス”や“現場の空気”までは届かないから。
たとえば、こういう場面。
監督:「ここ、昨日と同じ手順でやってって言って」
通訳:「昨日の手順でお願いします」
職人:「……(どこまでの工程?昨日って午前?午後?)」→ミス!
こうして「何度も言ったのに!」というストレスが、どんどん積もっていく。
現場監督のストレスは“見えにくい負担”
外国人職人の受け入れで、一番しわ寄せが来るのが現場監督です。
- 作業進行の責任者なのに、育成も丸投げ
- 自分でやった方が早いけど、任せないと育たない
- 一人のミスで工程が遅れれば、責任は全部自分
- 本音を言えば「誰か代わってくれ!」状態
だけど、誰も文句を言えない。
なぜなら「外国人職人の育成=善いこと」とされているから。
こうして、現場監督の“限界”は誰にも気づかれずに放置されていくのです。
教える人にこそ「教える技術」が必要なのに…
外国人職人がうまく育たないとき、どうしても「本人が悪い」となりがちです。
でも、ちょっと待って。
教える側が“教え方”を学んでいないことこそ、大きな原因じゃないですか?
- どうやって伝えるのが効果的か
- ミスしたとき、どうフォローすれば改善するか
- 文化的にNGな伝え方とは何か
- 叱り方・褒め方のタイミングとは?
こういう「教えるスキル」がないまま、「何とかしてくれ」と言われるのは酷ってもんです。
職人道場は“育成する人”の負担まで設計している
職人道場の一番の強みは、育つ側だけじゃなく、育てる側のストレスまで考慮しているところにあります。
- 教材はすべて多言語+視覚化+実演つき
- 現場監督向けに「ここまで教えた」「ここから任せてOK」という指導引継ぎ書を提供
- 教育マニュアルではなく、“実務ベースの指示例”を渡す
- さらに、教育の進捗を道場側が記録・共有してくれる
つまり、監督は“ゼロから”じゃなく、“引き継いだ状態”で育成を始められる。
この設計だけで、ストレスはだいぶ軽減されるんです。
「育てたいけど、もう無理」な気持ちに寄り添う必要がある
正直な話、現場監督も人間です。
疲れるし、イライラもするし、モチベーションが落ちる日もある。
それを「あなたの努力が足りない」と言うのは、あまりに無責任。
必要なのは、“育てる人を支える仕組み”です。
- 教える時間を工面する人員配置
- 通訳との連携ルールの整備
- 成長を「見える化」して達成感を与える工夫
- 教えた結果を評価する制度(←これ超重要)
これらが整っていないのに「育てろ」って言われたら、そりゃ誰でも折れます。
現場監督は、会社にとって“教育の柱”
外国人職人の育成が上手くいくかどうかは、現場監督の支え方次第です。
だから、社長や経営層が本気で考えるべきは、
- 「現場監督が教育を続けられる仕組みがあるか?」
- 「指導に関するストレスや不安を吐き出せる場があるか?」
- 「“うまく育てた”ことに報酬や評価をつけているか?」
という部分なんです。
最後に:限界の手前で、“支える仕組み”を
「もう無理」と思ったそのタイミングが、実は教育の形を変えるチャンスかもしれません。
限界を責めるんじゃなく、
「じゃあどうすればもう少しだけ頑張れるか?」を一緒に考える。
現場監督の“育成限界”を乗り越えるカギは、育てる人へのケアと工夫にあります。
⑧ 助成金で採用はしたけど…結局、現場が回らないってどういうこと?

「助成金あるから、外国人採用しとこう」
「人手が足りないし、今は外国人しか取れないしな」
「でもさ…全然、現場が回らないんだよね…」
—このセリフ、もう何度耳にしたか分かりません。
建設業界における“助成金頼みの人材確保”、実は今、ものすごく危うい綱渡り状態にあるんです。
助成金は確かにありがたい。でも“目的”を間違えると痛い目に
たしかに、外国人職人を雇うことで利用できる制度は多い。
特定技能や技能実習、厚労省系の人材確保助成金など、いろいろあります。
でも、ここが落とし穴。
助成金は“人を確保するため”の道具であって、“育てる仕組み”じゃない。
「人さえ来ればなんとかなる」って思っていると、結局現場は混乱するだけ。
気づけば、こんな状況に——
- 仕事を振れない
- ミスが連発する
- 教える人がパンク寸前
- 他の職人たちもストレスでギスギス
で、最後には「やっぱり外国人は無理だったな」って結論に…。
助成金は“きっかけ”、現場づくりは“自力”
助成金で人を採るのは、正直“スタートライン”にすぎません。
そこからどうやって「働ける」「育つ」「辞めない」環境を作るかが勝負。
つまりこういうことです:
| 項目 | 助成金でカバー | 自社で用意するべきこと |
|---|---|---|
| 採用費用 | ○ | ― |
| 教育体制 | △(外部研修補助はある) | ◎(現場マニュアル、担当者の配置など) |
| 定着支援 | × | ◎(フォロー体制、相談窓口など) |
| 成長評価 | × | ◎(目標設定、振り返り) |
助成金に頼るなら、それに見合った「自社の受け入れ設計」も整える必要があるんです。
だからこそ、まず基本の技術を習得して、自社に戻った時に「働ける」「育つ」「辞めない」人材を
教育出来るかが大事なことになります。道場は教育のプロ、もちは餅屋に任せるべき。
現場が回らない“本当の理由”はここにある
よく「日本語ができないから仕事にならない」って言いますが、それって本当でしょうか?
- そもそも、何をどの順番でやるのかが決まってない
- 教え方が人によってバラバラ
- 誰がリーダーで、誰が指導するかが曖昧
- 職人間の連携も不安定
つまり、人の問題じゃなく、現場の構造が曖昧なんです。
外国人じゃなくても、新人が入ったら混乱する現場って、実は多いんですよね。
職人道場は“助成金+現場教育”をパッケージで設計
職人道場のアプローチは明快です。
「助成金を使って人を採る」ではなく、**「助成金を使って、ちゃんと育てて戦力にする」**まで設計されています。
- 研修受講で“人材開発支援助成金”が活用可能
- 国が認めた内容の教育だから、助成対象も明確
- 教育終了後、現場側に“指導ポイント”をパッケージで渡す
- その後の“定着支援”まで相談できる仕組みあり
つまり、「人を採ったあと、何をすればいいか?」が全部セットになってるんです。
“制度だけ使う”から“制度を活かす”へ
結局、助成金も制度も、“使い方”で未来が変わります。
- 目先の費用削減だけを追うのか
- 長期的な戦力化を見据えて活用するのか
この違いが、企業の生産性、現場の安定、そして離職率に直結します。
最後に:人を育てられる会社は、どこでも勝てる
助成金はどの会社でも申請できます。でも、人を育てられる会社は限られている。
今後、建設業界で生き残るのは、
「制度で得た人材を、会社の財産に変えられる現場」だけです。
人を“集める”だけでは、もう足りません。
人を“育て、定着させる”ことが、真の経営力になる時代です。
⑨ あの研修、意味あった?現場とのギャップがエグすぎる問題

「研修で勉強してきたって言うから期待してたのに…」
「現場に出たら全然使いもんにならん!」
「覚えたって言うけど、何を?どこで?って感じよ…」
——これ、現場監督や先輩職人が外国人職人を初めて迎えたときによく口にする“がっかりコメント”です。
そう、問題は——あの研修、ほんとに現場で役立ってるの?
という、超リアルなギャップの話です。
「研修は受けてます」→「じゃあ、なんでこんなに違うの?」
外国人職人の多くは、日本に来てすぐに「入国後講習」や「技能実習前研修」などを受けます。
法律やマナー、最低限の用語、安全教育など、それなりに時間をかけて勉強している。
でもね、現場の感覚としてはこうなんです:
「そこまで教わったっていうなら、なんで“安全帯のつけ方”ひとつ満足にできんの?」
「材料の名前すら分かってないのに、何の研修だったん?」
——これが、現場と研修のギャップの正体です。
研修が“現場のリアル”に追いついてない理由
このギャップ、なぜ起きるのか?
- 内容が抽象的すぎる
→「安全第一」「報連相」「KY活動」など、概念だけで実務がない。 - 現場設備での練習がない
→道具や材料の“本物”を使った訓練ができていない。 - 言語中心で、体で覚える場面が少ない
→「聞いたけど覚えてない」「分かったつもり」が多発。 - 教える人が“現場未経験”
→教科書どおりの説明は上手でも、“その場の判断”は教えられない。
つまり、現場の汗と泥の中で必要なスキルを、研修ではカバーできていないわけです。
職人道場の研修が“現場とズレない”理由
そんな中、職人道場が圧倒的に現場評価が高い理由は、
“現場主導で作られた研修”だからです。
- 実際の建設資材・設備を使った実技訓練
- 20日間で「この作業は一人でできる」レベルに到達
- 指導者は“現場を知ってる元職人”ばかり
- NG作業例を“わざと失敗させて”覚えさせる逆転教育
- 日本語ではなく“動き”で理解できる指導方法
つまり、「勉強しました」ではなく、「動けます。任せてください。」という状態で送り出されるんです。
「育成のスタート地点」を間違えると、全部ズレる
このギャップ問題で一番怖いのは、
企業が「できる前提」で現場に入れてしまうこと。
結果として…
- 現場は任せたのにミス多発
- 職人本人は怒られて萎縮
- 教える側は「研修受けたのになんで?」とイラつく
- お互い不信感だけが募っていく
こうなったら、もう教育どころじゃありません。
最初の“期待と現実のズレ”が、その後すべての悪循環のスタートになる。
企業と研修機関の“連携”がカギになる
だから大事なのは、「教育した」じゃなく、「現場で役立つ教育がされていたか?」を企業側が把握すること。
職人道場では、
- 研修終了時にスキルチェック表を企業に共有
- 「できること・できないこと」が一覧化されている
- 監督が“どこから教えればいいか”がすぐ分かる
- 道場で使用した教材を現場にも展開可能
この仕組みがあるから、研修と現場がつながるんです。
最後に:教育は「送り出したら終わり」じゃない
外国人職人の教育は、“出荷”じゃありません。
「送り出して終わり」ではなく、「送り出してからが始まり」です。
だからこそ、企業も、
- どんな研修を受けたか
- どのレベルまでできるのか
- 何に困っているのか
をちゃんと知っておくべき。
それが分かれば、現場での“教えるコスト”は圧倒的に下がります。
⑩ 「限界がある」は言い訳じゃない。けど、もう一度だけ希望を持ってみようか

「外国人職人の教育には限界がある」
その言葉、何度も何度も、いろんな社長や現場監督から聞いてきました。
そして正直、自分自身もそう思ったことがあります。
- 伝わらない
- 動かない
- 育たない
- 辞める
——そのたびに、「やっぱり無理だったか…」と肩を落とした。
誰も責められない。だって、それが現実だったんだから。
でも、ちょっと待って。
本当に“限界”なのかな?
“限界”を感じたのは、どこだったのか?
「限界がある」と言いたくなる瞬間って、たいていこういうときです。
- 何度言っても通じない
- 育てたのに辞められた
- 期待したほど成長しない
- 日本人職人との軋轢が止まらない
- 管理者のストレスが限界
これ、全部「人の問題」に見えるけど、よく考えてみると、
・通じないのは、伝え方が合ってなかったのかも?
・辞められたのは、フォロー不足だったのかも?
・育たなかったのは、成功体験を積ませなかったからかも?
—そう、“やり方”次第で変えられる可能性があるんです。
「限界」は悪ではない。むしろ出発点
建設業の現場って、変化に対して保守的な部分が強いですよね。
「昔からこのやり方でやってきた」
「甘やかすな」
「根性が足りない」
でも、“限界を感じる”ってことは、そこに変える余地があるってこと。
限界を感じるってことは、あなたが本気で取り組んできた証拠です。
本気で育てようとして、うまくいかなくて、疲れて、それでもまだ何とかしたいと思っている。
—それこそが、次の一歩を踏み出す力になるんです。
職人道場が教えてくれた、“もう一度だけ信じてみる価値”
職人道場には、何人もの「限界を感じた社長」がやってきます。
- 「3人続けて辞められた」
- 「育成担当が音を上げた」
- 「監督が鬱っぽくなってしまった」
そんな現場が、たった20日間の研修で見違えるように変わった例が、いくつもあるんです。
- 「やれること」が見える
- 「できたこと」が自信になる
- 「褒められたこと」でモチベが上がる
- 「育て方」が分かるから、監督も前向きになる
つまり、“限界を感じた”からこそ、本物のやり方を探し始めた企業が、再起動に成功してるんです。
外国人職人は“問題”じゃない、“可能性”だ
ここまでいろんな苦労や愚痴を書いてきましたが、最後に一つだけ言わせてください。
外国人職人って、
伸びしろの塊なんです。
- 真面目で
- 向上心があって
- 仲間意識も強い
- 家族のために頑張る覚悟がある
そんな人たちを“諦める”んじゃなくて、
“活かす道”をもう一回だけ探してみませんか?
最後に:希望は、工夫の先にある
「限界がある」って言うのは、甘えじゃない。現場の本音です。
でも、それを“終わりの言葉”じゃなく、“始まりの合図”にしてみてください。
- 伝え方を変える
- 教え方を学ぶ
- 成長を見える化する
- 支える人を守る仕組みをつくる
たった一つの“やり方”が、
“もうダメだ”と思っていた現場を変える力になります。
その第一歩、職人道場と一緒に踏み出してみませんか?
【まとめ】「限界」から始まる、建設現場の未来づくり
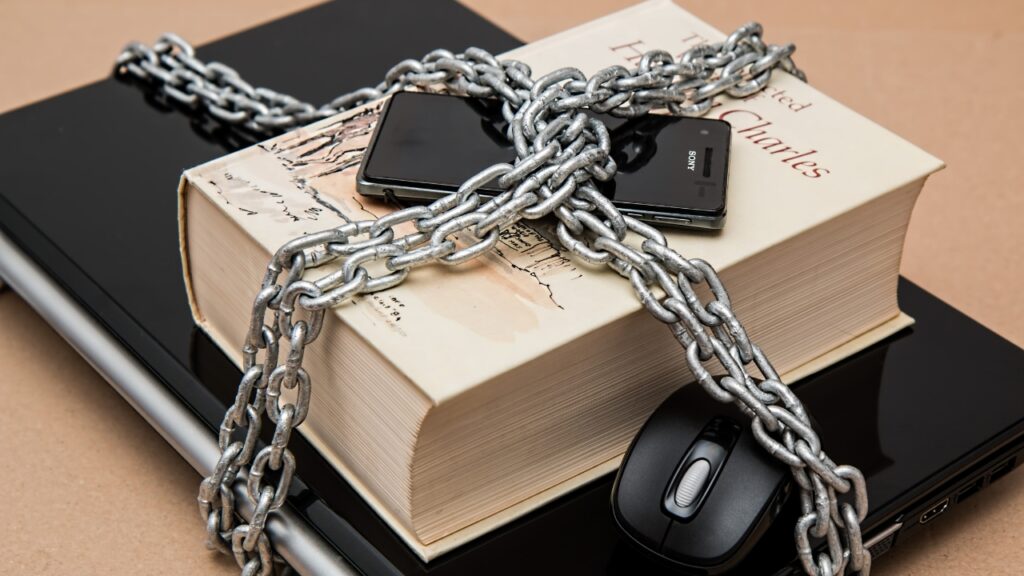
「正直、外国人職人の教育って限界がある」——これはただの弱音ではなく、多くの建設現場が直面しているリアルな声です。
言葉が通じない、教えても育たない、通訳がいてもイライラする、現場監督は疲弊、助成金だけじゃ回らない…。そんな“育成疲れ”が、いま業界全体を覆っています。
でも、その“限界”の正体は、人材ではなく、「育て方」や「受け入れの仕組み」の限界だったのかもしれません。
- 指導法が時代に合っていない
- 現場と研修の内容がズレている
- 文化の違いを理解していない
- 管理者への支援が足りていない
- 成功体験を積ませる仕組みがない
こうした“育てられない構造”をそのままにして、「限界だ」と片付けるのは、あまりにもったいない。
職人道場のように、実践的で即効性のある教育、育てる側の負担を考えた仕組み、文化の違いを前提にした伝え方を取り入れれば、わずか20日で「この子なら任せられる」と思えるレベルまで引き上げることが可能です。
今の時代、「外国人を育てられる会社」こそが、次の時代の競争力を持つ会社になります。
“限界”を認めることは、決して敗北ではありません。それは、次の改善を生み出すスタートライン。
もう一度だけ、外国人職人の育成に希望を持ってみませんか?
変われる現場は、もう始まっています。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。