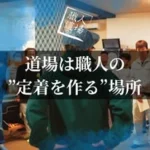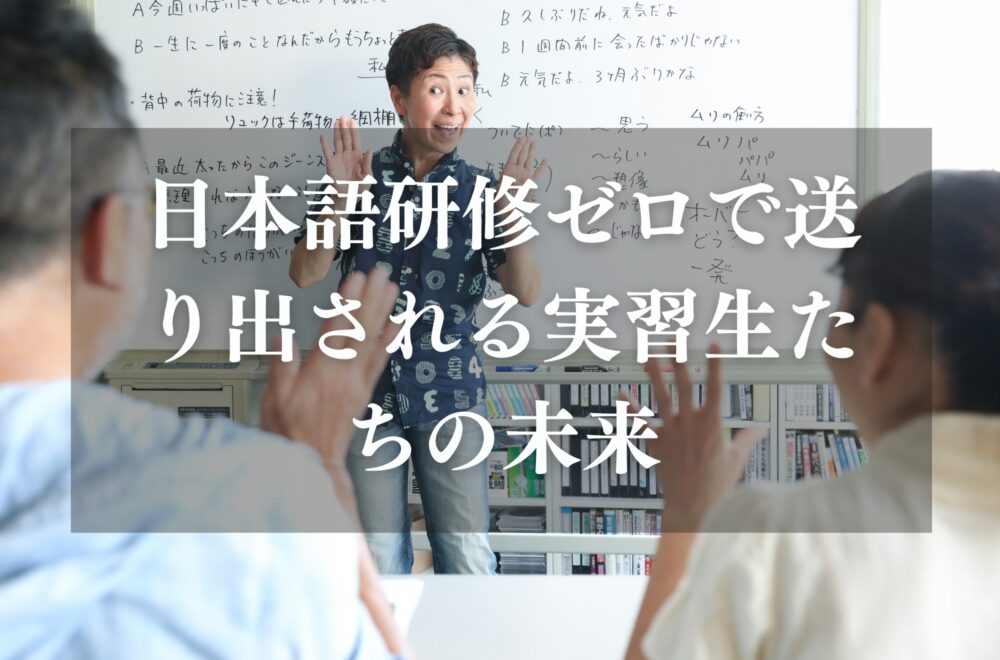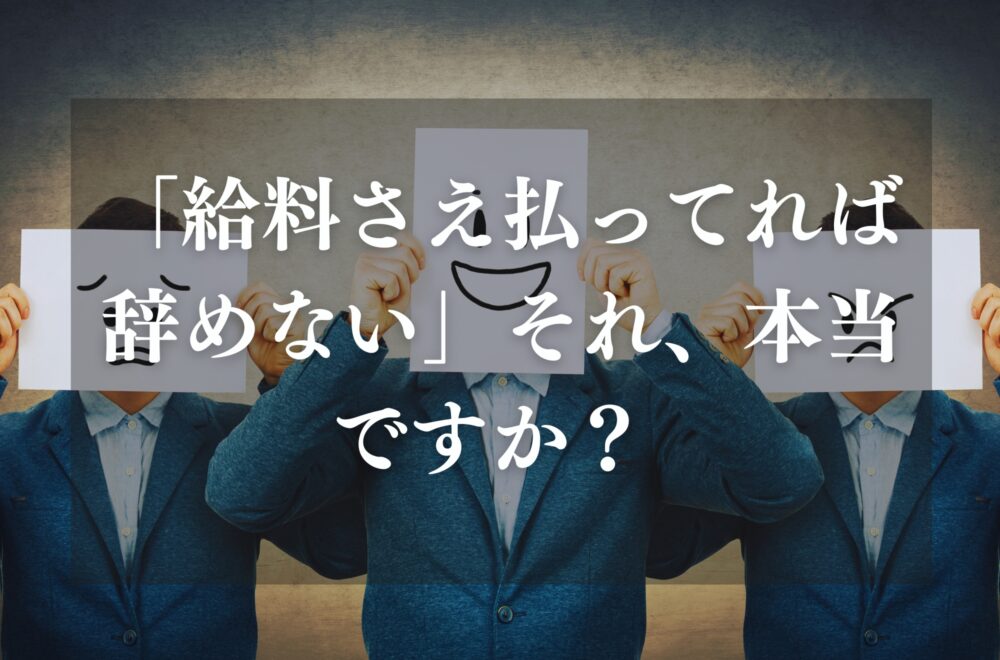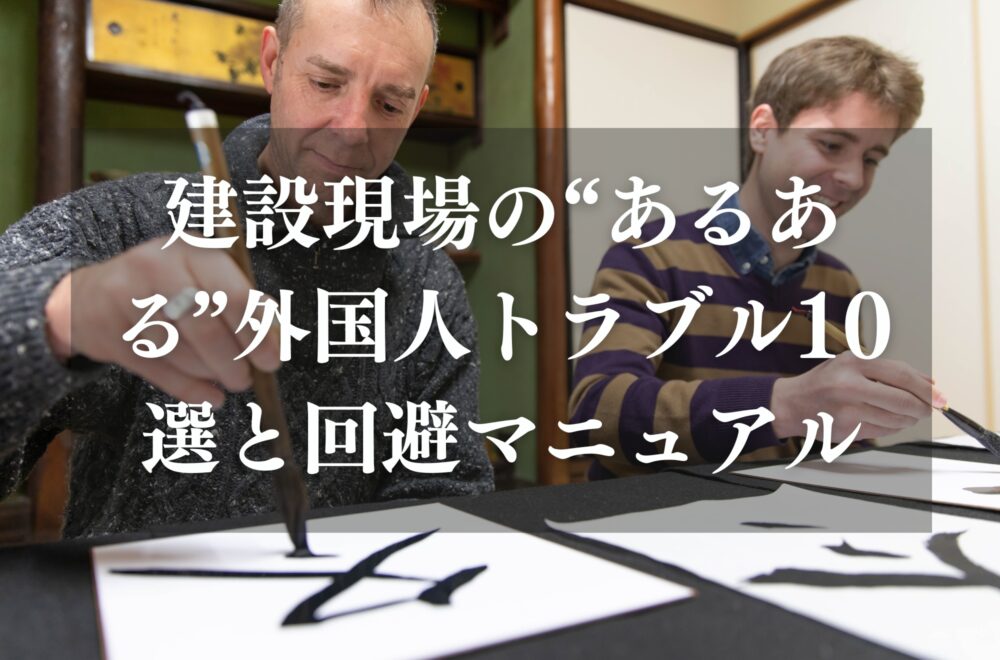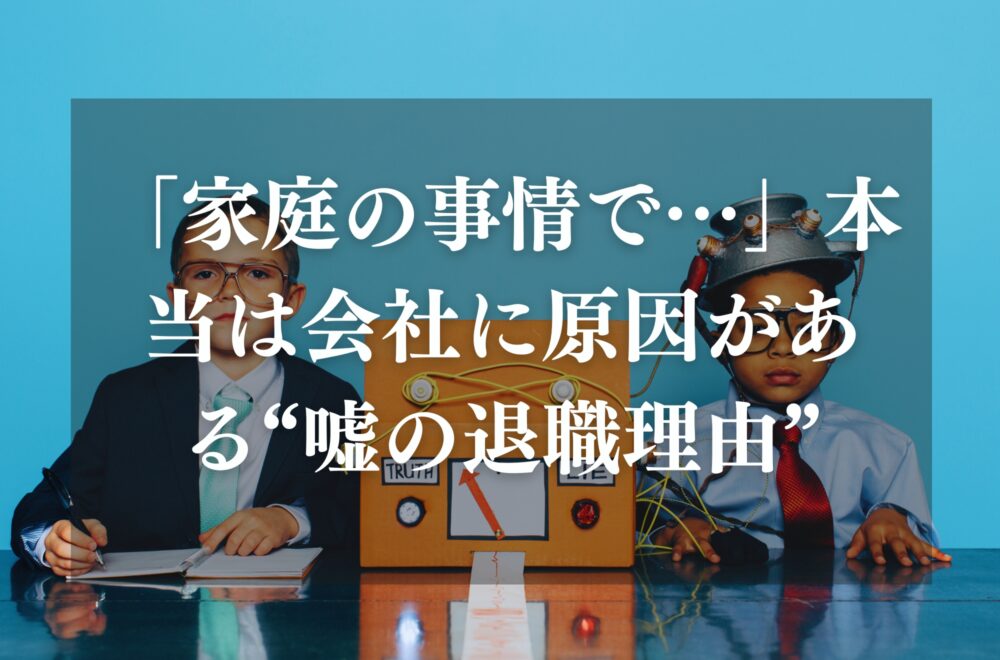左官工事で外国人がミス連発…その理由と対策
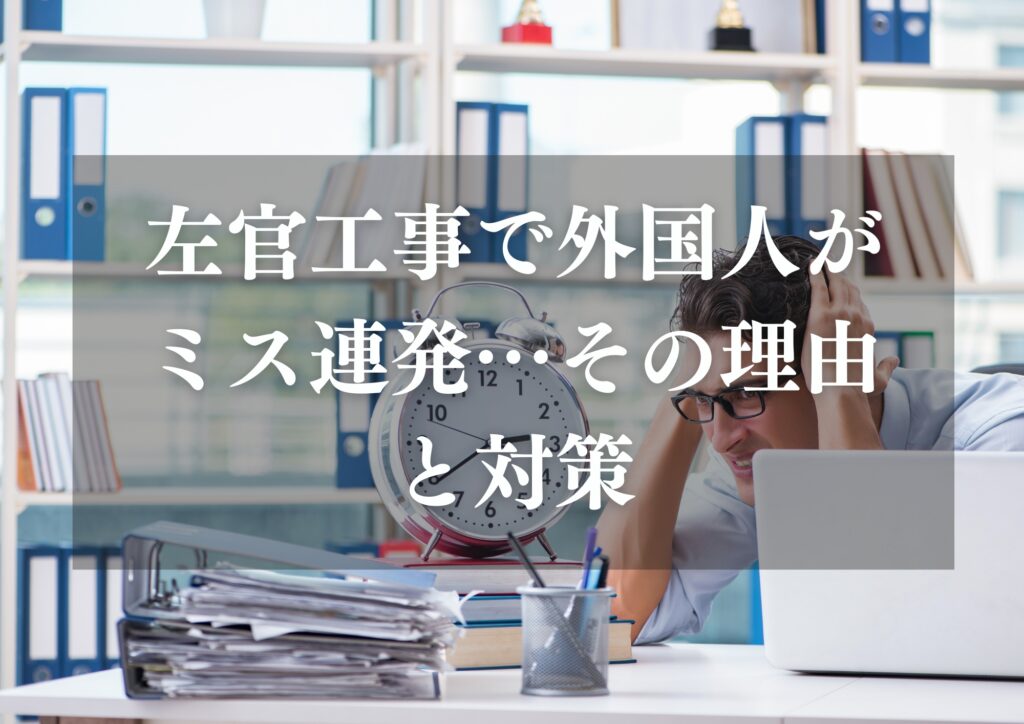
>目次(気になる記事のリンクをクリック下さい)
- ①「仕上がりが荒い」「ムラが出る」——左官で起きる典型的なミスとその原因
- ② 職長が見抜いた!コテの持ち方が間違っている外国人職人の“基礎欠落”
- ③『段取り』が通じない!配合・塗り・乾燥の連携が崩壊する理由
- ④「塗り厚がバラバラに?“感覚で覚える作業”が通じない外国人教育の限界」
- ⑤『聞けばいいのに』が通じない——報連相できない構造的な背景とは
- ⑥「ベテランの“技術見せ”が逆効果?見て覚えろ文化のすれ違い」
- ⑦「朝と同じ材料なのに違う仕上がり」——湿度・天候と外国人ミスの意外な関係
- ⑨「ある企業が実践!外国人左官職人を一人前に育てた“3ステップ教育法”」
- ⑩「日本人も驚いた!“外国人左官チーム”が生んだ高品質仕上げの裏側」
- 【まとめ】“できない”は誤解だった——外国人左官職人が戦力に変わる現場の真実
- この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武
- 多能工職人育成学校・技術研修所「職人道場紹介動画」
①「仕上がりが荒い」「ムラが出る」——左官で起きる典型的なミスとその原因

「塗った後にムラが目立つ」
「仕上がりがザラついていて、光を当てると波打って見える」
「乾いたあとで細かいひび割れが入っていた」
——こうした施工不良の報告は、外国人職人が左官作業に関わる現場で後を絶たない。
現場監督や職長たちは口をそろえて言う。
「一通りやらせてみると、基本はできている。でも、仕上がりが甘い」
「言われたことはやってる。でも、結果にムラがある」
「同じ材料を使って、同じ塗り面を担当しても、日本人と外国人で仕上がりに歴然とした差が出る」
なぜ、同じ工程、同じ道具、同じ材料で、外国人職人だけが“仕上がらない”のか?
そこには、左官という仕事特有の“感覚に頼る構造”と、外国人実習生の育成構造のミスマッチが隠されている。
左官のミスは“見た目”で即バレる
左官工事は、建設作業の中でもっとも“結果が目に見える”分野のひとつだ。
たとえば鉄筋のズレ、配線のミス、配管の継ぎ手不良などは、壁の中や床下で隠れることも多い。
だが、左官は違う。
仕上げのムラ、塗り厚の違い、コテ跡、ひび割れ、浮き、剥がれ——
これらは、完成直後に誰の目にも見える形で現れる。
そして問題なのは、それが“技術不足”として即断されやすいことだ。
「雑にやった」
「手を抜いた」
「慣れていない」
——だが、本当にそうなのか?
実際には、外国人職人は真剣にやっている。むしろ一生懸命すぎてミスになることさえあるのだ。
よくあるミス①:仕上げ面の“ザラつき”と“ムラ”
左官仕上げの代表的なミスが、「面が荒れる」「ムラが出る」ことである。
主な原因は以下の3つ。
コテ圧の不安定さ
→ 力加減が均等でないため、押しムラができる。力を入れすぎると材料がよれてしまう。
乾燥スピードへの対応不足
→ 気温・湿度により乾きが早くなっても、塗りスピードを変えられず、仕上げ前に硬化してしまう。
混練や材料配合のブレ
→ 材料の混ぜが不十分で、粒子が揃っておらず、表面に粗さが出る。
この3つは、いずれも“見て学べ”では身につかない。
理屈と感覚の両方を理解しなければ再現性が取れない技術だ。
よくあるミス②:塗り厚の不均一とコテ跡の残留
左官工事のなかでも塗り厚の不均一は特に深刻なミスとされる。
見た目のムラだけでなく、強度や耐久性にも直接影響するからだ。
このミスが起きる主な原因は次のとおり。
厚みの感覚をつかめていない
→ 5mmの厚みを「5mmとして理解している」わけではなく、「おそらくこれくらい」という主観的な判断で施工してしまう。
塗り方の手順が定着していない
→ 一度に塗りすぎたり、逆に何度も重ねて塗ることで、塗膜が厚くなりすぎたりムラが出たりする。
コテの扱い方が安定していない
→ 面に対してコテを水平に保てない、エッジが立ってしまいコテ跡が残るなど、基本動作が定着していない。
これらはすべて、「感覚」や「習熟」に依存している技術だ。
つまり、言葉では伝えきれない技術領域でのギャップが、外国人職人のミスを生んでいるのである。
よくあるミス③:タイミングのずれ
左官工事において、“塗るタイミング”“抑えるタイミング”“仕上げるタイミング”は非常に繊細である。
たとえば、気温や湿度によって乾きのスピードは大きく変わる。
それに応じて施工スピードや順番を変える必要があるが、ここにも外国人職人の“見落とし”が多い。
・乾きすぎてコテが引っかかる
・まだ柔らかいうちに抑えてしまい、表面が荒れる
・焦って手を出し、余計にムラを広げる
これらはすべて、「今がそのタイミングなのか」を判断する“感覚”のズレが原因だ。
時間と材料の状態を同時に把握する力がないと、適切な施工はできない。
なぜ外国人にこれらのミスが集中するのか?
① 左官が“感覚に頼る職種”だから
→ 手の動き、材料の状態、湿度、圧力、重心……すべてにおいて、熟練者の「手の記憶」によって成り立っている。
マニュアルや言語だけでは学びきれない。
② 教育時間が圧倒的に足りない
→ 研修で一通りの流れを学ぶが、「反復練習による定着」までには至らない。
③ 指導者が“技術を言語化できていない”
→ 「こんな感じ」「それじゃ遅い」「もっと薄く」といった抽象的な指示では、外国人職人には伝わらない。
④ 文化の違いが“確認不足”を招く
→ わからなくても「はい」と言ってしまう、質問するのを遠慮する、など“聞けない文化”がミスを助長する。
対策の第一歩は“見えない技術”を見える化すること
左官工事における外国人のミスを減らすには、
①感覚に頼らない構造をつくること
②言語化とビジュアル化をセットで行うこと
が不可欠である。
具体的には:
コテの動きや角度を動画で見せる(スローモーション付き)
塗り厚の基準をカラーボードで可視化
タイミングを図で示し、“ここから何秒後に次の工程”などと定義化
気温・湿度ごとの作業マニュアルを作成し共有する
さらに、“わかっているつもり”を排除する確認文化も重要だ。
「やる前に説明させる」「やった後に振り返らせる」など、実践型のフィードバック体制が不可欠である。
最後に:ミスは“やる気”の問題ではない
外国人職人が左官作業でミスを繰り返すのは、怠けているわけでも、やる気がないわけでもない。
“感覚で伝わる世界”に、“論理で学んできた職人”が迷い込んでいるだけなのだ。
だからこそ、教える側が言語と視覚で“感覚を構造化”し、学ぶ側が安心して確認できる環境を整えることが大切である。
左官の技術は、人の手と目と感覚で作られる。
だからこそ、それを“見えるもの”“伝えられるもの”に変えたとき、外国人職人もまた、本物の左官職人へと成長していくのだ。
② 職長が見抜いた!コテの持ち方が間違っている外国人職人の“基礎欠落”

「なぜ、同じ材料、同じ手順、同じ環境なのに、あいつだけ仕上がりが悪いんだ?」
ある日、現場でベテラン職長が首をひねった。
外国人実習生に左官作業をやらせると、どんなに丁寧に指導しても、どうしても仕上がりが荒くなる。
繰り返し練習させ、見本も見せ、言葉でも伝えた。それでも改善されない。
そんなある日、職長はついに気づいた。
「そもそも、コテの持ち方が間違っている——」
“手本を見せたのに”通じないワケ
職長はこう語る。
「俺はちゃんとコテの角度も見せたし、手のひらの位置も説明した。なのにあいつは、コテを立てすぎたり、寝かせすぎたりする」
「普通なら一度やればコツが分かるんだけど、あいつには伝わらないんだよ」
——これは、決して本人のセンスの問題ではない。
そう、問題はもっと根本的なところ、つまり“左官作業における基礎運動の欠落”にある。
なぜコテの持ち方が“できない”のか?
外国人実習生の中には、コテそのものを初めて手にする者も多い。
さらに言えば、「右手で道具を握り、左手で支持する」という“両手の使い分け”や、「対象面に対する角度調整」など、運動的な基礎習熟が圧倒的に不足している。
原因は以下のとおり:
母国に左官文化がない
→ 土壁文化がない国では、塗るという動作そのものが日常に存在しない。
手先を使う作業経験が少ない
→ 工場勤務や荷運び中心の職歴では、細かい道具の使い分けに慣れていない。
教育段階で“コテの基本動作”を教わっていない
→ 多くの送り出し機関では、安全管理や道具名は教えるが、“使い方”の実技訓練は不十分。
結果、彼らは「なんとなく見た通りにマネしている」だけで、使い方そのものは理解できていないのだ。
職長が気づいた“コテミス”の具体例
実際の現場で発見された「間違ったコテの使い方」には、以下のようなものがある:
力を入れすぎて、表面がヨレる
手首を固めすぎて、柔らかく滑らせることができない
コテを立てすぎて塗膜を削ってしまう
寝かせすぎてコテ跡が目立つ
先端ではなく、中央で押してしまい面圧が均一でない
こうした動作は、どれも“クセ”ではなく、正しい使い方を教わっていないことによる基礎欠落の現れだ。
対策①:フォームの分解と“動作の見える化”
指導側がすべきことは、まず“職人の動作を分析する”ことだ。
熟練者の動きはスムーズだが、それがなぜスムーズなのか、本人も自覚していないことが多い。
だからこそ、動画やスローモーション撮影で“手首の角度”“圧のかけ方”“道具と面の距離”などを見える化する必要がある。
さらに、教える順番も重要だ:
正しい持ち方を“静止状態”で確認する
手首の可動域を使ってコテを動かす練習をする
対象面に向かってコテを滑らせる“感覚の習得”
壁・床・角など、部位ごとの動作を分けて練習
この“構造的トレーニング”が、基礎を築く鍵になる。
対策②:“体で覚える”ための反復機会の設計
外国人職人の多くは、仕事中に練習する時間がほとんどない。
また、失敗すれば「なぜできない」と叱られ、試行錯誤をする機会すら奪われてしまう。
だからこそ、“ミスしてもよい練習機会”を意図的に設計することが必要だ。
たとえば:
施工外の余白スペースでの塗り練習
時間内で“何面こなすか”ではなく“安定性を見る”時間を設ける
毎週1回の「技能確認日」を設け、変化をチェックする
こうした時間の確保が、本人の技術的自信を育てる。
対策③:基礎を教える「専門指導者」の存在
技術指導は、職長任せにしてはいけない。
彼らには現場管理の責任もあり、マンツーマンの指導には限界がある。
そこで、職人道場のような“技能基礎に特化した育成機関”の活用が効果的だ。
ここでは、外国人に合わせた日本語+図解+実技反復を組み合わせた教育が実施されており、
たった20日間で基礎フォームの定着、施工の安定化まで実現している事例も多い。
最後に:コテの握り方から、すべては始まる
「何度教えても通じない」と嘆く前に、
「そもそも教えていなかったのは何か」を振り返る必要がある。
道具の使い方、体の動かし方、作業の意味——
それらの一つひとつが“感覚”に隠れてしまっていては、外国人職人には届かない。
だからこそ、一流の現場は「見て盗め」ではなく、「見えるようにして、伝える」ことを選んでいる。
そしてそのスタートは、まさにコテの持ち方、つまり“手の基本”からなのだ。
③『段取り』が通じない!配合・塗り・乾燥の連携が崩壊する理由

「段取り八分、仕事二分」——これは建設現場でよく聞かれる言葉だ。段取りをしっかり組めば仕事の8割は成功すると言われるほど、“準備と流れの組み立て”は職人仕事の根幹である。左官工事も例外ではない。材料の配合、現場への運搬、塗り手の動線、乾燥時間の計算、次の作業への引き渡しまで、あらゆる工程が“段取り”という見えない設計によって動いている。ところが、そこに外国人職人が加わると、なぜかその流れが頻繁に途切れる。
「先に混ぜておいてって言ったよな?」
「これ、まだ乾いてないのに重ね塗りしたの?」
「なんでそっち塗り終わってないのに次のエリア入ってるの?」
こうした声は、外国人職人のいる左官現場で日常的に飛び交うフレーズだ。実際、配合から乾燥までの一連の流れが“寸断”され、現場が混乱に陥る例は数多い。ではなぜ、外国人職人に段取りが通じないのか? そしてどうすればその連携を回復できるのか?
まず前提として理解しておくべきは、「段取り」は日本の現場文化に深く根づいた“共通認識”であり、外国人職人にとっては極めて抽象的な概念だということだ。たとえば「先に準備しておく」「相手の仕事の進み具合を見て次の工程に入る」といった判断は、形式的に教えられるものではなく、現場経験と文化的背景に根ざした感覚に近い。
外国人職人の多くは、与えられた仕事を「言われたとおりにこなす」ことを求められてきた。自主判断や流れを読む力は、育っていないことが多い。だから、「ここを塗って」と言われれば、それがどのタイミングであるべきか、材料が固まってからか、周囲との兼ね合いはどうかといった“段取り的思考”は一切働かない。
さらに言語の壁がそれに拍車をかける。「混ぜておいて」と言っても、混ぜ方の時間、回数、硬さの目安が曖昧で、伝わっていない。「乾かしてから次に」と言っても、“乾く”の判断基準が共有されていないため、自己判断で次の工程に進み、結果として仕上がりがムラになる。
段取りが通じないもう一つの理由は、時間感覚のズレだ。日本の職人文化では、次工程を見越して動くことが美徳とされる。逆に、外国人職人は「自分の持ち場が終わったら指示を待つ」という“タスク型”の思考が強い。結果、連携がなく、動線がぶつかり、乾かないまま塗る、材料が足りない、道具がない、といった事態が連鎖して起きる。
では、どうすればこの段取り崩壊を防げるのか。まず必要なのは、段取りを“見える形”で共有することである。たとえば、ホワイトボードで一日の流れを「時間軸+工程図」で描く。次に誰がどこをやるか、その後誰が何を準備するかを明示する。さらに、「準備→作業→片付け→報告」のように、“各作業の前後”も含めて流れを意識させる仕組みを作る。
また、段取りの確認タイムを導入するのも有効だ。朝礼後や作業前に、今日の流れを再確認し、「いつ・どこで・誰が・何を・なぜやるのか」を口頭で繰り返す。実習生に質問して答えさせる形式にすれば、理解度も見える。
言葉で伝わらないなら、写真や図、簡単な動画を使うのも一つの手だ。特に混練や塗布の“順番”や“適切なタイミング”は、ビジュアル化することで理解が進む。
最も重要なのは、「段取りの意味を教える」ことである。なぜ段取りを守る必要があるのか、段取りが崩れるとどうなるのかを、現場のトラブル事例とともに示すことで、実習生にも“段取り=無駄を防ぐ技術”だと理解させることができる。
最後に、段取りとは「周囲を見る力」でもある。職長が率先して周囲の作業に目を配り、「今、誰が困っているか」「どこで手が止まっているか」を教えることで、実習生も少しずつ“全体を見て動く”力を育てていける。
段取りが通じないのは、文化の違いでも言語の壁でもなく、「段取りが“教える技術”として扱われていない」ことが原因なのだ。見えないものを、見えるように。感覚で行うことを、構造で説明する。それが、段取りを通じて“通じる現場”をつくる第一歩となる。
④「塗り厚がバラバラに?“感覚で覚える作業”が通じない外国人教育の限界」

「そこ、厚すぎる」
「こっちは逆に薄すぎる」
「面がうねって見えるの、わかるか?」
左官の世界では、“塗り厚”の均一さが命だ。見た目の美しさだけではなく、強度、乾燥スピード、耐久性、最終仕上げにまで影響する。たった1ミリ、いや0.5ミリのズレが、数メートルの壁で顕著な“波”となって現れることもある。
そして、この「均一に塗る」という感覚こそが、外国人職人の教育で最も苦労するポイントの一つだ。
なぜ塗り厚が揃わないのか?
現場でよく見るのは、「一生懸命やっているのに、結果がバラバラ」という外国人職人の姿だ。コテの扱いに慣れてきて、スピードも少しずつ上がってきた。でも、ふたを開けてみれば——厚さが違う、平面が波打っている、隅が薄い、中央が盛り上がっている。
その原因は明確で、「厚さ」という感覚が、具体的に何を意味するのかが分かっていないからである。
たとえば、日本人職人に「3ミリで塗って」と言えば、ほとんどの人が“だいたい”正確な厚さで塗ってくる。これは、過去の経験、手の感覚、力の入れ具合などの“身体記憶”があるからだ。しかし、外国人職人にはその記憶がない。過去の施工経験もなければ、“塗り厚の感覚”を測る目も育っていない。
さらに言えば、ミリ単位の感覚が生活の中に存在しない国も多い。そもそも「厚さ3ミリってどれくらい?」という段階から始めなければならないのだ。
感覚頼りの教育が通じない理由
これまでの左官教育は、「見て覚える」「やりながら慣れる」が基本だった。
しかしこの方法は、文化や言語、感覚が共有できる者同士だからこそ成立する。外国人職人にとっては、“見ても何が違うか分からない”“やっても正解が分からない”という状態になりやすく、結果として「厚さがバラバラ」になる。
「このくらいでいいよ」
「もうちょっと薄く」
「さっきより少し厚く」
こうした言葉が、まるで暗号のように聞こえるのだ。
感覚を「可視化」しなければならない
対策の第一歩は、塗り厚を目で見て理解できるようにすることである。たとえば:
色分けした厚みサンプルを作り、実際に触ってもらう
“3ミリ塗り”のビフォー・アフターを並べて比較させる
コテ圧のかけ方による厚さの違いを、板サンプルで実演する
厚さゲージを使って、実際に測らせて確認する
こうした取り組みを通じて、「塗った感覚」と「数値的な結果」を結びつける練習を繰り返すことで、少しずつ“塗り厚の感覚”が育っていく。
“厚さ”を“構造”として理解させる
もうひとつ重要なのが、「なぜ厚さが重要なのか」を伝えることである。単に「薄いとダメ」「厚いと時間がかかる」という説明ではなく、工程全体の中での厚さの役割を教える必要がある。
たとえば:
厚すぎると乾燥が遅れ、次工程が遅延する
薄すぎると表面が割れやすく、再施工のリスクが上がる
塗り厚がバラバラだと、最終仕上げがムラになる
これらを図解し、「適正な厚み=現場全体の品質と効率に直結する」という意識を持たせることが大切だ。
練習は“感覚→確認→修正”の反復で
外国人職人の教育では、「できるまでやらせる」のではなく、「なぜ違うのかを一緒に考える」スタンスが求められる。
塗り厚のトレーニングでは、必ず以下の3ステップを繰り返すようにしたい。
感覚で塗る(自分の判断で施工)
測定する(厚さを実測して確認)
原因をフィードバックし、次に修正する
この「感覚と結果の照合」を繰り返すことで、技術が“経験”に変わっていく。
最後に:感覚は“教えられる”ものに変えられる
「塗り厚なんて感覚だろ?」
「数こなせば分かるよ」
そう思っていた時代は、もう終わりだ。
多国籍な現場では、感覚に頼らず、構造的に技術を教えることが求められる。
その積み重ねこそが、外国人職人を一人前に育てる最短ルートであり、結果的に現場全体の品質向上につながっていく。
塗り厚は感覚ではある。
だが、その感覚を“見える化”し、“教える技術”に変えたとき、
私たちは“通じる教育”の扉を開けることができる。
⑤『聞けばいいのに』が通じない——報連相できない構造的な背景とは

「分からなかったら聞いてって、何回も言ってるのに」
「黙ってやって、ミスしてるってどういうことだよ」
「報告もなしに勝手に工程変えるなんてありえない」
左官工事の現場で、こうした言葉が飛び交うことは珍しくない。とくに外国人職人に対して、「どうして報告・連絡・相談ができないんだ」といった不満は、職長や監督の間で慢性的なストレスとなっている。
だが、それは本当に“できない”のだろうか?
もしかしたら——“できない”のではなく、“できない構造の中に置かれている”のかもしれない。
「聞けばいい」が通じない、5つの理由
日本人の感覚では、分からないことがあれば「確認する」「相談する」は当然の行動だ。
しかし、外国人職人にとっては、その行動が“できない理由”が構造的に存在する。
語学力の壁が想像以上に厚い
→ 分からないから聞きたい。でも、何をどう聞けばいいのか分からない。質問文そのものが組み立てられない。
聞く=恥をかく、という文化背景
→ 特に東南アジア圏では、「分からない=勉強不足」「質問する=失礼」という文化が強い。
上司に話しかけることへの心理的ハードル
→ 年上・上司に対して自分から声をかけるのは“越えてはいけない壁”とされる国も多い。
怒られるかもしれない、という恐怖
→ 過去に質問して怒られた、あるいは失敗して叱られた記憶が、「話しかけない方が安全」という自己防衛に変わる。
“報連相”という概念そのものを知らない
→ 日本人が当然だと思っている“報告・連絡・相談”の重要性を、制度として教えられていない。
これらが複合的に絡み合い、「聞けない環境」「話しかけられない空気」を現場に作ってしまっている。
“沈黙”は無関心ではない——防衛反応である
外国人職人が無言で作業を進めていると、「やる気がない」「勝手なことをしている」と見られがちだ。
だが実際には、“聞けない”“分からない”“どうしていいか分からない”という状態に陥っているだけのケースが多い。
たとえば、以下のような場面でよく問題が発生する。
材料の配合比率がわからないが聞けない
作業の順番が曖昧なままスタートしてしまう
自分のミスに気づいたが、報告せずにそのまま隠してしまう
他の職人の行動が間違っていると気づいても、注意できない
これらはすべて、“報連相ができないこと”による連携ミスであり、結果として現場のトラブル、作業品質の低下、職長との信頼崩壊を招いてしまう。
対策①:報連相を“仕組み”にする
報連相を「やってほしいこと」から、「やるべきルール」に変える必要がある。
そのためには、“タイミング・方法・内容”を具体的に定義し、日常業務に落とし込むことが重要だ。
たとえば:
作業開始前・終了後に必ず職長へ声をかける(朝礼で反復)
報告する内容を3つに固定(何をした/何があった/次に何をする)
通訳を介さずとも使える“報連相チェックカード”を導入する
誤作業や変更が発生したら5分以内に報告、というルールを全体共有
このように“報連相を可視化・明文化”することで、「やった方がいい」ではなく、「やるのが当然」へと意識が変わる。
対策②:“質問しやすい”空気を作る
報連相ができるようになるには、職長や先輩職人の「話しかけやすさ」が何より重要である。
・怒らない
・否定しない
・「ありがとう」で終わる
・「聞いてくれて助かる」と伝える
この4点を意識するだけで、実習生の心理的ハードルは大きく下がる。
さらに、「困っていることある?」「他にやりたい作業ある?」など、“聞く前に、聞いてあげる”アプローチが効果的だ。
そうすれば、実習生は「話しかけてもいい人なんだ」と安心できる。
対策③:“見ればわかる”ツールの活用
言語の壁を超えるには、ビジュアル化も効果的だ。
「報連相の流れ」を図解にする
作業ごとの報告内容をアイコンで表示する
成功例と失敗例のBefore/Afterを掲示する
これにより、実習生が「何を・いつ・どうやって」報告すればいいかを視覚的に学べる。
最後に:「聞けない人」は、「聞けない環境」で黙っているだけ
外国人職人が報連相できないのは、本人の性格や能力ではない。
「聞いていいよ」と伝え、「聞きやすい場」を整え、「聞いてくれてありがとう」と返す——
その繰り返しが、やがて“報連相の習慣”をつくる。
報連相は文化であり、環境であり、組織の器である。
だからこそ、それを通じて“通じ合える現場”が生まれるのだ。
⑥「ベテランの“技術見せ”が逆効果?見て覚えろ文化のすれ違い」

「見てれば分かるだろ」
「俺の動き、ちゃんと見てたか?」
「説明なんかいらねぇよ、技術は盗むもんだ」
——これは多くの現場で繰り返されてきた、日本の職人文化を象徴する言葉である。
実際、ベテランの職人たちは、何も言わずに黙々と見本を見せ、「後は自分でやれ」と言い、
それを見て若手が必死に真似をしながら覚える——というやり取りが、ごく自然に行われてきた。
だが、このやり方が、外国人職人にはまったく通用しない。むしろ“逆効果”になっているという現場の悲鳴が、年々増えている。
「見て覚えろ」の落とし穴
外国人職人が成長しない原因として、「本人にやる気がない」「集中していない」「観察力がない」といった指摘がされることが多い。
しかし、その多くは見当違いだ。
そもそも、「見る」ことで学べる人間は、“見るべきポイント”が分かっているからこそ可能なのだ。
たとえば、コテの動き、材料の取る量、塗るスピード、抑えるタイミング、力の入れ方……
これらを一度に観察し、しかも自分の手に置き換えて実践できるのは、“予備知識”がある者に限られる。
外国人実習生の多くは、その予備知識がゼロ、あるいは限りなく少ない。
「職人の動き」を見ても、ただの“手の運動”としてしか理解できないことがほとんどだ。
つまり、「見て学ぶ」という方法自体が成立しない立場に彼らは置かれているのである。
なぜ“見せる”だけでは伝わらないのか?
身体の動かし方が違う
→ ベテランの微細な動きは、“やってきた人”にしか分からない。
目的が共有されていない
→ 「なぜそう動くのか」が分からなければ、真似しても意味をなさない。
言葉での補足がない
→ 「今のは仕上げのコテ」「あれは空気抜き」などの説明がなければ、違いが理解できない。
タイミングが見えていない
→ 「今、ここで押さえる理由」が見えていなければ、ただ“やっている”としか映らない。
結果として、実習生は「一応見たけど、何をしていたのか分からなかった」という状態で作業に入る。
当然、精度は上がらず、ミスが出て叱られる。
その繰り返しが、“自信喪失”と“学習の停止”を招いてしまうのだ。
ベテランの“無意識の技術”を言語化する
「見て覚えろ」から脱却するためには、まずベテランの持つ技術を“言語と図解”に変換する努力が必要だ。
職人道場などでは、以下のような取り組みが進んでいる。
コテの角度や手首の動きをスローモーションで撮影し解説
「このタイミングで抑える理由」を図で示す
材料の取り方を量で示す(例:こぶし1つ分=300gなど)
「やってはいけない例」との比較で理解を促す
こうすることで、実習生は“なぜそうするか”という思考と、“どうやるか”という動作のつながりを理解できるようになる。
実習生は“見えた動き”より“説明された意味”で学ぶ
日本人は「見て覚える」文化で育っている。
一方で、外国人実習生の多くは「説明を受けてから理解する」教育を受けてきた。
つまり、両者の“学習スタイル”が根本的に違うのだ。
職長や職人が「教えたつもり」になっていても、実際には“見せただけ”で、説明も確認もフィードバックもされていないことが多い。
結果、実習生は「分からないけど、聞いても怒られるから、とりあえずやる」→ミス→叱られる、の悪循環に陥る。
“見せる+言う+やらせる”の三位一体教育が鍵
効果的な教育は、以下の3ステップで構成されるべきだ。
見せる(動作の実演)
→ できればスローモーション、もしくは分割して見せる。
言う(動作の意味を解説)
→ 「なぜこの角度か」「なぜこの順番か」をセットで説明。
やらせる(実践)+フィードバック
→ 本人にやらせて、何が違っていたかをその場で修正。
この繰り返しが、実習生の“理解”と“再現力”を育てていく。
最後に:伝わる技術は、現場の財産になる
技術を“見せる”だけでは不十分。
“見せて伝える”ことができて初めて、それは現場の共有財産になる。
日本の職人文化には誇るべき精度と伝統がある。
だからこそ、その技術を“見える化し、言葉にして、次世代に伝える力”が、これからの多国籍現場にとって不可欠となるのだ。
外国人職人は「見えない」からできないのではない。
「説明されていない」から、理解できないだけなのだ。
それを変えるのは、私たちの“教え方”である。
⑦「朝と同じ材料なのに違う仕上がり」——湿度・天候と外国人ミスの意外な関係

「朝はうまくいってたのに、午後になったらムラが出た」
「同じ配合なのに、なぜか硬くなってる」
「なんで夕方になると仕上がりが悪くなるんだろう……」
左官工事において、材料・道具・工程が同じでも、「仕上がり」が変わることは日常茶飯事である。
その最大の要因のひとつが、天候と湿度の変化だ。
そしてこの“目に見えない要因”こそが、外国人職人の連続ミスを引き起こす盲点となっている。
■ 左官工事における“湿度”と“天候”の影響とは?
左官作業は、水・セメント・砂などの「湿式材料」を使用し、乾燥・硬化を経て仕上がるプロセスを持つ。
したがって、空気中の水分量=湿度、気温、風速、日射の有無などが、乾燥スピードに大きく関係する。
たとえば:
湿度が低い日(乾燥が早い)
→ 表面だけが先に硬化し、内部の水分が閉じ込められる。結果、割れ・浮きの原因に。
湿度が高い日(乾燥が遅い)
→ 乾燥が追いつかず、仕上げに入るタイミングが読めない。
日中と夕方での温度差
→ 同じ材料でも、塗りやすさや硬化の始まりが異なる。
これらを把握して施工に反映できなければ、「朝と同じことをしているのに仕上がりが違う」という現象が頻発する。
■ 外国人職人が“気候変化”を読み取れない理由
「同じことを繰り返す」教育で育っている
→ 材料の配合や塗り方を“固定された手順”として記憶する傾向があり、変化に対応する柔軟性が育っていない。
湿度・温度の重要性が理解されていない
→ 自然条件の変化が作業に及ぼす影響について、基礎教育で学ぶ機会がない。
気候の変化に敏感な感覚が育っていない
→ ベテラン職人は「風が変わった」「空気が重い」といった感覚で判断するが、外国人職人にはその経験がない。
報告・相談の習慣がない
→ 材料の状態が違う、乾きが早いと感じても、それを伝えたり質問する習慣がないため、ミスを防げない。
つまり、“気候に合わせて変える”という日本的な現場勘が共有されていないのだ。
■ よくある“湿度が原因”の失敗事例
乾きすぎて、抑えるタイミングを逃す
→ 結果、表面がざらつく・粉が出る・ひび割れ。
仕上げ中に材料が固まり始める
→ 硬化とともにコテが引っかかり、仕上がりに線が残る。
雨天後の高湿度状態で塗装し、乾燥不良
→ 表面が固まっても中が乾かず、後から浮き・剥がれの原因に。
■ 対策①:「気候対応マニュアル」を共有せよ
外国人職人に対し、“環境に応じた対応”を感覚ではなく言語化して教える必要がある。
たとえば:
気温30℃超のとき:材料を少し柔らかく配合/塗り面を小分けに施工
湿度80%超のとき:送風機を併用/乾燥確認をしてから次工程へ
雨の日翌朝:吸水性の高い下地への施工は避ける or プライマー強化
これを“気温別・湿度別・時間帯別”にパターンとして整理し、簡単な表や図解にして共有すれば、誰でも“読み替え”が可能になる。
■ 対策②:「異変報告」を習慣化する
「いつもと違う」を察知したら、必ず報告するという習慣づけが必要だ。
例:
「材料が重いです」
「乾きが早いです」
「コテが滑りにくいです」
こうした“微妙な違和感”を発信する文化がなければ、現場は問題が起こるまで気づけない。
実際に、外国人職人が「いつもと違う」と感じていたのに言えず、現場全体の仕上がりに影響した例も多い。
■ 対策③:気象データの活用と教育
スマホや現場用タブレットで、当日の気温・湿度・風速を毎朝確認するルーチンを作る。
さらに、それに応じた作業の“変更点”を明確にすることで、「なぜ今日は違うか」が腹落ちする。
この習慣を繰り返すことで、「天候によって変える」という考え方が徐々に浸透していく。
■ 最後に:「感覚」から「判断」へ
ベテラン職人は気候を“肌で感じて”仕事を変える。
だが、外国人職人には、その“肌感覚”がない。
だからこそ、私たちはそれを“見える化”し、“判断できる仕組み”に落とし込む必要がある。
「朝と同じ材料なのに、違う仕上がり」——
その正体は、材料ではなく“空気”にある。
そして、それを読み解く力こそが、外国人職人を“本物の職人”に近づける鍵になるのだ。
「言ったよな?ちゃんと通訳した?」
「いや、言いましたけど……たぶん伝わってます」
現場で起きる施工ミス。その原因が「通訳の誤訳」だったと判明したとき、指導者の多くは驚く。そして同時に、深い無力感を抱える。「通訳がいても伝わらない」——その現実は、外国人職人との現場運営において避けて通れない壁となっている。
左官工事は、専門用語の宝庫である。「塗り付け」「抑え」「返し」「浮かし」「しごき」「仕上げ」……これらの言葉は、熟練職人同士なら通じるが、一般的な語学教育では決して触れない言葉ばかりだ。つまり、通訳がいても伝わらないことが多いのは当然とも言える。
■ よくある「通訳ミス」された左官用語トップ10
職人道場が過去にヒアリングした実例から、特に誤訳・誤解が多かった左官用語をランキング形式で紹介する。
第1位:「抑える」→「押す」「強く当てる」と誤訳
本来は“表面を均す仕上げ工程”だが、力を込めて押しつける動作と誤解され、ムラが発生。
第2位:「しごく」→「こする」「削る」と誤訳
余分な材料を均す工程を、材料を“除去する”意味で捉えられ、必要以上に塗りを取ってしまう。
第3位:「浮かし」→「浮かべる?意味が曖昧」
下地との間に空気を残さず滑らせる動作だが、物理的に“浮かす”動作と誤解される。
第4位:「返す」→「戻る」と誤訳
コテの裏面を使う“返し塗り”が、動作の“巻き戻し”と誤解され、動作に支障が出る。
第5位:「中塗り」→「真ん中だけ塗る?」
「下塗り→中塗り→上塗り」の意味が伝わらず、範囲のことと誤認する実習生も多い。
第6位:「コテ跡」→「道具の跡?それが何?」
“跡を残すな”という指示の意味が通じず、「道具を使えば跡はつくのが当然」と判断されてしまう。
第7位:「均す(ならす)」→「終わらせる」と誤訳
“高さを整える”という意味が、「作業を終わらせる」と勘違いされ、途中で止めてしまう例あり。
第8位:「厚みを出す」→「材料を多く使う?」
適正な厚みを保持するという意図が伝わらず、ひたすら多く盛り付けてしまう。
第9位:「練りが甘い」→「味の話?」と混乱
モルタルの混ぜ不足を指す言葉だが、文字通り“甘い”と捉えて意味不明に。
第10位:「こて返し」→「道具を交換する」と誤訳
“コテの面を反転させて塗る”技術が、道具を別のものに変えるという指示と取られてしまう。
■ 通訳の限界と、“専門用語バリア”の実態
上記のような誤訳が起きる背景には、以下のような要因がある:
通訳が建設現場経験者ではない
→ 多くの通訳者は“日常会話レベル”の語学には長けていても、専門知識は未経験。
左官用語に相当する表現が母国語に存在しない
→ コテを使う文化自体がない国では、動作を説明する言葉が存在しない。
通訳自身も意味を曖昧に理解したまま訳してしまう
→ 「なんとなくそれっぽく」訳してしまい、ニュアンスが大きくずれる。
一度誤訳が浸透すると、間違ったまま定着してしまう
→ 職人同士で誤った理解を共有し、“現場用語”として根付いてしまう。
■ 対策①:「現場用語ビジュアルブック」の活用
誤訳を防ぐ最も効果的な手段は、“言葉を減らす”ことである。
言葉の代わりに使えるもの——それが写真・動画・イラスト・図解だ。
たとえば:
「抑える」は、仕上げ直前の“表面を押さえる”動作を動画で見せる
「しごき」は、余分なモルタルをコテで滑らせる過程を連続写真で表現
「返し」は、コテの表裏を使った動作をスローモーションで示す
こうした“動作を見せる辞書”のような教材が、通訳を介さずに意思を伝える強力な武器になる。
■ 対策②:現場で“使ってはいけない日本語”を定義する
通訳や外国人職人にとって特に混乱する表現(例:「これ、いい感じにやっといて」「ちょっと厚めに」)を整理し、“曖昧禁止ワード集”として全現場で共有する。
そしてその代わりに、「具体的な数値」「時間」「材料量」で指示を出す文化を育てる。
■ 対策③:通訳も“現場の一員”として教育する
通訳を“翻訳機”ではなく、“現場理解者”に育てる取り組みも重要だ。
週1回の現場同行+施工見学
左官職長によるミニ講座(用語・工程の意味など)
通訳向けの専門用語テストの導入
こうすることで、通訳が「言葉」だけでなく「意味」まで含めて伝えられるようになる。
■ 最後に:通訳に頼らず、“見える言葉”で伝える時代へ
外国人職人の育成で最大の障壁は、実は“翻訳の限界”にある。
通訳が間違えれば、職人も間違える。
伝えたつもりでも、全く違う指示として実行される。
その結果、ミスが続き、信頼が崩れ、現場が荒れる。
だからこそ、私たちは「言葉が通じること」に依存せず、「伝え方そのものを変える覚悟」が求められている。
それが、未来の多国籍現場で信頼と品質を両立させるための第一歩となるのだ。
⑨「ある企業が実践!外国人左官職人を一人前に育てた“3ステップ教育法”」

「正直、最初は無理だと思ってたんです」
こう語るのは、神奈川県内にある中堅建設会社の左官部門責任者だ。
ベトナムから来日した実習生2人が、現場に入って3日で仕上げミスを連発。
コテは滑らず、塗り厚はバラバラ、報告・相談もなし。職長たちは困惑し、現場の雰囲気も悪化した。
だが、そんな2人が半年後、ベテランと肩を並べるレベルにまで育った。
その成功のカギが、“3ステップ教育法”だった。
■ ステップ①:技能の“構造理解”から始める
この企業が最初に取り組んだのは、「感覚を教える」のではなく、「構造を理解させる」ことだった。
左官作業を“工程単位”で分解
→ 下塗り、中塗り、仕上げの役割、材料の種類、塗る順番などを、フローチャートと写真で視覚的に整理。
材料・道具を“意味付き”で教える
→ ただの道具名ではなく、「このコテは厚塗り用」「この練りは水分量の調整が目的」といった“なぜ”をセットで指導。
動画教材を活用して、繰り返し確認
→ 実際の現場映像をスロー再生し、作業の意図をその都度説明。理解が深まるまで繰り返した。
この段階では、まだ実際の作業には入らせず、「頭で分かる」「言語で説明できる」ことを重視した。
まさに、“手を動かす前に、頭を動かす”フェーズである。
■ ステップ②:ミスしてもいい“練習現場”を整備
次に実践されたのは、「安心してミスできる環境づくり」だった。
この会社では、使用済みの合板を利用した“練習壁”を倉庫内に設置。
毎朝30分、作業前にそこで左官練習を行った。
“一発勝負”ではなく“反復練習”
→ 「今日のテーマはコテ圧の安定」など、目的を決めた練習を毎日続けた。
職長が横について指導しない
→ あえて“自分のペース”で取り組ませ、終わったあとに動画を見ながら一緒に振り返るスタイル。
「できた部分」に着目したフィードバック
→ ミスを責めず、「この厚みは安定してきたね」「今日は昨日より速くなった」などの前向きな評価を徹底。
この環境が、彼らの“挑戦する姿勢”を育て、「失敗しても報告する」「聞いてみる」文化を根づかせた。
■ ステップ③:現場配属後も“毎日5分”の振り返り面談
そして実習生が実際の現場に入ったあとも、この企業は“育成の手を緩めなかった”。
毎日の終業後、職長が実習生と5分のフィードバックタイムを実施。
内容は非常にシンプルだ。
今日一番うまくいった作業は何か
分からなかったこと、困ったことはあったか
明日はどの作業をもう一回やってみたいか
この“質問と対話の習慣”が、実習生の“考える力”と“主体性”を育てた。
そして何より、「自分は見てもらっている」「評価されている」という安心感が、技術向上の土台になった。
■ 結果:半年で“使える戦力”に育った
この3ステップを徹底した結果、2人の外国人実習生は半年後、以下の成果を上げた。
一人で下塗りから仕上げまでの基本作業を任せられるようになった
仕上がりのムラが激減し、やり直しがゼロに
他の外国人職人への簡単な指導もできるようになった
現場での報連相がスムーズになり、職長の負担が大きく軽減された
担当職長は言う。
「教え方を変えれば、ちゃんと育つ。今まで“わからないやつ”って切り捨ててたのは、結局こっちの都合だったんだなって思います」
■ ポイントは“技術”よりも“伝え方の構造化”
この成功事例が教えてくれるのは、外国人を育てるには“技能伝達の仕組み”を見直す必要があるということだ。
・“見て覚える”から“構造で伝える”へ
・“ミスを減らす”から“試行錯誤を許す”へ
・“叱る指導”から“対話による定着”へ
教育対象が変われば、教育方法も変わるのは当然だ。
そしてその変化を柔軟に受け入れ、仕組みとして整えた企業だけが、“育つ現場”を実現している。
⑩「日本人も驚いた!“外国人左官チーム”が生んだ高品質仕上げの裏側」

※この物語はフィクションですが弊社が経験したことをモデルに作成しております。
「これ、本当にあいつらが仕上げたのか?」
現場監督の目が、仕上がった壁をじっと見つめていた。
見事なまでに均一な塗り厚。コテ跡は一切残っておらず、光を当てると面全体が美しく反射する。
下地から仕上げまで、寸分の狂いもない左官面——それを手がけたのは、外国人職人4人で構成された左官チームだった。
かつて「何をやらせてもムラだらけ」「指示しないと動けない」と言われた彼らが、どうしてここまで成長できたのか。
そこには、“技能”だけではない、“環境と関係性の変革”があった。
■ 外国人だけの左官チーム、その誕生
このプロジェクトは、ある住宅建設会社の社内実験から始まった。
背景には、「外国人を単なる補助作業員にしていては、いつまでも育たない」という経営陣の危機感があった。
「だったら、最初から最後まで外国人職人だけで1面を仕上げさせてみよう」
そうして立ち上がったのが、ベトナム、ミャンマー、インドネシア出身の実習生4名による“外国人左官専属チーム”だった。
■ 実践された3つのチーム戦略
成功の裏には、明確な教育と運営戦略が存在していた。
① 明確な役割分担で“混乱”を防ぐ
「誰がどの段階を担当するか」を、固定ポジション制にすることで、責任と集中力を高めた。
A:配合・運搬担当(材料と時間管理)
B:下塗り専門(塗り厚と段差処理)
C:中塗り・しごき担当(均しの要)
D:仕上げ専門(最終面の精度・コテ跡処理)
この固定制により、「全員が全部やる」から「自分の専門を極める」教育にシフト。結果、動きに無駄がなくなり、技能の定着が早まった。
② 作業前と後に“必ずレビュー時間”
朝礼時と終礼時に、「今日の重点作業」と「昨日の振り返り」を全員で共有。
・昨日のミスは何か?
・成功した点は?
・なぜそれがうまくいったのか?
・明日はどこを注意する?
この5分間の習慣が、思考と言語による技能の“内面化”を促した。
③ 日本人職人を“サポーター”に役割変更
日本人のベテラン職人は、直接教えるのではなく、“サポート役”に徹した。
質問があれば答える
材料や工程で判断に迷ったら助言
口出しではなく、提案ベースでアドバイス
この姿勢が、「自分たちが主役だ」という自覚を芽生えさせた。結果、責任感が芽生え、作業への集中力と連携が飛躍的に向上した。
■ 結果:評価されたのは“技術”だけじゃない
実際に外国人チームが担当した物件の完成後、現場監督と顧客から出た評価はこうだった。
「表面の平滑性がすばらしい」
「どの面を見てもムラがない」
「施工中も現場が静かで、動きに無駄がなかった」
「一人ひとりが自信を持って作業しているのが分かる」
つまり評価されたのは、技術そのもの以上に、“現場の空気と組織力”だったのだ。
■ この成功が示す2つの本質
① 外国人職人も“プロ意識”を持つようになる
「できない」から「やらせない」では、職人には育たない。
「信じて任せる」「支える構造を作る」ことで、彼ら自身が“職人である”自覚を持つようになる。
② 技能は“関係性”の中で育つ
厳しく叱られ、失敗すればすぐ怒鳴られる——そんな現場では、人は育たない。
支えられ、尊重され、期待される関係性の中で、技能は飛躍的に伸びる。
■ 最後に:“育つかどうか”ではなく、“育てる仕組みがあるかどうか”
外国人職人のポテンシャルは、決して日本人に劣らない。
違うのは、育て方。
育たないのではなく、育つ仕組みがなかっただけなのだ。
この“左官外国人チーム”の成功は、単なる一企業の成果ではない。
これは、日本の建設業界全体が「多様性の時代にどう職人を育てるか」という問いに対する、明確な答えの一つである。
任せれば、応える。
支えれば、伸びる。
尊重すれば、信頼が返ってくる。
そんな当たり前を、私たちがようやく“職人教育の未来”として受け入れるときが来たのだ。
【まとめ】“できない”は誤解だった——外国人左官職人が戦力に変わる現場の真実

「厚さがバラバラ」「ムラが出る」「段取りが通じない」「報告がない」——
左官工事において外国人職人が犯すミスは、確かに数多くある。
だが、それらは“本人の能力”や“やる気”の問題ではない。
その多くが、教え方・伝え方・仕組みの側にあるという現実を、私たちはそろそろ受け入れる時期にきている。
このブログでは、ミスの具体例を一つひとつ深掘りし、なぜそれが起きるのか、どうすれば防げるのかを明確にしてきた。
そこから浮かび上がるのは、感覚で伝える文化の限界と、構造で教える仕組みの必要性である。
ベテランの“見て覚えろ”は、外国人には通じない。
「聞けばいいのに」は、そもそも“聞ける空気”がなければ成り立たない。
コテの持ち方、配合の順番、乾燥の見極め——それらを言葉と図と反復で教えていく。
そして、「失敗してもいい」という環境があって初めて、人は自ら学び、技術を身につけていく。
最終的には、日本人も驚くような品質を出す外国人左官チームまで誕生した。
その裏には、感覚から構造へ、叱責から支援へ、作業者から主役へのパラダイムシフトがあった。
“育てる”とは、ただ教えることではなく、“信じて仕組みを整えること”だったのだ。
この事例が教えてくれるのは、「できる人を探す」のではなく、「できる環境をつくる」ことこそが最重要だということ。
多国籍時代の現場でこそ、教える側の変化が問われている。
外国人左官職人が真の戦力となるかどうか——その鍵は、現場ではなく、我々の教え方にある。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。