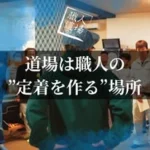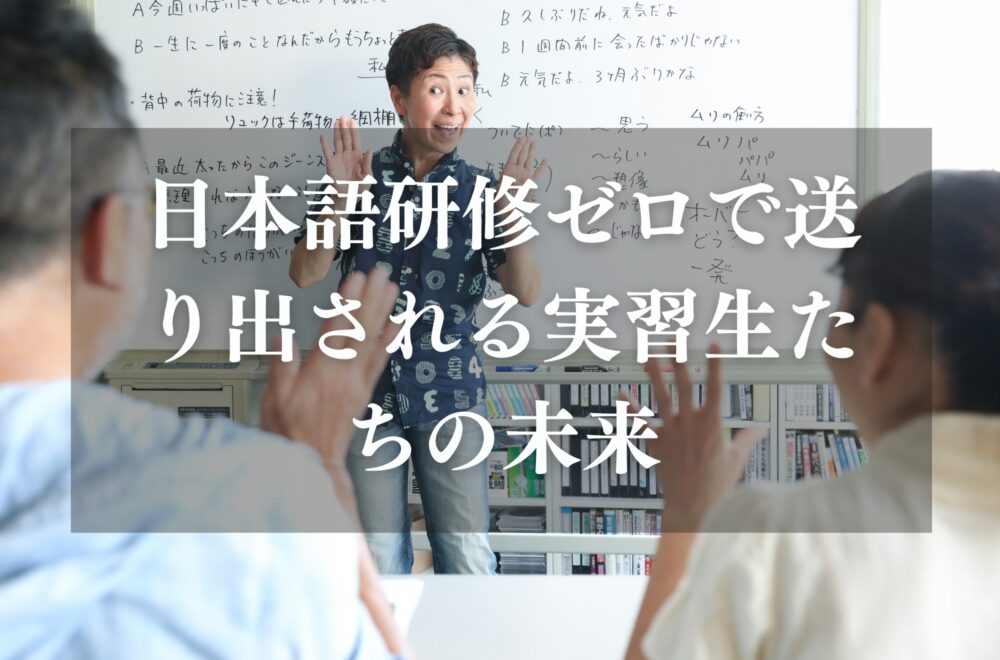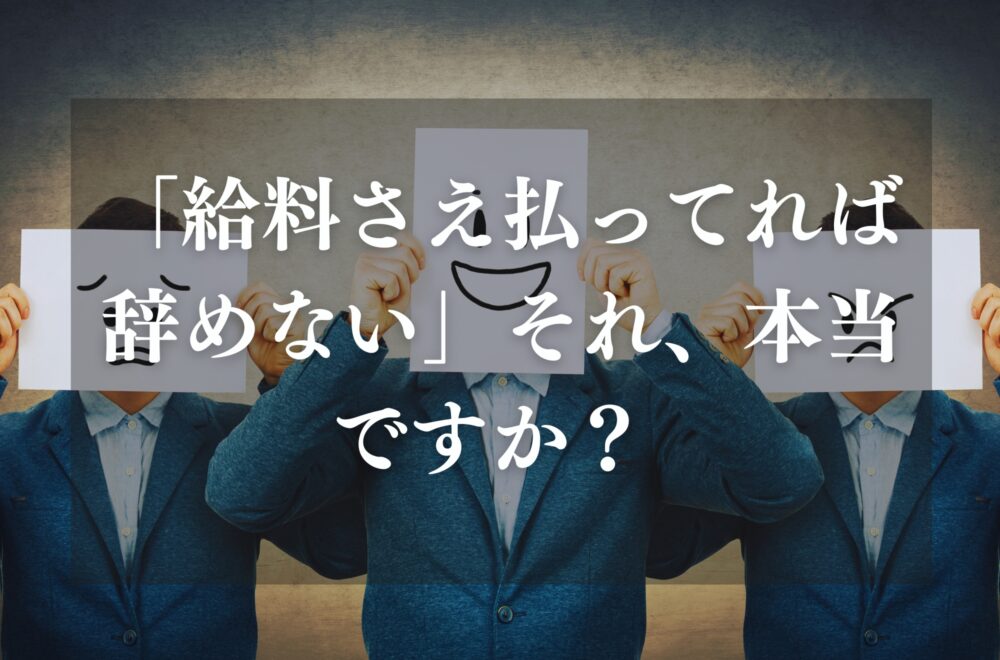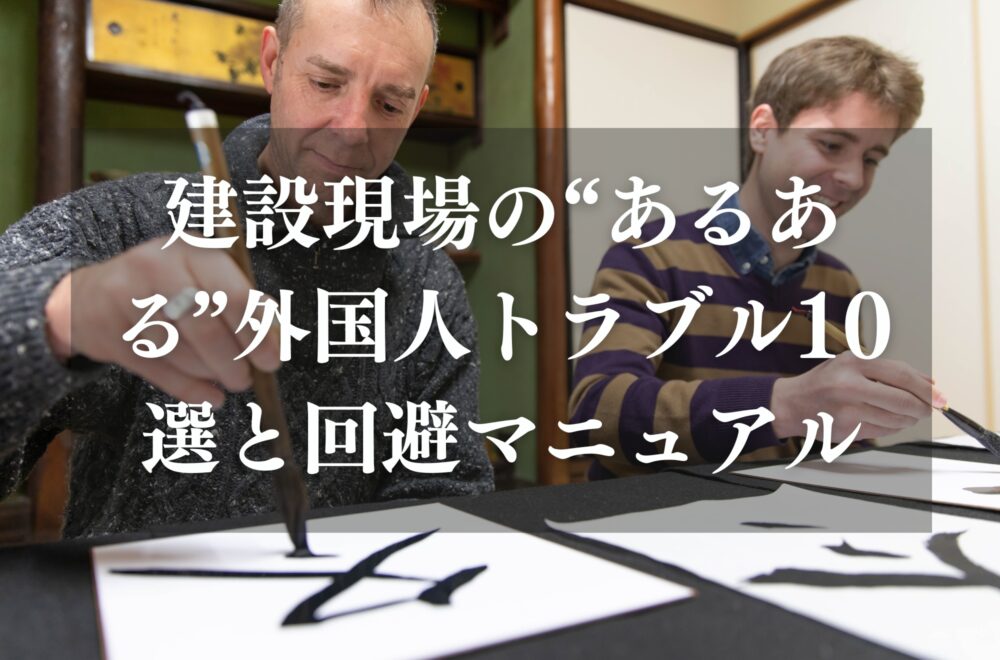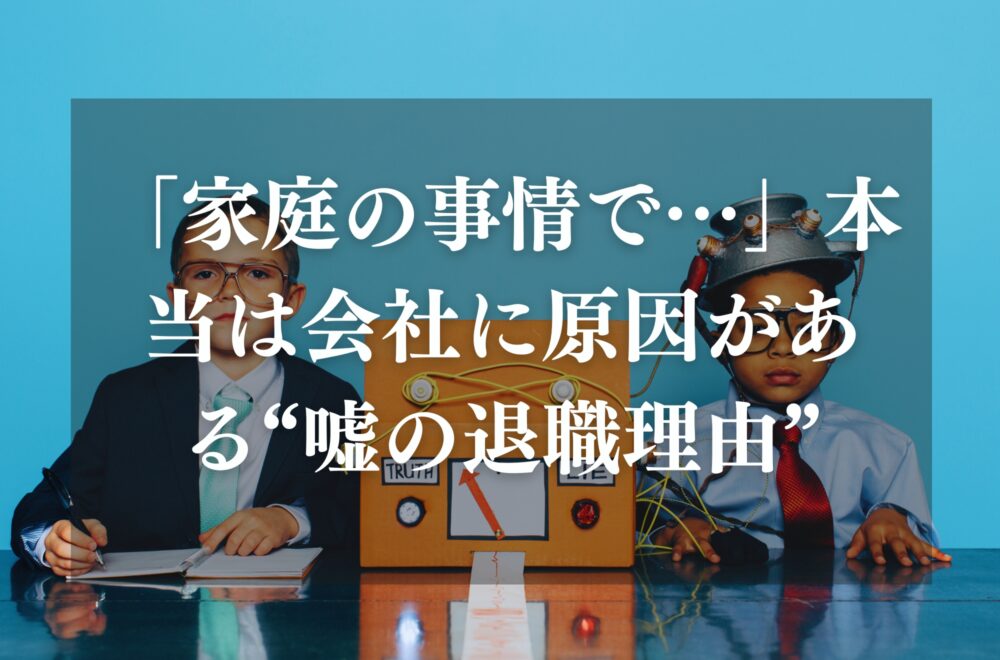「家庭の事情で…」本当は会社に原因がある“嘘の退職理由”
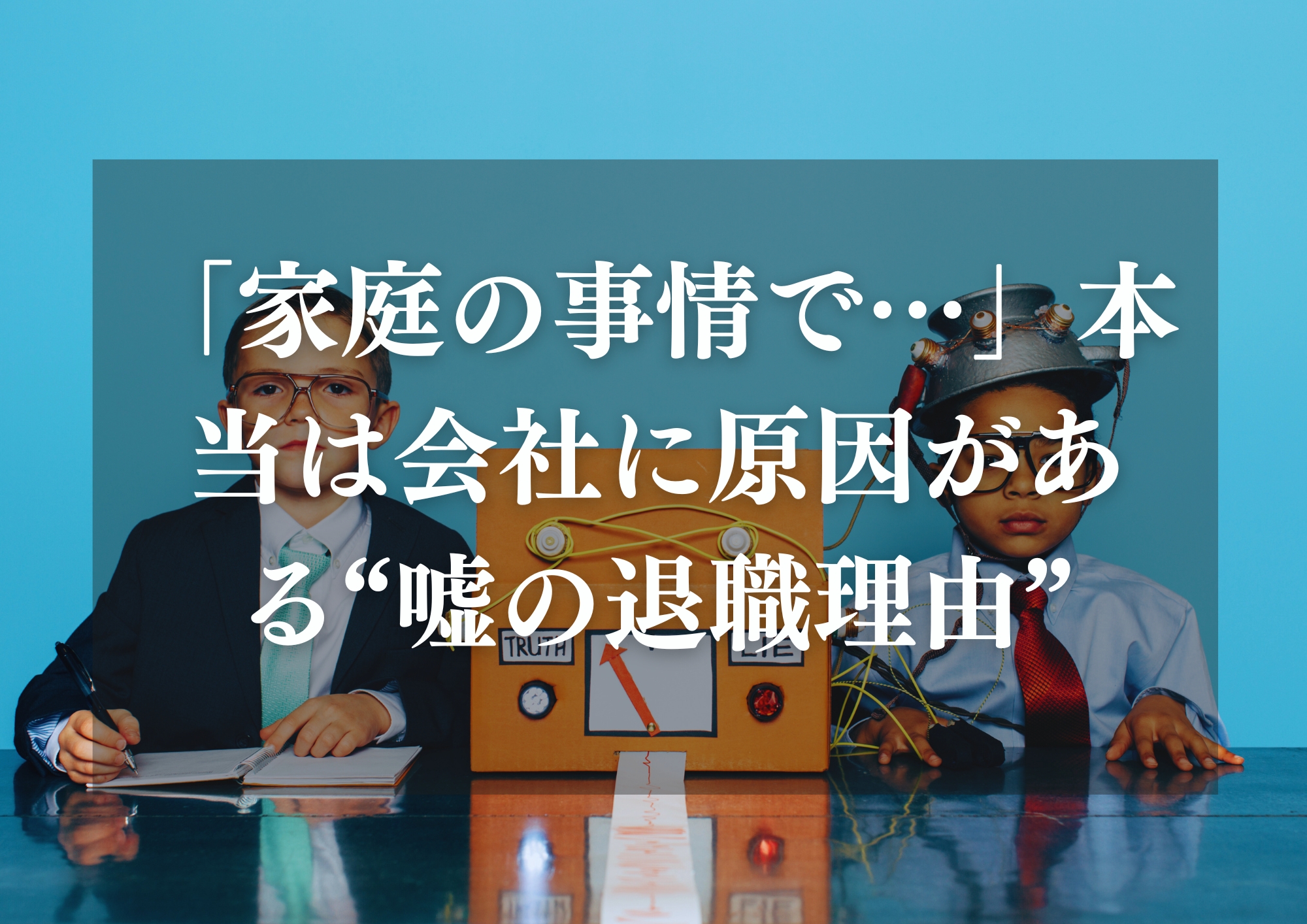
目次はこちらです気になる記事をクリックして下さい
- ①「家庭の事情」は本当か?退職理由に潜む本音を読み解く
- ②辞める理由を「家庭」にすり替える背景:なぜ会社の問題を隠すのか
- ③現場の声:若手が語らない“本当の理由”
- ④管理職が見落としがちな「会社に潜む退職の種」
- ⑤厳しすぎる上下関係と人間関係の摩擦:居場所を失う若手
- ⑥評価されない現場、見えない将来像が生む無力感
- ⑦「辞める=甘え」ではない!管理職が気づくべき時代の変化
- ⑧「家庭の事情」の裏にある心のサインを見逃さない方法
- ⑨辞めた人を責めるな:本音を話せる職場づくりが離職を防ぐ
- ⑩退職理由の“嘘”をなくすために管理職がやるべきこと
- 【まとめ】
- この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武
- 多能工職人育成学校・技術研修所「職人道場紹介動画」
①「家庭の事情」は本当か?退職理由に潜む本音を読み解く

「家庭の事情で退職します」――人事担当や管理職として、一度は耳にしたことのある言葉ではないでしょうか。しかしその裏には、単なる家庭の事情では済まされない、本当の理由が隠されていることが少なくありません。実際、厚生労働省の調査では、退職理由の建前と本音が食い違っているケースが非常に多いことが明らかになっています。なぜ、社員は本当の理由を隠し、「家庭の事情」と言わざるを得ないのでしょうか。
そこには、辞める人なりの“気遣い”や“諦め”が存在します。若手社員にとって、会社の環境や人間関係に不満があっても、「それをはっきり言うのは難しい」と感じるのは自然な心理です。特に建設業界や職人の世界では、上下関係の厳しさや「根性で続けるのが当たり前」という空気が強いこともあり、退職を決意した若手が「自分の弱さだと思われたくない」という思いから、本音を隠しがちです。
一方、管理職や経営陣は、こうした“表向きの理由”をそのまま鵜呑みにしてしまいがちです。しかし、それではいつまで経っても「なぜ辞めるのか」という課題の本質は見えません。辞めた人の本音を正しく読み解けなければ、結果として次の若手も同じ理由で辞めるという負のスパイラルが続いてしまいます。
また、辞める側にとっても「家庭の事情」という言い訳は、自分を守るための防御線です。「現場がきつい」「上司が怖い」「給料が上がらない」など、会社に直接関わる問題は、伝えれば角が立つし、逆に自分が悪者にされかねない。それなら「家庭の事情」を理由にして、無用な摩擦を避ける方が得策だと考えてしまうのです。
この構図の背景にあるのは、企業風土の問題です。「辞めるのはお前が悪い」とする風潮がある職場では、本音を打ち明けることが許されない空気が漂っています。管理職として本当に問われるのは、この空気に気づき、変えていく力です。辞めた人が「家庭の事情」と口を閉ざすとき、それは企業への最後のメッセージとも言えるのです。
ここから先、ブログの残りの見出しでは、「なぜ若手が本当の理由を隠すのか」「その嘘の裏にどんな職場の問題が潜んでいるのか」「管理職は何をすべきなのか」をさらに深く掘り下げていきます。辞める人の言葉を鵜呑みにしないこと、それが管理職に求められる第一歩なのです。
②辞める理由を「家庭」にすり替える背景:なぜ会社の問題を隠すのか

「家庭の事情で辞めます」――その言葉の裏には、実は職場に潜む問題が隠されていることが少なくありません。なぜ若手社員は本当の理由を口にせず、「家庭の事情」というオブラートに包んだ言い訳を選ぶのでしょうか。その背景には、職場の空気、会社の体質、そして辞める側の心の葛藤が複雑に絡み合っています。
まず、「家庭の事情」は嘘の理由ではなく、いわば“最後の逃げ道”として選ばれやすいのです。職場に問題があったとしても、それを真正面から指摘するのは勇気が必要です。特に建設業界のように上下関係が厳しい業界では、若手が「辞めたい理由を正直に話すのは裏切り行為だ」と感じてしまうこともあります。上司に面と向かって「働き方や人間関係が辛い」と言えば、それはすなわち上司や会社への批判になる。そんな空気の中では、若手が口を閉ざすのも無理はないのです。
もう一つの理由は、「辞める自分を正当化したい」という心理です。職場の問題を口にすることは、自分が「被害者」として見られることを意味します。しかし、若手の多くは「結局、自分が続けられなかっただけ」と感じてしまうものです。だからこそ、家庭の事情という“第三者の事情”を理由にすることで、自分を責めずに退職を正当化しようとするのです。
また、管理職や人事担当者の側も、「家庭の事情なら仕方ない」と受け止めやすい心理があります。職場の問題で辞められると、それは管理職自身の責任にもなる。しかし家庭の問題であれば、「それなら仕方ない」と納得できる。こうした甘えの構造が、退職理由の“嘘”を許容する空気をつくり出しているのです。
しかし、この嘘の理由は企業にとって大きな危険です。家庭の事情にすり替えられた「本当の理由」を見過ごすと、職場の問題は放置されたままになります。結果として、同じ問題で次の若手がまた辞めるという負の連鎖が続くのです。管理職として本当に大切なのは、「家庭の事情で辞めた」という言葉をそのまま受け入れないこと。本音を引き出すための仕組みや信頼関係を築くことが、問題の根本解決につながります。
この後の見出しでは、「若手が語らない本当の理由」「管理職が見落とす離職のサイン」などをさらに深く掘り下げていきます。家庭の事情という言葉に隠れた現場の真実を見逃さないことこそ、管理職の真の役割なのです。
③現場の声:若手が語らない“本当の理由”
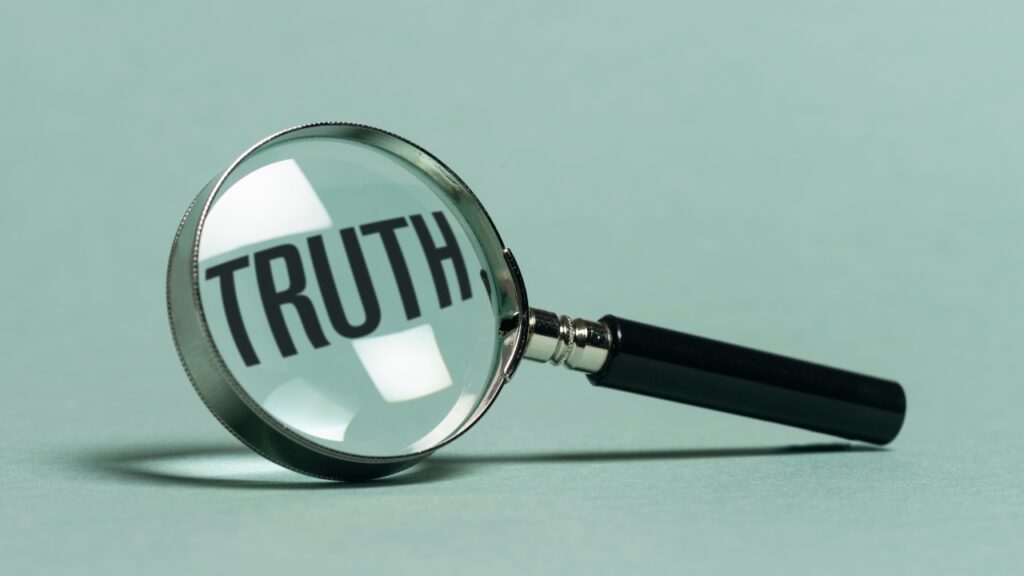
「家庭の事情で辞めます」――若手社員がこう口にするとき、その裏には口には出せない“本当の理由”が隠されています。管理職や人事担当者として、その声なき声に耳を澄ませることは、離職の連鎖を断ち切るために欠かせない視点です。実際に、若手が心の奥に隠している“本当の理由”とはどんなものなのでしょうか。
よく聞かれるのは、まず「職場の人間関係のストレス」です。特に上下関係が厳しい職場では、若手は意見を言えずに飲み込むしかありません。先輩や上司からの理不尽な指示や怒号が日常茶飯事の現場では、「これ以上は無理だ」と感じても、それを口にできない。だからこそ、家庭の事情という建前を選ぶのです。実際、「辞める理由を正直に話したら、余計にややこしくなる」という若手の声は、管理職が想像する以上に多いのです。
次に、「将来が見えない」という不安。建設業界に限らず、職人の世界ではキャリアの明確な道筋が見えにくいことがあります。年功序列や曖昧な評価制度の中で、「自分が成長していけるのか」という疑問を持ちながらも、それを上司に直接言うことは簡単ではありません。だからこそ、「家庭の事情で…」としか言えないのです。
さらに、過酷な労働環境や安全面の不安も、若手が本音を隠す理由になります。長時間労働や休日出勤が当たり前の職場では、体力的にも精神的にも限界を感じる若手が少なくありません。とはいえ、「働き方がきつすぎる」と口に出すと、「甘えている」と一蹴されるかもしれない――そんな不安が、若手の口をつぐませます。
こうした現場の声を拾い上げるのは簡単ではありません。しかし、若手が語らないからといって問題がないわけではないのです。むしろ、語れない状況そのものが職場の問題を示しています。職人道場の事例でも、研修前に若手が「なぜ辞めたのか分からない」としか言わなかったケースが、研修後に「現場での居場所がなかった」「誰にも相談できなかった」と打ち明けるようになることが少なくありません。それは、本音を引き出す環境が整えば、若手の言葉は必ず出てくるという証でもあります。
管理職として問われるのは、こうした本音を引き出す力です。「家庭の事情」という言葉をそのまま受け取るのではなく、その奥にある若手の心の声に気づけるかどうか。そこに、離職を防ぎ、会社を強くするヒントが隠されているのです。
④管理職が見落としがちな「会社に潜む退職の種」

若手が退職する背景には、必ずと言っていいほど「会社に潜む退職の種」があります。管理職は日々の業務に追われる中で、どうしてもこうしたサインを見落としてしまいがちです。しかし、その種を放置すれば、いずれ若手が「家庭の事情」という建前を選ぶしかない状況を生んでしまうのです。
まず見落とされやすいのは、評価制度の不透明さです。若手は「頑張れば報われる」と信じているからこそ挑戦を続けられます。しかし、その評価軸が不明確だと、「いくら頑張っても無駄だ」と感じる瞬間が訪れます。特に現場仕事の多い建設業界では、成果が目に見えるようで実際には「誰がどんな基準で評価されているか」がブラックボックスになっていることが少なくありません。若手にとってこれは大きな不安要素です。
次に、コミュニケーションの断絶も大きな退職の種です。管理職が「話しかけにくい雰囲気」を出していたり、日々の声かけを怠っていると、若手は「自分の居場所がない」と感じます。現場での孤立感は、身体の疲労よりもはるかに深刻な離職の引き金になります。逆に言えば、「ちょっと最近どうだ?」と声をかけるだけで、若手が心を開くきっかけになることも多いのです。
さらに、成長の機会が用意されていない職場環境も見逃せません。若手にとって「技術が身につく」「キャリアが開ける」という実感は、やる気を支える重要な要素です。もし現場が単調な作業ばかりで、技術を教わる機会もないと感じれば、若手は「この会社に未来はない」と判断するしかなくなります。
そして最後に見落としがちな視点が、「辞めた人の声を活かさない」文化です。若手が去っていったときに、「あいつは根性がなかった」と切り捨てるだけでは、同じ理由でまた別の若手が辞めていきます。むしろ、辞めた人が残した不満や不安にこそ、組織改革のヒントが隠されているのです。
管理職として大切なのは、こうした退職の種を“若手の問題”として片付けないことです。それらは全て、「会社のあり方」や「マネジメントのあり方」に直結しています。若手の離職を「仕方ない」とあきらめるのではなく、「自分が見えていないものは何か」を問い続けることが、会社を強くする第一歩なのです。
⑤厳しすぎる上下関係と人間関係の摩擦:居場所を失う若手

建設業界に限らず、現場仕事には「厳しい上下関係」がつきものです。しかし、その厳しさが度を越えたとき、若手にとって職場は単なる労働の場ではなく、息苦しさに満ちた「居場所のない空間」へと変わってしまいます。退職理由を「家庭の事情」とする若手の多くが、本当はこの“人間関係のストレス”に耐えきれなくなっているのです。
建設現場では、経験の差が大きく物を言うため、どうしても上下関係が色濃くなります。ベテラン職人の指導は時に厳しさを伴いますが、そこに「教える」姿勢があれば、若手にとっては学びの場になります。しかし問題なのは、単なる叱責や一方的な押し付けに終始する指導です。若手にとって、何をどう直せばいいのかも分からないまま怒られるだけの現場は、「自分には向いていない」と感じさせる要因になります。
さらに、上下関係の厳しさは、若手が意見を言うことを封じます。「生意気だと思われるのが怖い」「口答えするなと言われるのがオチだ」と感じれば、若手は黙るしかなくなります。こうして声を奪われた若手は、いよいよ職場に自分の居場所を見いだせなくなっていくのです。
もう一つの問題は、現場内での“派閥”や“グループ”の存在です。職人の世界では、特定のリーダーに従う派閥が自然発生することもあります。そうした中で若手は、どのグループにも馴染めず、孤立感を深めていく。誰にも相談できず、どの方向に努力すればいいのかも分からない――それは精神的に大きな負担です。
このような状況に置かれた若手が、退職時に「家庭の事情」を持ち出すのは自然な防御反応です。本当は職場の人間関係に苦しんで辞めるのに、それを口に出せば「お前が悪い」と逆に攻撃されるかもしれない。だからこそ、若手は本音を隠し、「家庭の都合」を選ぶのです。
管理職として問われるのは、この人間関係の問題にどれだけ敏感になれるかです。人間関係のトラブルは、表面化しにくい分、放置すると取り返しのつかない孤立を生みます。職場で誰が居場所を失いかけているのか、どこに軋轢が生まれているのか――日々の観察と声かけが、若手を守る最初の一歩なのです。
⑥評価されない現場、見えない将来像が生む無力感

若手が「家庭の事情で辞めます」と口にするその奥底には、評価されない現場で感じる無力感と、「この先どうなるんだろう」という将来への不安が隠されています。管理職や人事担当者は、日々の業務に追われる中でつい見落としがちですが、若手にとって「評価されない」「先が見えない」という状況は、肉体的疲労以上に精神をすり減らす深刻な問題です。
建設業界の現場は、目に見える成果が多い世界です。完成した建物やインフラが形として残る――それは大きなやりがいにつながる反面、「誰がどの貢献をしたのか」は見えにくい構造でもあります。特に若手は、必死で仕事を覚えようと努力しても、成果が数字や書面に残らないため、上司に「誰でもできる仕事だ」と思われてしまうことが多いのです。
加えて、評価制度そのものが不透明な会社も少なくありません。年功序列や古い慣習にとらわれ、「どれだけ頑張ったか」ではなく「どれだけ年数を積んだか」で評価が決まる――そんな職場では、若手がいくら汗を流しても報われません。これは若手にとって、まさに「努力が意味をなさない」という無力感に直結します。
また、将来のキャリア像が見えにくい職場環境も、若手にとっては大きな壁です。「今は見習いだから仕方ない」と言われ続け、数年先の姿が全く見えない――そんな状態では、いくら現場を頑張っても「どこへ向かっているのか分からない」という不安が募ります。仕事の先に希望がないと感じたとき、若手は退職を決断するしかなくなるのです。
職人道場では、こうした「見えない将来像」を埋めるために、短期間で基礎技術を徹底的に教え込むだけでなく、「自分の技術が社会でどう役立つのか」までをしっかりと伝えています。単なる技術指導ではなく、若手が「ここでなら未来を描ける」と感じられる土台をつくる――それが、評価されない現場から若手を救うヒントでもあります。
管理職として問われるのは、「誰がどこで輝いているのか」を見つけ、きちんと評価の言葉を届けることです。そして、「ここで学べば、こうなれる」という将来像を、若手に具体的に語れるかどうかです。評価のない職場に希望はありません。若手が未来を見失う前に、声をかけ、方向を示す――それが管理職の最も大切な仕事なのです。
⑦「辞める=甘え」ではない!管理職が気づくべき時代の変化

建設業界に限らず、多くの管理職が「辞めるなんて甘えだ」と考えてしまいがちです。しかし、その発想はもはや過去のものです。時代は大きく変わり、働き方や価値観、そして仕事に求めるものが劇的にシフトしています。いま、管理職に求められているのは「辞めることは甘えではない」という新しい視点を持ち、若手の退職の背景に目を向けることです。
一昔前は、現場の厳しさに耐え抜くことが美徳とされてきました。若いころは怒られて当たり前、苦労してこそ一人前になる――そんな価値観は、現場の技術継承においてある意味で不可欠だったかもしれません。しかし、現代の若手は違います。社会全体が「働き方改革」や「労働環境の見直し」を進める中で、若手にとっては「理不尽な我慢」より「やりがいのある仕事を長く続ける」ことが当たり前の価値観になっているのです。
また、今の若手は仕事を「自己実現の場」と捉えています。「自分が成長できる」「社会に役立っている」と感じられない職場に、長く居続ける理由はありません。だからこそ、無理やり残らせるよりも「なぜ辞めたいと思ったのか」「どこに壁を感じたのか」を聞き、職場を変えるヒントを見出す姿勢が管理職には求められています。
実際、退職理由を「家庭の事情」とする若手の多くは、本当は「ここではもう成長できない」と感じています。それは甘えではなく、自己防衛です。管理職が「若手の根性が足りない」と決めつければ、問題はいつまでも解決しません。逆に「何が彼らを辞めさせてしまったのか」を探る視点を持てば、組織全体が大きく変わるきっかけになるのです。
時代の変化は厳しい現実でもあります。人手不足の中で、昔ながらのやり方に固執していては、人が育たないどころか、会社そのものの未来も失われかねません。しかし、これはチャンスでもあります。若手が辞める理由に真剣に向き合い、管理職自身が学び直す覚悟を持つ――それが離職を防ぎ、組織を未来へつなぐ最初の一歩なのです。
⑧「家庭の事情」の裏にある心のサインを見逃さない方法

「家庭の事情で辞めます」――その言葉の裏に隠された本当の思いに、管理職がどれだけ敏感になれるかは、離職防止のカギを握ります。多くの場合、この言葉は単なる表向きの理由にすぎず、若手が本音を語れない苦しさの表れでもあります。管理職として重要なのは、この「表の言葉」の奥にある心のサインを見逃さない姿勢です。
若手が家庭の事情を理由に退職を申し出るとき、しばしば表情や声のトーンに微妙な違和感がにじみます。例えば「申し訳ない」と言いながらも、どこか諦めたような目をしていたり、質問に対して短く曖昧な返事しかできなかったり…。それは「本当のことは言えない」という心の叫びかもしれません。だからこそ、管理職は「なぜ?」と一歩踏み込んだ問いかけをする必要があります。
さらに、普段のコミュニケーションの中で「最近、顔色が良くない」「作業中にぼんやりしている」など、ちょっとした変化を見逃さないことが大切です。これは決して詮索するのではなく、「君が大事だからこそ気にかけている」というメッセージを伝える行為です。若手は管理職のその真剣さを敏感に感じ取り、少しずつ心を開いていくものです。
加えて、退職を申し出たときに即座に「分かった」と受け入れず、「この会社でやりたいことは他にないのか」「もしも残れるならどんな働き方がいいのか」と柔らかく問いかけるのも有効です。これは若手に「自分の考えを聞いてくれる人がいる」と思わせるだけでなく、辞める理由を見つめ直すきっかけを与えることにもなります。
職人道場でも、若手が「辞めたい」と打ち明ける背景には、職場の空気や上司の態度が大きく影響していることを繰り返し指摘しています。だからこそ、管理職自身が「辞めるのは仕方ない」で片付けるのではなく、「辞める前に本音を話せる空気を作れなかったか」を振り返ることが不可欠なのです。
若手の退職は、会社にとって痛手です。しかし、それは同時に「会社が変わるチャンス」でもあります。「家庭の事情」に隠れた心のサインを敏感に読み取り、若手の声に寄り添う姿勢こそが、離職を防ぎ、会社をより強くする道筋なのです。
⑨辞めた人を責めるな:本音を話せる職場づくりが離職を防ぐ
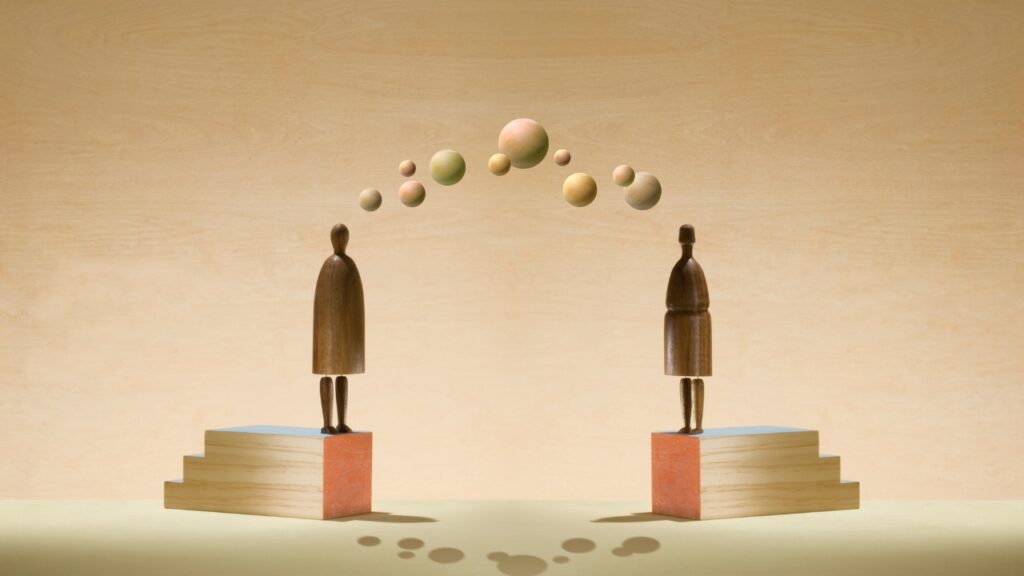
若手が退職を決めたとき、つい「根性がない」「もう少し頑張れなかったのか」と責める気持ちが湧いてしまうかもしれません。しかし、その瞬間に「なぜ辞めるのか」「どうすれば止められたのか」という視点を持てるかどうかが、会社の未来を大きく分ける分岐点です。辞めた人を責める文化は、結果として残った人をも苦しめ、本音を隠す空気を温存してしまうのです。
建設業界の現場では特に、辞めた人の話題を「根性なし」「向いてなかった」と片付ける空気が根強くあります。しかしこれは、管理職にとっても自分の責任を直視しない“免罪符”に過ぎません。本音を言えない職場では、辞めた人の声だけでなく、残っている人の声も届かなくなっていきます。結果として、問題はずっと見えないまま蓄積し、やがては大きな組織崩壊を招くリスクとなるのです。
一方で、「辞めた人を責めない」文化を作ることは、会社の強い土台を築くことにつながります。辞めた人の理由を真剣に分析し、「どこに問題があったのか」「次は同じことを繰り返さないために何ができるか」をチームで話し合う。この姿勢が、職場全体に「ここでは本音を話していいんだ」という安心感を広げていきます。
職人道場のような研修現場でも、辞めた人の声は貴重な“学びの種”です。若手が感じた「やりがいのなさ」や「人間関係のストレス」を真正面から見つめることで、次の若手が同じ道を歩まずに済む道筋をつくれるのです。こうして辞めた人の声を活かせる職場こそが、技術を継承し、会社を未来へと繋ぐ力を持つのです。
管理職にとって大切なのは、辞めた人に「残念だ」と感じるだけで終わらせないことです。その声に真剣に耳を傾けることで、見えなかった問題が見えてきます。辞めた人を責めるより、辞めた理由を責任として受け止める――それが、管理職としての本当の仕事であり、若手の「ここなら頑張れる」という気持ちを育てる最大の土台なのです。
⑩退職理由の“嘘”をなくすために管理職がやるべきこと

「家庭の事情で辞めます」という言葉を若手から聞いたとき、管理職として本当にやるべきことは、その言葉をそのまま受け入れるだけではありません。むしろ、「なぜその言葉を選ばせてしまったのか」「どうすれば本音を話せる環境を作れたのか」を真剣に考え、改善の行動を取ることこそが重要です。退職理由の“嘘”をなくすには、管理職自身が意識を変え、職場環境を見直す覚悟が求められます。
まず大切なのは、普段からのコミュニケーションの質を見直すことです。日常の声かけや雑談を軽視せず、「最近どう?」「困っていることはない?」といった小さな問いかけを積み重ねることが、本音を引き出す第一歩です。若手が「言っても大丈夫」と思える空気は、管理職の姿勢からしか生まれません。
次に、職場の評価制度や教育の仕組みを透明化することです。若手は「どこを目指せばいいのか」「何を評価されるのか」が見えない職場では、やる気を失ってしまいます。目標設定や成果の見える化、技術指導の場の整備は、若手が自分の価値を実感しやすい環境を作り出します。これにより、「どうせ言っても無駄だ」と感じさせない職場が形づくられるのです。
また、「失敗を許す」文化の醸成も不可欠です。建設業界では、失敗や間違いが大きなリスクにつながるため、つい「完璧さ」を求めすぎる傾向があります。しかし若手にとって、最初から完璧にできる人はいません。ミスを共有し合い、改善に活かせる環境を整えることで、「自分の弱さを正直に話せる職場」へと変わります。
さらに、「辞める前に言いやすい相談先を明確にする」ことも大きなポイントです。直属の上司には言いにくいこともあります。メンター制度や外部相談窓口の整備など、「どんな悩みでも話せる場」を持つことが、退職理由の“嘘”をなくす土壌となります。
職人道場が行う研修でも、「辞めたくなる理由」をあえて言語化させ、若手が「ここでなら成長できる」と感じられる視点を与えています。これは管理職にとっても学びのヒントです。若手の本音を聞き、言いやすい空気を作ること。それは単なるマネジメントの技術ではなく、「人を大切にする経営者としての覚悟」そのものです。
退職理由の“嘘”をなくすのは、一朝一夕ではできません。しかし、管理職が「本当の声を聞く」ことを恐れずに向き合うことで、職場は確実に変わります。それが、若手にとっての「辞める理由」を「続ける理由」に変える、最大の武器なのです。
【まとめ】
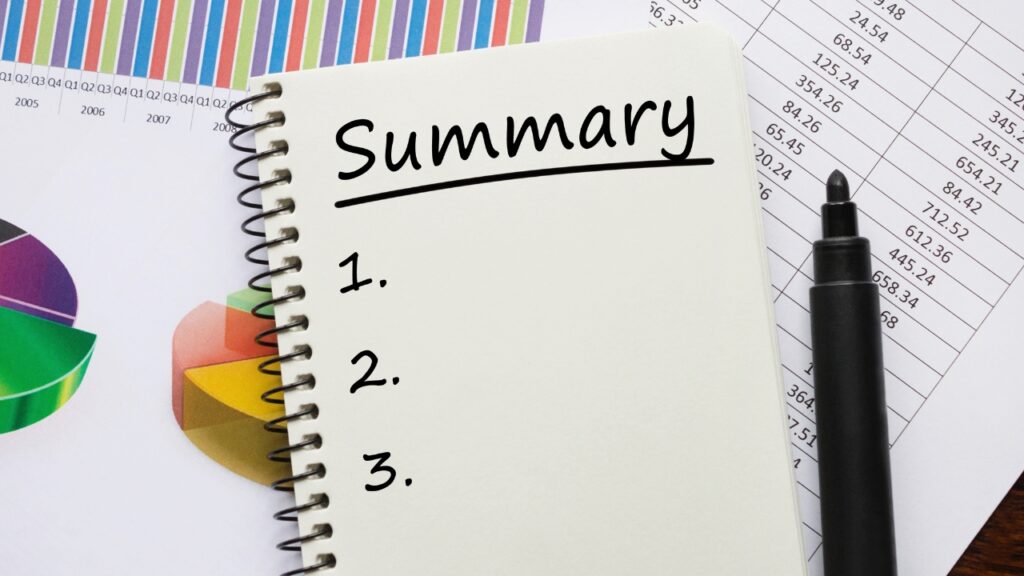
「家庭の事情で辞めます」――この言葉の裏にある若手の本音を、管理職はどれだけ感じ取れているでしょうか。厳しすぎる上下関係、曖昧な評価制度、成長を実感できない環境…。若手が本音を隠して辞める背景には、必ず「会社に潜む問題」があります。それを見過ごせば、退職は連鎖し、技術も人材も会社の未来も失われていきます。
今回の記事では、若手が語らない“嘘の退職理由”を解き明かしながら、管理職が気づくべき職場の課題を深堀りしました。そして最後にたどり着くのは、「辞める人を責めるな」という原点です。若手が辞めるときに残した小さなサインを見逃さず、耳を傾け、変える覚悟を持つこと。それが、未来をつくる管理職の役割なのです。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。