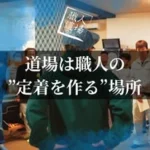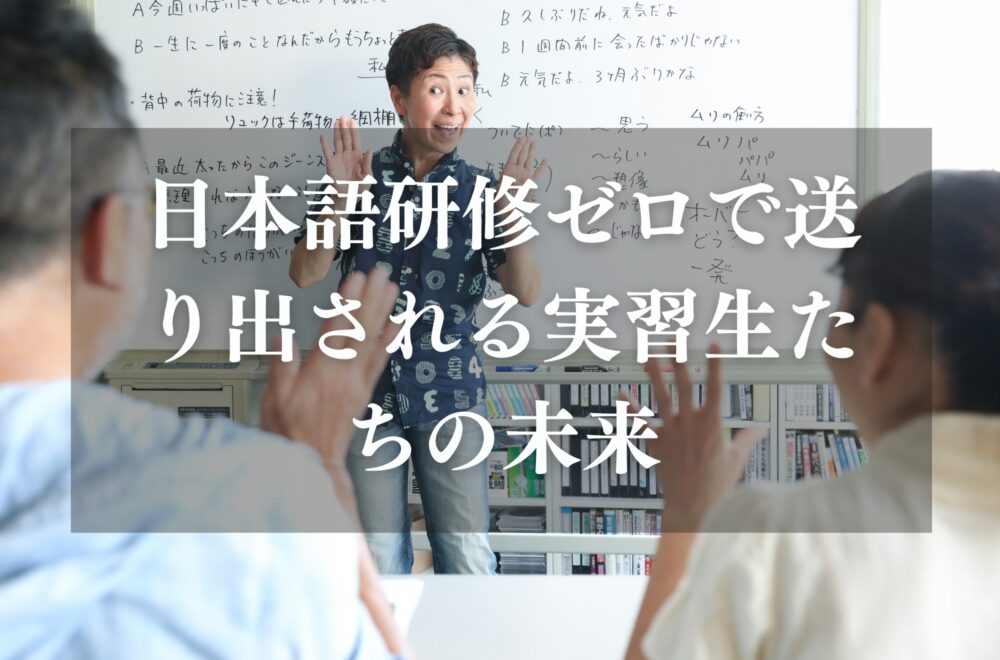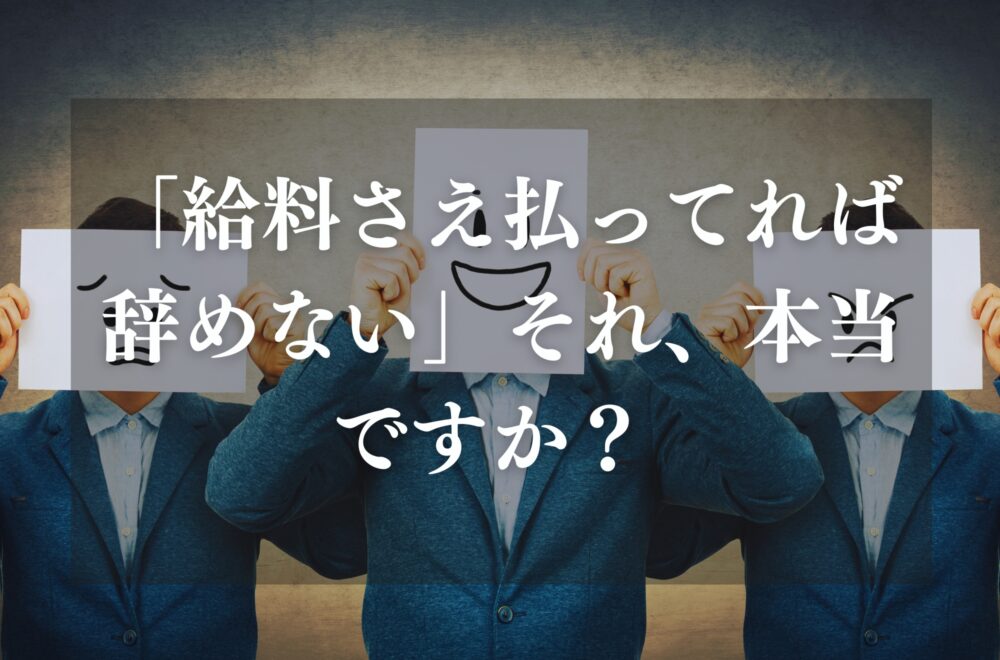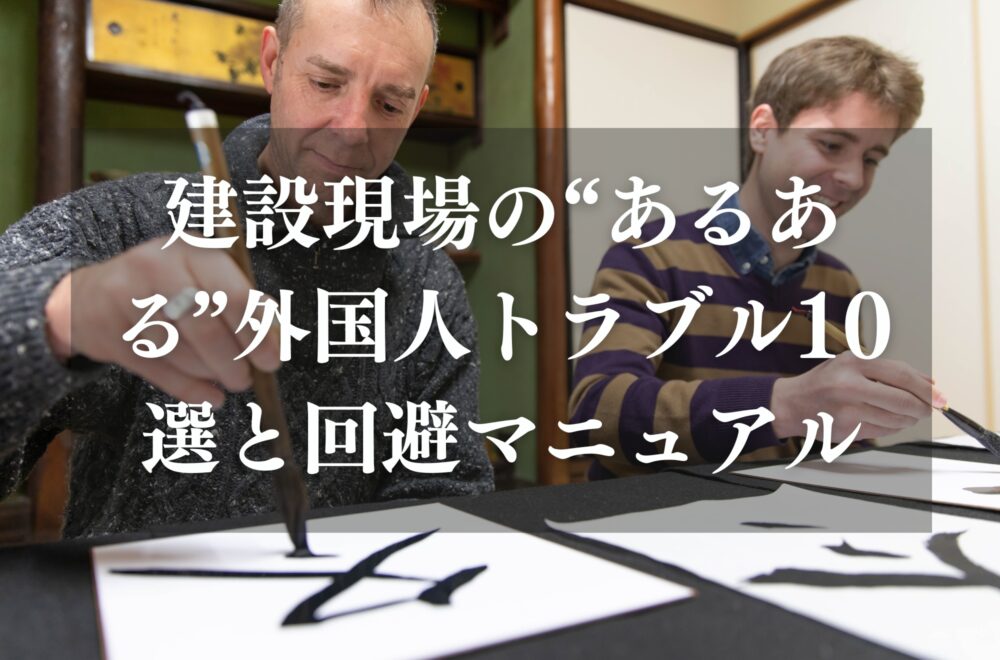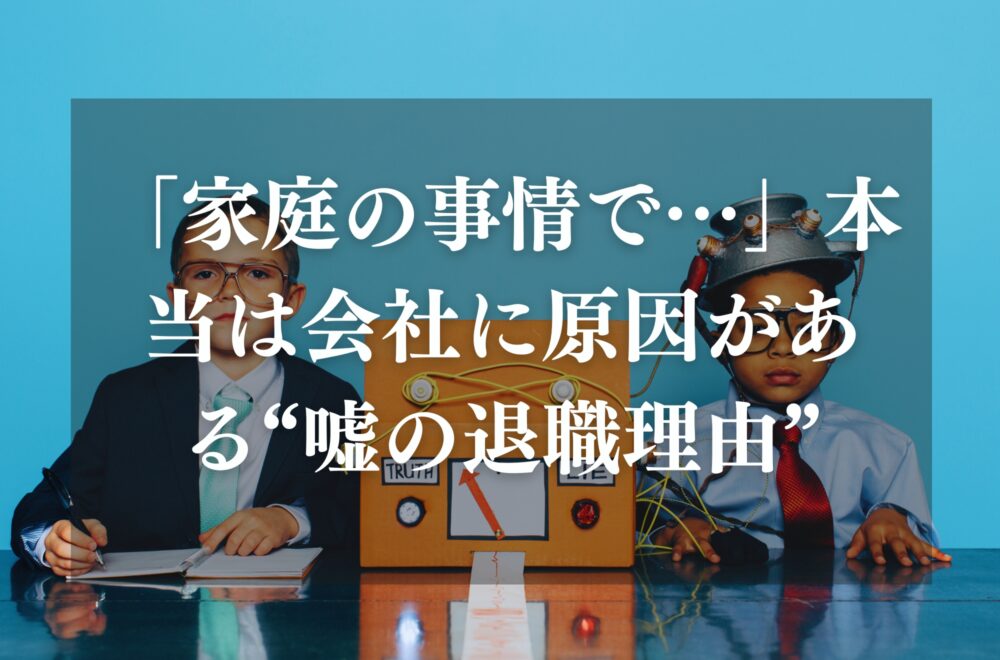「給料さえ払ってれば辞めない」それ、本当ですか?
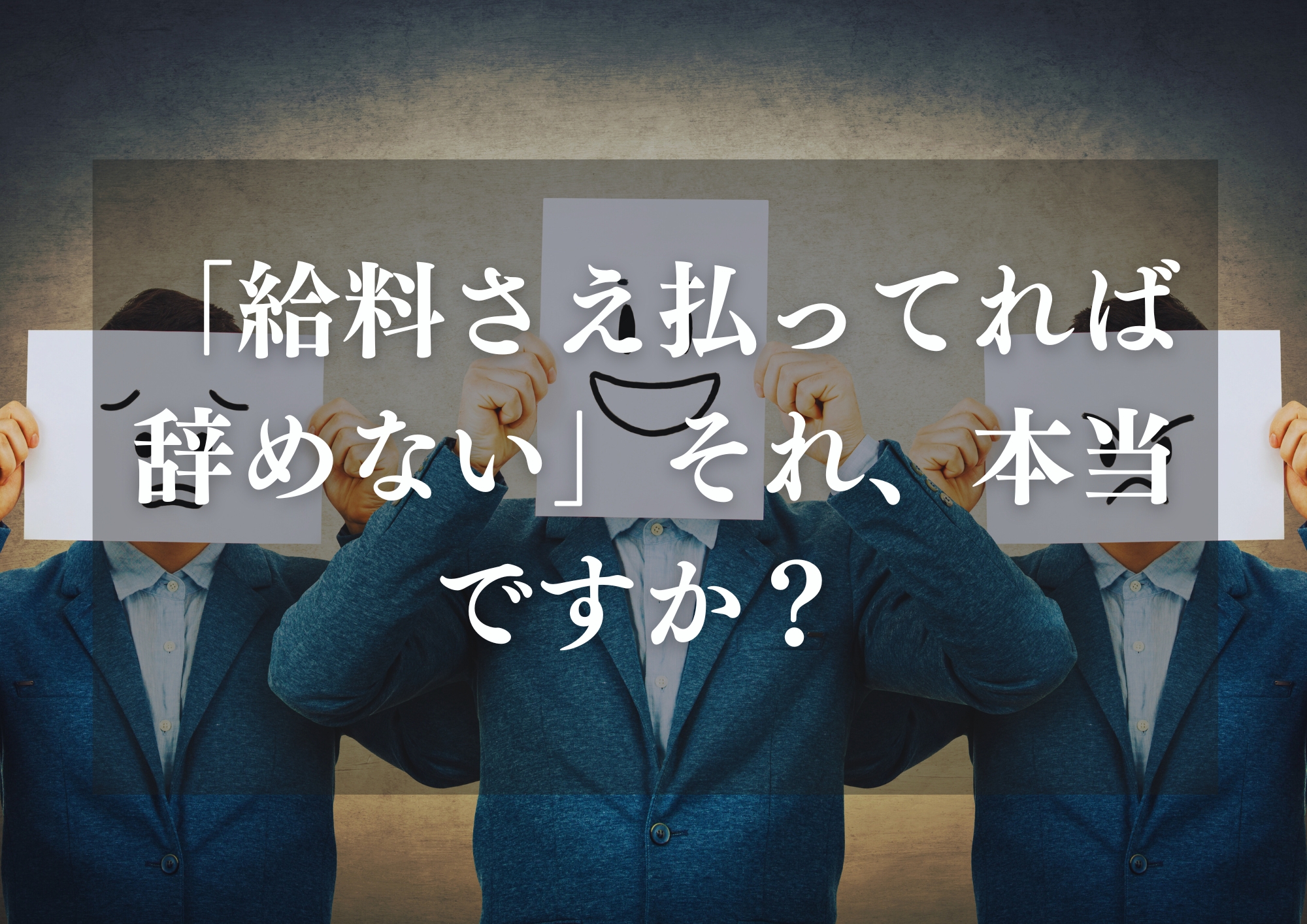
>目次はこちらです。気になる記事をクリックしてください。
①給料だけではない!若手が求める「働く理由」とは

「うちは給料をきちんと払っている。だから辞めるなんておかしい」。多くの経営層が抱きがちなこの考え方は、いまや時代にそぐわないものです。給料が高いからといって若手が会社に居続けるとは限らない――この厳然たる事実を、役員層は改めて理解する必要があります。なぜなら、若手が求めている「働く理由」は、給料という数字だけでは測れない価値にシフトしているからです。
もちろん給料は大切です。生活を支え、将来の安心を生むものです。若手にとっても、「給料が低すぎるから辞めたい」と感じることは現実にあります。しかし、いまの若手世代にとって、「お金だけ」では決して満たされないのです。そこには「働く意味」や「成長実感」といった、かつては二の次とされてきた価値観が重要な役割を果たしています。
職人道場の現場でも、若手がよく口にするのは「給料より、やりがいがないのがつらい」「教えてくれる人がいないのが苦しい」という言葉です。彼らは決して贅沢を言っているわけではありません。むしろ「自分がどう役立てるのか分からない」「誰からも必要とされていない気がする」という孤独感と戦っているのです。
ここで注目すべきは、「人間は社会的な生き物である」という基本です。お金は確かに生活の土台ですが、同時に「自分の存在が認められる場所」であることが職場の最大の価値になります。評価されない、成長が実感できない、相談できる相手がいない――このどれかが欠けただけで、給料が高くても辞める決断をする若手は少なくありません。
さらに、いまの時代は「自己実現欲求」が強い若手が増えています。単なる作業の繰り返しや指示待ちではなく、「自分が考え、成長し、社会に役立っている」という実感を求めています。役員層にとっては「甘え」に聞こえるかもしれませんが、これは時代の価値観の変化です。昭和のように「家族のために我慢して働け」という時代は終わったのです。
会社が問われているのは、若手に「ここでなら成長できる」「ここでなら意味を持って働ける」と思わせること。職人道場の研修でも、「技術を教えるだけではなく、なぜそれが必要かを納得させること」に力を注いでいます。これはどんな現場でも応用できるヒントです。若手にとって「意味のある仕事」が何かを、会社が明確に示すことが、給料以上に大切なのです。
役員として問われるのは、「給料さえ払っていればいい」という思い込みを手放す勇気です。若手が辞める理由の根底には、「自分の居場所を感じられない」という深い不安があります。それを埋めるのは、給料明細ではなく、日々の声かけや成長機会、そして心からの承認です。「給料だけではない働く理由」をつくれる会社こそが、これからの時代を生き抜けるのです。
②「給料が高い=満足」ではない時代の現実

かつては「給料が高ければ誰も文句を言わない」という考えが、会社経営の常識のように語られていました。もちろん、お金は生活の基盤です。だからこそ給料をしっかり払うことは最低限の責任です。しかし、時代は大きく変わりました。給料が高いだけでは、若手は満足できない。むしろ、「お金よりも大事なもの」を若手は敏感に感じ取り、それを得られない職場からは迷わず離れていく――これがいま、経営者や役員が直視すべき現実です。
多くの現場で「うちは同業他社より給料がいい。それなのに辞めるのは甘えだ」と嘆く管理職の声を聞きます。けれど、それはあくまで経営者側の視点です。若手の視点に立てば、給料が高い職場でも、「成長できない」「評価されない」「人間関係が最悪だ」という状況では、お金だけでは気持ちは続きません。実際に厚生労働省の調査でも、「給料」より「職場の人間関係」や「仕事内容のやりがい」を離職理由に挙げる若手が増加しています。
この現実を役員層が見落としているのは、数字にばかり目がいくからです。決算書やコスト管理の指標としては給料は分かりやすい数字です。しかし若手の「働く意味」「仕事への満足度」は数字には表れません。むしろ、数字には表れない「日々の声かけ」「小さな承認」「成長の実感」こそが、彼らを会社につなぎ止める糸なのです。
さらに言えば、給料が高い職場ほど、若手の心が見えにくくなる危うさがあります。役員として「十分な給料を払っている」という自信があると、「それ以上の何を望むのか」と反発心が生まれがちです。しかし、給料はあくまで若手にとってのスタートラインに過ぎません。そこから「この仕事を続けて意味があるのか」「会社に大切にされていると感じるか」を日々問いながら、彼らは職場を見つめているのです。
職人道場の現場でも、給料の良し悪し以上に「ここで自分は何を得られるのか」が若手の本音です。目の前の数字より、将来への期待感や安心感を会社が示せるか――それが、給料以上に響く時代のキーワードです。
役員として問われるのは、若手の辞職を「給料の問題じゃない」と決めつけるのではなく、「なぜ給料だけでは満足しないのか」を真剣に探る視点です。辞めていく若手は決してわがままではありません。むしろ会社に「お金だけではない価値」を求めているのです。給料が高いから満足、という時代は終わった。だからこそ今、会社の本当の魅力をつくる経営が問われているのです。
③辞める人の本音:お金よりも大事なことがある

「給料は十分払っているのに、なぜ辞めるのか」。役員層にとっては納得しがたい問いかもしれません。しかし実際、辞める人の本音に耳を傾けると、給料よりも大事な理由がいくつも語られています。それは決して「お金がいらない」という話ではなく、「お金だけでは埋められないものがある」という切実な思いです。
若手が辞めるときに最もよく口にするのは、「誰も見てくれない」「自分がここで働いている意味が分からない」という言葉です。いくら給料が高くても、仕事が単なる作業の繰り返しに感じられたり、頑張っても誰からも承認されなかったりすると、「ここにいても意味がない」と感じてしまうのです。これは若手だけでなく、どんな世代の人間にとっても辛いことです。
また、人間関係のストレスも大きな理由です。現場で理不尽な叱責や陰湿な人間関係が続くと、給料の高さは心の支えにはなりません。むしろ「給料をもらっているから我慢しろ」と暗に強制される空気が、さらに若手を追い詰めることすらあります。お金がもらえるからといって、毎日心がすり減る場所に居続けたい人はいないのです。
職人道場で若手の声を集めると、しばしば「一番つらかったのは、誰にも頼れないことだった」という声が聞かれます。給料以上に求めているのは、仲間意識やチームとしての支えです。役員層にとっては些細に見えるかもしれませんが、若手にとっては「自分を支えてくれる人がいるかどうか」が、会社に残るか去るかを決める大きな要素なのです。
さらに、「成長の実感がない」というのも若手が語る本音の一つです。給料が高くても、仕事が単調でスキルが磨かれないと感じれば、若手は「ここにいる意味がない」と感じます。現代の若手は「自己成長」を非常に重視しています。それは決して贅沢な願いではなく、「長く働くなら、成長できる場で働きたい」という当然の思いです。
こうした辞める人の本音は、職場の空気や上司の接し方、日々の小さな言動にすべて表れています。役員として、「辞める人はお金より何を求めていたのか」を真剣に見つめることは、会社の未来を左右する経営判断です。給料だけで人は動かない。人は、誰かに認められたい、成長したい、チームで支え合いたい――その当たり前の願いを、どれだけ会社が応えられるかが試されているのです。
④職場の空気が若手を辞めさせる:給料だけでは埋められない溝

給料が高くても、職場に漂う空気が若手を辞めさせてしまう――これが現場で起きているリアルな現実です。役員層が「待遇を整えているから問題ない」と思っていても、若手が感じる職場の空気はお金では埋められない深い溝をつくります。むしろ、待遇が良い分だけ「それ以上の何が必要なのか」に気づかない危うさがあります。
職場の空気とは、日々のコミュニケーションや上司の態度、チームの雰囲気など、数字では見えない部分に宿ります。例えば、現場で「質問するのは生意気だ」「ミスをしたら即怒鳴られる」といった空気が蔓延していれば、どれだけ給料が高くても若手は心を閉ざします。「もう何をしてもダメだ」と感じさせる空気は、若手の可能性を奪い、会社への愛着を根こそぎ奪うのです。
また、誰がどんな仕事をしても評価されない、努力しても「当たり前」とされる空気も問題です。若手は「仕事ができるかどうか」以上に、「自分の存在を認めてもらえるか」を敏感に感じ取っています。頑張っても誰にも気づかれない職場では、給料だけが残り、「もうここにいる意味はない」と感じてしまうのです。
さらに、古い上下関係のしきたりが残る職場では、「意見を言うな」「黙って従え」という空気が若手を追い詰めます。これでは、せっかく若手がアイデアや工夫を出そうとしても、何も言わない方が楽だと感じてしまう。こうして職場は活気を失い、若手が「自分には何もできない」と無力感を深める悪循環に陥ります。
職人道場でも、こうした空気に苦しむ若手の声を多く聞きます。「技術を教えてもらう以前に、人として認められていないのが一番つらかった」という声は、まさに職場の空気が若手を辞めさせる決定的な要因であることを示しています。
役員として大切なのは、「職場の空気をどう変えるか」を真剣に考えることです。給料は経営判断で決められますが、空気は日々の会話や小さな態度の積み重ねでしか変わりません。「辞めるのは若手の甘え」と決めつける前に、「どんな空気を自分たちが作っているか」を見つめる――それが、給料以上に価値ある離職防止策です。
⑤「やりがい」を奪う職場の問題点とは
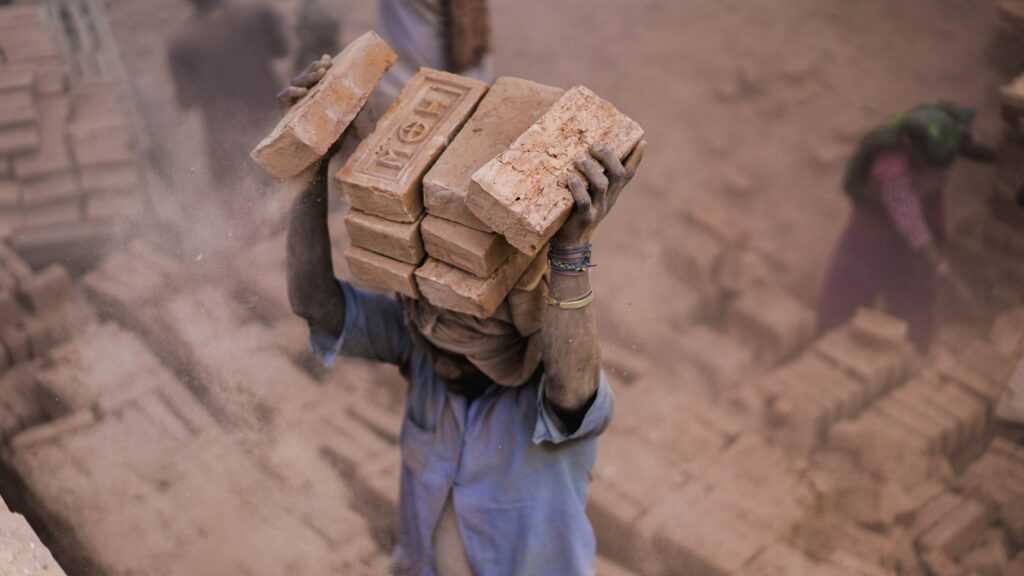
「給料さえ払っていれば辞めない」という幻想が崩れた今、若手が仕事に求めるのは「やりがい」です。給料は生活の土台ですが、「やりがい」は働く理由そのもの。役員層がこのやりがいを奪う職場の問題点に気づけなければ、若手の離職は止められません。
やりがいとは、単なる「好きな仕事」ではありません。若手にとってやりがいとは、「自分が役に立っている」という実感であり、「成長している」という確信です。しかし、いくら給料が良くても、会社の仕組みや空気がこれを奪ってしまう職場は少なくありません。
まず問題なのは、業務が単調で若手に裁量や挑戦の余地がない職場です。「言われたことだけをやればいい」という文化が根付くと、若手はやりがいを感じる前に「自分はただの歯車だ」と感じてしまいます。特に建設業界では、「安全第一」「効率優先」といった正論の裏に、若手の成長の機会が埋もれてしまう現実があります。
さらに、役割の意味づけが不十分な職場も若手からやりがいを奪います。「なんでこの作業をしているのか」「どう役に立つのか」を上司が説明しないと、若手は「とにかく働け」という圧力しか感じられません。これは仕事への誇りを奪う大きな要因です。
そして、管理職自身が若手の意欲や挑戦心に無関心な態度も問題です。若手が提案や挑戦をしたときに、「余計なことはするな」と言われてしまえば、やりがいどころか「黙って指示だけ待っていればいい」という諦めに変わります。こうして若手の意欲は会社に根付く前に萎んでしまうのです。
職人道場の現場では、「若手に仕事の意味を伝え、挑戦を任せる」ことが離職防止の鍵だとされています。やりがいを育むのは「一緒に考えてくれる上司の存在」であり、「仕事の意味を納得できる場」です。逆にこれがない職場では、若手にとって給料がどれだけ高くても「やりがいのない日々」にしかなりません。
役員として問われるのは、「やりがいを奪う原因をつくっていないか」という自問です。数字ばかりを追い、現場の空気に目を向けなければ、やりがいは失われていきます。若手が「辞めたい」と思うとき、その決断は給料ではなく、やりがいの喪失にこそ根ざしているのです。
⑥厳しすぎる現場管理が若手の心を折る理由

給料が高くても、現場管理が厳しすぎると若手の心は確実に折れてしまいます。現場管理はもちろん安全や品質のために必要ですが、その厳しさが度を越えたとき、若手にとっては「働く意味」を奪う重圧に変わってしまうのです。
建設業界は特に安全面への意識が高く、厳しい現場管理が求められます。だからこそ、管理職もつい「ミスは許されない」という態度を強く出してしまう。しかし若手にとって、初めての現場は分からないことだらけです。細かいルールや段取り、ベテランには当たり前のことも、若手には全てが新しいチャレンジ。そんなときに「何でこんなこともできないんだ」と叱られ続ければ、挑戦心は消え、「怖いから何も言わない方がいい」という萎縮に変わります。
厳しすぎる現場管理の問題は、若手の失敗を成長の糧にできないことです。管理職が「失敗=許されない」と決めつけると、若手は「どうせ怒られるから言わない」「黙ってやるしかない」と感じます。こうして職場は単なる作業場になり、学びや挑戦の空気は消えていくのです。
さらに、厳しさ一辺倒の現場では、若手の心の余裕が奪われます。「安全第一」という正論の裏で、精神的な安全が守られない――これは、若手にとって耐え難い状況です。職人道場の研修でも「厳しさと育成のバランス」が繰り返し強調されています。若手の心を折らない厳しさは、単に叱るのではなく、「どうしてそれが大切なのか」を伝え、一緒に乗り越える姿勢にあります。
役員として問われるのは、「厳しさをどんな形で伝えているか」です。厳しさが現場の秩序を守るだけでなく、若手の成長を支えるものになっているか。それとも若手を押しつぶすだけの負担になっていないか。若手が心を折られる前に、その厳しさの意味と伝え方を見直すことが必要です。
若手の離職は、ただの人手不足ではなく、厳しさのバランスを見失った職場の“赤信号”です。給料が高くても、心が折れる現場に居続けたい人はいません。だからこそ、厳しさの意味を若手に伝え、共に成長を描く――そんな現場管理が、若手を支え、会社を未来へつなぐ道なのです。
⑦会社に残りたいと思わせる「評価」と「承認」の力

給料が高くても、会社に残りたいと思わせるものは別にあります。それは「自分の存在を認めてもらえている」という実感――つまり評価と承認の力です。若手が辞めるとき、往々にして「頑張っても誰にも認められなかった」という無力感が背景にあります。逆に、評価され、承認される職場には、給料以上に若手を引きつける魅力があるのです。
評価とは、単なる賃金や昇進に直結する制度ではありません。日々の仕事ぶりや挑戦に対する「よくやった」という言葉も立派な評価です。これを怠ると、若手は「どうせ何をしても意味がない」と感じてしまいます。役員層として、「評価は制度の問題」と片付けるのではなく、現場での小さな承認をどれだけ生み出せるかに目を向けることが重要です。
若手は特に、努力が誰かに見えているかどうかを敏感に感じ取ります。現場の雑談の中での「昨日の作業、助かったよ」「段取りが良かったな」という一言は、どんな昇給よりも若手の心を支えます。承認は、若手が「ここにいていい」と思える土台であり、会社への信頼感を育む根幹です。
さらに、評価や承認は若手にとって「自分の成長の道筋」を教えてくれるものでもあります。ただの作業者ではなく、技術者として、チームの一員として、どう伸びていけるかを見せてくれるのが、役員や管理職の評価の役割です。それがない職場では、給料をもらっていても「ここにいても未来がない」と感じてしまうのです。
職人道場でも、「褒める力」が若手の定着に直結するとされています。厳しさの中にも「やれば報われる」と思わせる承認がある職場は、若手の心を引きつけ、仕事を楽しくします。逆に、頑張りが当然視されるだけの職場では、若手はすぐに心を閉ざしてしまうのです。
役員として問われるのは、「評価や承認を単なる仕組みではなく、現場の日常にどう根づかせるか」です。若手は給料の額よりも、「自分が必要とされている」という感覚を求めています。だからこそ、会社に残りたいと思わせるのは、評価制度の表面ではなく、「日々の承認」にある――それが若手の本音であり、経営に活かすべき大切な視点なのです。
⑧短期的な報酬の罠:給料アップだけでは続かない理由

若手が辞める兆しを見せたとき、会社として最も手軽にできる対策の一つが「給料を上げる」ことです。確かに短期的には効果があります。給料が上がれば、一時的に不満は和らぐかもしれません。しかし、これは「短期的な報酬の罠」に過ぎないことを、役員層はしっかり認識しなければなりません。なぜなら、給料アップはあくまで“対症療法”にすぎず、根本の問題を解決できなければ、若手はやがて再び辞める決意を固めるからです。
給料アップは若手に「会社が自分を大事にしてくれている」というサインを与えます。これは重要なことですが、同時に「なぜ自分は不満を感じていたのか」を直視しなくなる危険もあります。根本にあるのは、人間関係のギスギス感、評価や承認の欠如、成長機会の不足――こうした問題は、給料アップでは絶対に埋められません。むしろ、一度給料でつないでしまうと、次にまた辞めたい気持ちが芽生えたときに「前より辞めにくい」と葛藤を深め、結果的に精神的に追い込まれてしまうケースすらあります。
また、給料アップは「条件闘争」にもつながります。若手は「次も給料を上げればいい」と考えるようになりますが、会社としては無限に賃金を上げられるわけではありません。若手にとっても、給料が上がるたびに「次のステップは?」と疑問が湧き、「この職場での成長はどこにあるのか」という根本的な問いに行き着きます。給料だけでは満たされない「自己成長の欲求」こそが、いまの若手の離職を左右する最大の要素なのです。
職人道場の研修でも、若手の「ここで成長できる」という実感が、どんな給料の増額よりも離職を防ぐとされています。短期的に給料を上げるより、仕事の意味やチームとの関わり、成長を認めてもらう環境づくりを優先する――これが、若手をつなぎ止める本当の答えです。
役員として問われるのは、「給料アップをどんな文脈でやるか」という視点です。ただ金額を上げるだけではなく、その裏に「なぜここで働くのか」「どう成長できるのか」という意味を持たせることが不可欠です。若手にとって、給料はあくまで「働く理由の一部」にすぎません。報酬という目に見える部分だけではなく、目に見えない「やりがい」や「安心感」まで整えなければ、短期的な給料アップは、やがて若手を遠ざける逆効果になりかねないのです。
⑨役員だからこそ見直すべき「職場文化」の課題

給料や待遇だけではなく、若手が会社を去る大きな理由の一つに「職場文化」があります。これは日々の会話やちょっとした態度にまで浸透し、知らず知らずのうちに若手を追い詰める大きな力を持っています。だからこそ、職場文化の見直しは役員にしかできない大仕事でもあります。
職場文化とは、単に「明るい雰囲気」といった表面的なものではありません。「誰の意見が尊重されるか」「ミスを許す空気があるか」「挑戦を応援するか」といった、組織の根底にある価値観のことです。ここが古いままだと、若手は給料が良くても長くはいられません。むしろ、給料が高いからこそ「本当にここで働きたいか」を若手はよりシビアに見ています。
特に建設業界では、「ベテランが絶対」「若手は黙って覚えろ」という古い空気が根強く残っている会社もあります。こうした文化は、若手の挑戦心を摘み、やがて「ここにいても成長できない」という無力感を育てます。職人道場でも、「職場文化が若手の定着に直結する」と繰り返し指摘されてきました。
役員として問われるのは、「自分自身がその古い文化を再生産していないか」という視点です。若手が辞めるとき、決して彼らだけの問題ではありません。管理職や役員が「昔はこうだった」と言い続けるだけで、若手は「自分たちの時代は関係ないのか」と感じてしまう。役員の言動や価値観は、職場文化を形づくる大きな力です。
もう一つ見落としがちなのは、「言いやすい雰囲気」の欠如です。どんなに立派な施策を掲げても、日々の会話で若手が意見を言えない空気が残れば、何も変わりません。役員だからこそ、「意見を言った若手にどんな態度を示しているか」「聞く耳を持っているか」を自ら問い続ける必要があります。
職場文化の見直しは、一度や二度の施策で完了するものではありません。役員が「うちはいい職場だ」と思っているだけでは、何も変わらないのです。むしろ若手が本音を言える小さな場を積み重ね、その声を本気で受け止める――そこからしか、文化の変革は生まれません。役員にしかできないのは「経営判断」であり、同時に「文化を守り、育てる責任」なのです。
⑩給料以上に響く「人を大切にする経営」の真価

若手が辞める背景には、給料や待遇だけでは測れない「人を大切にする経営」の有無が大きく関わっています。数字に表れる賃金よりも、日々の態度や言葉ににじみ出る「この会社は自分を大切にしてくれているのか」という実感が、若手の心を決めるのです。役員層にとっては「給料を払えば十分」という考えを手放し、「人を大切にすることこそが経営戦略の根幹だ」と位置づけ直すことが、未来の企業を形づくる分水嶺になります。
人を大切にする経営とは、単に「仲良くしよう」といった甘い話ではありません。むしろ厳しさや期待をきちんと伝えながら、同時に「あなたの成長を信じている」「困ったらいつでも相談していい」という土台を築くことです。若手にとって、何より響くのは「見捨てられない」という安心感。職人道場の研修でも、「厳しさの中にある信頼」が若手の成長と定着を支えていることが何度も強調されています。
また、人を大切にする経営は「時間をかけること」でもあります。業務の効率だけを優先し、会話を省略し、若手の声を置き去りにしてしまえば、どんな給料を払っても気持ちは離れていきます。逆に、忙しい中でも若手の話を聴く時間をつくることが、「ここで働いていいんだ」という確信を与えるのです。
そして何より、役員自身が「人を大切にする姿勢」を体現することが求められます。若手が見ているのは、上司や社長の口先の言葉ではありません。行動や判断の中に、誰を大切にしているかが透けて見えています。人をコストや数字でしか見ない経営は、給料をどれだけ積み上げてもやがて空洞化します。逆に、誰一人として見捨てない経営は、給料以上の信頼と結束を生み出します。
若手の離職は、「給料ではなく、ここで働く意味を感じられるかどうか」に集約されます。役員として、その意味を日々問い直し、人を大切にする文化を根づかせる覚悟こそが、会社を未来へ導く最大の経営戦略なのです。
【まとめ】
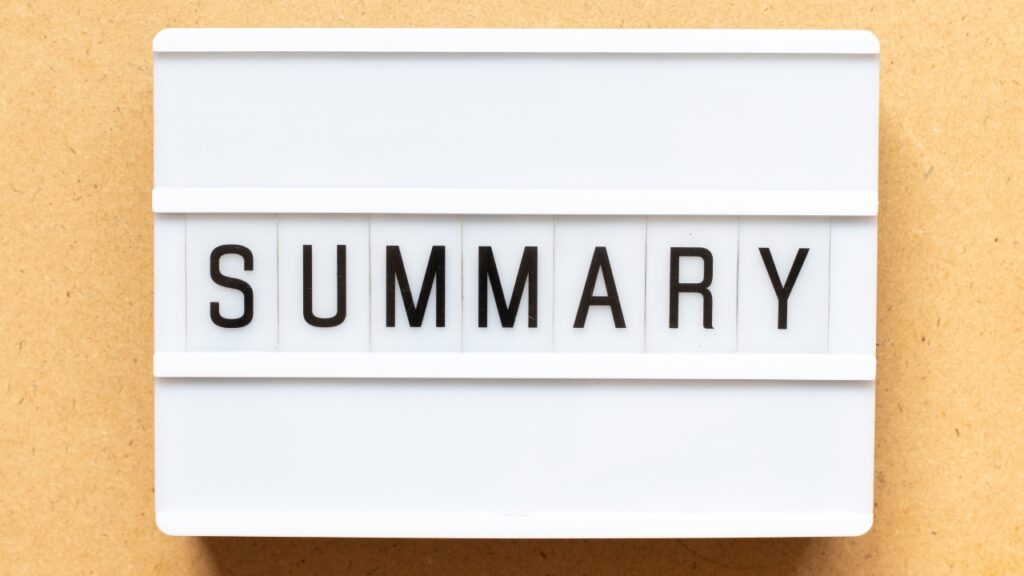
「給料さえ払っていれば辞めない」という考え方は、もはや時代にそぐわない幻想です。若手が求めているのは、単なる数字の報酬だけではありません。成長の機会、評価や承認、挑戦できる空気、そして何より「人として大切にされている」という実感です。給料が高くても、そのどれかが欠ける職場では、若手は迷わず去っていきます。
今回の記事では、給料だけでは若手を引き止められない理由を多角的に探り、役員が直視すべき職場文化や評価の重要性、人を大切にする経営の本当の意味を深掘りしました。辞める若手を「根性がない」と片付けるのではなく、会社の課題を見つめ直すチャンスととらえ、未来の組織を形づくる経営判断に変える。それが、これからの時代を生き抜く企業の必須条件なのです。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。