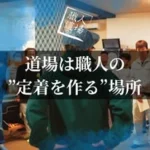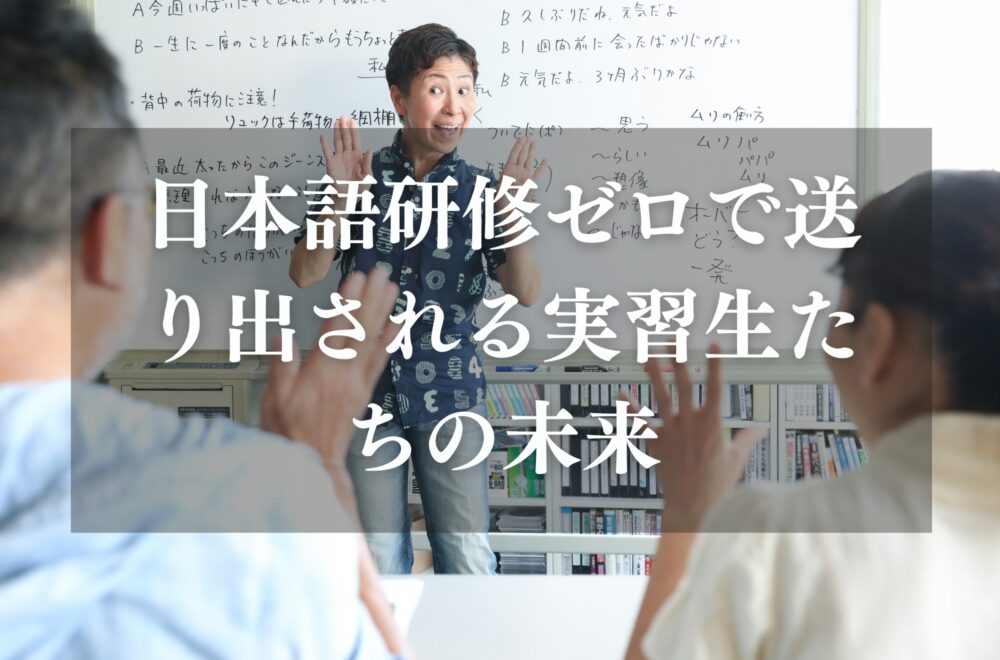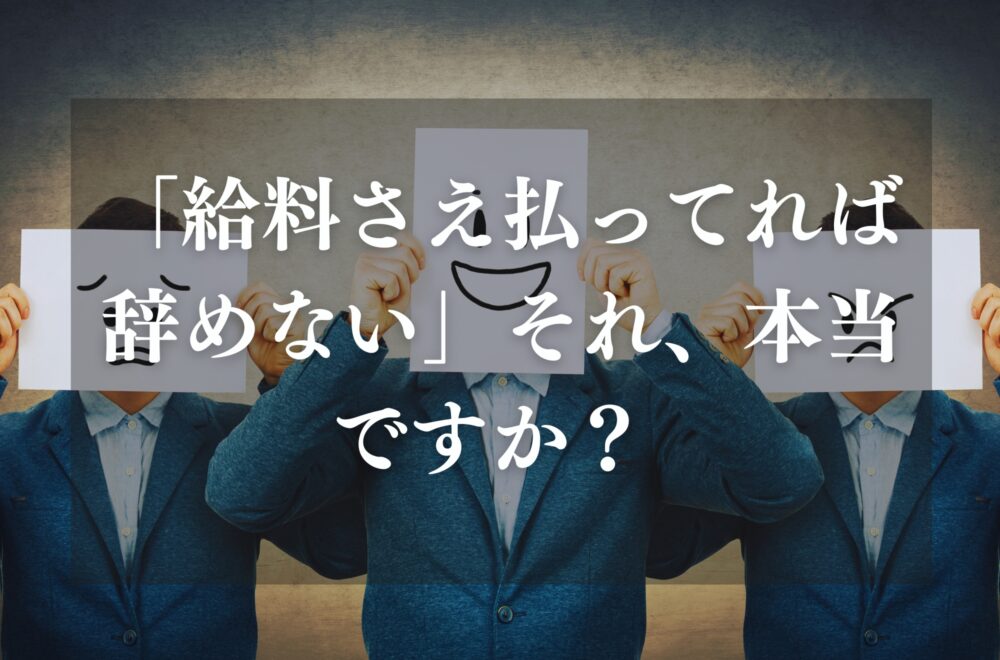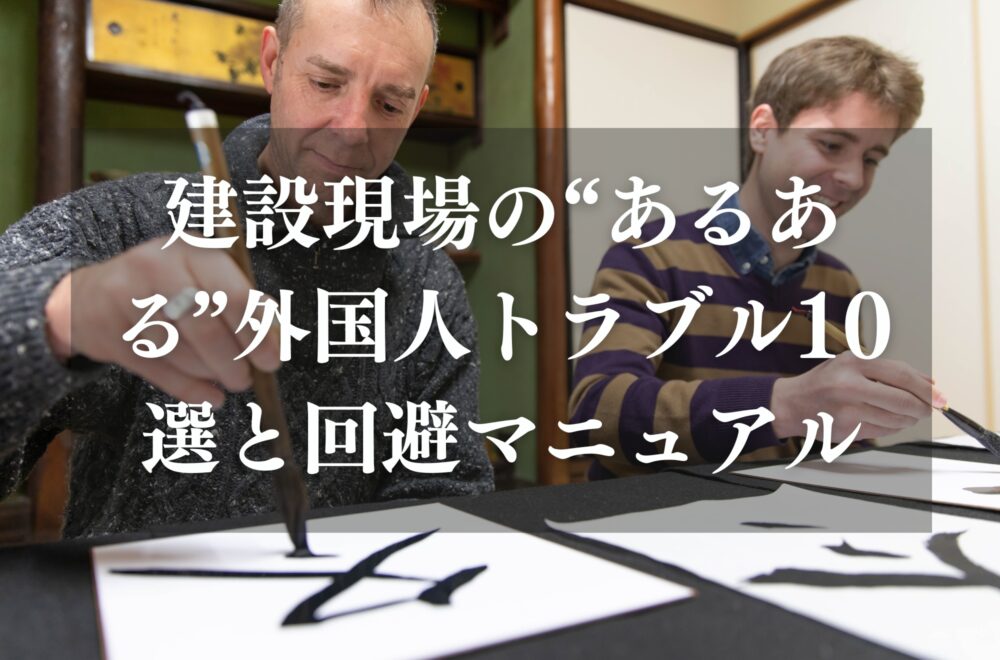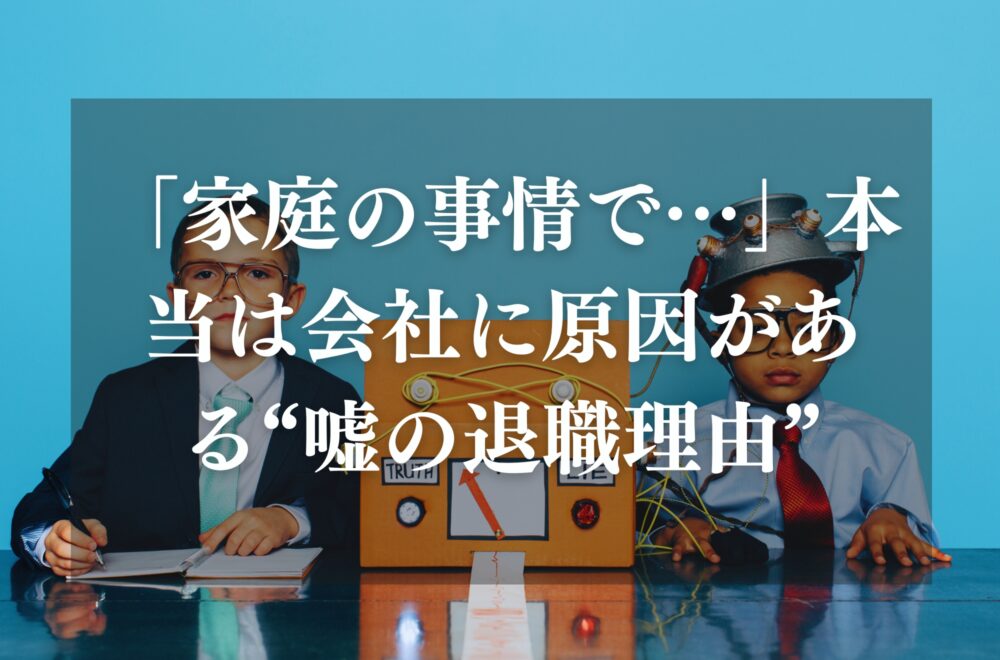外国人技能実習生って本当に即戦力になるの?現場のリアルとは
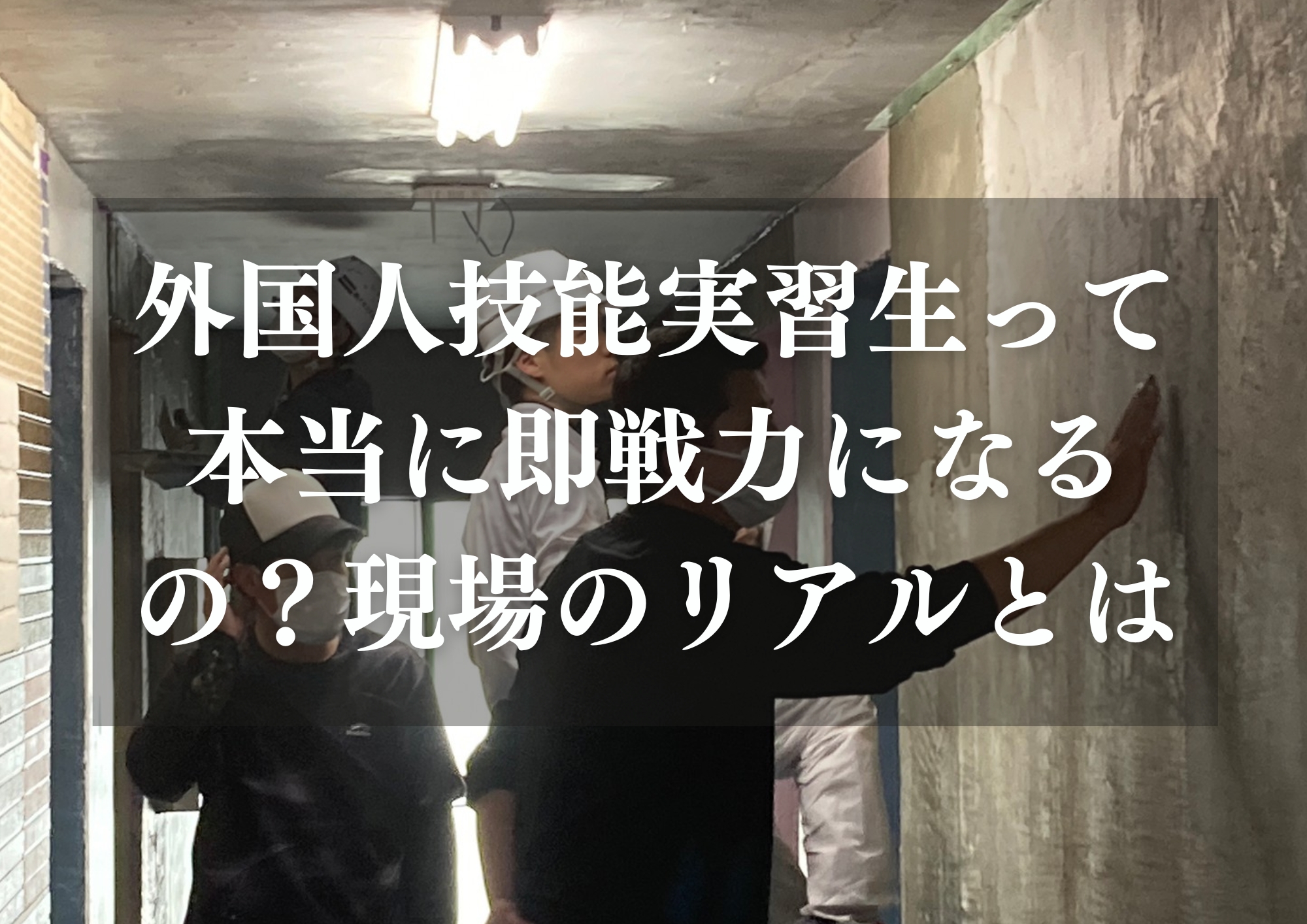
>目次はこちら気になる記事をクリック下さい。
①「3年経っても育たない外国人職人、その理由とは」
「外国人を雇っても、3年経っても一人前にならない」
そんな声を、建設業界の経営者から数え切れないほど耳にしてきました。
日本の建設現場における外国人技能実習生の受け入れは、ここ10年で急増しています。背景には人材不足、特に若手の日本人職人の確保が極めて困難になってきたという厳しい現実があります。しかし、実際に技能実習制度を利用して外国人を雇用した経営者の多くが、**「思っていたほど育たない」「3年いても1人で任せられない」**という壁に直面しています。
では、なぜ3年間という時間をかけても、育たないのでしょうか?
■原因①:「教える文化」が職人現場に根付いていない
日本の職人文化は、長年「背中を見て覚えろ」が基本でした。しかし、これは日本人同士だから成立していた側面が強いのです。
言葉が通じない外国人に対してこのやり方を続けても、当然ながら理解は進みません。
しかも、現場では忙しさが優先されるため、教育の時間を確保することすら難しい。
さらに、職長クラスの職人たちも教育スキルを学んでいないため、**「どう教えたらいいか分からない」**という声も多いのが実情です。
これは「育て方」の問題であり、本人のポテンシャル以前に、教えられていないのです。
■原因②:配属される現場が教育向きではない
技能実習生は「実習」という建前のもと、原則的には教育を目的に受け入れられる制度です。
しかし現実の建設業界では、「とにかく現場が足りない」「即戦力が欲しい」ことから、実習生であってもすぐに戦力化を求められる傾向があります。
たとえば、足場、左官、配管など現場系の仕事は、時間単位で成果が求められる現場が多く、トレーニングに不向きです。
言い換えれば、「失敗してもいい環境」ではないのです。
結果的に、ただ毎日「作業を見ているだけ」になり、何年経っても上達しないという悪循環に陥ります。
■原因③:日本語教育が現場レベルと乖離している
多くの技能実習生は、母国で数ヶ月間の「日本語研修」を受けてから来日します。
しかし、実際に現場で使われる日本語は、専門用語や略語、怒鳴り声の中で聞き取られるようなレベルとは程遠く、言語の壁が根深い問題として残ります。
例:
- 「墨出ししておいて」→ “墨”?インク?ペン?
- 「そこ、チョイ持って」→ “チョイ”ってどれくらい?
こういった細かいニュアンスが通じないことで、指示の理解がズレたり、作業が進まず、本人も「怒られた」という体験ばかりが積み重なり、自信を失ってしまいます。
■原因④:モチベーションが維持できない構造
技能実習制度はあくまで「技能を学ぶこと」が建前です。
しかし現実には、低賃金で労働力として使われているケースも少なくありません。
結果、技能の習得よりも「お金を稼ぐこと」が目的化してしまい、モチベーションの持続が難しくなります。
また、制度の複雑さや不透明な管理体制が、実習生と企業の信頼関係を築きづらくしているのです。

■では、どうすれば“育つ”のか?
実は「育たない」実習生の多くは、育てる側の仕組みや考え方のミスによって本来のポテンシャルを発揮できていないケースが大半です。
その鍵となるのが、以下のような要素です。
- 教育を前提とした受け入れ体制(制度化されたカリキュラム)
- 専門職の技術と日本語を同時に教えるトレーニング
- 失敗が許される現場環境
- “できた”を積み重ねる指導法
たとえば、職人道場では「20日で即戦力に育てる」というプログラムを掲げ、実習生に対しても段階的なスキル取得+言語対応+文化理解のトレーニングを並行して行っています。
このような教育型の受け入れ体制があって初めて、3年かけなくても1ヶ月で“光る”職人が育つのです。
■まとめ
「3年育てても育たない」のではなく、「3年、育てていない」のが実態。
外国人技能実習生が戦力にならないと嘆く前に、
本当に彼らを“育てるための現場”を用意できていたかを、見直すことが重要です。
②「実習生と一人親方、どっちを雇うべき?現場の本音」
建設業界において、慢性的な人手不足が深刻化する中で、
「外国人実習生を育てるか?」「それとも一人親方を即戦力で入れるか?」
という選択を迫られる経営者が増えています。
どちらにも一長一短があり、経営のスタンスや現場の状況によって答えは変わってきます。
しかし、**「どちらがより現場の戦力として機能するのか?」**という視点で見れば、明確な答えが見えてくるのです。
■即戦力で現場を回すなら「一人親方」
やはり即効性という点では、一人親方に軍配が上がります。
彼らは職人歴10年、20年というベテランも多く、現場の動き方、工具の扱い方、危険回避の感覚が体に染みついています。
何より、**指示を出せば即対応できるレベルの「段取り力」**が違います。
現場では「早く」「正確に」「安全に」が常に求められる中で、一人親方のようなプロフェッショナルの存在は、工程の遅延を防ぎ、監督側のストレスも軽減します。
しかし、ここで見逃してはいけない落とし穴がいくつかあります。
■一人親方の課題:安定性と“教えない文化”
1人で現場を渡り歩く一人親方は、フリーランスです。
つまり、繁忙期に頼ることができても、閑散期に繋ぎ留めるのが難しいという課題があります。
また、彼らは「教えることが仕事ではない」という意識が強く、後進育成には消極的な傾向があります。
現場に実習生や若手がいたとしても、「自分の作業に集中」してしまい、現場が分断されることも少なくありません。
■育てて将来の財産にするなら「実習生」
対して、外国人実習生は「ゼロから育てる存在」です。
最初は時間がかかりますし、失敗も多い。
それでも、1年、2年と継続的に指導していけば、社風に馴染み、技術力も伸びていく可能性を秘めています。
とくに、職人道場のような体系的な研修機関を通して実践的なスキルを短期集中で身につけさせると、
驚くほど短期間で「使える人材」になるケースも出てきます。
さらに、技能実習制度の仕組みにより3年間、一定の雇用が確保されるという安定性は、事業計画上のメリットにもなります。
■現場から聞こえる“リアルな声”
実際に、実習生と一人親方を両方使っている経営者にヒアリングすると、こんな本音が聞こえてきます。
- 「即戦力は助かるけど、将来を考えると若手を育てたい」
- 「毎回違う親方が来ると現場がバラバラになる」
- 「実習生が育ってくると、うちの看板職人みたいになる」
- 「一人親方は辞めるときあっさり。実習生は3年はいてくれる」
つまり、「短期的な戦力確保」か、「中長期的な戦力育成」かという視点で選ぶことが肝心なのです。
■コスト面では?
ここも意外と誤解されがちです。
一人親方は高単価での契約が基本で、日当ベースでは高いコストがかかります。
一方、技能実習生は労働基準法に基づいた給与体系であるため、長期的にはコストを抑えて労働力を確保できるメリットがあります。
また、助成金の活用や教育コストの効率化次第では、
実習生の方が“育てがいのある投資対象”になることも珍しくありません。
■結論:即戦力だけでは未来がない
建設業は属人的な力に依存してきた業界ですが、
少子高齢化が進む今、**「教える文化」「育てる体制」**がなければ、数年後には人手も技術もすっかり失われてしまいます。
一人親方に頼るのは、今を生き抜くため。
実習生を育てるのは、未来を作るため。
■経営者への提案
ベストな答えは「両方を適材適所で使い分ける」ことです。
- 急ぎの現場や品質管理が重要な工程は一人親方へ
- 長期的に担わせたい職域は実習生を育成して配属
そして、職人道場のような教育プログラムで実習生を“早期に戦力化”できれば、
**3年という時間が単なる拘束期間ではなく、「未来の柱を作る育成期間」**に変わります。

③「日本語が通じない?コミュニケーションの壁を超える方法」
「それ、昨日も言っただろ!」
「…すみません、わかりません。」
現場でのそんなやりとりに、フラストレーションを感じたことはありませんか?
外国人技能実習生を受け入れる建設業界において、**「言葉の壁」**は避けて通れない課題です。
とくに、忙しく騒がしい現場環境では、意思疎通の難しさが作業ミスや事故にも直結します。
しかし、**「日本語ができない=戦力にならない」**とは限りません。
実は、ちょっとした工夫やルールを取り入れるだけで、現場の空気は劇的に改善されるのです。
■現実:実習生の日本語能力には“ばらつき”がある
技能実習制度では、来日前に「日本語研修」を受けてから入国する仕組みが整っています。
ですが、研修の内容はあくまで基礎的な日常会話やひらがな・カタカナレベルが中心。
現場で飛び交う専門用語や業界スラングには対応できていないのが実情です。
たとえば──
- 「墨出ししといて」→「墨?書くの?」
- 「サンダー取って」→「Thunder…雷?」
- 「そこチョイ持って」→「“チョイ”って何センチ?」
このように、日本人なら一瞬で伝わる言葉が、実習生にとっては“異国語の呪文”に近いのです。
■実は「言葉」より「伝え方」に問題がある
言語力の違いを責める前に、一度立ち止まって考えてみてください。
本当に「日本語の問題」だけが原因でしょうか?
- 同じ言葉を使っても、口調が怒鳴り声では委縮してしまう
- ジェスチャーもなく、言葉だけで伝えようとする
- そもそも指示が曖昧、主語が抜けている
日本人同士でも伝わらないような指示を、外国人相手に投げていませんか?
問題は、語学力よりも「伝え方の質」にあることが少なくないのです。
■即効性あり!現場で使える“伝わる工夫”
外国人実習生とのコミュニケーションを円滑にするには、次のような工夫が効果的です。
✅ 視覚で伝える「写真」「動画」「図解」
- 作業手順は口頭より写真や動画で示す
- 前日の作業をスマホで記録して復習
- 図解を壁に貼ることで指示の共通認識を持たせる
現場は五感で覚える場所です。
「言葉」でなく「目」で理解させることが、学習定着には効果抜群です。
✅ 「業界用語」は共通の“辞書”を作る
- よく使う言葉を現場内でリスト化
- ベトナム語・ミャンマー語・日本語の多言語表記の単語帳を作成
- 朝礼や昼休みに5分だけ“言葉の勉強時間”をつくる
毎日少しずつでも繰り返せば、**現場内だけの“共通言語”**が自然と育ちます。
✅ 感情ではなく“仕組み”で指導する
「何回言ったらわかるんだ!」
怒りたくなる気持ちは分かりますが、それは「伝わってない」のではなく、「伝える工夫をしていない」可能性もあります。
怒鳴るより、
✅“見せて”
✅“やらせて”
✅“確認する”
というステップ指導を徹底することで、理解度は格段に上がります。
■「通じる」には、心の距離も必要
ある企業では、お昼ご飯を実習生と一緒に食べるという取り組みをしています。
最初は無言だった彼らも、徐々に「今日は暑いですね」から始まり、「昨日、彼女と電話した」なんて話もするようになったそうです。
言葉だけじゃなく、**“心の通訳”**も大切だということ。
関係性ができれば、多少の言葉の壁は乗り越えられます。
■まとめ:言語は“障害”ではなく“育成チャンス”
日本語が通じないことを「問題」と捉えるのではなく、
それを**「育てる仕組みを整えるチャンス」**と考えるべきです。
- ゆっくり、丁寧に、繰り返す
- 見せる・やらせる・確認するを徹底
- 心の距離を近づける時間を意識的に持つ
この3つを実践すれば、言葉の壁はいつか笑い話に変わります。

④「技能実習制度の“限界”と“可能性”」
「技能実習制度って、結局“安い労働力”じゃないの?」
そんな疑問を、経営者や現場監督が抱くのも無理はありません。
本来、技能実習制度の目的は“国際貢献”です。
日本で技術を学び、それを母国で活かしてもらう。
しかし現実には、**建設業界の人手不足を補う“苦肉の策”**として使われている面が大きく、
制度本来の趣旨と、現場の実態に乖離が生じています。
この章では、技能実習制度の**構造的な“限界”と、
それでもなおこの制度に見出せる“可能性”**について、深く掘り下げます。
■技能実習制度の構造的な“限界”
① 育成制度なのに「労働力」として酷使されている
建設業界では「実習生=作業員」と見なされることが多く、
現場では即戦力的な扱いを求められるのが現実です。
教育プログラムや育成スケジュールは形式的で、
結局は「言われたことをやる」毎日になってしまい、“技能習得”が空洞化しているケースも多々あります。
② 監理団体・送り出し機関の質にバラつきがある
実習生の受け入れは、送り出し国と監理団体の連携が必要ですが、
その中には**“ブローカー的”に手数料目的で人を回すだけの団体**も存在します。
こうした団体を通じた実習生は、
・教育レベルが不十分
・意欲も低い
・サポート体制が脆弱
など、現場でのミスマッチが頻発しやすくなります。
③ 実習期間が終わると「はい、さようなら」
実習期間は原則3年間(延長含め5年)ですが、
多くの企業では実習期間が終了した時点で雇用も終了となります。
せっかく3年間かけて育てたのに、
その技術や現場理解が自社の戦力になりきる前に帰国してしまうのです。
これでは「人材投資」の回収が難しく、
教育に時間と手間をかける意欲も削がれてしまいます。
■それでも技能実習制度に“可能性”はある
ここまで聞くと、技能実習制度には未来がないように思えるかもしれません。
しかし、見方を変えればこの制度は**“人材育成の起点”**にもなり得ます。
✅ 特定技能制度への“架け橋”になる
現在、技能実習を修了した実習生が「特定技能」へ移行するルートが整備されてきています。
これは、実習を終えた後も日本で働き続けられる制度であり、
**「せっかく育てた人材を、継続して雇用できるチャンス」**でもあります。
職人道場のように短期間で実習生を即戦力レベルまで引き上げられれば、
特定技能への移行後は、“チームの中核”として現場を支えてくれる存在になるのです。
✅ 教育に投資すれば、確実に返ってくる
「時間をかけて育てたら辞められるかもしれない」
という不安は、多くの経営者が抱くものです。
しかし、逆に考えてみてください。
“放置していたから辞めた”というケースの方が圧倒的に多いのです。
外国人実習生であっても、
- 技術を教えてくれる
- 気にかけてくれる
- 名前を覚えてくれる
そういう企業であれば、むしろ強いロイヤリティを持って働き続ける傾向が強く見られます。
育成に投資することは、リスクではなく“保険”なのです。
✅ 地方企業こそチャンスがある
都市部に比べて若者の流入が少ない地方の建設企業ほど、外国人実習生の重要性は高まっています。
・言葉の壁も、長くいれば乗り越えられる
・地域に馴染みやすく、定着率が高い
・人間関係が密になりやすい環境
こうした要素が揃っている地方企業では、実習制度が“人材戦略の柱”として機能するケースが多いのです。
■まとめ:「制度」ではなく「使い方」が問われている
技能実習制度に限界があるのは確かです。
でも、それを理由に使いこなせないままでいるのは、もっと損です。
必要なのは、制度を前提に人を育てる設計力。
職人道場のような外部教育機関を上手に活用し、
制度の“建前”を“実力”に変えていける企業こそが、
これからの建設業界の人材戦略をリードしていく存在になるのです。

⑤「外国人職人は日本人職人の代わりになるのか?」
「外国人職人って、日本人職人の代わりになるの?」
建設業の現場で、この問いを口にするのは決して珍しくありません。
高齢化と若者離れが進む建設業界にとって、外国人材は“救世主”にも“未知の存在”にもなり得ます。
果たして、彼らは日本人職人の代替となる存在なのか?
それともまったく別の価値をもたらす存在なのか?
現場の声と実情を踏まえながら、リアルな答えを探っていきましょう。
■結論から言えば「代わりにはならない、だが補完はできる」
外国人職人は、日本人職人の“コピー”ではありません。
言葉、文化、価値観、働き方、すべてが違うため、「代わり」と考えると失敗します。
しかし、役割分担と育成の工夫によっては、“補完”する存在にはなり得ます。
つまり、「完全な代役」ではなく、「別の特性を持った人材」として活かすことが重要なのです。
■日本人職人が持つ強みと“代替困難な価値”
まず、日本人職人の強みとは何でしょうか?
- 長年の経験による“現場勘”
- 空気を読んだ動きと察知力
- 材料や工程の微妙な感覚的判断
- 伝統的な施工技術の継承
これらは一朝一夕では身につかない、**“文化と時間が磨いたスキル”**です。
したがって、外国人がすぐに同レベルのパフォーマンスを発揮することは困難だと言えるでしょう。
■一方で、外国人職人にも強みはある
「外国人=劣る存在」と見るのは完全に誤解です。
むしろ、彼らには日本人とは違った“可能性”があります。
✅ 吸収力が高く、素直に学ぶ
多くの外国人実習生や技能者は、真面目で誠実。
日本の技術を学びたいという思いが強く、教えたことを一生懸命吸収しようとします。
中には、1年で中堅レベルに成長する人材も少なくありません。
✅ チームワークを大事にする文化もある
ベトナムやインドネシア、ミャンマーなど、**“仲間を助ける文化”**を持つ国から来ている実習生も多く、
グループ作業への適応力が高いのも特徴です。
✅ 身体能力が高く、現場でもタフ
若く、体力がある彼らは、重作業や継続的なルーチン作業に対して高い適性を見せます。
特に日本人が敬遠しがちな「単調」「暑い」「汚れる」といった現場でも前向きに取り組む姿勢が見られます。
■“使い分け”が現場最適化のカギ
ここで重要なのは、**「誰に何を任せるか」**を明確に分けることです。
- 熟練した日本人職人には:難易度の高い加工や仕上げ工程、現場監督業務など“判断力”が求められる業務を
- 外国人職人には:繰り返し作業や段取りの固定された工程など、熟練より継続力・実行力が求められる業務を
このように適材適所で配置すれば、全体の生産性を最大化することができます。
■“混成チーム”こそがこれからのスタンダード
実は、これからの建設現場は、
「全員日本人」でも「全員外国人」でも、うまく機能しません。
大切なのは、**多様な人材をどう“チームとしてまとめるか”**という視点です。
- 外国人職人の感覚や習慣を理解できる中堅職人
- 異文化マネジメントに長けた職長
- 明確な役割と指示を出せる現場監督
こうした人材が揃うことで、**“日本人と外国人が互いに学び合いながら高め合う現場”**が実現していくのです。
■育成できるかどうかが“代替”の条件
最後に強調しておきたいのは、
外国人職人が日本人の代わりになれるかどうかは、**「育成次第」**ということです。
教育を放棄すれば、どんな人材も戦力にはなりません。
逆に、育て方を体系化し、文化的背景を理解しながらサポートできれば、
日本人に劣らない、いや、それ以上に“貴重な戦力”となる可能性を秘めているのです。
■まとめ:代わりではなく、共に進む仲間へ
外国人職人は、日本人の代替ではありません。
しかし、育て方次第で、**“欠かせないパートナー”**にはなれる。
そのためには、現場全体が「教えること」「任せること」に対する認識をアップデートする必要があります。
日本人×外国人で構成されたチームが、未来の建設業を支える基盤となる――
そのビジョンを持つ企業こそが、生き残っていくのです。

⑥「外国人実習生の現場トラブルとその対策とは?」
「外国人実習生が失踪した」
「言っても理解されない、現場が回らない」
「作業中にケガをしたのに報告がなかった」
外国人実習生を受け入れている建設会社で、実際に起きている“現場トラブル”。
これは決して例外的な話ではありません。むしろ、制度と現場のミスマッチが生む“必然”の側面もあるのです。
本章では、現場で起きがちなトラブル事例とその背景、そして今すぐ取り組める“対策”を徹底解説します。
■【事例①】突然の“失踪”——なぜ逃げるのか?
最も深刻でインパクトの大きいトラブルが「失踪」です。
入国管理局のデータでは、毎年数千人規模の実習生が失踪しているという現実があります。
✅ 原因は「職場環境」と「生活不安」
- 過剰な労働時間
- 暴言や差別的な扱い
- 手取りが想定よりも低い
- 相談できる相手がいない
こういった要因が積み重なり、実習生は「ここでは働けない」と判断し、
非正規労働者として地下経済に流れてしまうのです。
✅ 対策:生活・相談サポート体制の構築
- 生活面の困りごとを定期的にヒアリング
- 第三者的立場で相談できる“通訳スタッフ”の設置
- 賃金・労働時間を明確に説明、契約内容を文書化
職場の人間関係・住環境・給与条件——この3つを**“納得感ある形で整備”**することが、失踪を防ぐ最大の予防策です。
■【事例②】“指示が通じない”ミスの連発
「そこ違うよって言ったのに…」
「なんで、また同じ間違いするんだ?」
これは単に言葉の壁だけでなく、指示の出し方の問題も大きく関係しています。
✅ 原因は“日本語力”と“現場の曖昧さ”
日本語のレベルが十分でない実習生に対して、
- 「やっといて」
- 「ちょっとこっち持って」
など、主語や動詞が曖昧な日本語が通じるはずもありません。
✅ 対策:作業マニュアル+写真・動画+ジェスチャー
- 作業工程を動画に撮って見せる
- 指示は短く具体的に:「ボード4枚を左側に運んで」など
- “これ”と指差す、身体で見せることも有効
**言葉より“見せる指導”が即効性あり。**現場はスピードが命だからこそ、視覚に訴える方法が最も効果的です。
■【事例③】“作業中のケガ”を報告しない
「実は昨日、足をひねったらしい…でも黙ってたらしい」
こんなケースは少なくありません。
✅ 原因:報告=怒られると思っている
文化的背景や、過去の経験から「報告=ミス=怒られる」と認識してしまい、
トラブルや体調不良を隠す傾向が実習生にはあります。
✅ 対策:報告のハードルを下げる
- 「悪いことじゃない、報告してくれてありがとう」と伝える
- 朝礼や昼休みに「困っていることある?」と声かけする
- 月1回、母国語通訳を交えた“ホンネ相談日”を設定
報告することで“信頼される”という空気を職場に根付かせることが大切です。
■【事例④】“道具の使い方”による事故や故障
現場でありがちなのが、工具の誤使用や破損です。
- サンダーを逆回転で使って火花を撒き散らす
- 電動ドリルを壊す
- ハンマーの使い方が分からず、周囲を傷つける
これらのトラブルは、教える側が「常識」と思っていることが、実習生には“初めて”であることに起因します。
✅ 対策:道具トレーニング+“教える文化”の醸成
- 各道具の使い方を“体験型”で練習させる
- 「使ったら片づける」など基本動作を反復練習
- 初期の1〜2週間は“付き添い制度”を導入し、先輩職人が手取り足取り指導
「見て覚えろ」では事故は防げません。“実技”と“習慣”の両方を教える時間を意図的に設けることが不可欠です。
■【事例⑤】“文化的なズレ”による摩擦
- 「急に来なくなった」→→ 家族で祭りだから
- 「黙っている」→→ 怒っているのではなく、聞き取れないだけ
- 「注意されると笑う」→→ 緊張からくる反応(怒っているわけではない)
文化の違いを理解せずに接すると、誤解が誤解を生み、職場の人間関係が悪化してしまいます。
✅ 対策:文化理解の共有と“寛容さ”の育成
- 朝礼などで文化ギャップの事例を紹介し、笑いに変える
- 日本人側にも“多様性マナー研修”を取り入れる
- 「どうしてそうしたの?」と対話の機会を意識的に作る
実習生に歩み寄るのと同時に、日本人職人にも“受け入れる力”が求められている時代です。
■まとめ:トラブルは“問題”ではなく“育成の種”
トラブルが起きた時、
「やっぱり外国人はダメだ」ではなく、
「なぜそうなったのか?どうすれば防げるのか?」を考える視点が必要です。
そして、対策を“仕組み化”することが、次のトラブルを防ぐ最大の予防策になります。
職人道場のような教育型施設では、こうしたトラブルの傾向を分析し、**“現場で即使える教育マニュアル”**として活用しています。
だからこそ、短期間での即戦力化が可能になるのです。

⑦「仕事ができる実習生」と「できない実習生」の決定的な違い
「同じ国、同じ年齢、同じ時期に入ったのに、なんでこんなに差が出るんだ?」
これは多くの現場監督や経営者が感じる疑問のひとつです。
外国人技能実習生を複数人受け入れている企業の現場では、
明らかに“できる”実習生と、“なかなか戦力にならない”実習生が出てきます。
いったい何が違うのか?
性格?教育?運?
実は、そこには明確な“理由”が存在します。
■ポイントは「本人の資質」より「受け入れ環境」
結論から言うと、「できる・できない」を分ける最大の要因は、本人のポテンシャルではありません。
それは、育成される“環境”の差です。
では、その具体的な違いを5つの視点から見てみましょう。
■違い①:教える“先輩”がいるかどうか
現場によっては、実習生に対して「教える係」が存在せず、
現場任せ・自己流・丸投げの状態になっているケースもあります。
対して、“できる実習生”が育っている現場では、
必ず**一人の「教える責任者」**が付いています。
- 日々の進捗を見て声をかける
- ミスした時は原因を一緒に考える
- 翌日の目標を立ててあげる
このように、“教えることを業務とする先輩職人”がいるかどうかで、成長のスピードが劇的に変わります。
■違い②:「できた!」を実感する経験があるか
「できない実習生」は、言われたことをやっているだけで、
自分の仕事に対して“達成感”や“意味”を感じられていない場合がほとんどです。
逆に“できる実習生”は、
- 初めて一人で型枠を立てられた
- 職長から「うまいな」と褒められた
- 先輩が「助かったよ」と声をかけてくれた
など、「認められた体験」を繰り返しています。
人は“できた”という実感を持つことで、意欲が高まり、仕事が好きになります。
それがまた成長を促し、好循環が生まれるのです。
■違い③:言語の壁を“壊す工夫”があるか
“できる実習生”がいる現場では、言葉だけに頼らない指導方法が導入されています。
- 写真で手順を説明
- 動画で工程を確認
- ジェスチャーや模型を使って伝える
- 一緒に手を動かして覚えさせる
言語に頼らずとも伝える工夫があれば、スピーディに吸収できる環境が整います。
逆に、「なんでわかんねえんだよ!」と怒鳴るだけの職場では、萎縮と混乱が続くだけです。
■違い④:「文化的な理解」があるか
“できない実習生”が育たない現場には、文化の違いに対する理解がまったくないケースが目立ちます。
たとえば──
- 「怒られたくないから報告しない」文化
- 「Yes」と言っても、実は理解していない
- 無言でいるのは“敬意”を示している場合もある
これらの背景を理解していないと、誤解が重なり信頼が崩れていきます。
逆に、理解と尊重がある職場では、実習生が“心を開く”スピードが違います。
■違い⑤:スタートダッシュで“環境整備”できたか
実習生が来てからの最初の1ヶ月間が、成長速度を大きく左右します。
この期間に、
- 仕事内容とゴールを明確に示す
- 教育係を決めて伴走させる
- 道具やルールを1つずつ丁寧に教える
- 成長を数値やチェックシートで“見える化”する
こうした仕組みを整えておくことで、実習生は“安心してチャレンジ”できる環境を手に入れます。
スタート時に投げっぱなしだと、実習生は“失敗体験”ばかりを重ねてしまい、
結果的に「できない」まま時間だけが過ぎていきます。
■まとめ:実習生の“質”を決めるのは、企業の育て方
「できる実習生が来てくれれば…」という願望を抱く前に、
**“できる実習生が育つ仕組み”を用意できているか?**を考えることが重要です。
実習生の“能力の差”よりも、“受け入れの差”の方が圧倒的に結果を左右する。
そして、その“仕組み”を最短で構築する方法の一つが、
職人道場のような教育施設での事前育成・即戦力化プログラムなのです。

⑧「面倒な手続き?技能実習制度を使いこなすためのコツ」
「外国人を雇いたいが、制度が複雑でよく分からない」
「手続きが煩雑すぎて、うちは無理だと思った」
技能実習制度の導入を検討する建設業経営者の多くが、こうした壁にぶつかります。
確かに、外国人雇用には日本人の採用とは比べ物にならない手間と制度理解が求められます。
しかし、それでも実習生を受け入れ、成功している企業があるのも事実。
では、彼らはなぜうまく制度を使いこなせているのでしょうか?
本章では、煩雑な制度を“活用可能な仕組み”に変えるコツを具体的に解説します。
■そもそも技能実習制度とは?
技能実習制度とは、発展途上国の若者に日本の技術を学ばせ、
その技術を母国の産業発展に役立てることを目的に設けられた制度です。
実際には、建設業・製造業・農業など多くの業界で、慢性的な人材不足を補う手段として活用されています。
■制度が“複雑”に感じる理由はここにある
✅ ① 複数の機関が関与している
- 送り出し機関(外国):候補者の選定・事前教育
- 監理団体(日本):実習生と受入企業の仲介・指導
- 受入企業(あなたの会社):実際に雇用・指導する事業者
この三者に加えて、入国管理局、地方労働局、入管、技能検定機関…と、
関与機関が多岐にわたるため、手続きの流れを把握しにくいのです。
✅ ② 書類と報告が多すぎる
- 技能実習計画の作成・申請
- 雇用契約書の提出
- 月次・年次の実習報告
- 技能検定の受験準備
これらがすべて**“日本語で”“所定のフォーマットで”“期日通りに”**求められます。
慣れていないと、何度も差し戻されるケースも。
■うまく活用するための“3つのコツ”
✅ コツ①:「優良な監理団体」を選べ
制度を使いこなす上で、最も重要なのが監理団体の質です。
悪質な団体に当たると…
- 手続きは丸投げ
- 実習生の教育は未整備
- トラブル時も対応が遅い
一方、優良な監理団体は…
- 申請から配属までスケジュール管理をサポート
- 書類もテンプレート化し、記入方法を丁寧に案内
- 配属後も月1回の訪問やZoom相談対応あり
選ぶ基準は、**「実習生を“労働力”としてではなく、“人”として扱っているか」**です。
導入前に、過去の実績、支援内容、サポート体制をしっかり確認しましょう。
✅ コツ②:最初から“3年分の計画”を立てる
技能実習は原則「1年→2年→2年」の段階で進みますが、
多くの企業が初年度の受け入れで力尽きてしまうことが多いのです。
その結果…
- 書類の期限を忘れる
- 技能検定の準備が間に合わない
- 再申請が面倒で「もういいや」と脱落
これを防ぐには、最初に“3年間のスケジュール表”を作成すること。
たとえば:
| 時期 | やること | 担当 | 完了チェック |
|---|---|---|---|
| 1年目4月 | 技能実習計画の提出 | 総務 | ✅ |
| 1年目6月 | 配属前オリエンテーション | 現場責任者 | ✅ |
| 2年目3月 | 技能検定(基礎級)対策 | 教育担当 | … |
“見える化”することで、慌てず制度を回すことが可能になります。
✅ コツ③:実習生“前提”の社内マニュアルを整備する
制度面のコツと同時に、忘れてはいけないのが**“現場側”の準備**です。
- 「実習生用:1日の動き方」
- 「道具・工具の使い方マニュアル(写真付き)」
- 「日本語・母国語の指差し会話表」
こういった**“受け入れの土台”を整えておくことで、トラブルが激減します。
特に、職人道場では実習生向けの研修と同時に、企業側にも「受け入れ体制マニュアル」を提供**しており、導入企業から高い評価を得ています。
■制度の“面倒くささ”を“育成の型”に変える
技能実習制度は、確かに手間がかかります。
でも裏を返せば、それだけ**“人材育成の型”が整っている制度**とも言えます。
この制度を通じて育成スキルを磨けば、外国人だけでなく日本人新人にも応用が可能。
結果的に、「教える文化」「仕組みで育てる文化」が社内に根づくことになるのです。
■まとめ:使いこなす企業は“マニュアル化と外部活用”が上手い
煩雑な手続きに振り回される企業は、
“人”に頼りすぎて、属人的に運用してしまっています。
反対に、成功している企業は…
- 外部パートナーを“チームの一員”として使い倒す
- 社内に“型”を持ち、誰でも回せるようにする
- 実習生の成長が“自社の戦力”に繋がる流れを明確にしている
そう、制度を“使われる”のではなく、“使いこなす”企業こそが、
今後の建設業界を人材戦略でリードしていくのです。

⑨「外国人を戦力化するためにやってはいけない3つのこと」
「一生懸命教えてるのに、全然伸びない」
「うちに来た実習生はみんな辞めていく」
「気合が足りないんじゃないか?」
——そんな声をよく耳にします。
しかし、それは実習生のせいでしょうか?
もしかすると、育てる側が“やってはいけないこと”をやってしまっているのかもしれません。
外国人を即戦力として育てるには、「これをやるべき」と同じくらい、「これだけはやってはいけない」が重要です。
ここでは、現場でよく見られる“3つのNG行動”を紹介し、その理由と解決策を解説します。
■NG①:「怒鳴る・無視する・急かす」——感情で接してしまう
これは、もっとも多くの現場で見られる“失敗の第一歩”です。
- 指示を理解できていないのに怒鳴る
- 失敗しても「もういい、やるな」と放置
- 無言でイライラした態度をとる
これらは、日本人同士でもNG行動ですが、
外国人実習生にとってはなおさら「怖い・不信感・委縮」の原因になります。
✅ なぜNGなのか?
文化や言語の壁を越えて働こうとしている実習生にとって、
怒鳴り声や無視は「見捨てられた」と感じる最大のトリガー。
これにより、実習生は…
- 萎縮して質問できなくなる
- ミスを隠すようになる
- 成長意欲をなくす
結果的に、「伸びない人材」に変えてしまうのです。
✅ 対策
- 感情的な対応を避けるルールを“チーム内で共有”
- ミスを責めるのではなく、“なぜそうなったか”を一緒に考える
- 「できた時」にはしっかり言葉で認める
職人道場の講師も徹底しているのが、“怒らないが、妥協しない”教育方針。
このバランスが、安心感と成長意欲の両立を実現します。
■NG②:「放置する・説明しない・背中を見て覚えろ」——教えることを放棄
日本の職人文化に根強く残るこの指導法。
しかし、それが通用するのは、同じ言語・文化圏の間だけです。
外国人実習生は、
- 専門用語が分からない
- 作業の手順も初めて
- 道具の名前すら覚えていない
そんな彼らに対して、説明もなく「見て覚えろ」では、理解できるはずがありません。
✅ なぜNGなのか?
放置は、信頼の欠如と解釈されます。
説明のない指導は、混乱とストレスを生み、早期離職の大きな要因になります。
✅ 対策
- 1つの作業に対して「説明→実演→実践→振り返り」の4ステップを徹底
- マニュアル+写真+動画+通訳で多層的に伝える
- 初期1ヶ月は“付き添い職人”を配置し、質問しやすい環境に
“放置”は教育ではありません。
「育てること=説明し続けること」という認識を、現場全体で共有することが重要です。
■NG③:「安価な労働力として見る」——“人”として接しない
「給料が安いからこのくらいでいい」
「やらせとけばいいでしょ」
「帰る人間にそこまで教えなくていい」
——これは、外国人実習生の“モチベーションを潰す”最大の要因です。
✅ なぜNGなのか?
誰でも、自分が「評価されていない」と感じた時、やる気を失います。
外国人実習生も例外ではなく、**「一緒に働く仲間として扱ってもらえるかどうか」**にとても敏感です。
また、技能実習は“国際貢献”という建前があります。
その精神が欠けると、制度自体への不信感を持ち、失踪・離職の原因にもなりかねません。
✅ 対策
- 「ありがとう」「助かったよ」などの声かけを徹底
- 食事や行事に一緒に参加するなど“人と人”のつながりを作る
- 成長すれば給与や役割が変わる“明確なステップ”を提示する
彼らは、**労働力ではなく“可能性”**です。
その価値を見出し、育てようとする姿勢が、信頼と定着につながります。
■まとめ:「怒らない・放置しない・軽視しない」——これが戦力化の基本姿勢
即戦力化のための一番の近道は、「やるべきこと」を増やすよりも、
**「やってはいけないことをやらない」**ことです。
- 怒るより、理解させる
- 放置せず、伴走する
- 使い捨てにせず、育てる
この3つを徹底することで、
外国人実習生は、あなたの会社の「戦力」から「戦略の柱」へと成長していくのです。

⑩「技能実習生の“成長スピード”は教え方で決まる」
「うちに来た実習生は3ヶ月で現場を回せるようになったよ」
「逆に、半年たっても片づけすらできない子もいた」
——同じ制度で来日し、同じような仕事に就いているはずなのに、
技能実習生の成長スピードには大きな差が出ることがあります。
その違いはどこにあるのか?
本人の能力?やる気?運?
実は違います。
もっとも成長スピードを左右するのは、“教え方”=教育の設計力です。
■職人現場に足りなかった“育成の仕組み”
日本の職人文化には「背中を見て覚えろ」という長年の教育スタイルがあります。
これは熟練の日本人同士なら通じる“阿吽の呼吸”に基づいた方法です。
しかし、外国人実習生に対してそれを求めるのは、高等数学を初見で解けと言っているようなもの。
むしろ今求められているのは、**誰でも、どの現場でも、再現できる「育て方の仕組み」**です。
■“体系化された教え方”が成長を加速させる
たとえば、職人道場では**「20日間で即戦力化」**を実現する独自カリキュラムを構築しています。
この背景には、以下のような“教え方の工夫”があります。
✅ ステップ1:「やって見せる」
- まずは講師が“丁寧にゆっくり”作業を実演
- ポイントごとに解説+動画撮影し、繰り返し見せる
- 五感をフルに使った“見て学ぶ”体験
✅ ステップ2:「一緒にやる」
- 実習生に道具を持たせて、並んで一緒に作業
- できていない部分はその場でフォロー
- “できた瞬間”にしっかりフィードバック
✅ ステップ3:「ひとりでやらせてみる」
- 小さな範囲からスタートして“成功体験”を積ませる
- 「任せる」→「任される」→「責任感が芽生える」の循環
- 失敗しても怒らず、振り返りと再チャレンジをさせる
この3ステップを回すことで、実習生の成長スピードは飛躍的に上がるのです。
■“育成スピード”は“教える側の意識”で決まる
多くの現場では、「人を育てる」ことが業務として認識されていません。
そのため、現場の先輩も忙しさを理由に“なんとなく教える”“たまに怒る”という対応になりがちです。
しかし、即戦力化を目指すなら、「育てる人材」を明確に決め、「育て方の方法論」を持たせる必要があります。
- 誰が育てるのか?(担当者の明確化)
- 何を教えるのか?(マニュアル・動画の整備)
- いつまでに何ができれば合格なのか?(成長評価指標の設定)
これらが整っていれば、“属人的な教え方”ではなく、“仕組み化された教育”が実現します。
■“できるようになる順番”を意識する
実習生にいきなり難しいことを任せて、
「できなかった」「だから使えない」
という判断をしてしまうのは、非常にもったいないことです。
技術には“身につく順番”があります。
たとえば左官なら——
- 材料の混ぜ方
- 道具の名前と使い方
- 壁面への下地塗り
- 仕上げ塗りの実演と模倣
- ひとりでの実践と修正
この順番を飛ばしてしまうと、理解も定着もできません。
逆に、順序立てて反復すれば、誰でも技術を“使える形”で覚えることができるのです。
■“教え方”を磨けば、外国人だけでなく日本人も育つ
面白いことに、外国人実習生の教育を通じて、
「教える力」が社内に蓄積されていく企業が増えています。
そしてその育成メソッドは、日本人の新人教育にもそのまま使えるのです。
- 図解や動画で説明する
- 成長指標を明文化する
- 小さな成功を積み重ねる
これは、今後の建設業界において不可欠な“技術継承”のベースになります。
■まとめ:“誰が来ても育つ会社”が選ばれる時代へ
成長スピードは、本人のやる気や能力だけで決まりません。
それ以上に重要なのは、**“どんな教え方で育てているか”**です。
教える仕組み、教える文化、教える人材。
この3つを整えた会社には、実習生だけでなく、良い人材が自然と集まってきます。
そして、そうした会社こそが、これからの人手不足時代を勝ち抜いていくのです。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。
多能工職人育成学校・技術研修所「職人道場紹介動画」