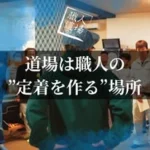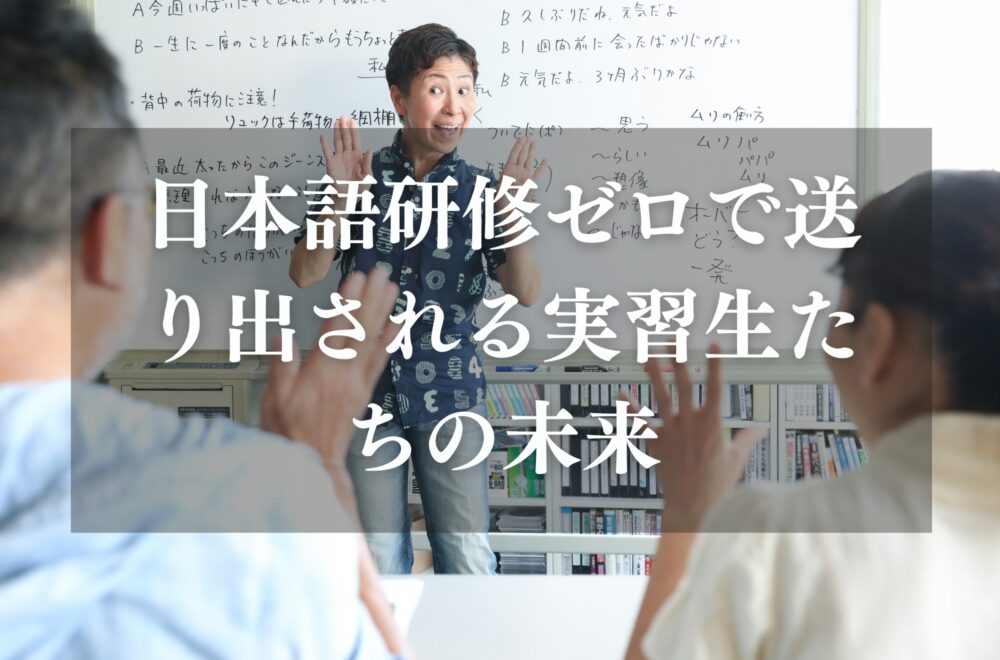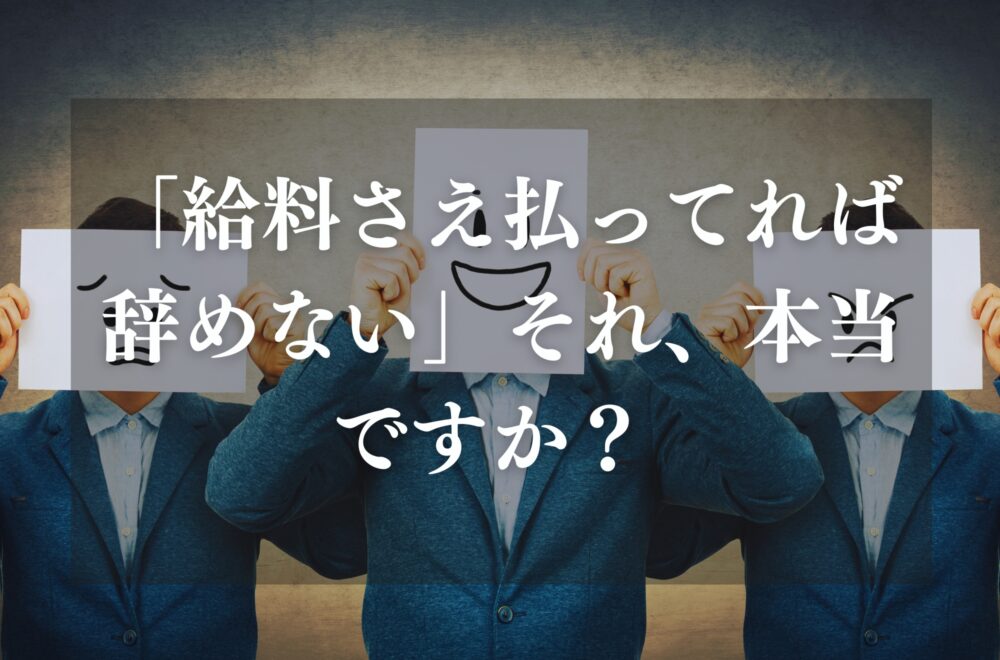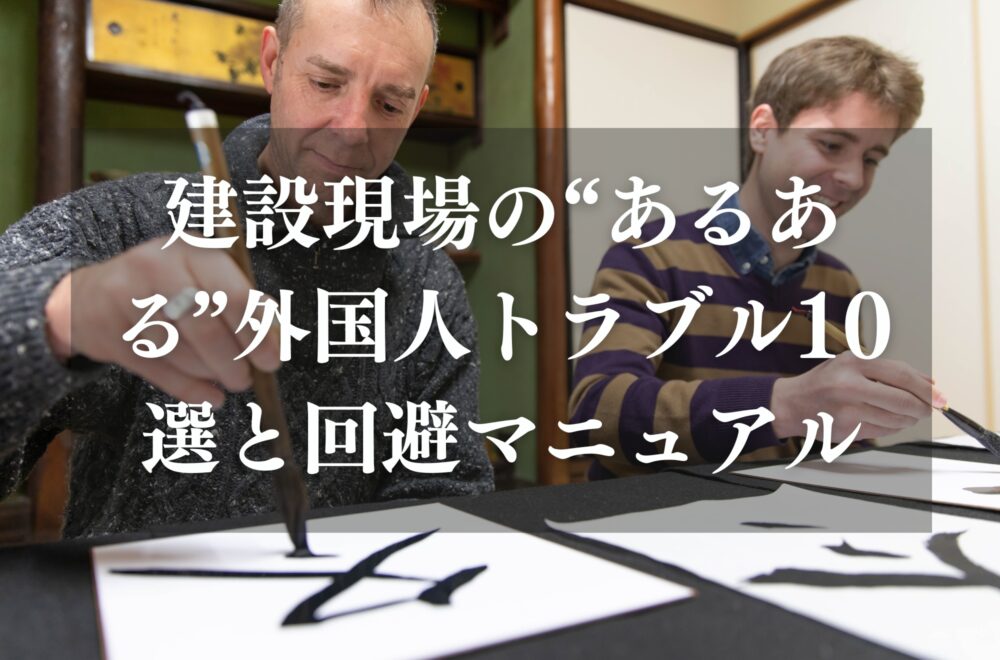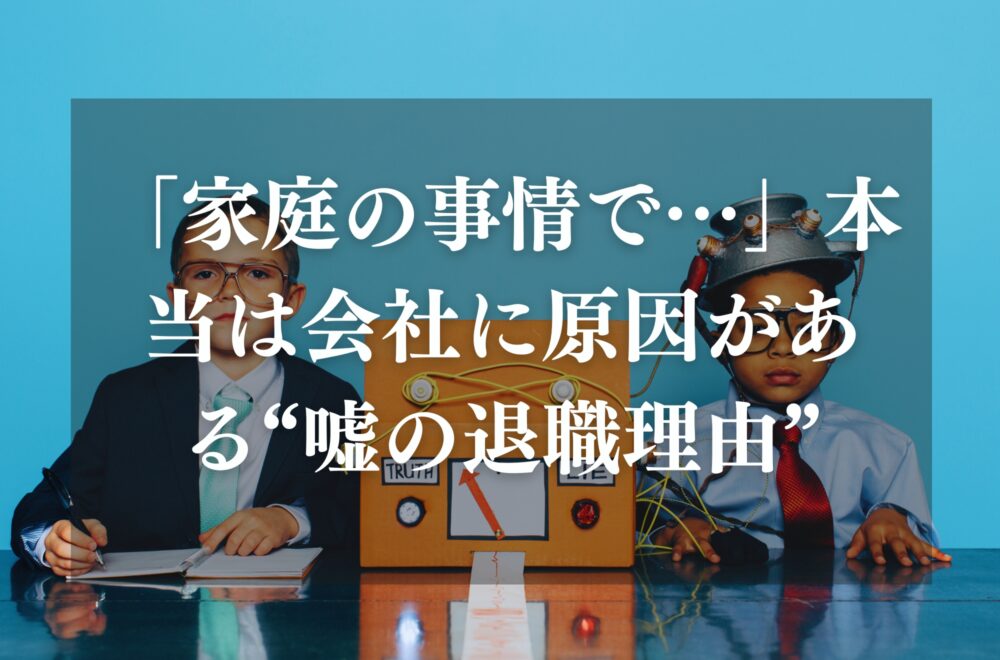外国人技能実習生の離職率が高すぎる理由とその対処法
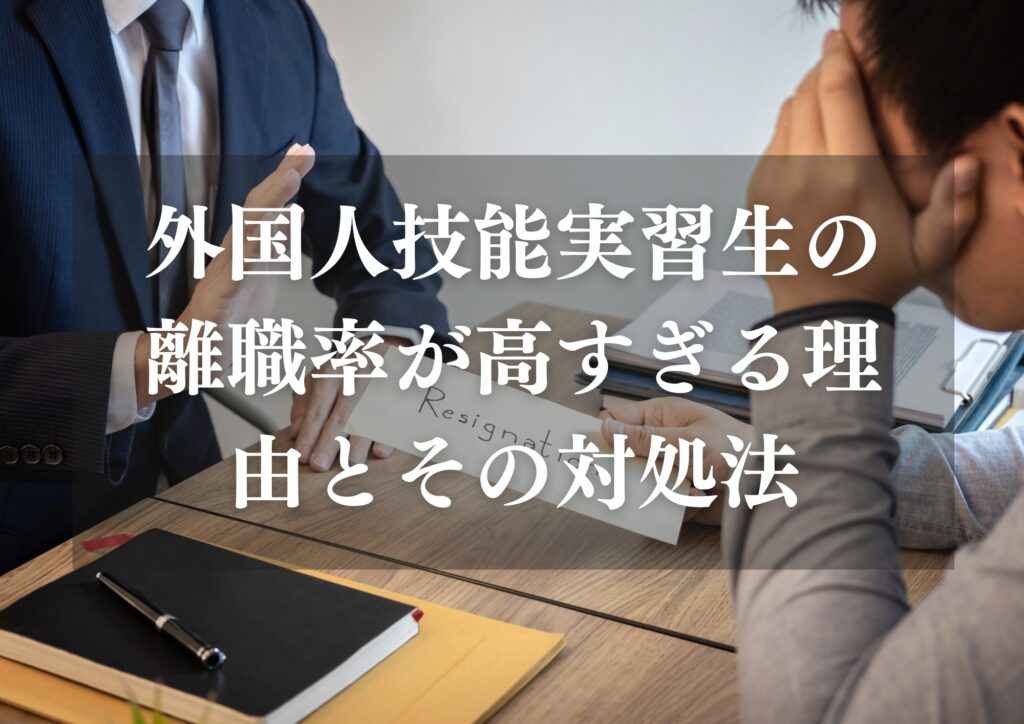
>目次(気になる記事のリンクをクリック下さい)
- ① 「気づいた時にはもう辞めてた」なぜ、技能実習生は突然消えるのか?
- ② 離職率45.8%の衝撃。日本の建設現場で何が起きているのか
- ③ 「やる気はあった」ではもう遅い——すれ違う期待と現実
- ④ 監督者の“沈黙”が辞職を招く。伝わっていないのは技術だけじゃない
- ⑤ 「うちは厳しいからしょうがない」と諦めていませんか?
- ⑥ 実習生の目に映る“日本の現場”は想像とどれだけ違ったか?
- ⑦ 「逃げた」「裏切られた」と言う前に考えるべきこと
- ⑧ 辞めた理由を“聞けてない”企業が、次に失敗する理由
- ⑨ 離職を防ぐカギは“指導”より“対話”。成功企業がやっていること
- ⑩ 離職を減らすたった1つの原則——「人として接する」
- 【まとめ】外国人技能実習生が辞める本当の理由、そして“辞めない現場”をつくるために
- この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武
- 多能工職人育成学校・技術研修所「職人道場紹介動画」
① 「気づいた時にはもう辞めてた」なぜ、技能実習生は突然消えるのか?

朝、いつも通り現場に出ると、ひとり足りない。
「寝坊か?」
「体調でも悪いのか?」
そんな程度の心配で電話をかけるが、繋がらない。
数時間後、監理団体から一本の連絡が入る。
「〇〇さんがいなくなりました。今、警察にも届けています」
——この瞬間、頭の中が真っ白になる。
「どうして?昨日まで元気だったのに」
「何かあったのか?それともウチに原因があったのか?」
…こんな経験をしたことがある建設会社の社長、少なくありません。
“突然の離職”は突然ではない
一見、何の前触れもなく見えるこの出来事。
でも、よくよく振り返ると、小さな“サイン”はいくつもあったはずです。
- 昼休みに誰とも話さなくなっていた
- 「大丈夫?」と聞いても、うつむくだけになっていた
- 笑顔が減っていた
- 指示への反応が鈍くなっていた
- 目を合わせなくなっていた
それを見逃してしまった。
いや、見ようとしていなかったのかもしれません。
「外国人だから、そういうもんだろ」
「大人しいタイプだから、まあ大丈夫」
「言葉も通じないし、細かいことは分からないし」
そうやって、“異変”を“誤差”として片付けてしまった結果が、突然の離職という形で返ってくるのです。
技能実習生が辞める理由は“言えなかったこと”にある
厚労省や監理団体の報告では、技能実習生の離職理由としてよく挙がるのは、
- 長時間労働
- 賃金の未払い
- 暴言やハラスメント
- 人間関係のストレス
- 文化や宗教への無理解
でも実際の現場では、もっと曖昧で、もっと根が深いものが理由になっているケースが多いんです。
たとえば、
- 「質問しても怒られそうで聞けなかった」
- 「失敗が怖くてずっと緊張していた」
- 「誰も話しかけてくれないから孤立した気がした」
- 「ミスを重ねて、自分がいてはいけないと感じた」
要するに、“言えない空気”に押しつぶされてしまったんです。
「うちはそんなブラックじゃない」は通用しない
ここでよくある反応が、「うちはきちんと指導していた」「他の職人とも普通に接していたはずだ」というものです。
でも、問題は“制度”でも“法律違反”でもないんです。
本人が「ここにいていい」と感じられなかったこと。
それが最大の“辞めた理由”です。
そしてこの「居場所感」は、制度やマニュアルでは作れません。
日々の小さなコミュニケーション、ちょっとした声かけ、ミスへのフォロー、そういう“人と人との関係性”が鍵になります。
「気づいたときにはいなかった」では遅すぎる
ある実習生は、こう言っていました。
「やめる決意をしたのは、1ヶ月前。でも言い出せなかった。誰も聞いてくれなかったから」
胸が痛む話です。
でも、これが現実です。
本人はずっと迷って、苦しんで、それでも誰にも相談できずに、
最後は“逃げる”しか選べなかった。
それを防ぐには、“日常の中に”聞ける環境、言える関係、安心できる瞬間が必要です。
最後に:問いかけてほしいたった一言
「最近、どう?困ってることない?」
たったこれだけで、救えるかもしれない離職があります。
たったそれだけで、「自分のことを気にかけてくれてる」と感じてくれる実習生がいます。
辞められてから後悔する前に、
言葉の壁を超える“想いのやり取り”があるかどうか。
それを、私たちが見直す時が来ているのではないでしょうか。
② 離職率45.8%の衝撃。日本の建設現場で何が起きているのか

45.8%。
これは、ある調査で明らかになった外国人技能実習生の建設業界における離職率です。
実習期間の途中で辞めてしまった、もしくは職場から“失踪”した実習生の割合。
「そんなにいるのかよ…」と驚く人もいれば、
「いや、うちの実感だとそれ以上だよ」とため息をつく人もいるでしょう。
この数字、決して一部の例外ではありません。
今、日本の建設現場全体が抱えている“共通の痛み”です。
技能実習制度は「人材育成」ではなく「人手補填」になっている
本来、外国人技能実習制度の目的は、発展途上国の人材に日本の技術や知識を伝え、母国の発展に役立ててもらう「国際貢献」でした。
しかし、現実にはどうでしょうか?
日本人が集まらないから、外国人で埋めよう
低コストで働く人材を確保しよう
3年間“使えれば”それでいい
——こうした“短期的発想”で制度を利用する企業が、少なからず存在しています。
その結果、教育よりも即戦力としての労働力を求め、育てる準備も支える体制もないまま現場に放り込まれる技能実習生が増えているのです。
「辞めた理由」は本当に“本人の問題”か?
辞めた技能実習生に理由を聞くと、決まってこう言います。
「仕事が難しすぎた」
「監督が怒ってばかりだった」
「誰も助けてくれなかった」
「話せる人がいなかった」
「休みが取れない」
でも、それを聞いた企業側の反応は、こんなふう。
「根性がない」
「文化の違い」
「本人が悪い」
「しょうがないことだ」
……この食い違いが、まさに今の建設業界の“縮図”です。
離職率の高さは、単なる個人の問題ではありません。
制度、現場、教育の仕組み、企業の意識——すべてが重なった“構造的な問題”なのです。
受け入れ人数は増えているのに、定着率は下がっているという事実
実習生の数は年々増加しています。
特に建設業は「特定技能制度」への移行も進み、外国人職人の受け入れに積極的です。
なのに、辞める人も比例して増えている。
これ、ものすごく矛盾してませんか?
人は来るけど、育たない。
育たないから、任せられない。
任せられないから、教育者が疲弊する。
疲弊するから、さらに辞める。
——この負のスパイラルを、現場任せで放置しているのが今の建設現場の姿です。
定着している現場は、何が違うのか?
では、逆に離職率が低い現場は、何が違うのでしょうか?
現場リーダーが、毎日一言だけでも声をかける
ミスがあった時に、“叱る前に説明する”文化がある
成長を“見える化”するノートや記録シートがある
教える人が“教え方”を学んでいる
通訳だけに頼らず、ジェスチャーや図で伝えている
こうした、“小さな違い”の積み重ねが、辞めない現場をつくっているのです。
つまり、「人のせい」ではなく「現場の設計」の問題。
最後に:45.8%の離職率を“仕方ない”で片付けない
離職率45.8%という数字は、もはや危機的です。
このまま放置すれば、「外国人は定着しない」「結局ダメだった」という偏見と諦めが広がっていくでしょう。
でも、その前に一度だけ立ち止まって考えてほしい。
辞めた理由は、現場の“何”だったのか?
定着している会社は、どんな工夫をしているのか?
自分たちは、“教育”と“労働”を履き違えていなかったか?
この問いかけこそが、
離職率を下げ、未来を変える第一歩になるのです。
③ 「やる気はあった」ではもう遅い——すれ違う期待と現実

「彼は最初、すごくやる気があったんです」
「ニコニコして、何でも“ハイ”って言ってくれた」
「まさか、辞めるなんて思ってもみなかった」
——これは、実習生が離職した後に企業側がよく口にする言葉です。
確かに、最初はやる気があった。
でも、その“やる気”は、どこかのタイミングで静かに消えてしまった。
気づいたときにはもう、現場にいなかった。
「やる気はあった」ではもう遅い。
実習生が去ってしまったあとに、そう思い知らされるんです。
「期待していたのに…」と落胆する前に
企業は当然、外国人実習生に期待します。
「少し教えれば動けるようになるだろう」
「まじめそうだから続けてくれるだろう」
「母国では建設経験があると言っていた」
——でもその期待が外れるとき、現場は混乱します。
「なに、これが“経験者”?」
「やる気あるって言ったよな?」
「口だけじゃないか…」
そしていつの間にか、期待は“失望”に変わり、
失望は“冷たさ”に変わっていく。
これが実習生との心の距離を広げ、離職を引き寄せてしまう一因です。
その“やる気”は、伝わっていたか?
ここで一つ、問いかけてみてください。
「実習生のやる気は、こちら側の期待と“すれ違っていた”だけではないか?」
たとえば、実習生は「もっと技術を学びたい」と思っている。
でも企業は、「とにかく戦力になってくれ」と思っている。
実習生は、「怒られるのが怖いから指示を待つ」。
でも現場は、「自分で考えて動いてくれ」と願っている。
——どちらも悪くない。だけど、ズレている。
このズレを修正しないまま日々が過ぎると、
「言われたことしかやらない」
「覚えが悪い」
「成長しない」
という評価になってしまう。
結果、実習生は「期待に応えられない自分」を責め、辞める決断をする。
“期待”は伝えなければ、ただの押しつけになる
実習生に対して「もっと頑張ってほしい」と思うなら、
まずその“期待”を、具体的な言葉で伝える努力が必要です。
- 「今はこれができればOK」
- 「次はこの作業を任せたいと思ってる」
- 「間違えてもいい。でもチャレンジしてほしい」
- 「君のことを信じてるから、練習してみよう」
こうした言葉があるだけで、
実習生の“やる気”は安心感に変わり、行動へとつながっていきます。
「やる気」だけでは乗り越えられない壁もある
建設現場の仕事は、決して簡単ではありません。
- 体力的にきつい
- 高所や重機など、恐怖感がある
- 天候やスケジュールによって変動が激しい
- 日本語での複雑な指示が飛び交う
- 職人気質の空気がプレッシャーになる
この中で、言葉も文化も違う実習生がやっていくには、
「やる気」だけでは正直、限界があるんです。
必要なのは、「どうやったらこの人が動けるか」を“設計する力”です。
成功している現場の“やる気の育て方”
ある企業では、実習生に“できたことリスト”を毎日書かせています。
- 今日できたことを3つ
- 明日やりたいことを1つ
- 困ったことを1つ
それを現場リーダーが軽く目を通し、1言だけコメントを書く。
たったこれだけのやりとりが、実習生の“やる気”を持続させ、
「自分は見てもらえてる」と感じさせ、離職率が大きく下がったのです。
やる気は最初に与えるものじゃない。
日々の積み重ねで“育てる”ものなんです。
最後に:すれ違いをなくす“ひとこと”の力
「期待してるよ」
「昨日より上手くなったね」
「大丈夫、少しずつでいいから」
「失敗しても、ちゃんと見てるよ」
こうした何気ない一言が、
実習生の中で「やる気」を“続ける力”に変えていきます。
「やる気はあった」では遅い。
でも、“やる気を続かせる関わり”があれば、離職は確実に減らせます。
④ 監督者の“沈黙”が辞職を招く。伝わっていないのは技術だけじゃない

「特に怒った覚えはない」
「いつも通りに接していたつもりだ」
「むしろ、何も言わず見守ってた」
——そう語る現場監督のもとから、また一人、外国人技能実習生が辞めていく。
“伝えていない”は、“優しさ”ではない。
むしろ、それが最大の孤立のサインになっていることに、気づいていない監督は多い。
技術は教えても、「気持ち」は置き去りにされている
建設現場で監督者が担う役割は大きい。
作業の指示、安全管理、スケジュール管理…その中で、外国人実習生の育成という新たな負担がのしかかる。
でもここで多くの監督がやってしまうのが、
- 必要最低限の指示しかしない
- 難しいことは通訳に任せる
- 仕事だけ見て、心の動きは見ない
という、“物理的には正しいが、心理的には何も伝わっていない関わり”だ。
これが続くと、実習生はこう感じるようになる。
「自分のことはどうでもいいんだ」
「失敗しても何も言われない…ってことは、期待されてない?」
「この現場に、自分の居場所はないのかも」
そう、技術以前に、“人としての接触”がなければ、誰だって不安になるのです。
“叱らない”=“安心”ではない
日本人の価値観では、「怒られない」は「大丈夫」と捉える人が多い。
でも、外国人実習生にとって、“沈黙”はむしろ怖い。
- 表情が読めない
- 何を考えているか分からない
- 「自分は嫌われているのでは?」と感じやすい
実習生は、叱られた方がまだ安心することもあります。
少なくとも、関心を持ってくれている証拠になるから。
だからこそ、ただ“何も言わない”のではなく、
「今のはこうしたらもっと良かったよ」
「ちょっと注意して見とこう」
「大丈夫、今のはみんな最初にやるミスだから」
——こうした“伝わる声”が、本当に必要なのです。
監督者は“仕事を回す人”から“人をつなぐ人”へ
今の建設現場では、現場監督に“教育者としての役割”が求められています。
でも、誰もそのやり方を教えてくれない。
結果として、「教えるのが苦手だから…」「外国人は難しいから…」と、関わること自体を避けるようになっていく。
その結果、現場には**“沈黙”だけが残る**。
沈黙の中で育つのは、信頼ではなく、不安と誤解。
やがてそれが積もって、辞職というかたちで“音を立てて”現場から消える。
「声をかける文化」が実習生の命綱になる
成功している企業は例外なく、“監督者の声”を大事にしています。
- 朝礼で「昨日、○○さんのここが良かった」と発言する
- 作業後に「今日どうだった?」と聞く時間を5分だけとる
- 日本語が伝わらなくても、笑顔とジェスチャーで反応する
- 小さな成長を「見逃さず」その場で褒める
これらはすべて、“沈黙”ではなく、“関わり”を伝える行為です。
実習生にとっては、それが**「ここにいてもいいんだ」と思える大きな支え**になります。
最後に:「黙っているから、大丈夫」ではない
技術は教えている。言葉も翻訳アプリで伝えている。
でも、それだけじゃ足りないんです。
- 「見てるよ」と伝えること
- 「失敗しても大丈夫」と感じさせること
- 「一緒に働く仲間」として認めていること
それが、外国人実習生が“辞めない現場”の共通点です。
監督者の一言、たった5秒のやりとりが、
人をつなぎ、未来を変える力になります。
⑤ 「うちは厳しいからしょうがない」と諦めていませんか?

「うちは昔から厳しい現場だから」
「言葉が通じなくても、自分で覚えてもらうしかない」
「あいつも最初は苦しんだけど、乗り越えたしな」
——そうやって、離職していく外国人実習生を“しょうがない”で済ませていませんか?
確かに、建設現場は甘くない。
体力勝負、危険作業、納期のプレッシャー、厳しい指導。
でも、それを“理由”にしてしまえば、未来の可能性は永遠に閉ざされてしまいます。
「厳しさ」と「無関心」は、違う
職人の世界には“厳しさ”がつきものです。
それ自体が悪いわけではありません。
問題は、その“厳しさ”が、
- 「本気で育てたい」から来ているのか
- 「教える余裕がない」から来ているのか
- 「相手に期待していない」から来ているのか
という**“中身”の違い**です。
前向きな厳しさには、必ず“フォロー”がついてきます。
- ミスの理由を説明する
- できたことをきちんと評価する
- 挑戦する姿勢を褒める
でも、そうしたフォローのない厳しさは、実習生にとってはただの無関心な冷たさに映ります。
「うちは厳しい」で済ませると、何も変わらない
この言葉は、実は非常に“危険な逃げ道”です。
- 教える仕組みをつくらない
- 声をかけないことに慣れる
- 辞めても「合わなかった」で片づける
こうして、気づけば外国人実習生の定着率はどんどん下がり、
「また採り直し」「また教え直し」…この繰り返し。
そのうち、現場は“誰も育てたくない空気”になっていきます。
「厳しさ」の意味を“翻訳”しよう
外国人実習生にとって、日本の建設現場の空気は“未知”です。
- 「怒鳴られる=嫌われている」と受け取る
- 「質問できない空気=話しかけちゃいけない」と思い込む
- 「何も言われない=期待されてない」と感じる
つまり、あなたが伝えたい“厳しさの中の愛”は、ちゃんと翻訳されていないんです。
だったら、そのままでは意味がない。
伝わらなければ、それはただの“ノイズ”になってしまう。
成功している現場は、厳しくても「辞めない」
「厳しくしてるけど、実習生が辞めない」
——そんな現場も、確かに存在します。
そこには、次のような特徴があります:
- 厳しさの後に必ず“フォロー”の言葉がある
- 小さなミスを成長のチャンスと捉える文化がある
- 「乗り越えた後の成長」を共に喜べる関係がある
- 厳しくしても、「嫌われない自信」がある監督がいる
つまり、厳しさを“愛のある教育”としてデザインできているんです。
「しょうがない」を“変えよう”に変えた企業の変化
ある建設会社では、実習生が3ヶ月で3人連続退職。
「うちは現場が厳しいからしょうがない」と諦めかけていました。
しかし、ある日リーダーが言いました。
「しょうがないって言葉を、“変えよう”に置き換えてみないか?」
それをきっかけに、小さな改革が始まりました。
- 朝礼での一言感謝メッセージ
- ミスの原因を一緒に振り返る時間の設定
- 1週間に1度の面談(5分だけ)を通訳と一緒に実施
その結果、離職ゼロが8ヶ月以上続いたのです。
最後に:厳しさは残していい。でも“届くように”しよう
厳しくあることを否定する必要はありません。
でも、その厳しさが“伝わっていない”なら、それは独りよがりです。
- 厳しい中にある温度
- 指導の先にある信頼
- 期待しているというまなざし
それを、伝わる形で届けてこそ、実習生は辞めず、ついてきてくれるのです。
“しょうがない”を“変えよう”に変える勇気を、今こそ。
⑥ 実習生の目に映る“日本の現場”は想像とどれだけ違ったか?

「日本の建設現場で働けば、技術が学べると思ってた」
「きっと丁寧に教えてもらえて、将来にも役立つはずだと期待してた」
「でも現実は、ただ毎日怒られて、何も学べなかった…」
これは、ある外国人技能実習生が離職した直後に口にした言葉です。
何気ない一言に聞こえるかもしれませんが、ここには制度の理想と現場の現実の深いギャップが詰まっています。
実習生が抱いていた“日本”は、もっと希望に満ちていた
実習生の多くは、母国で高い費用を払って来日しています。
なぜか?
- 日本で技術を学び、母国で仕事に活かしたい
- 安定した収入を得て、家族を支えたい
- 礼儀正しく、整った職場環境で働けると思った
- 真面目に頑張れば評価されると思っていた
つまり、彼らは“未来”に希望を抱いて来日しているのです。
しかし、そんな希望が現場で一瞬にして崩れていく瞬間がある。
「話が違う」
「夢を見すぎていたのかもしれない」
「早く帰りたい」——そう思ってしまったとき、離職という選択肢が現実味を帯びてくるのです。
日本の“当たり前”が、彼らには“異常”に映ることもある
私たちにとっては当たり前の現場でも、彼らの目線で見るとこんなふうに映っています。
- 作業前の段取りが説明されない(いきなり始まる)
- 怒鳴ることが普通の会話に思える
- 「察してくれ」がすべての前提
- 安全と言いながら、危ない作業が日常的にある
- 休憩中も誰も話しかけてくれない
これは、単なる文化の違いでは済まされない“構造の壁”です。
どれだけ丁寧に接しているつもりでも、伝わっていなければ意味がない。
実習生の“落差”が大きいほど、離職のリスクは高くなる
最も危険なのは、実習生が抱いていた“理想”と、現実の“差”が大きすぎる場合。
たとえば…
| 想像していた日本 | 実際に配属された現場 |
|---|---|
| 手取り足取り教えてくれる | 仕事は見て覚えろ |
| ゆっくりでも丁寧に指導される | スピード命、怒号が飛ぶ |
| コミュニケーションを大事にしてくれる | 誰とも話さず一日が終わる |
このギャップが続けば続くほど、「ここにいたら壊れてしまう」と感じるのは当然です。
認識のズレを埋めるには「最初の一週間」がカギ
このギャップを防ぐために最も重要なのは、実習生が現場に配属された“最初の一週間”の関わり方です。
- 現場のルールを丁寧に説明する
- 一日の流れをホワイトボードやスケジュール表で可視化する
- 「怒っているのではなく、緊張感を持ってほしい」と説明する
- 不明点を聞きやすい空気を最初に作る
この“初期対応”をするかしないかで、実習生の“心の姿勢”が180度変わります。
「伝えてる」はNGワード。「伝わっているか?」が重要
企業側はよくこう言います。
- 「ちゃんと説明した」
- 「通訳を通じて注意した」
- 「ルールは最初に教えた」
でもそれが“伝わっていたか”は、まったく別の話です。
- 実習生はその場で理解できたのか?
- 日本語の意味だけでなく、意図まで汲み取れたのか?
- 誤解があるまま放置されていなかったか?
この確認がないまま“スタートダッシュ”を失敗すると、実習生の心はどんどん現場から離れていってしまう。
最後に:理想を壊すのではなく、現実を育てる努力を
実習生が持っていた“日本の理想”をバカにしてはいけません。
むしろ、それだけ期待して来てくれたことを、誇りに思うべきです。
そして、その理想に少しでも近づけるように、
- 見える指導
- 聞ける雰囲気
- 伝わる言葉
を、現場の中に作っていく努力が必要です。
彼らにとって、日本の現場が“絶望”ではなく、“挑戦したくなる場所”になれば、離職率は必ず下がります。
⑦ 「逃げた」「裏切られた」と言う前に考えるべきこと
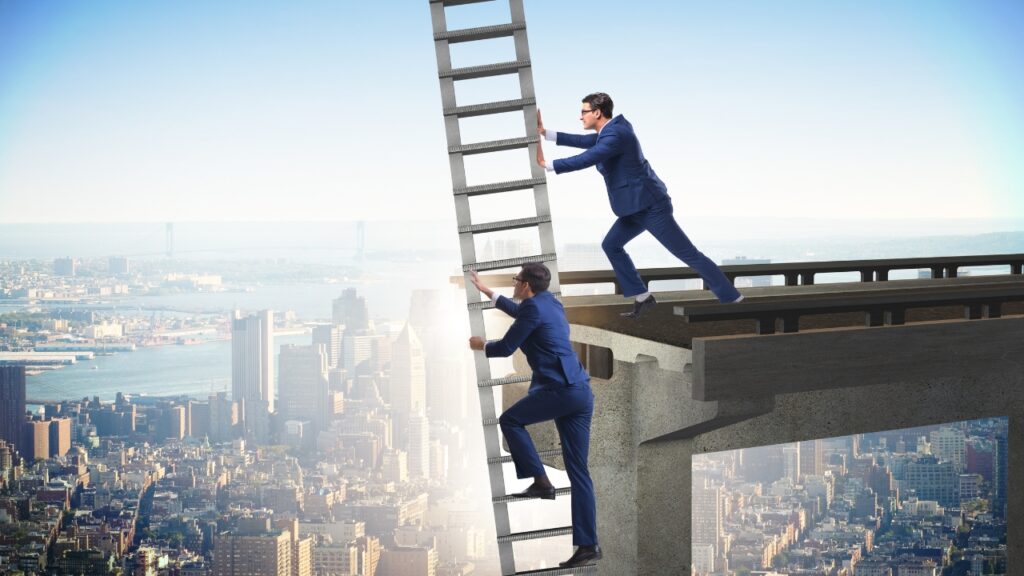
「また逃げたよ、あの実習生」
「真面目そうだったのに…裏切られた気分だ」
「金も時間もかけて育てたのに、何なんだよ」
——こうした声、現場のリアルな嘆きとしてよく聞きます。
確かに、途中で辞められることはつらい。
企業としては、期待して、投資して、信じていたわけですから、感情的になるのは当然です。
でも、その感情のまま「逃げた」「裏切りだ」と片づけてしまうと、本当に大切なことを見落としてしまうかもしれません。
本当に「逃げた」のか?それとも「逃げるしかなかった」のか?
私たちはつい、自分の立場からしか物事を見られなくなります。
「逃げた」と感じるその出来事、
実習生の側から見れば——
- 「どう伝えたらいいか分からなかった」
- 「相談する相手がいなかった」
- 「毎日が怖くて、何も考えられなかった」
- 「辞めるとは言えず、黙って去るしかなかった」
……という背景があることも少なくありません。
つまり、“逃げた”のではなく、「耐える言葉を持たなかった」だけなのです。
裏切りは、信頼があってこそ生まれる言葉
「裏切られた」という言葉の裏には、
- 信じていたのに
- 期待していたのに
- 頼りにしていたのに
という想いが隠れています。
だからこそ、離職は企業側にも痛みを残します。
でも、それを一方的に「裏切り」とすることで、
実習生の中にあった“葛藤”や“迷い”をすべて無視してしまうのは、少し寂しい気がしませんか?
本当に関係性があったなら、話せたはず
実習生が辞める前、何かサインはなかったでしょうか?
- 表情が曇っていた
- 元気がなかった
- 作業のペースが落ちていた
- 目を合わせなくなっていた
こうした“違和感”を感じたとき、
一言でも「最近どうした?」と声をかけていたら——
もしかすると、結末は変わっていたかもしれません。
離職という“答え”だけを見て怒るのではなく、
その“問いかけ”をしなかった自分たちに、一度立ち返ってみることも必要です。
失った信頼を、“次”にどう活かすか
一度離職されてしまえば、もう戻ることはありません。
でも、そこから学べることはたくさんあります。
- なぜ辞めたのか、原因をチームで共有する
- 実習生の声を、聞ける仕組みをつくる
- 辞めさせないための“日常のケア”を仕組みにする
- 育成担当者に、教育のスキルと裁量を与える
「裏切られた」ままで終わらせるか、
「教訓に変える」かで、次の実習生の未来は変わっていきます。
辞められた痛みを、前向きな問いに変えよう
「なぜ辞めた?」と怒るのではなく、
「どうすれば辞めなかった?」と考えてみてください。
- どこで気づけたか?
- どんな一言があれば防げたか?
- 誰が関われたら変わったか?
この“前向きな問い”こそが、離職を減らし、実習生との信頼をつくる出発点になります。
最後に:責めるより、次をつくる
離職は、企業にとって大きな損失です。
でも、“次に同じことを繰り返さない”と決めたとき、それは貴重な財産に変わります。
逃げられたのではない。
裏切られたのではない。
声を届けられなかった。
ただ、それだけかもしれません。
だからこそ、次の一人には、
「君の声は聞こえているよ」と伝えられる現場を、
一緒につくっていきましょう。
⑧ 辞めた理由を“聞けてない”企業が、次に失敗する理由
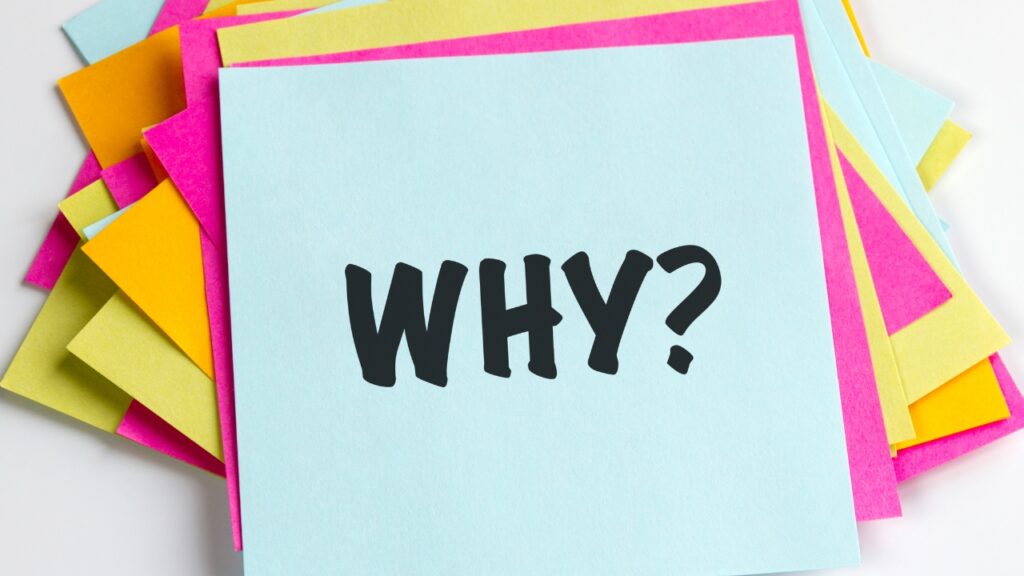
「理由は分からない。何も言わずにいなくなった」
「こっちから聞く前に辞めちゃったんだから、しょうがないよ」
「まあ合わなかったんだろうな、次の子に期待するしかない」
——こんな風に、実習生の離職理由を“うやむや”のまま終わらせていませんか?
でも、ここに次の離職が起こる種が、確実に蒔かれていることに、気づいている企業は少ないのです。
理由を聞けなかったのではない。「聞こうとしなかった」だけかもしれない
辞めていった実習生に、「なぜ?」と尋ねても、
- 「家族の都合です」
- 「体調が悪くて…」
- 「もっと違う仕事がしたくなった」
と、どこか本音を避けるような回答が返ってくることが多い。
でも本当は——
「怒られるのが怖かった」
「誰にも話しかけられなくて孤独だった」
「ミスをしたとき、誰も助けてくれなかった」
そんな声が、心の奥に隠れていたかもしれない。
しかしそれは、“聞かれなかったから話さなかった”のです。
辞めた理由を可視化しなければ、現場は永遠に変わらない
技能実習制度は“送り出して終わり”ではありません。
「定着率」と「現場の改善」は、次の採用の成否を分けます。
それなのに、辞めた理由を明確にしないまま「次」を採用すればどうなるか?
- 同じミスをまた繰り返す
- 教える人も同じ壁にぶつかる
- 実習生は同じところで心が折れる
- 「やっぱり外国人は続かない」とレッテルが貼られる
こうして、人が育たない“負のサイクル”が回り続けるのです。
本音は“退職後”でないと語れないこともある
興味深い話があります。
職人道場が独自で行っている「退職後インタビュー」では、在職中は話せなかった本音が、ポロリと出てきます。
- 「怖くて聞けなかっただけです」
- 「作業自体は好きだったんです。でも怒られると泣きそうになった」
- 「もっと話せる時間があれば違ったと思います」
ここに、次の人材を守るための“教訓”が山ほど詰まっているのです。
「うちは大丈夫」こそが最大の危険サイン
企業の中には、離職者が出ても「今回はたまたま運が悪かった」と処理してしまうところもあります。
でも、辞めた理由を深掘りしなければ、「根本的な問題」がどこにあったのか、永遠に分からないまま。
結果、次の実習生にも同じような接し方をしてしまい、
また数ヶ月後、「いなくなった」「続かなかった」「期待外れだった」となる。
この繰り返しは、
単なる失敗ではなく、“学ばない姿勢”が原因で起きる事故なんです。
成功している企業は、“聞く力”が違う
実習生の離職率が低い企業には、共通点があります。
- 辞職の理由を本人・監理団体・現場全員で振り返る
- 改善点を“可視化”して、次の配属に活かす
- 面談を“建前”ではなく、“信頼関係構築の場”として活用する
- 実習生の“声”を現場マネジメントの中心に据えている
つまり、「話を聞く」ことを“仕組み”として組み込んでいるんです。
最後に:辞めた人の声が、未来の誰かを救う
もう辞めた人の話なんて、聞いても意味がない?
いえ、むしろ逆です。
辞めた人こそが、何が足りなかったかを一番知っている。
その声を無視するか、活かすかで、
次の実習生が“1日で辞めるか”、“3年続くか”が決まる。
だから、勇気を出して聞いてほしいのです。
「君が辞めた理由を、次に活かしたい」と。
⑨ 離職を防ぐカギは“指導”より“対話”。成功企業がやっていること

「どうやって教えるか」を必死に工夫しているのに、なぜか辞められてしまう。
「技術は伝えた。仕事もさせた。じゃあ、何が足りなかったのか…?」
その答え、実はとてもシンプルかもしれません。
それは――「話していなかった」こと。
建設業の外国人実習生の離職を防ぐ最大のカギは、
“指導”よりも“対話”にあるのです。
指導している「つもり」が実は一方通行
現場ではよくこう言います:
- 「こうやるんだって言ったよな?」
- 「昨日も教えたよな?」
- 「マニュアルも渡しただろ?」
たしかに“指導”はしている。
でも、それが相手に届いているかは、まったく別問題です。
伝えた内容が理解されているか、
相手がどう受け止めているか、
何か困っていることはないか――
それを確認するのが、「対話」の役目です。
対話とは、信頼を“つなぐ橋”
外国人実習生にとって、
見知らぬ国、文化、言葉、現場、ルール…
すべてが“異国の圧力”としてのしかかっています。
そんな中で唯一心をつなぎ止めてくれるのが、
自分のことをちゃんと“聞いてくれる人”の存在です。
- 「今日はどうだった?」
- 「困ったことあった?」
- 「無理してない?」
- 「これ、どう感じた?」
この何気ない対話の積み重ねが、
「この人になら相談していいかも」と感じさせ、
辞めずに残る決断へとつながるのです。
成功している企業は“会話の習慣”がある
離職率が低く、実習生が定着している企業には共通点があります。
それは、“会話の場”を意図的につくっていること。
例えば――
- 朝礼後に1対1の3分間トーク(週2回)
- 作業終わりに「できたことノート」を一緒に見る
- 月に一度の“ざっくばらん”面談(通訳付きでもOK)
- 食事や休憩時間にあえて一緒に座るルール
これらは単に雑談ではなく、信頼構築の儀式のようなものです。
「日本語が通じない」ではなく、「伝わる工夫が足りない」
よくある誤解が、「言葉が通じないから話せない」という考え。
でも、対話は言語だけではないんです。
- ジェスチャー
- 笑顔
- うなずき
- 図解
- 翻訳アプリ
どれも立派な“会話のツール”です。
大事なのは、「話そうとする姿勢」と「相手の声を受け止める構え」。
これさえあれば、国も文化も超えて“信頼”は生まれます。
指導はスキル、対話はケア。どちらが欠けても人は育たない
技術は、指導で伝えられる。
でも、継続は、対話でしか生まれない。
- 指導だけでは、関係が“業務的”になる
- 対話があって初めて、“人と人”の関係になる
- 技術は「やらせる」で教えられるが、心は「話す」でしか支えられない
だからこそ、育成のプロセスに“対話の時間”を組み込むことが、
離職を防ぐ最大の工夫となるのです。
最後に:「教える」前に、「話せる関係」を
仕事の前に、関係がある。
作業の前に、信頼がある。
育成の前に、「大丈夫?」と聞ける関係がある。
この“順番”を間違えなければ、
外国人実習生は必ず、職場に残ってくれます。
教えることに集中する前に、
まずは話しかけてみてください。
それが、離職を防ぐためのいちばん確実な第一歩です。
⑩ 離職を減らすたった1つの原則——「人として接する」

外国人技能実習生が辞める理由はさまざまです。
言葉の壁、文化の違い、指導不足、孤独、不安、恐怖、誤解、誤認、そして“無言の拒絶”。
けれど、それらすべてを一言でまとめるとすれば――
「人として接されていない」と感じたこと。
この感覚こそが、彼らを静かに、しかし確実に現場から遠ざけていく最大の理由です。
技術を教えても、人としての尊重がなければ定着しない
どれだけ立派な技能を教えても、
どれだけ安全管理が完璧でも、
どれだけ制度や書類が整っていても、
その人自身を“労働力”としてしか見ていなければ、辞めていきます。
外国人実習生にとっての離職は、
単なる転職でも移動でもありません。
ときには“絶望からの脱出”です。
だからこそ、そこに至る前に、
「あなたを人として尊重している」という態度が、何よりも必要なのです。
叱ってもいい。厳しくしてもいい。でも「無関心」はNG
日本の建設現場には、「育成=厳しく叱ること」という文化がまだ根強く残っています。
それ自体が悪いわけではありません。
でも、そこに**“見ているよ”“気にかけているよ”という眼差し**がなければ、
その厳しさはただの“拒絶”になります。
人として扱うとは、こういうことです。
- ミスしたときに「なぜそうなったのか?」と聞くこと
- 作業が遅くても「できるようになろう」と励ますこと
- 苦しんでいる表情に気づいたら「大丈夫?」と声をかけること
- 辞めそうな空気を感じたら、引き止める勇気を持つこと
こうした些細な行動が、“見られている安心感”と“信頼”を生むのです。
「人として接する」ができる現場は、どこまでも強い
職人道場で育った実習生たちに、
「一番印象に残っているのは?」と聞くと、
多くが「日本人の講師が、自分の目を見て話してくれたこと」と答えます。
技術じゃないんです。
道具の使い方でもない。
“人として扱ってくれた”という体験こそが、最も記憶に残る。
その経験があるからこそ、
- つらくても耐えられる
- 指導にも耳を傾けられる
- 怒られても逃げずにいられる
- 3年を乗り越え、さらに働き続けようと思える
そんな現場は、外国人実習生にとって“居場所”になります。
人手不足の時代に求められるのは「人扱いの技術」
AI、ロボット、機械化、デジタル化。
どれだけ進化しても、建設現場は「人の力」に支えられています。
だからこそ、これからの現場に必要なのは、
“人を扱う技術”ではなく、“人として接する姿勢”です。
「使える人」ではなく、「一緒に働ける人」を育てる。
その発想の転換が、これからの採用と定着の鍵になります。
最後に:あなたは、彼らを“人”として見ていますか?
「仕事はしている」
「指示は出している」
「怒ってないし、放ってもいない」
でもそれだけでは、足りません。
- 「その人がどう感じているか」
- 「今、苦しんでいないか」
- 「孤立していないか」
- 「未来に希望を持てているか」
そうした“人としての視点”を持てたとき、
はじめてあなたの現場は、“辞めたくない場所”に変わります。
離職を減らすたったひとつの原則。
それは**「人として接する」こと。**
このシンプルで、でも最も大切な原則に立ち返るとき、
あなたの現場に新しい風が吹き始めるはずです。
【まとめ】外国人技能実習生が辞める本当の理由、そして“辞めない現場”をつくるために

外国人技能実習生の離職率が高い――その事実に、私たちはもう目を背けることはできません。
制度の限界、文化の壁、言葉の違い、そして現場の“無関心”。そのすべてが絡まり、彼らの“離職”という選択を後押ししています。
でも、辞めるまでには、必ず小さなサインがあったはずです。
- 話しかけても目をそらした
- 作業スピードが落ちた
- 表情が硬くなった
- ミスのあと、沈黙が続いた
それを「気づかなかった」と言ってしまうのか。
それとも「気づける現場」に変えるのか。
そこに、未来のすべてがかかっています。
今回ご紹介した10の視点からわかるのは、
離職の原因は“人のせい”ではなく、“仕組みと関係性”の問題であるということです。
厳しさがあってもいい。ミスがあってもいい。
でも、「この人になら話してもいい」「ここなら安心して働ける」と思える場をつくれるかどうか。
それが、離職率を大きく左右するのです。
外国人実習生は、決して“労働力”ではありません。
夢と希望を抱えてやってきた、一人の人間です。
その人に、私たちがどれだけ“人として”接することができるか――
その問いに、もう一度真剣に向き合うときが来ています。
そしてその先には、辞めない実習生、成長する現場、笑顔で働くチームという、確かな未来が待っています。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。