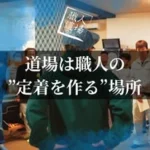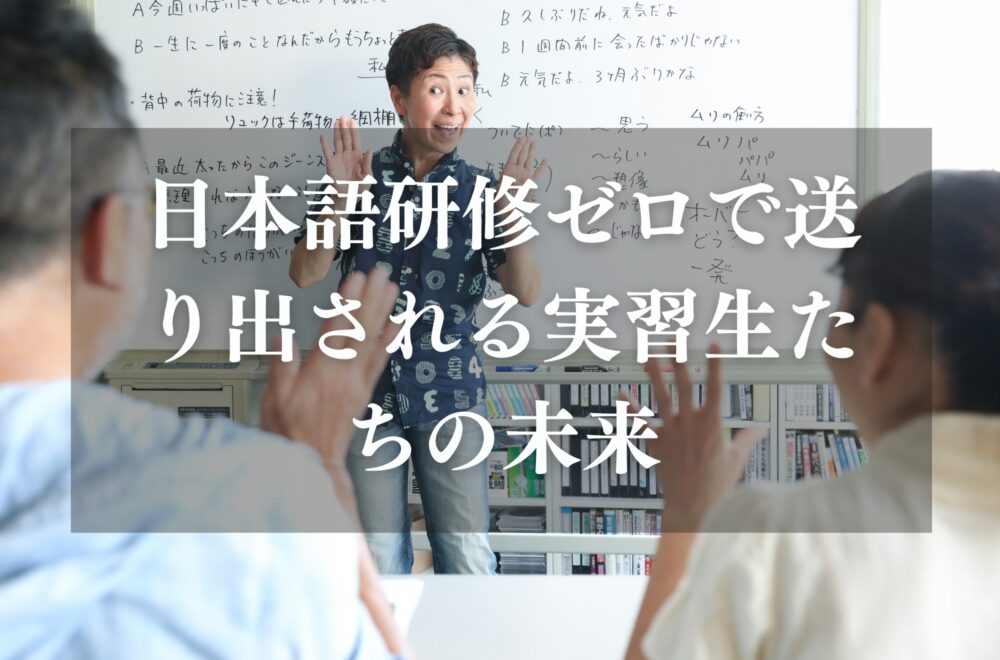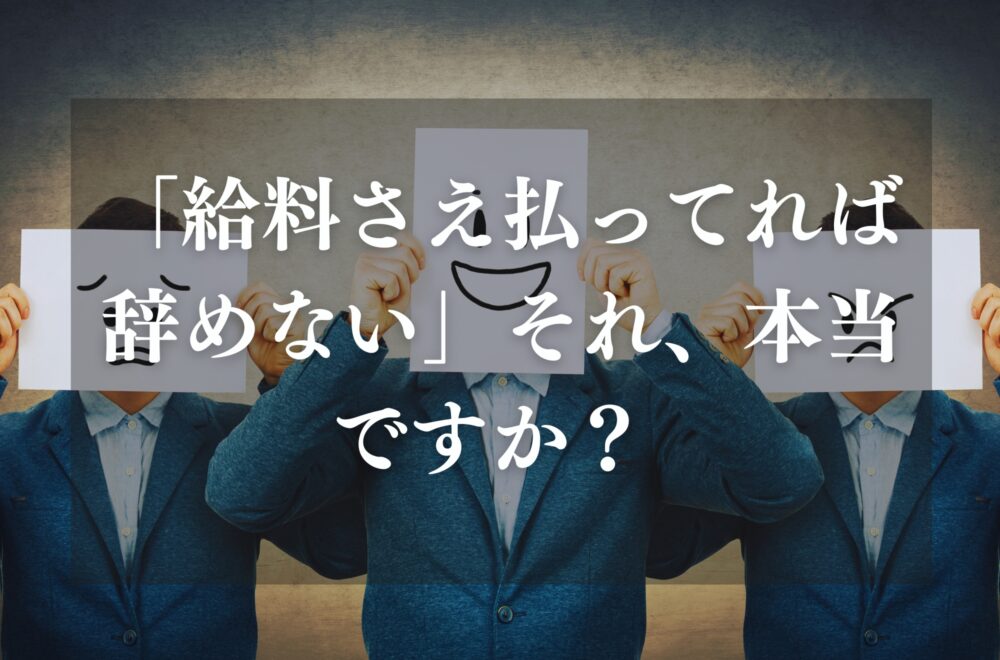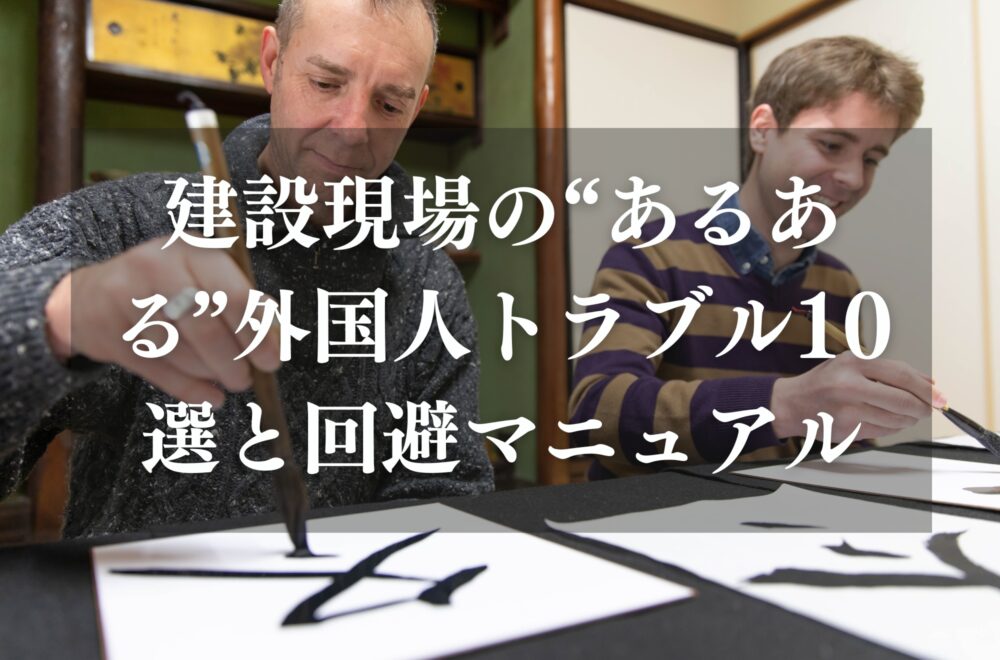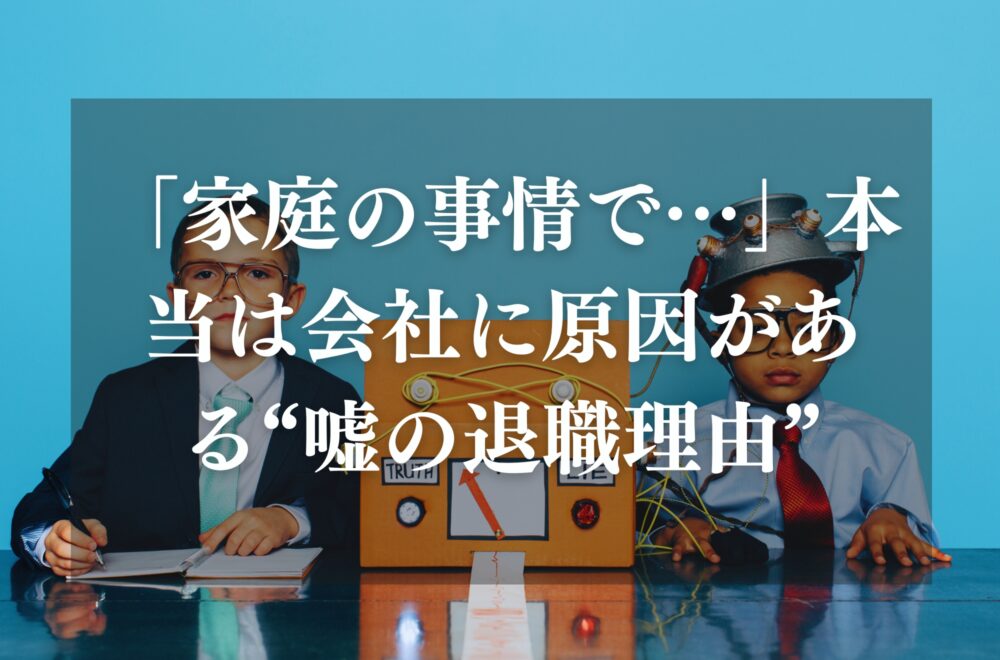外国人職人が定着する現場とすぐ辞める現場、何が違う?
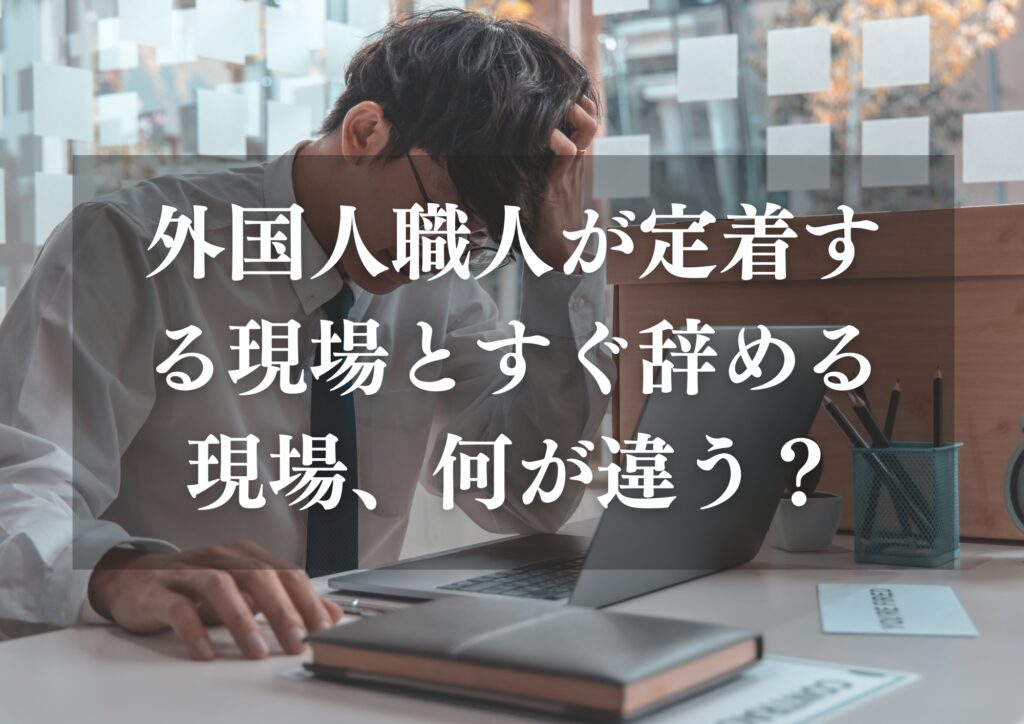
>目次(気になる記事のリンクをクリック下さい)
- ① 外国人職人の離職率はなぜ高い?数字が示す現場の実態とその背景
- ② 「定着する現場」には何がある?共通する“3つのキーワード”
- ③ すぐ辞める現場の特徴①:教育は“放任”で、指示が曖昧
- ④ すぐ辞める現場の特徴②:“仲間意識”が希薄な人間関係
- ⑤ 言葉だけじゃない。外国人職人との“伝達の質”が定着率を左右する
- ⑥ 定着する企業がやっている“期待の見える化”とは?
- ⑦ モチベーション管理の成否が離職率を決める——“声かけ”の科学
- ⑧ 定着率を高める現場の“指導者育成”という視点
- ⑨ 失敗から学んだ企業の改革事例——「もう辞めさせない」への挑戦
- ⑩ 定着率を改善するために、今すぐ見直すべき5つのポイント
- 【まとめ】外国人職人が定着する現場とすぐ辞める現場、その分かれ道は“仕組み”ではなく“姿勢”だった
- この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武
- 多能工職人育成学校・技術研修所「職人道場紹介動画」
① 外国人職人の離職率はなぜ高い?数字が示す現場の実態とその背景
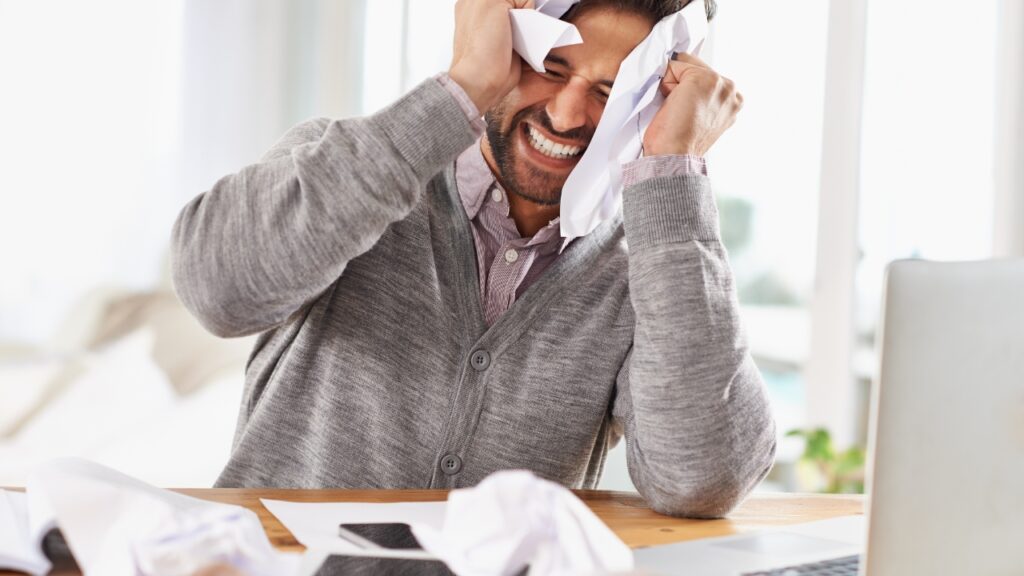
建設業における人材確保の打開策として、外国人職人の受け入れはここ10年で急速に進んできました。
技能実習制度、特定技能、さらには企業独自の採用ルートを通じ、多くの外国人材が現場に送り込まれています。
しかし、その一方で見逃せないのが高い離職率です。
とくに3年未満での離脱率は、日本人若手よりも高い傾向にあり、一部の現場では半年以内の離職率が30%を超えるケースも報告されています。
この現象は一過性の問題ではなく、構造的な課題として産業全体の生産性や継続性に深刻な影響を与えています。
離職率のデータが語る現場の“ゆがみ”
厚生労働省や出入国在留管理庁、JITCOなどの機関が公表する統計資料からも、外国人職人の早期離職が慢性化している実態は明白です。
- 技能実習生の途中離脱率:約12〜15%(業種により異なる)
- 特定技能移行前の離職:最大約40%超
- 建設業に限った調査では、「現場に定着しない」「数か月で失踪」などの報告が急増
この数字の裏には、「個人の能力や適性の問題」ではなく、受け入れ体制の不備と現場環境の設計ミスが存在します。
高離職の要因は“多重構造”で発生している
離職率の高さは、単一要因で語れるものではありません。むしろ、以下のようにいくつもの構造的問題が複雑に絡み合っています。
- コミュニケーション障害
言語的障壁だけでなく、非言語コミュニケーション(空気の読み合い、察する文化)が機能しない。 - 指導者側の準備不足
教える側に“教育スキル”や“異文化理解”がないまま実務を任せてしまう。 - 労働環境の過酷さ
現場の安全・衛生・作業時間管理が曖昧なまま放置され、実習生が精神的・肉体的に疲弊する。 - 制度設計の“ズレ”
技能実習制度の目的(人材育成)と企業側の目的(即戦力労働力)が乖離し、「学ばせる場」が「働かせる場」に変質している。 - 帰属意識の欠如
職場に“仲間”を感じられない環境では、多少の不満や困難でも即離職につながりやすい。
離職は「突然」ではない。数字に表れない“予兆”がある
数字として表れるのは「辞めたあと」です。
しかし実際には、離職という行動には必ず“予兆”があります。
- 会話量の減少
- 小さなミスの連続
- 朝の挨拶が曖昧になる
- 昼休みに一人で過ごす時間が増える
- 指示に対するリアクションが鈍くなる
こうした兆候を見逃さず、拾い上げる仕組みや感度を企業が持っているかどうかが、定着率を左右する分水嶺となるのです。
数字を“現象”で終わらせないために、企業が持つべき視点
離職率の高さを単なる「仕方のないこと」「外国人は続かない」と捉える姿勢は、結果として企業自身の組織力を損なう原因になります。
必要なのは、離職率を“現象”ではなく、“警鐘”として受け止める力です。
- なぜ辞めたのかを記録し、蓄積し、分析する
- 現場責任者に離職原因と対策の研修機会を与える
- 外国人職人への定期面談・満足度アンケートを実施する
- 成功している現場の要素を“モデル化”して横展開する
こうしたデータとフィードバックを基にした定着率向上策が、今の建設業界に求められている“次の常識”です。
最後に:数字は真実を隠さない。読み取るのは“企業の姿勢”である
離職率が高いという“結果”だけを見て、「人が悪い」「制度が悪い」と責任を押しつけ合うのではなく、
その数字から何を学ぶかが企業の成熟度を示します。
外国人職人が本当に定着する現場とは、**「数字を感情ではなく構造で捉え、改善を続けられる場所」**です。
② 「定着する現場」には何がある?共通する“3つのキーワード”
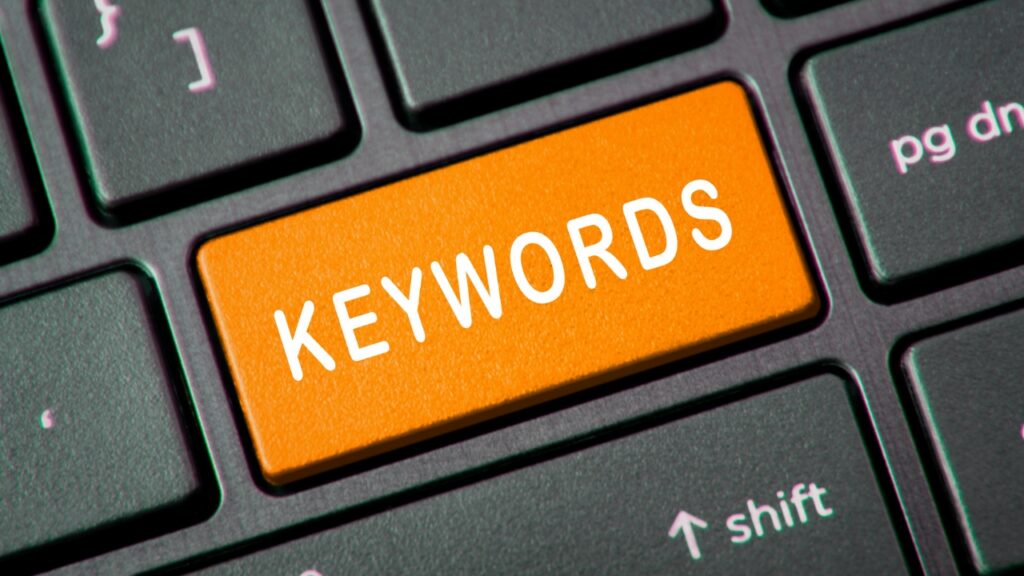
外国人職人の離職率が高いという現実の一方で、**「定着率90%超」「3年以上勤務が当たり前」**という企業が存在するのもまた事実です。
同じ制度、同じ文化の壁、同じ言語環境の中で、なぜここまで差が出るのか?
その答えは、“仕組み”ではなく、“現場に根付いた文化と意識”にあるのです。
職人道場のフィールドリサーチと、複数企業の定着事例をもとに導き出された、定着する現場の共通点を象徴する3つのキーワードをご紹介します。
キーワード①「可視化」
定着する企業では、「職人の成長」「期待されている役割」「できたこと・できなかったこと」を常に**“見える化”**しています。
- 今日できた作業をチェックリストで可視化
- 習得スキルをホワイトボードで掲示
- ミスした内容と、改善策の共有ノート化
- 翌日の予定や目標を簡単に翻訳して伝達
この“可視化”によって、外国人職人は**「自分が前に進んでいる感覚」**を持てます。
それが自信につながり、モチベーションの維持へと直結します。
キーワード②「対話」
定着率が高い現場に共通するのが、「業務外の対話」が自然に行われていることです。
- 「今日はどうだった?」と毎日の声かけ
- 週1回、雑談中心の個別面談を5分間だけでも実施
- 昼休みに日本人職人と一緒に過ごすよう配置を工夫
- 宗教や文化背景について話題にするオープンな空気
こうした“小さな会話”が、
**「話してもいいんだ」「ここにいてもいいんだ」**という感覚を芽生えさせ、離職の引き金となる孤独や不安を大きく減らします。
キーワード③「期待」
意外と見落とされがちなのが、「あなたに期待している」というメッセージを明確に伝えているかどうかです。
- 「来月から、この作業を任せたいと思ってるよ」
- 「君の段取りが上手くなったって、みんな言ってる」
- 「あと少しで一人前だね。楽しみだ」
これらの言葉が、**本人の「ここで働く理由」**をつくります。
定着する現場は、“作業指示”だけでなく、“期待表現”を日常的に行っているのです。
「可視化・対話・期待」が根づく現場の成果
職人道場と連携するA社では、この3つのキーワードを教育設計に組み込んだことで、
それまで6ヶ月で3割離職していた実習生が、過去2年間、1人も辞めていません。
- 技能の評価をスコアカードで見せる
- 週報に「本人の声」と「指導者のコメント」両方を記録
- 全体朝礼で1人ずつ「今週のがんばり」を発表
単に制度を整えるだけでは得られない、**現場の一体感と“人間関係の粘度”**が、ここに現れています。
最後に:「根性」ではなく、「構造」で定着は生まれる
定着率の高さは、偶然でも気合いでもありません。
それは、現場に根づいた文化=「人を育てる意思」が構造として表れている結果です。
可視化・対話・期待。
この3つを軸にした育成文化こそが、外国人職人が「ここで働き続けたい」と思える職場を生み出します。
③ すぐ辞める現場の特徴①:教育は“放任”で、指示が曖昧

「とりあえず現場で見て覚えてもらう」
「一回やってみれば、なんとかなる」
「日本人と同じように扱ってるつもりだけど…なぜか辞める」
——この“教育スタイル”、外国人職人にとっては放任と混乱の連続でしかありません。
離職率の高い現場を調査すると、最も顕著な問題として浮かび上がるのがこの「指示の曖昧さ」と「教育の不在」です。
「任せる」と「放っておく」は違う
建設現場では、熟練職人の“背中を見て覚えろ”という文化が根強く残っています。
これは日本人の若手にはある程度機能する場面もあるかもしれません。
しかし、外国人職人にその前提は通用しません。
- 言葉が完全に理解できていない
- 工具や作業名称が母国と異なる
- “察する”文化がない
この状況下で「とりあえずやってみろ」は、“何をやればいいのか分からない”という不安と孤立を生むだけです。
指示の曖昧さは“業務エラー”の元凶
以下は、定着率の低い現場でよく見られる問題点です:
- 作業指示が抽象的:「あれやって」「昨日と同じで」
- 進捗のフィードバックがない:「何も言われない=合っている?」
- 間違っても訂正がされない:「また怒られるかも…次はどうしよう」
- 一人で悩む時間が長い:「質問できない空気が怖い」
こうした状況が積み重なり、外国人職人の中で**「ここには居場所がない」という認識**が強まっていきます。
「教えている」は“伝えている”ではない
企業側はよく言います:
- 「教えたよ」
- 「マニュアル渡してる」
- 「一緒に現場入ってる」
しかし、伝えたつもりと、相手に伝わっているかは全く別の話。
- 日本語の表現を理解できていない
- 作業手順を言葉だけで説明されてもイメージできない
- 質問しても“雑に返された”記憶が残っている
教育が“機能していない現場”では、職人本人が常に不安の中で動いている状態になります。
その結果、身体的な疲労よりも前に、精神的な限界が訪れるのです。
教育=設計+継続+観察である
職人道場では、外国人職人を定着させる教育の3原則として、以下を重視しています。
- 設計:段階的に「今日はここまでできればOK」という指標を明確化
- 継続:1日10分でもいいので、毎日“習慣として教える”時間を確保
- 観察:本人の表情・動き・反応から、理解度とストレスを測る
この3つがそろってはじめて、“指導”が“教育”になります。
最後に:放任は自由ではない。曖昧さは信頼の欠如である
すぐ辞める現場は、「本人に任せた」という名のもとに放置しているのが実態です。
そして、あいまいな指示の裏には、「この人には細かく教える必要がない」という無意識の諦めがあることも少なくありません。
外国人職人にとって最も重要なのは、「この現場で成長できるか」という実感です。
それを与えるためには、**“明確な道筋”と“教える覚悟”**が不可欠です。
教えない現場に、職人は残りません。
④ すぐ辞める現場の特徴②:“仲間意識”が希薄な人間関係

建設現場はチームで成り立つ職場です。
職長、監督、作業員、それぞれが連携しながら、一つの工程を成し遂げていく。
だからこそ、本来は“仲間意識”が最も根づきやすい業種でもあるはずです。
しかし、外国人職人の離職率が高い現場では、驚くほどこの**「仲間意識」が希薄**です。
それは明確ないじめや差別ではなく、“無関心”や“排他的空気”という形で現れます。
「誰とも話さない一日」が、彼らの心を蝕む
職人道場の聞き取り調査で、離職経験のある外国人職人がこう語っています。
「一日中、誰とも言葉を交わさない日が続いた」
「仕事中、誰も目を合わせてくれなかった」
「“よそ者”として扱われている気がした」
これは、指導や教育以前の問題です。
“仲間として迎え入れる意思”が感じられない現場は、たとえ待遇や制度が整っていても、実習生の心はすぐに離れていきます。
現場の“空気”が辞める理由になる
仲間意識の欠如は、目に見えない形で職人の心理に影響を及ぼします。
- ミスをしても誰も声をかけない
- 昼休憩は外国人だけで固まり、日本人は別の場所で談笑
- 相談できる相手がいない
- 一緒にいても“ひとり”と感じる
こうした状態が続けば、仕事そのものよりも“職場にいること”がつらくなるのです。
これは精神的な孤立であり、まぎれもなく「人間関係による離職」です。
「仲間」として扱われることは、教育より先に必要な要素
外国人職人の多くは、「仕事ができるようになりたい」と強く願っています。
しかしその前に、「安心して働ける関係性」がなければ、学ぶ気持ちは生まれません。
- 「わからない」と言える空気
- ミスをしても責められず、支えてもらえる感覚
- 自分の存在が認められていると実感できる場
これらが整って初めて、「この人たちと一緒に働きたい」「もっと役に立ちたい」と思えるのです。
仲間意識の“きっかけ”は、ほんの小さな行動から始まる
定着率の高い企業では、以下のような“人間関係の設計”を工夫しています。
- 毎朝のラジオ体操後に全員で輪になって短い会話をする
- 昼食をグループで取ることを推奨し、話題提供をする
- 誕生日や国の祝日にささやかなメッセージカードを渡す
- 1ヶ月に1回、全職人参加の“技能交流会”を開く
これらは、強制ではありません。
しかし、こうした“仲間づくりの仕掛け”が離職を未然に防ぎ、チームとしての一体感を生み出しているのです。
最後に:一緒に汗を流した日は、「仲間」になれるか?
人間関係とは、“時間”と“接点”の中で育つものです。
外国人職人が日本人職人と一緒に過ごす時間が、単なる作業時間にとどまらず、“感情の共有”を含んでいるかどうか。
そこにこそ、“すぐ辞める現場”と“ずっと働きたい現場”の決定的な差があります。
仲間にされなかった人は、職場ではなく「逃げ場所」を探し始める。
仲間として扱われた人は、「もっと役に立ちたい」と思い始める。
人は、人によって辞める。
そして、人によって残るのです。
⑤ 言葉だけじゃない。外国人職人との“伝達の質”が定着率を左右する

「日本語が通じないから仕方ない」
「通訳を通して言ったんだけど…伝わってなかった」
「言っても無反応で、やる気があるのか分からない」
——現場で外国人職人と接するなかで、こんな悩みを抱えている監督・職長は少なくありません。
しかし本当に問題なのは「言語能力」ではありません。
伝えている“内容”ではなく、“伝わり方”に問題があるケースが圧倒的に多いのです。
言語力よりも“伝達設計力”が問われる時代
現場でのコミュニケーションには、以下のような3つの要素があります。
- 情報の正確さ
例:どの作業を、どの順序で、どこまでやるのか - 意図の共有
例:なぜその作業が重要なのか、失敗するとどうなるのか - 感情の伝達
例:できたことに対する評価、感謝、期待
このすべてが「伝達の質」です。
つまり「作業指示だけでは不十分」であり、背景や感情を伝えることが信頼構築につながるのです。
定着しない現場では“伝わったフリ”が常態化している
外国人職人の多くは、こんなふうに考えています。
「分からないけど、うなずいておこう」
「また聞いたら怒られるかもしれない」
「“はい”と言えば乗り切れるかも」
一方、現場側は…
「はいって言ったよな?」
「伝えたよな?やってなかったのは本人の責任だ」
「通訳に任せたのに、なんで?」
このすれ違いが日々蓄積され、最終的に**「辞めます」の一言で破綻**します。
「伝わる現場」は工夫の塊である
定着率が高い企業では、“言葉の限界”を前提に、あらゆる工夫がなされています。
- 作業工程をイラスト+母国語で掲示
- 「見せて→やらせて→フィードバック」で伝える指導法
- 翻訳アプリではなく、“業務用会話”を事前に音声収録
- 伝えた内容を本人に復唱させる“リマインド文化”
ここに共通するのは、「伝える責任は伝える側にある」という姿勢です。
日本語ができる=理解できるではない
もうひとつ、現場で誤解されがちなのが「日本語は話せる子だから大丈夫」という過信。
- 単語はわかっていても、文脈が理解できていない
- 「危険」「禁止」「一時中断」などの専門用語が曖昧
- 「間に合うように」は、“急げ”ではなく“やめろ”と誤解されることも
つまり、日本語能力と“作業理解力”は別次元。
そのギャップを埋める努力を怠ると、「言語のせい」にして責任を押しつける構図が生まれてしまいます。
最後に:伝えるのではなく、「伝わる形で届ける」
伝えた。説明した。通訳を使った。
——それでも辞められる現場がある一方で、
ほとんど日本語が通じない相手でも、辞めずに定着している現場があります。
その違いは、「伝わるまでやり方を変える」という覚悟と仕組みです。
- 伝わらなかった理由を毎日記録し、次に活かす
- 指導担当者が“伝え方”の研修を受ける
- 習得状況を“見える化”し、本人とすり合わせる機会を持つ
これが、外国人職人の定着を支える「伝達の質」そのものです。
⑥ 定着する企業がやっている“期待の見える化”とは?

外国人職人が職場を離れる理由は、待遇や労働環境だけではありません。
その多くは、**「自分がどう評価されているか分からない」「何を求められているか伝わってこない」**という“無音の空間”による精神的な孤立です。
この問題に真正面から取り組んでいる企業が、実は一つの答えを出しています。
それが――**「期待の見える化」**です。
期待されていないと感じた瞬間、人は離れる
人は誰でも、“自分が必要とされている”と感じられる場所に居続けようとします。
逆に、「何を期待されているか分からない」「いてもいなくても同じ」と感じた瞬間に、心は離れ始めます。
特に外国人職人の場合、その感覚は顕著です。
- どの作業ができれば合格なのか
- 次に何を目指せばよいのか
- 自分の成長を誰が見ているのか
- 期待されているのか、それとも放置されているのか
こうした情報が曖昧な現場では、本人がどれだけ真面目でも、自分の存在意義を見失ってしまうのです。
見える化の方法①「スキル評価シート」
定着率が高い現場では、個人別のスキル評価シートを導入しています。
- 習得すべき作業ごとに、4段階で達成度をチェック
- 月に1度、本人と一緒に見直し・振り返り
- 達成ごとに“バッジ”や“称号”を付与する文化
- 他の職人と比較しない“自分との進歩”を評価
この取り組みは、単なる管理ではありません。
**「見られている」「成長が可視化されている」**という実感を本人にもたらし、継続の意欲を高めます。
見える化の方法②「期待の言語化」
日本人同士では“察する”ことで成り立つ文化も、外国人には通じません。
そのため定着率の高い企業は、“期待”を明文化する文化を持っています。
- 「君には来月、墨出しの補助を任せたい」
- 「今月の目標は“先読み”の意識を身につけること」
- 「この作業が一人でできたら、次のステップへ進もう」
こうした明確な“方向性の提示”があると、外国人職人は**「何をすれば良いか」が具体的に理解できるようになります。**
結果として、不安や戸惑いが激減し、自信が芽生え始めるのです。
見える化の方法③「成果のフィードバックを即時に伝える」
「よくやった」
「昨日よりスムーズだったな」
「ここがよくなってる、気づいたか?」
——こうした日常の“即時評価”も、期待の見える化には不可欠です。
特に重要なのは、「怒られたこと」よりも「認められたこと」の回数。
実際に、定着している外国人職人は共通してこう語ります:
「褒められたことは、母国の家族に話すくらい嬉しかった」
「頑張ったことを“見ててくれた”のが一番嬉しい」
人は“見られている”という感覚があるとき、成長しようとします。
見えない期待ではなく、“伝わる形”での評価こそが、離職を防ぐ最良の仕組みです。
最後に:「評価」はコストではない、“定着への投資”である
忙しい現場で、「いちいち評価してられない」「そんな時間はない」という声があるのも事実です。
しかし、それを理由に期待の見える化を怠れば、**もっと大きなコスト――“人材流出”**を企業は支払うことになります。
たった一言で、たった一枚のシートで、
たった一回の目線で、
外国人職人の心は「残ろう」と動き始めます。
定着率を変える鍵は、“人を見る力”ではなく、“人に伝える意志”です。
⑦ モチベーション管理の成否が離職率を決める——“声かけ”の科学
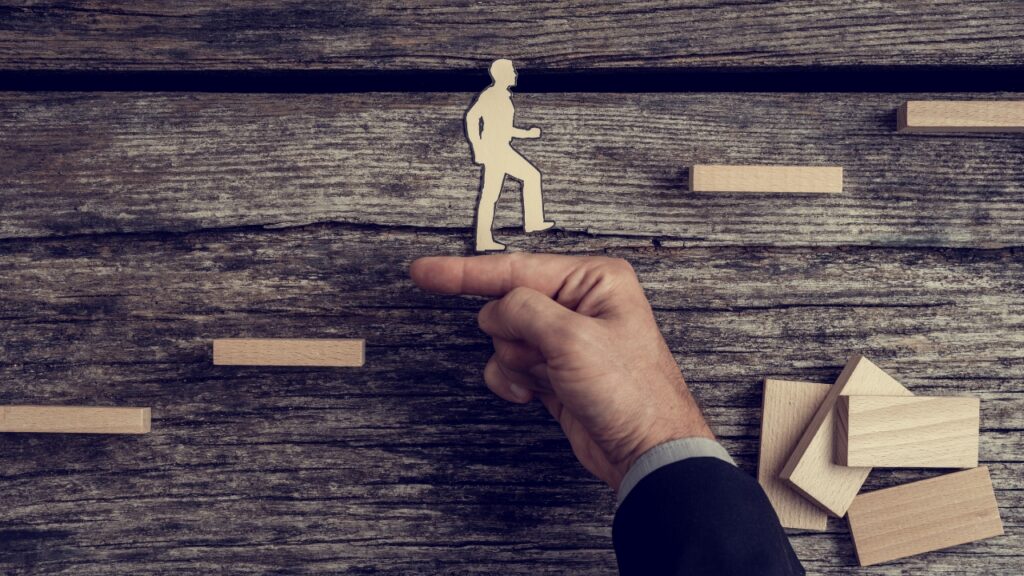
離職率の高い現場と低い現場の最大の違いは、作業内容でも待遇でもありません。
それは、日々の“声かけ”があるかどうかです。
特に外国人職人にとって、異国での労働は「常に正解が分からない」状態。
そんな彼らの心を支えるのが、小さな承認の積み重ね=声かけの力なのです。
モチベーションは“感情”の管理であり、仕組みで支えられるべき
建設業は厳しい業種です。
体力・気候・納期・安全・重圧。
そこに“言葉・文化・習慣”の違いが加われば、外国人職人は常に緊張と不安の中で働くことになります。
そんな状況で最も重要なのは、感情のマネジメント=モチベーションの維持です。
つまり、「続ける理由」を日々与え続けること。
そしてそれを実現するのが、「声かけ」という、最もシンプルで最も効果的な手段です。
科学的にも証明されている“声の力”
最新の認知心理学では、以下のようなデータが報告されています。
- 人はポジティブな声かけを1日3回以上受けると、自己肯定感が継続的に高まる
- 「名前を呼ばれる」「具体的に褒められる」行為は、ドーパミンの分泌を促進し、作業効率を最大14%改善する
- 批判よりも称賛の方が、記憶定着や技能習得に3倍の効果がある
つまり、声かけはメンタルの栄養であり、生産性の起爆剤でもあるのです。
離職率が低い現場の“声かけルール”
定着率90%超を誇るある企業では、以下のような“声かけルール”が徹底されています。
- 毎朝「昨日よかったこと」を1人に伝える
- 小さな改善点でも気づいたら即フィードバック
- 「ありがとう」を1日3回、誰かに伝える
- 新しい作業を任せる前には「期待してるよ」と必ず言う
これらはマニュアルでなく文化です。
職人同士が“見合い、認め合い、支え合う”空気が、職場の風土として根付いています。
逆に、声をかけられない現場はどうなるか
- 「分からないけど聞きづらい」
- 「自分はここにいていいのか」
- 「注意されるだけで、褒められたことがない」
- 「できたことを誰も見てくれていない」
このような感覚が続くと、やがて実習生は“機械的に働くだけの存在”に感じてしまう。
心が職場から離れた瞬間、身体も現場から離れていくのです。
最後に:声は「コスト」ではない、最強の“投資”である
「忙しいから、わざわざ褒めてられない」
「甘やかすのではなく、厳しく教えるべきだ」
そんな声もあるでしょう。
しかし、“辞める”という結果に対して、
たった一言の「今日もありがとう」が持つ効果は、数十時間分の再教育より大きいのです。
日本語が完璧じゃなくても、言葉の数が少なくてもいい。
心が届く“声かけ”があれば、人は辞めません。
それは、人間関係をつくる最初で最大の一歩です。
⑧ 定着率を高める現場の“指導者育成”という視点
外国人職人の定着率を上げるために、多くの企業が「制度」や「仕組み」の見直しを行っています。
もちろん、それらは必要不可欠です。
しかし、それと同等以上に重要なのが、“指導者”という存在の質を高めることです。
なぜなら、制度を運用するのも、日々の接点をつくるのも、すべては現場の“人”だからです。
指導者次第で、同じ職場でも離職率が大きく変わる
職人道場の導入企業における分析では、同じ現場・同じ待遇・同じ作業内容でも、指導担当者が違うだけで離職率が3倍以上変わるという実例が報告されています。
これは何を意味するのか?
結論は明白です。
**「人が人を辞めさせている」**という事実です。
だからこそ、“指導者をどう育てるか”は、実習生の定着率を左右する最重要ファクターなのです。
技術がある人=教えるのが上手い人ではない
よくある誤解に、「ベテランに任せれば教えられるだろう」というものがあります。
しかし、これは非常に危険な思い込みです。
- 熟練者ほど無意識のスキルに頼っており、説明が苦手
- ミスへの許容度が低く、「何でできないの?」となりやすい
- 日本語・文化前提の価値観が強く、“違い”を受け入れにくい
その結果、「教える」はずの存在が、実習生にとっては“怖い人”“話しかけられない人”になってしまうのです。
成果を出している企業の共通点=“教え方”を訓練している
定着率の高い企業は、指導者に対して明確な「教育スキル向上」の研修や評価を行っています。
- 毎月、簡易指導チェックリストを記入
- 実習生からのフィードバックを回収・共有
- 外国人への声かけや説明の「型」をマニュアル化
- 指導者同士での“教え合い研修”を実施
これにより、現場に「教える文化」が根づき、
“育てる人を育てる”という好循環が生まれています。
指導者は“技術の伝承者”ではなく、“定着の鍵”である
もはや、指導者の役割は「技を見せる人」ではなく、
**「働き続けたいと思わせる空気をつくる人」**です。
そのためには、以下の視点が求められます:
- 相手の文化や宗教を尊重する知識
- 日本語が苦手な相手への“伝え方の工夫”
- ミスした際の“励まし方”と“修正の方法”
- 小さな成長を“評価し、伝える”コミュニケーション力
これらは、自然に身につくものではなく、“学びによって得られる能力”です。
最後に:指導者育成は“コスト”ではなく、“未来への投資”
「指導者に研修なんて、手間と金がかかる」
「うちは実践で覚える方針だ」
そう考える企業も少なくありません。
しかし、定着しないたびに発生する再教育コスト・離職による生産性低下・人材募集のコストは、指導者研修の比ではありません。
人を育てる人を育てる。
これが、外国人職人の定着率を劇的に改善する“最短ルート”なのです。
⑨ 失敗から学んだ企業の改革事例——「もう辞めさせない」への挑戦

どんなに優れた制度を導入しても、どれだけ高待遇を提示しても、人は辞めるときは辞める。
とくに外国人職人の場合、言語・文化・信頼の壁が複雑に重なるため、「突然の離職」に見えるケースが後を絶ちません。
ただし、その“突然”には、必ず前兆がありました。
そして、それを見逃してきたという事実を直視し、本気で現場改革に乗り出した企業たちがいます。
彼らは「辞めさせない」ために、何を変えたのでしょうか?
ここでは、失敗から学び、変化を起こした実例を紹介します。
事例①:3人連続で実習生が逃亡。信頼回復までの180日間(埼玉県A社)
A社は、2022年に3人のベトナム人技能実習生が半年以内に立て続けに失踪。
理由は「通訳を通しての指示が雑だった」「話しかけても無視された気がした」というもの。
当初は「若い連中は根性がない」と片付けていたが、監理団体からの改善勧告を受け、初めて社内の“無関心”を見つめ直した。
そこから始めたのは以下のこと:
- 指導者の日本語教育研修への参加
- 作業指示をすべてイラスト+ベトナム語で掲示
- 実習生のための“声かけチェックシート”を導入
- 「昼食は職長と一緒に取る」ルールを新設
すると、次に配属された実習生3名は現在2年目に突入し、1人も辞めていない。
「何をするかより、どう接するかが変わったことが大きい」と担当者は語る。
事例②:リーダーの暴言が離職連鎖に。現場ごと“指導者交代”で立て直し(大阪府B社)
B社では、建設現場の現場監督が外国人職人に対し、怒鳴る、無視する、作業をやり直させるといった“無意識のハラスメント”が常態化。
結果、半年で5人中4人が離職。
口コミが広がり、「外国人にとってブラック現場」として定着してしまった。
会社は危機感を抱き、以下の思い切った改革に踏み切る:
- 現場監督を別現場へ異動、教育意識の高い中堅社員に交代
- 外国人職人と現場指導者の“相互評価”シートを導入
- 定期的なメンタルヘルスアンケート(翻訳付き)を実施
この対策により、新たに受け入れた実習生の離職はゼロ。
「監督が“先生”から“相談相手”になったのが大きい」と実習生も語っている。
事例③:「うちは問題ない」の盲信が生んだ、静かな崩壊(千葉県C社)
C社は「実習生に優しく接している」「休憩も自由」「怒鳴る人はいない」と思っていた。
しかし、気づけば1年で7名中5名が離職。
理由は「何をすれば評価されるか分からない」「できても無反応だった」というもの。
つまり、“無関心の優しさ”が“評価されていない感覚”に変わったのだ。
改善点:
- 毎週1回の面談(5分)で「できたこと・困っていること」を聞く
- 「先週より成長した点」を見つけて、朝礼で一言伝える
- 翻訳アプリではなく、簡易フレーズカードで直接会話する
「結局、人間は“見てもらえてる”と感じられないと、辞めるんだ」と社長は反省を口にする。
改革の本質は「仕組み」ではなく「意識の転換」
どの企業にも共通するのは、離職を“自社の課題”として受け止め、変える責任を引き受けたこと。
そして、次のような行動を具体的に起こした点です:
- 他責ではなく自責で考える
- 小さな工夫を積み上げる
- 現場の“当たり前”を疑う
- 実習生の声を“評価”ではなく“情報源”と捉える
これが、「辞めさせない現場」へと変化するための本質的な第一歩です。
最後に:「失敗」を恥じるな、「変化」こそが評価される
人は、完璧な組織に残るのではありません。
**「変わろうとする現場」「聞いてくれる上司」「見守ってくれる仲間」**がある場所に残るのです。
失敗の経験を隠すのではなく、
それを次の人のためにどう活かすか。
その姿勢が、企業の“信頼資産”となり、
やがて「辞めない文化」を生む源泉になります。
⑩ 定着率を改善するために、今すぐ見直すべき5つのポイント

外国人職人が「すぐ辞める」現場と、「定着する」現場の差は、偶然ではありません。
その差は、企業が“何を意識的に整えているか”に集約されます。
では、あなたの現場は今、何を見直すべきなのでしょうか?
これまでの成功事例・離職要因・教育の現場から抽出された、即実行できる5つの改善ポイントを解説します。
① 「教えたつもり」を捨て、“伝わったか”を確認する文化を
定着率の低い現場では、指導者の口癖がこうです:
- 「言ったはず」
- 「教えたよね?」
- 「何回も同じことを言ってるのに」
この考え方こそが、すれ違いの根源です。
改善策:
- 指示は紙・図・音声など多角的に伝える
- 作業後に「今日理解したこと」を本人に確認
- 翻訳アプリ任せにせず、現場で使う定型表現を整備
伝えるのではなく、“伝わるかどうか”を基準に指導設計を変えることが重要です。
② 役割・期待・評価基準を“可視化”する
外国人職人が最も不安に感じるのは、「自分が今どこに立っているか分からない」ことです。
- 何ができれば合格か
- 次に目指すスキルは何か
- 誰が自分の努力を見てくれているのか
これらが曖昧だと、成長しても自信にならず、離職につながります。
改善策:
- スキルマップと達成表を個人別に設置
- 「今月の目標・来月の役割」を事前に共有
- 評価・表彰の機会を定期的に設ける
職人を“認知されている存在”に変える仕組みが、定着への近道です。
③ 「1日1回の声かけ」ルールを仕組みにする
最もシンプルで最も効果的なのが、“毎日の声かけ”の習慣化です。
- 朝礼後に「体調どう?」
- 昼に「今日の作業、前より上手かったな」
- 終業時に「ありがとう、明日もよろしく」
この“目を合わせて、名前を呼んで、言葉をかける”行為が、
外国人職人にとっての**“ここにいてもいい”という感覚の土台**になります。
④ 指導者を“教える人”ではなく、“支える人”に育てる
定着率を改善するには、指導者教育は避けて通れません。
- 技術の継承者ではなく、「心のケア担当」になる意識
- 「言わなくても分かる」は通じない前提で接すること
- 叱るときも“なぜそうなったか”を必ず確認する癖づけ
企業は「育てる人を育てる」ことで、定着率の根本を支えることができます。
⑤ 離職理由の“分析と共有”を習慣化する
「辞めた理由が分からない」「突然だった」では改善のしようがありません。
改善策:
- 離職時面談を徹底し、通訳も交えて“本音”を聞く
- 月次で“定着会議”を実施し、現場の声を集約
- 成功事例と失敗事例を社内マニュアル化
このPDCAサイクルが、企業全体の“辞めさせない力”を底上げします。
【まとめ】外国人職人が定着する現場とすぐ辞める現場、その分かれ道は“仕組み”ではなく“姿勢”だった

外国人職人の離職問題に悩む企業は多くあります。
制度の限界、文化の違い、言語の壁……確かに課題は多い。
しかし、**定着する現場とすぐ辞める現場を分けている最大の要因は、「人への接し方」と「教育する側の意識」**です。
本記事で紹介した10の視点から見えてくるのは、以下のような現実です。
- 「教えたつもり」が通じない現場では離職が続く
- 仲間意識のない現場は、職場であっても“居場所”にはなり得ない
- “指導”だけでなく、“対話と信頼の仕組み”が必要不可欠
- 定着率の高い現場は、教育・評価・声かけが可視化されている
- 「仕組み」よりも「温度」が、職人の心を動かしている
そして、最も重要なのは、定着率は“運”や“相性”ではなく、“改善できる経営課題”であるという認識を持つことです。
すでに取り組みを始めている企業は、「辞めさせない」から「共に育つ」現場へとシフトしています。
そこには、制度を超えた“人を人として見る”姿勢があります。
あなたの現場は、どちらを選びますか?
今すぐ始められる、小さな“声かけ”と“仕組みづくり”が、未来の人材を定着させる最初の一歩です。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。