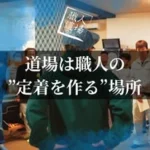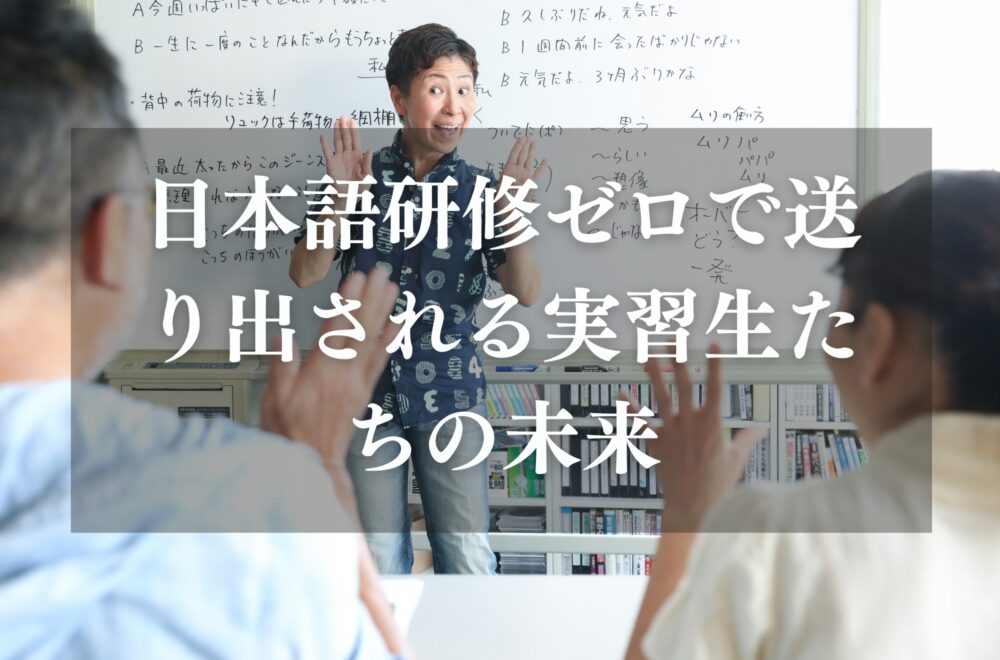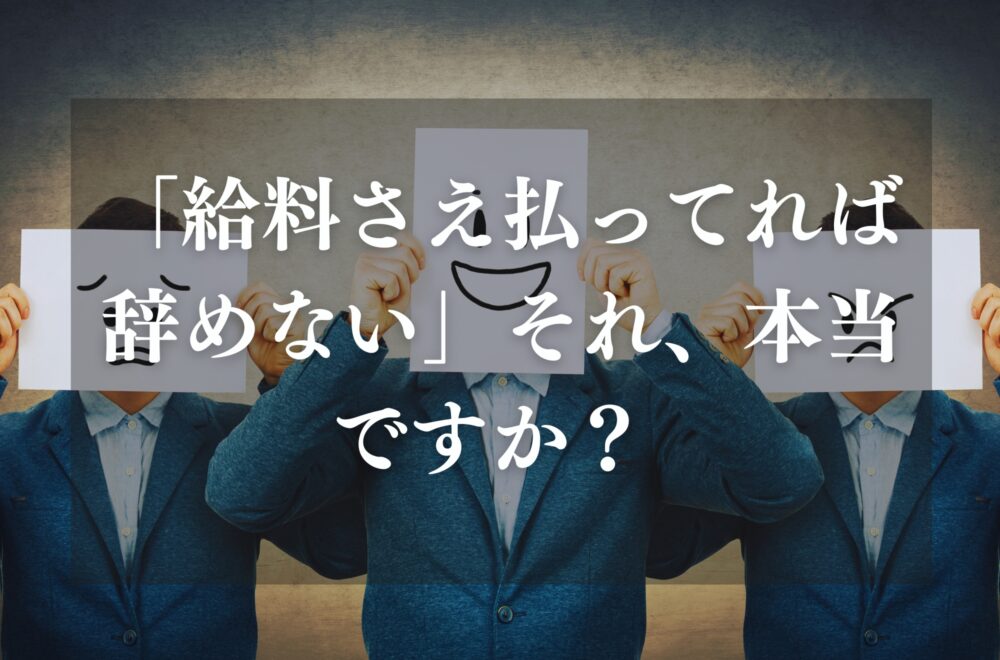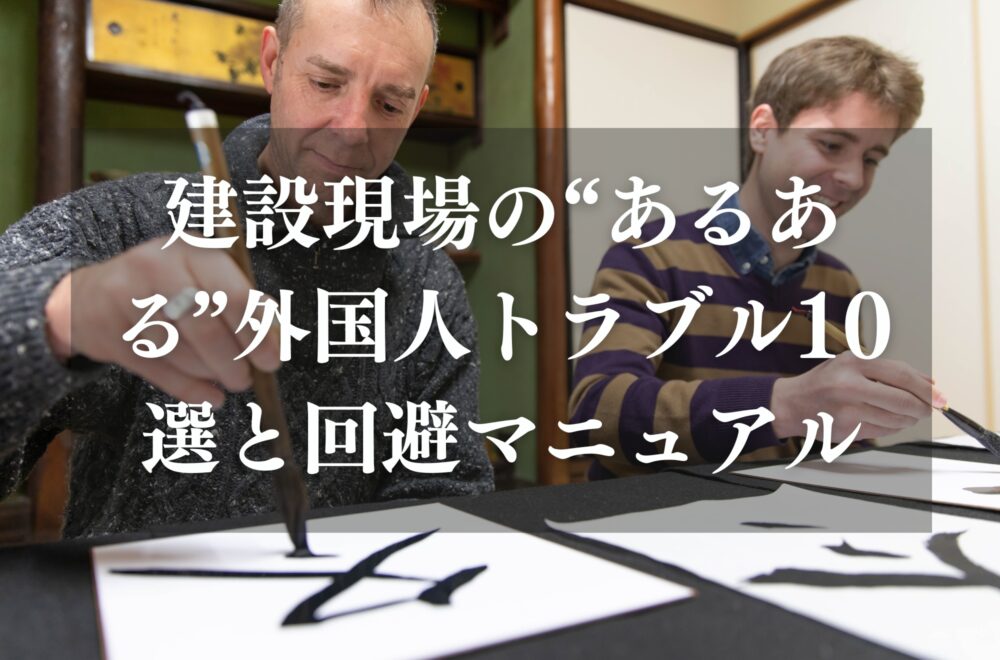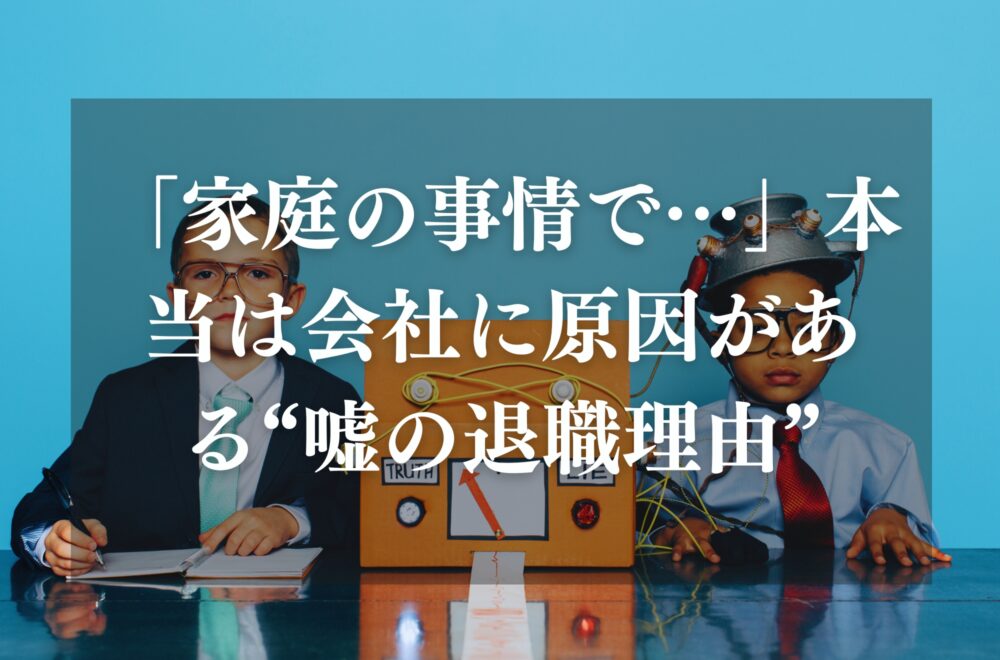建設現場の“あるある”外国人トラブル10選と回避マニュアル
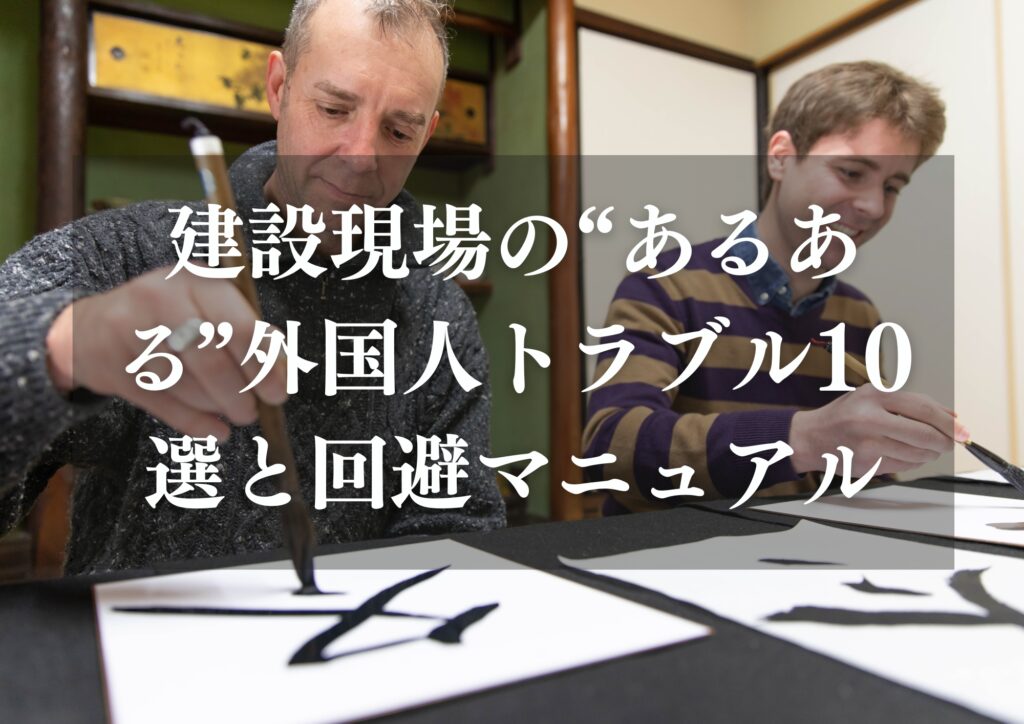
>目次(気になる記事のリンクをクリック下さい)
- ① 作業中の「分かってるフリ」確認不足が引き起こす重大ミスとは
- ② 「言ったつもり」「聞いたつもり」の指示が通じない理由と改善法
- ③ 休憩中は無言、雑談ゼロ——孤立した外国人職人の“心の離職”
- ④ 無断欠勤・遅刻の背景にある文化と生活リズムの違い
- ⑤ 「危険だから触るな」が伝わらない?安全意識のギャップを埋める方法
- ⑥ 「すぐ辞める」は本当か?短期離職の予兆とその防止アプローチ
- ⑦ 「気が利かない」は誤解?“指示待ち型”の背景にある異文化理解不足
- ⑧ SNS投稿で企業情報が漏洩!?プライバシーとモラル教育の盲点
- ⑨ 「宗教上できません」に戸惑う現場——配慮と生産性を両立させる方法
- ⑩ トラブルを“教育の糧”に変える!現場で活かす再発防止マニュアルの作り方
- 【まとめ】外国人職人との“あるある”トラブル——現場は学びの宝庫だった
- この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武
- 多能工職人育成学校・技術研修所「職人道場紹介動画」
① 作業中の「分かってるフリ」確認不足が引き起こす重大ミスとは

建設現場で起きる外国人職人とのトラブルの中で、最も“見えにくく、そして危険”なのが、「分かってるフリ」による作業ミスです。
表面的にはうなずき、作業に向かっているように見える。
言葉に対して「ハイ」と返事をする。
でもその実、作業の本質やリスクをまったく理解していないまま動いている。
——それが、重大な事故や手戻り、ひいては現場の信頼崩壊にまでつながることは、決して珍しくありません。
“分かってるフリ”はなぜ起きるのか?
外国人職人が「分からない」と言えない理由は、単なる遠慮や語学力の問題ではありません。
その背景には、複数の心理的・構造的要因が潜んでいます。
- 怒られるのが怖いから
→ 「また質問?」と思われるのではないかと怯える - 周囲との比較意識
→ 他の日本人職人に追いつかねばという焦りから、知ったフリをする - 指導側が忙しそうだから
→ 聞くと邪魔になると思い、自分の判断で動こうとする - “イエス文化”による誤解
→ 多くの国では、Noと言うことを失礼と感じ、うなずいてしまう
こうした要因が重なることで、「分かったつもり、やってみたつもり」の連続が、現場の安全と品質を大きく損ねていくのです。
実例:仮設足場の固定を誤り、現場が一時閉鎖に
ある中堅ゼネコンでは、ベトナム人技能実習生が仮設足場の締結部材を本来の位置とは異なる箇所に取り付けてしまったことで、
翌朝の点検で構造強度に不安が生じ、一時的に現場全体が閉鎖される事態となりました。
ヒヤリハット報告書にはこう記載されていました。
「本人は“締める”という日本語の意味を把握しておらず、“置くだけ”で済ませていた。注意されるのが怖くて、できていないと伝えられなかった」
結果として、工程は2日間ストップし、会社側は元請からの是正指導を受けました。
このようなケースは、実は全国の現場で日常的に発生しています。
「理解しているかどうか」は、本人の反応からは分からない
日本人職人同士なら「表情」「返答」「仕草」からある程度理解度を推測できます。
しかし、外国人職人にはその“空気読み”が通用しません。
だからこそ、「分かってるフリ」を未然に防ぐ確認プロセスを、日常的に仕組み化する必要があるのです。
回避策①:「指示後のリピートバック」を徹底する
指示を出したら、必ず次のような確認をします。
- 「じゃあ今、何をするのか説明して」
- 「何の工具を使う?どこで始める?」
- 「このあと誰に報告する?」
この“リピートバック(復唱)”は、相手の理解度を可視化する唯一の手段です。
通訳がいないときでも、ジェスチャーやイラストで補えば十分機能します。
回避策②:「チェックリスト方式」で作業前確認をルール化
言語能力や理解力に差がある現場では、事前の作業確認書が大きな効果を発揮します。
- 作業項目のリストを簡易イラストと母国語で記載
- 各項目にチェック欄を設け、本人が理解したらサイン
- 現場監督が5分間で目視確認・声かけを実施
この仕組みがあるだけで、「分かってないのに動く」という事態は激減します。
回避策③:ミスの“責任”より、“予兆”を評価する文化をつくる
重要なのは、ミスをしたときに「なんでやった!」と怒ることではなく、
「何が分からなかったのか」「なぜ聞けなかったのか」を一緒に振り返る姿勢です。
それにより、本人は「次は聞こう」「分からないと言っても大丈夫なんだ」と感じ、
“分かってるフリ”をやめるきっかけになります。
最後に:現場の“無言の了解”が、最大のリスクになる
建設現場のスピード感と緊張感の中で、つい確認を怠ってしまうこともあるかもしれません。
しかし、その一瞬の“まあ大丈夫だろう”が、大きな事故や損失につながるのが現実です。
外国人職人は、“言われたこと”よりも、“受け入れてもらえているかどうか”を深く見ています。
分かってるフリは、彼らの“防衛反応”であり、現場側がつくり出してしまった空気の結果でもあるのです。
だからこそ、必要なのは“信頼できる確認文化”と“安心して聞ける雰囲気”。
その両方が整ったとき、「分かってるフリ」は消え、現場は確実に安定していきます。
② 「言ったつもり」「聞いたつもり」の指示が通じない理由と改善法

建設現場で起きる外国人職人とのすれ違いは、突発的なミスや文化の違いによるものだけではありません。その多くは、何気ない日常の中で蓄積された「伝わっていない指示」が原因で引き起こされます。特に日本人同士では通用していたはずの「言ったつもり」「聞いたつもり」が、外国人職人相手にはまったく通じないという現実が、現場を混乱させるのです。
例えば、監督が「今日中にこの作業、お願いね」と軽く伝えたとしましょう。日本人職人であれば、その意味するところや優先順位、段取りを“空気”で読み取り、適切に進められることが多い。しかし、外国人職人にはその“前提条件”がありません。作業の具体的な範囲、完了基準、他との工程関係など、言葉で明確に伝えなければ、本人は「やるとは言われたが、いつまでに、どの範囲まで、どうやって」という肝心な部分を理解していない可能性が非常に高いのです。
さらに問題なのは、多くの外国人職人が「分からない」と言えない状況にあることです。これは単に日本語が不自由だからではなく、怒られるのが怖い、聞き返して嫌な顔をされた経験がある、自信がなくて確認できない——そうした心理的ブロックが存在するからです。結果として、「分からないけど、分かったフリをする」「聞いたことにしておく」ことでその場を乗り切ろうとし、重大なミスや工程の遅れが発生してしまいます。
この問題の本質は、「伝えた内容が正しく伝わったかを、伝える側が確認していないこと」にあります。つまり、“伝える責任”を受け手任せにしてしまっているのです。外国人職人にとっては、日本語が理解できても、それが“実行可能なレベルの理解”にまで落とし込まれていなければ意味がありません。「分かる」と「できる」は違う。この視点が欠如している現場ほど、トラブルを繰り返してしまうのです。
では、どうすればこの“伝達ギャップ”を防げるのか。最も基本的で効果的なのは、指示の後に「今から何をするか言ってみて」と復唱させることです。これにより、理解のズレが明確に分かり、その場での補足説明が可能になります。また、作業内容を写真やイラスト、簡単な図で示すことも非常に効果的です。視覚情報は言語の壁を超えて伝わりやすく、共通理解の土台になります。
さらに、作業内容を「何を」「なぜ」「どうやって」の三点で構造的に説明することで、作業者本人が意味を持って動くようになります。たとえば「なぜこの工程を先にやるのか」「なぜその道具を使うのか」という理由を共有することで、外国人職人は“作業の意義”を理解し、自発的な判断力が高まります。
現場ではどうしても時間に追われ、「細かく教える暇がない」「同じことを何度も言えない」といった声もあるでしょう。しかし、その短縮した数分が、後に起きる数時間分の手戻りやトラブルの原因になるとしたら、それは本当に効率的と言えるのでしょうか。
伝わっていない指示が事故やミスを引き起こし、さらには職人本人の自信を削ぎ、職場から心が離れる——こうした負の連鎖を止める鍵は、すべて「伝える側の姿勢」にあります。通じているかどうかを確認する。分からなければもう一度伝え方を変える。これを面倒ではなく“信頼構築の一環”として位置づけることが、外国人職人の定着率を上げ、現場の安定につながるのです。
「言った」ではなく、「伝わったか」。
この問いを毎日の現場に持ち込むことが、トラブルゼロの職場づくりの第一歩です。
③ 休憩中は無言、雑談ゼロ——孤立した外国人職人の“心の離職”

建設現場における外国人職人の定着を阻む最も深刻な原因の一つは、作業中の技術的なトラブルや言語の壁ではありません。それは、日々の休憩時間や昼食のときに表れる**「無言の空間」「雑談のなさ」「仲間との断絶」**です。表面的には何事もなく過ごしているように見えても、その静寂の中で外国人職人の“心の離職”は静かに、しかし確実に進行しているのです。
多くの建設現場では、「現場では仕事ができればいい」「休憩中は自由時間」という価値観が根づいています。確かに、日本人職人同士であれば、その価値観でもそれなりに成立します。しかし、異国からやってきた若い外国人職人にとって、その沈黙は単なる休憩ではなく、「自分は受け入れられていない」「ここに居場所がない」という疎外感を植え付ける時間になってしまうのです。
職人道場のフィールドリサーチでは、実際にこうした声が上がっています。
「毎日、昼ごはんのときは一人で食べています。誰も話しかけてこないし、自分から話す勇気もない」
「作業中は指示を聞くだけ。終われば、ただ帰るだけ。誰とも話すことがありません」
「日本の現場は静かで、何を話していいのか分からない。母国では皆で笑っていたのに」
このような心理状態が長く続けば、いくら仕事ができるようになっても、「この職場にずっといたい」とは思えなくなります。そしてある日、無断欠勤、体調不良、帰国希望、あるいは失踪という形で、現場から姿を消すのです。これが、技術や待遇の問題とはまったく別の次元で起きる“心の離職”です。
問題は、このような孤立が起きていることに、多くの企業や管理職が気づいていないことです。特に、実習生の文化背景や性格特性を理解せず、「声をかけてこないから大丈夫だろう」「問題があるなら本人が言うはず」と思い込んでいる現場では、知らない間に実習生が心を閉ざしていきます。彼らが自らSOSを出すことは、まずありません。だからこそ、周囲の“大人の側”が気づく力、接する技術を身につける必要があるのです。
では、どうすればこうした孤立を防ぐことができるのでしょうか。答えはシンプルです。**雑談を設計し、関係性をデザインすること。**これは自然発生的に生まれるものではありません。企業側、現場側が「関わることに意義がある」と認識し、仕組みとして日常の中に組み込まなければ、雑談や対話の文化は根づきません。
たとえば、昼食の時間をただの休憩にするのではなく、「必ず1人1回は、相手の目を見て今日の話をする」「週に一度、チームで5分の“最近の気づき共有”を行う」といったルールをつくるだけでも、大きな変化が起きます。誰かが「今日ちょっと寒いですね」と話しかければ、「はい、ベトナムより寒いです」と返ってくる。そこに生まれるたった一往復のやり取りが、外国人職人にとっては「この人は自分に関心を持ってくれている」「仲間として見てくれている」という安心感につながるのです。
こうした関係づくりは、決して特別なイベントや通訳を使った面談だけでなくても成立します。日々の小さな声かけ、リアクション、雑談の積み重ねが、**孤立を防ぐ最大の“教育”であり、最強の“離職防止策”**なのです。
さらに重要なのは、この雑談文化を“個人の性格”に依存させないことです。たまたま人当たりのいい先輩がいれば定着する、そうでなければ辞めていく、という属人的な環境では、組織としての安定は得られません。だからこそ、企業として「誰もが自然に声をかけられる」「異文化を前提としたコミュニケーションの場を持てる」ような教育方針と現場マネジメントが求められるのです。
日本語が堪能な実習生でも、心の距離を縮められなければ辞めていきます。逆に、日本語が苦手でも、「この人は自分に関心を持ってくれている」と感じられる現場であれば、粘り強く頑張ってくれます。結局のところ、“理解される”よりも、“関心を持たれる”ことの方が、職場に居続ける理由になるのです。
外国人職人の“心の離職”は、事故や欠勤と違って報告書には表れません。けれど、それが積み重なったときに起きる“突然の離脱”は、企業にとって最も予測困難で、対処の難しい課題になります。だからこそ、見えないリスクへの備えとして、今こそ“関係性の投資”を始めるべきなのです。
外国人実習生にとって、作業は仕事、でも雑談は安心です。
そのたった一言が、彼らの心を職場に留める力になります。
④ 無断欠勤・遅刻の背景にある文化と生活リズムの違い

外国人職人の定着を阻む問題として、多くの現場で頭を悩ませているのが「無断欠勤」や「頻繁な遅刻」です。これらは一見、「やる気がない」「責任感がない」と捉えられがちですが、実際にはその背景にある要因を深く掘り下げると、単なる“怠慢”では片づけられない多くの文化的・生活習慣的なギャップが見えてきます。
日本の建設業界では、「時間厳守」が現場の基本です。朝の集合時間に遅れれば連絡以前の問題とされ、「5分前行動」は常識。無断欠勤ともなれば重大なルール違反として処理され、現場責任者にとっては頭の痛いトラブルの一つです。しかし、外国人職人にとってその感覚は必ずしも共通ではなく、日本独特の“時間への厳格な価値観”が通じていないケースが非常に多く見られます。
たとえば、ある東南アジア出身の実習生が1時間遅刻してきた際に、「体調が悪かったので少し休んでから来た」と何の悪気もなく話したことがありました。日本人から見れば事前連絡なしの欠勤は“社会人としての常識に欠ける”と見なされますが、本人の文化圏では「体がしんどいときは家族や仲間に伝えておけば大丈夫」「上司への連絡は元気になってからでよい」といった緩やかな感覚が一般的だったのです。
このように、無断欠勤や遅刻の原因は、単なるルール違反ではなく**“常識の違い”によるミスコミュニケーションである場合が多いのです。では、それをどのように防ぎ、改善していくべきか。まず必要なのは、「本人に悪気はなかった」で済ませるのではなく、“なぜ違いが生まれるのか”を構造的に理解し、対策する姿勢**です。
第一に、文化的背景を理解した上で“日本の職場文化”を具体的に教えることが不可欠です。単に「時間は守ってください」と言うのではなく、「5分前集合が基本で、1分でも遅れたら“遅刻”になる」「体調が悪くても必ず事前に電話を入れる」といった**“暗黙の了解”を明文化することが重要**です。職人道場の実践でも、初期教育段階で“日本の現場ルール”をイラスト付きで説明し、ロールプレイ形式で疑似体験させることで、遅刻・欠勤が大幅に減少したという結果が出ています。
第二に、生活リズムそのものを支援・把握する視点も重要です。寮で暮らしている実習生の場合、夜中までスマートフォンを使って母国と通話していたり、生活時間が不規則になっていたりすることが、朝の遅刻や寝坊の原因になっているケースが多く見られます。このような場合は、単なる“自己責任”で済ませるのではなく、「なぜ不規則になるのか」「どうすれば生活改善できるか」を一緒に考える支援体制が求められます。
たとえば、ある企業では「22時以降はスマホ利用制限をする」「朝の起床時間に合わせて点呼・声かけを実施する」などのルールを寮内で導入。結果として、遅刻件数が1ヶ月あたり70%以上減少した事例もあります。さらに、本人と面談を重ねることで、「家族と話すのは大事。でも仕事が続かないと仕送りもできない」と本人自身が自覚を持ち、行動が変わったという好例も存在します。
また、無断欠勤の背景には“職場への心理的距離”が大きく関わっています。つまり、「職場に行きたくない」「誰にも相談できない」「ちょっとしたことでも叱られる」といった不安感や孤立感があると、体調不良や精神的なストレスと相まって「とりあえず休んでしまう」「報告せずに逃げる」といった行動につながるのです。これは、辞める前の“サイン”とも言えるでしょう。
こうした状況を防ぐには、“体調や生活状況を話しやすい関係”を日常的に築いておくことが重要です。毎朝の挨拶時に「体調どう?」「昨日ちゃんと寝れた?」といった一言があるだけで、職人は“見てもらえている”という安心感を得ます。それが、欠勤や遅刻の連鎖を防ぐ予防線となるのです。
結局のところ、無断欠勤や遅刻を単なる「職務怠慢」として捉えるのではなく、文化・生活・心理・制度の“ズレ”の表出として受け止め、仕組みと関係性で埋めていく視点が必要不可欠なのです。
建設現場においては、時間は命そのものです。だからこそ、そこに対する意識と理解を外国人職人と“共有する”ことが、定着率と安全性の両立に直結します。
「守らせる」前に、「分かち合う」。
これが、無断欠勤・遅刻というトラブルに対する、最も確実な対処法なのです。
⑤ 「危険だから触るな」が伝わらない?安全意識のギャップを埋める方法

建設現場で最も重要なテーマの一つが「安全管理」であることは言うまでもありません。労災リスクの高い環境において、ちょっとした確認ミスや油断が命取りになります。しかし、外国人職人との現場運営において最も悩ましいのが、「危険だから触るな」「今は入るな」「絶対にやってはいけない」といった、緊急性のある安全指示が正しく伝わらないという問題です。
日本人職人同士であれば、「そこは立ち入り禁止だぞ」「触ったら危ないからな」といった一言で意味が通じます。現場経験や共有された価値観があるため、簡易な言葉でも危険性が理解されやすい。しかし、外国人職人の場合、**「その言葉が危険のレベルをどこまで表しているのか」**が分からず、軽く受け止めてしまうことがしばしばあります。
実際にあった事例を紹介しましょう。ある鉄筋工事現場では、クレーンの稼働範囲にある資材を整理していたベトナム人実習生が、作業エリア内に立ち入ってしまいました。日本人職長が「そこ危ないから近寄るな!」と声をかけたが、本人は「注意された」とは思ったものの、それが“今すぐ離れないと命に関わる”レベルであるとは理解していなかったのです。結果的に事故は回避されましたが、「危険=怒られる程度のこと」と認識していたことが、重大なヒヤリハットを引き起こしていたのです。
このようなトラブルの本質は、“危険”の意味や重みが、文化や経験によって大きく異なるということにあります。母国では“多少の危険は自己責任”で済まされる環境で育った人も多く、「作業中にケガをしても働き続けるのが美徳」とされる場合もあるのです。そこに「安全第一」「絶対遵守」という日本の感覚をそのまま持ち込んでも、正しく伝わらないのは当然です。
では、このギャップをどう埋めるか。最初のステップは、“安全教育を前提とした設計”を導入することです。単に危険行為を叱る、禁止するだけでなく、「なぜ危険なのか」「どう危険なのか」「その結果、どうなるのか」を**“見える形”で伝えること**が重要です。
たとえば、職人道場では「危険行動シミュレーション動画」を活用しています。実際の事故事例をもとに再現された映像を見せることで、言葉が通じにくい場合でも“視覚で理解させる”ことができ、非常に高い効果を上げています。実習生自身が「これはヤバい」「これをしたら自分がケガをする」という実感を持つことで、指示への反応が明確に変わるのです。
また、安全に関する注意喚起は、“即時・簡潔・明確”に伝えるルールを設けることも有効です。
たとえば、「STOP」「NO GO」「DANGER」などの英語や母国語を使ったピクトグラム標識を設置するだけでも、危険エリアへの無意識な侵入を防ぐ効果があります。声だけではなく、**視覚・標識・色・音などを連動させた“多層的な注意喚起”**が、より確実に危険を伝える手段になるのです。
さらに、事故の芽を摘むためには、“なぜその行為がダメなのか”を丁寧に説明できる職長・指導者の育成が不可欠です。外国人職人にとっては、「怒られたからやめる」ではなく、「納得したからやらない」という理解があって初めて、継続的な安全行動につながります。
現場ではしばしば「また言わなきゃいけないのか」「毎回注意してもキリがない」と疲弊の声が上がりますが、それは裏を返せば、現場での伝え方がまだ“仕組み化されていない”状態であることを意味しています。伝える内容を絞り、重要なことは繰り返し、形式化する。それによって、「あの人が怖いからやめる」ではなく、「このルールは命を守るから守る」という、自律的な安全意識が根づくようになります。
外国人職人との安全コミュニケーションは、日本人にとって“当たり前”が通じないという前提に立ち戻る必要があります。そのうえで、どんな手段を使えば“理解できる形で危険を伝えられるか”を常に試行錯誤することが、事故ゼロ・ヒヤリゼロの現場につながるのです。
安全とは、ルールではなく文化です。そして文化は、言葉だけではなく“共有された理解”によって形づくられるものです。
外国人職人と本気で安全を共有したいなら、まずはこちらが“伝え方”を変えなければなりません。
⑥ 「すぐ辞める」は本当か?短期離職の予兆とその防止アプローチ
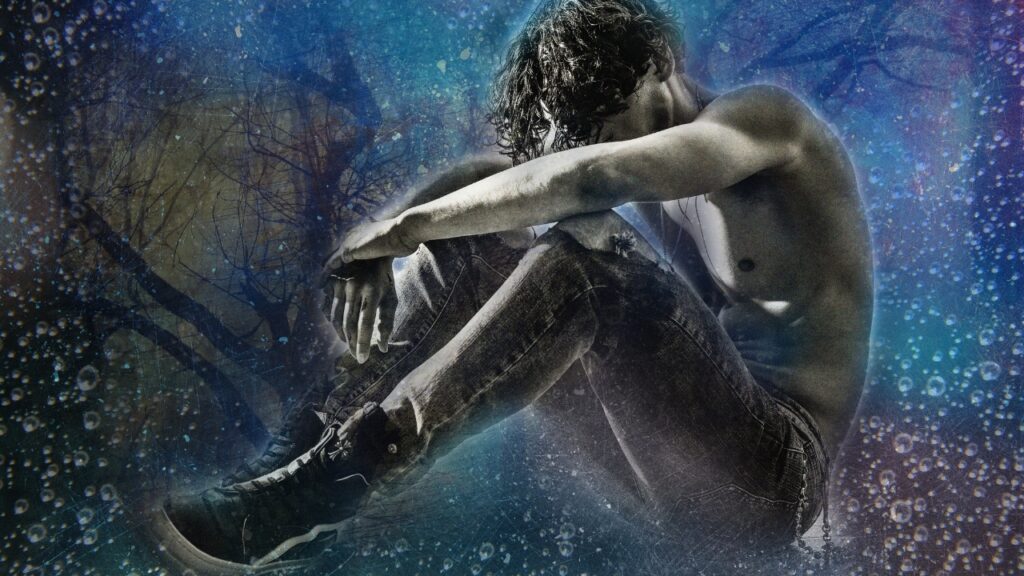
建設業界で外国人職人の受け入れを行っている多くの企業が抱える悩みの一つが、「外国人はすぐ辞める」というイメージです。実際、「半年持たずに辞めてしまった」「初任給をもらってすぐ辞めた」といった声は後を絶たず、定着率の低さに業界全体が頭を抱えています。しかし、この「すぐ辞める」という現象は本当に“外国人の気質”や“やる気の問題”だけなのでしょうか?
答えは否です。職人道場でのヒアリングや離職理由の分析を行うと、短期離職の多くは明確な“予兆”を伴っていたにもかかわらず、職場側がそのサインを見逃していたことが原因であると分かります。つまり、辞める直前の“突然の出来事”のように見える離職も、実際には日々の中にその兆しがあったのです。
では、どのような兆候があるのでしょうか。代表的な予兆には以下のようなものがあります。
・あいさつが小さくなる、目を合わせなくなる
・作業中のリアクションが薄くなる、質問が減る
・遅刻や早退、欠勤が増える(最初は「頭が痛い」「眠れなかった」などの軽い理由)
・休憩中や昼食時に一人で過ごすようになる
・指導に対して「はい」と言うものの、作業に自信なさそうな様子が見られる
・LINEやSNSで母国の友人と頻繁にやり取りを始める
・急に「母国に帰りたい」「親が病気」などの話を始める
これらはすべて、心の距離が職場から離れつつある証拠です。身体はまだ現場にいても、気持ちの面では「もう辞めたい」という方向に傾いている状態と言えるでしょう。
このようなサインを見逃さないためには、**職場側が「日常的な観察」と「気軽な声かけ」を仕組み化する必要があります。**特に忙しい現場では、「様子がおかしいな」と感じてもスルーされがちです。しかし、それを“感覚”で終わらせず、誰でも気づけるような“チェックリスト”として可視化することで、早期対応が可能になります。
たとえば、ある企業では月に一度の“感情スコアカード”を導入。項目には「今週、現場で楽しいと思ったことがあるか」「誰かと話す時間があったか」などがあり、5段階で記入させる方式です。本人の主観で記入されるため、小さな変化に気づく手がかりになり、実際にこの導入以降、早期離職が激減しました。
また、防止のもう一つの鍵は、「辞めたい」と思わせない関係性づくりにあります。特に入社直後の3か月間は、職場への“信頼”と“安心感”が定着する最も重要な期間です。この時期に孤立や放任が続くと、本人は「何かあっても助けてもらえない」と感じ、ストレスが蓄積していきます。逆に、「困ったことがあったらすぐ相談できる」「見守ってもらえている」という安心感があれば、多少のつらさも乗り越えようとする意志が生まれるのです。
ここで大切なのは、「離職防止=甘やかし」ではないということです。適切な規律や指導は必要ですが、それと同時に“心理的な安全基地”を提供できるかどうかが重要なのです。これが、今や建設業界でも注目される“定着型マネジメント”の基本的な考え方です。
加えて、外国人職人の離職を防ぐには、本人の成長実感を可視化する取り組みも不可欠です。成長が見えなければ、達成感も得られず、「ここにいて意味があるのか?」という疑問が生まれます。スキルシートや進捗表を用い、1週間単位で“できたこと”を見せてあげることで、「今、自分は成長している」「前より役に立てている」と実感させることができ、定着意欲の向上につながります。
さらにもう一点、特に重要なのが“期待の言語化”です。「将来こうなってほしい」「君に任せたい作業がある」「〇〇さんも期待してるよ」といった言葉は、本人にとって“ここにいる意味”をつくる栄養素です。何も言われずに作業だけをこなしていると、職人は“必要とされていない”と感じ、早期離職のリスクが高まります。
まとめると、「すぐ辞める」という現象の裏には、本人の性格ややる気ではなく、環境や関係性、職場の情報設計における“見落とし”が積み重なっているケースがほとんどです。
だからこそ、離職を“本人の責任”として片づけるのではなく、“未然に防げるマネジメント課題”として企業側が受け止めることが、定着率改善の出発点になります。
人は突然辞めません。
辞めたくなる前に、必ず“気配”を出しています。
それに気づけるかどうかが、現場の未来を左右するのです。
⑦ 「気が利かない」は誤解?“指示待ち型”の背景にある異文化理解不足

建設現場における外国人職人への不満としてしばしば耳にするのが、「あいつは気が利かない」「何度言っても自分で動こうとしない」という声です。確かに、日本人職人であれば「この場面ではこう動く」「次に何が必要か察して動ける」といった、いわゆる“先読み力”が求められる場面は多くあります。しかし、こうした期待をそのまま外国人職人に当てはめることは、大きな誤解とすれ違いを生む原因になります。
外国人職人が“気が利かない”ように見えるのは、多くの場合、指示の解釈や文化的前提の違いによるものであって、本人の性格や意欲の問題ではありません。
例えば、日本の現場では「言わなくても分かるだろう」「段取りを考えて先に動け」といった“察する力”を重視します。しかし、異文化圏では「言われたことを正確に守る」ことが最大の価値とされるケースが多いのです。特に東南アジアや南アジアの多くの国では、職場における上下関係が非常に明確であり、上司から明確な指示が出るまで“勝手に動くこと=越権行為”とされる文化すらあります。
この文化的背景を知らないまま、「なぜ言わなくても分からないんだ」「少しは自分で考えろ」と叱責を繰り返すと、外国人職人の心はどんどん閉じていきます。やがて「何をしても否定される」「何も言わない方が安全だ」と思うようになり、本来持っていた積極性や学ぶ意欲すら失ってしまうのです。
また、“気が利かない”とされる原因には、経験年数の浅さや作業手順の背景知識が不足していることも大きく関係しています。たとえば、片付けをする場面で、「これはもう使わない」と判断できるかどうかは、全体の工程を理解していなければ分かりません。日本人職人であれば、これまでの現場経験から「この流れなら次はあれだな」と推測できますが、外国人職人にはその“経験の蓄積”がなく、どうしても指示を待たざるを得ないのです。
この“指示待ち型”を「やる気がない」と切り捨ててしまうのではなく、まずは「なぜそのように行動しているのか?」という背景を探る姿勢が重要です。多くの場合、「迷惑をかけたくない」「間違うのが怖い」「自分で判断して失敗したくない」という、非常にまじめな気持ちから指示を待っているのです。
このような状況を改善するには、まずは“段取り教育”を設計する必要があります。職人道場では、職人にただ作業を教えるのではなく、「なぜその作業が今必要か」「この後何が起きるのか」という一連の流れを可視化するカリキュラムを導入しています。作業指示の背景を説明し、“なぜ”を理解してもらうことで、職人は少しずつ「先を読む力」を身につけていきます。
また、“気が利く”ためには、本人が「ここにいてもいい」と感じていることが前提です。心理的に萎縮している状態では、どれだけ優秀な人材でも自分から動こうとはしません。つまり、行動の背景には必ず“安心感”があるという事実を、指導者側が理解しておく必要があるのです。
実際に、ある企業では「先読み行動ができたら褒める」「自発的な行動を評価する」というルールを現場に導入。これにより、外国人職人の中で「考えて動くことが評価される」「失敗しても責められない」という安心感が生まれ、行動量が劇的に増えたといいます。これは、単に能力を育てただけではなく、“考えてもいい、行動してもいい”という心理的土壌を整えた結果なのです。
もう一つ重要なのが、フィードバックの仕方です。「なんで動かないんだ」と責めるのではなく、「ここは自分からやってくれると助かる」「次はこういう場面で動けるようになると一人前だよ」といった未来志向の声かけが、行動の質を高めていきます。
「気が利かない」のではありません。「気を利かせていい」と教えられていないのです。
「自分で考えて動けない」のではありません。「考える余白」や「行動の許可」が与えられていないのです。
外国人職人が“指示待ち”から脱却するには、まず現場が“関係性と文化の前提”を見直すこと。
その上で、「気が利く人材」を育てるのではなく、「気が利くようになる環境」を整えること。
それが、異文化マネジメントの本質であり、離職率を下げる一つの確かな答えなのです。
⑧ SNS投稿で企業情報が漏洩!?プライバシーとモラル教育の盲点
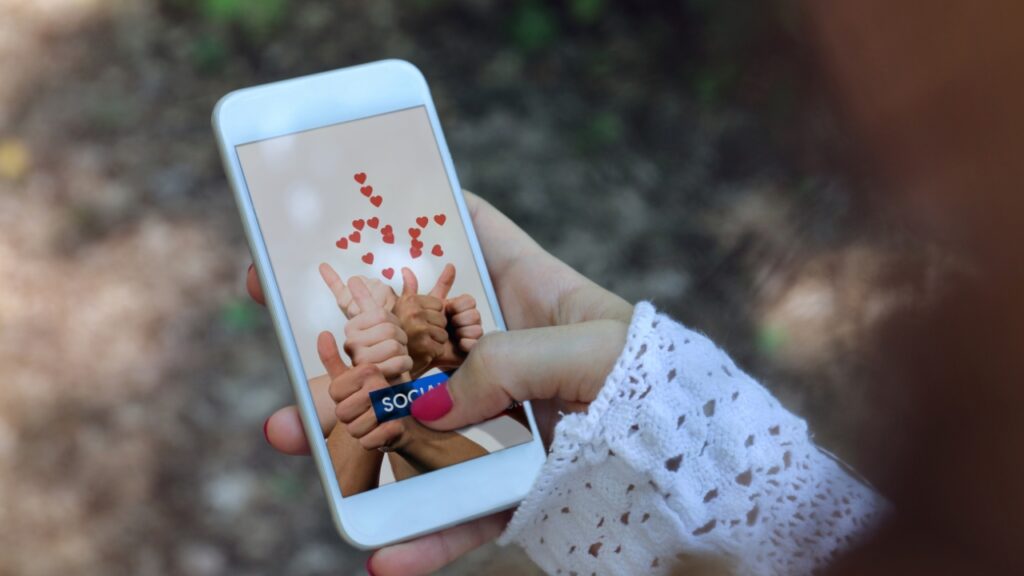
建設現場の安全や品質管理の徹底が叫ばれる中で、見落とされがちなリスクがひとつあります。
それは、外国人職人によるSNSへの無意識な情報発信です。
「昼休みに現場の風景を撮ってインスタにアップ」
「自撮りの背景に作業用の図面や資材、車両ナンバーが映り込んでいる」
「“日本の現場で頑張ってます”という投稿に、施工前の重要施設が写っている」
こうした投稿は、一見すると微笑ましい“異国で頑張る若者の記録”のように見えます。しかし、情報管理の観点から見れば、これらの行為は重大なリスクを含む企業の機密漏洩・法的問題・信用棄損につながる可能性を秘めているのです。
実際、過去には外国人技能実習生が現場で撮影した写真をSNSに投稿したことで、
・作業中の危険行為が写り込んで炎上
・ゼネコン名が判明し、施工中施設の工事スケジュールが特定されてしまった
・関係企業からの注意・謝罪対応に発展
といった事例も存在します。
こうした問題の根本には、**“モラル教育の不在”と“異文化的な情報観のギャップ”**があります。
つまり、日本では当然「撮ってはいけない」「投稿してはいけない」とされる感覚が、
母国では「記念に撮って投稿するのが普通」「働いていることを家族に見せたい」という前提であることが多く、
“悪意ではなく、善意から”行われているケースが大半なのです。
では、こうした無意識のリスクをどう防げばよいのでしょうか。
まず第一に必要なのは、ルールを感覚ではなく“仕組み”として設け、明文化して教育することです。
たとえば、職人道場で提案している対応策としては、
・入社時に「撮影禁止場所」「投稿禁止事項」をリスト化した説明書を配布
・SNSルールを母国語で記載し、図解とイラストを交えて直感的に理解させる
・日常的に「この場所ではスマホを出さない」「ロッカー保管を徹底」といった環境づくりを行う
などがあります。
これに加えて、「なぜダメなのか」を丁寧に説明する姿勢も欠かせません。
単に「禁止」と言われるだけでは、人は納得しません。
「この写真が外部に出ると、どんな影響があるのか」
「施工中の現場情報が知られることで、会社にどんな迷惑がかかるのか」
こうした背景と理由を説明することで、本人に“ルールを守る意味”が腹落ちするのです。
また、企業としては、SNSが“定着にも活用できる武器”になるという視点も忘れてはいけません。
たとえば、企業公認のSNS発信アカウントを用意し、
「安全に配慮した記念撮影」「オフショットや交流の様子」「成長記録としての投稿」などを発信することで、
本人の“発信したい”というモチベーションを満たしつつ、リスク管理の下でブランディングにも活用できる可能性があります。
重要なのは、禁止と自由のバランスをどうとるか。
全てを制限しても反発やモチベーション低下を招きます。
逆に、放任してしまえば、思わぬ情報流出につながる。
だからこそ、**「誰が、何を、どこまでなら投稿していいのか」**というラインを、
企業として定め、職場として共有し、外国人職人にも分かりやすく伝えることが求められるのです。
さらに、現場の管理者やリーダー層が、「見つけたときに注意する」だけでなく、
「投稿前に確認を取る文化をつくる」「何か気になるときは相談できる関係を築く」ことも、
日常的なリスク抑止力として大きな効果を発揮します。
時代は、誰もがスマホ一台で発信できる社会です。
だからこそ、外国人職人に対しても、企業文化や情報リテラシーを“学ばせる責任”があります。
SNSは、危険にも、武器にもなる。
その違いを生むのは、「教育の有無」と「伝え方の工夫」次第なのです。
⑨ 「宗教上できません」に戸惑う現場——配慮と生産性を両立させる方法
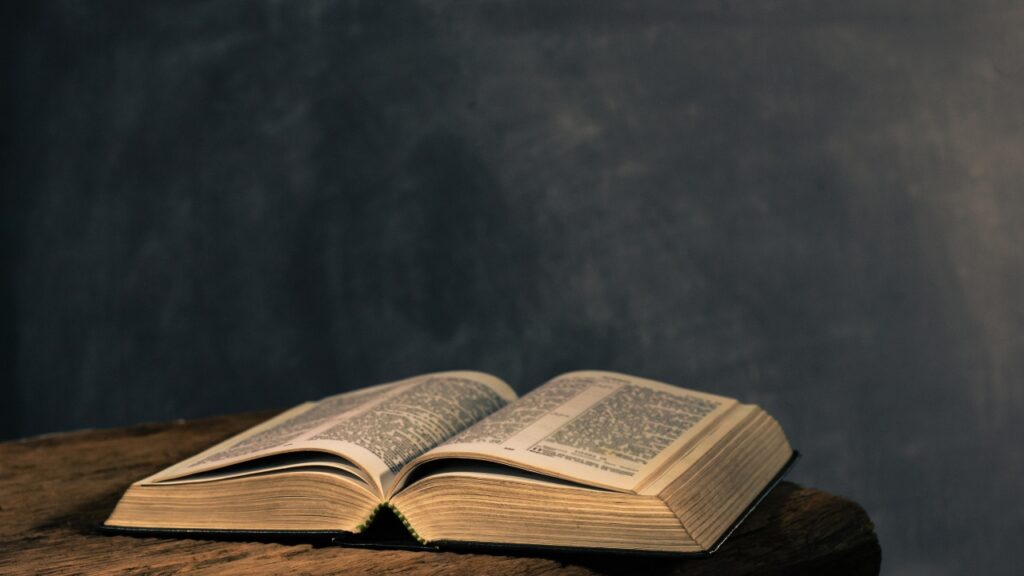
外国人職人の受け入れが進む建設業界において、近年ますます注目されるようになった課題のひとつが**「宗教的理由による制限や行動の違い」**です。たとえば、「礼拝のために作業を中断したい」「豚肉を使った食事ができない」「特定の祝日は働けない」など、これまでの日本人中心の現場では想定されなかったリクエストが現場で飛び交うようになっています。
現場の管理者や企業の多くが戸惑うのは、これらの要求が仕事にどのような影響を及ぼすのか分からず、対応に正解がないと感じているからです。無理に受け入れれば他の職人との不公平感が生まれるかもしれない。一方で、拒否すれば差別や人権侵害と捉えられるリスクもある。こうした板挟みの中で、「どう配慮すればいいのか分からない」と悩む管理者は少なくありません。
しかし、こうした宗教的配慮の問題は、“特別扱いを求めるわがまま”ではありません。
それは本人にとっての絶対的な信念や生き方に基づいたものであり、労働条件としても明確に保護されるべき法的権利なのです。
実際、外国人技能実習制度の中でも、労働基準法・人権尊重の観点から、宗教行為を理由に不利益な扱いをしてはならないという指導がなされており、厚労省も「礼拝や祝日など宗教的行為への合理的配慮は望ましい」と明言しています。
では、現場の混乱や生産性の低下を最小限に抑えながら、宗教的配慮をどのように実現していけば良いのでしょうか?
答えの第一歩は、**「知識の共有」と「事前のルール化」**です。
まずは、対象となる宗教の基本的な行動習慣(たとえばイスラム教の礼拝時間、ヒンドゥー教の食事制限、仏教の戒律など)について、管理者と現場スタッフが共通理解を持つことが不可欠です。
職人道場では、企業ごとに「宗教的配慮ガイドライン」を母国語と日本語で作成し、対応が必要な場面とその理由を整理しています。これにより、「なぜこれを求めているのか」「どこまで対応すべきなのか」という迷いがなくなり、対応が“個人判断”から“組織判断”に変わるのです。
次に重要なのは、**“代替案の設計”**です。たとえば、イスラム教徒が1日5回の礼拝を行いたいと申し出た場合、「そのたびに作業を止めるのは困る」と感じる現場もあるでしょう。そこで、
・礼拝は昼休みなどの既存休憩時間に重ねて調整する
・個別のスペース(更衣室の一角など)を一時的に礼拝場所として提供する
・時間をずらすことで、作業工程に影響を与えないタイミングに切り替える
など、業務への支障を最小限に抑える工夫が可能になります。
実際、こうした工夫を導入した企業では、「最初は驚いたが、ルールを決めたら混乱は一切なくなった」「逆に現場の結束力が高まった」といった声も上がっています。配慮を受けた側の外国人職人も、「自分たちの文化を理解しようとしてくれた」と感じて、より高い忠誠心と定着意欲を示すというデータもあります。
もう一つの成功ポイントは、**“現場におけるオープンな雰囲気づくり”**です。宗教的な行為はときに周囲から奇異な目で見られがちですが、それが無理解による“遠巻きな態度”や“いじり”として表れると、本人の心理的安全が崩れます。だからこそ、事前に「こういう文化を持った仲間がいます」「これは特別ではなく当然のことです」と全体に説明しておくことが、職場全体の成熟度を高め、不要な衝突を防ぐカギになるのです。
そして最後に重要なのは、生産性と配慮の両立は可能であるというマインドを、企業の“姿勢”として明確に持つことです。宗教的価値観に配慮することは、“効率を下げること”ではありません。むしろ、それによって現場に信頼が生まれ、定着率が向上し、結果的に生産性も高まるというサイクルが存在します。
“わからないから避ける”のではなく、“理解しようとすることで前に進む”。
それが、これからの多文化共生型現場に求められるリーダーシップであり、トラブルゼロの基盤になるのです。
⑩ トラブルを“教育の糧”に変える!現場で活かす再発防止マニュアルの作り方

外国人職人との建設現場において、トラブルがゼロになることはありません。
むしろ、言語、文化、価値観、労働観といった多くの違いを抱えた職場では、日々の些細な誤解やミスこそが“共に働くこと”の証拠とも言えます。
重要なのは、トラブルを起こさないことではなく、起きたトラブルをどう次に活かすかです。
ところが、多くの企業ではトラブルが起きると「個人の不注意」「たまたまの出来事」として処理され、再発防止に活かされることなく、同じミスが別の現場で繰り返されています。
これは非常にもったいないことです。トラブルの本質には、現場の課題や教育の盲点、制度の不備が必ず潜んでおり、それを言語化・共有することで、企業全体の“学習力”と“定着力”を高めることができるのです。
そこで注目されているのが、「外国人職人向け再発防止マニュアル」の整備です。
これは単なる注意書きではなく、**現場で実際に起きたトラブルを具体的に記録・分析・展開し、未然に防ぐための“教育ツール”**として機能します。
まず、再発防止マニュアルの第一歩は、“起きたトラブルを記録に残す文化”を育てることです。
たとえば、「作業中に間違った工具を使って部材を破損した」「休憩時間を勘違いして作業が遅延した」「現場の立ち入り禁止区域に誤って入った」など、日常的なミスをその場で報告・記録・共有する仕組みをつくります。
ここで重要なのは、「失敗を責めない」という風土です。
失敗を報告した人が損をする、叱られる、評価を下げられる——そんな空気では、誰も真実を語らなくなります。
職人道場の導入企業では、「報告=改善貢献」として評価に反映する制度を設けることで、トラブルを隠さず開示できるチーム文化の醸成に成功しています。
次に、記録されたトラブルの中から「繰り返しやすいもの」「他の職人にも起きうるもの」をピックアップし、事例ベースの学習資料として再構成します。
例:
・【トラブル】道具の名称を勘違いして違う作業をした
・【原因】同音異義語が多く、現場で使う日本語が正確に理解されていなかった
・【対策】業務用語の音声&イラスト付き辞書を配布/指導時に確認テストを実施
このように、「何が起きたのか」だけでなく「なぜ起きたのか」「どうすれば防げたか」まで掘り下げることで、マニュアルが“読むだけの資料”ではなく“学びの道具”へと変わります。
再発防止マニュアルは、紙ベースだけでなく、動画形式やワークショップ形式など多様な方法で展開するのが効果的です。
特に外国人職人にとっては、視覚・聴覚を使った教育が理解と定着に直結します。
ある企業では、「ヒヤリハット再現ドラマ」を制作し、実際のミスを演技で再現した動画を毎月の安全教育に活用。
この取り組みにより、離職率が3割以上低下し、職人の定着意欲も大幅に向上しました。
さらに、再発防止マニュアルの最大の強みは、組織知として横展開が可能になることです。
本来なら個々の現場で完結していたミスや改善点を、会社全体で共有することで、
・同じトラブルが他現場で起きることを防ぐ
・教育担当者が共通の指導ポイントを持てる
・新規採用者にも“事前学習”として活用できる
といった多層的な効果が生まれます。
そして忘れてはならないのが、マニュアルは「作って終わり」ではなく「運用して育てるもの」であるという視点です。
現場の状況は日々変化します。人も入れ替わります。
だからこそ、定期的にアップデートをかけ、現場の声を吸い上げて内容を見直していく運用体制が必要です。
現場で起きた“痛み”を会社の“成長材料”へ変える。
それこそが、外国人職人との共生を図る建設業界において、今最も求められるリスクマネジメントであり、未来への人材投資です。
トラブルは終わりではなく、はじまりです。
それをどう活かすかが、定着と信頼の分岐点になります。
【まとめ】外国人職人との“あるある”トラブル——現場は学びの宝庫だった

建設業界における外国人職人の活用は、人手不足を補うための“選択肢”ではなく、“未来を見据えた戦略”になりつつあります。
しかし、現場では「言葉が通じない」「文化が違いすぎる」「勝手な行動をする」など、さまざまな“あるある”トラブルが絶えません。
本ブログでは、その中でも特に多い10のトラブルと、その背景、具体的な回避策について解説してきました。
一見単純なミスやすれ違いに見える出来事も、深く掘り下げていくと、教育方法、伝え方、ルール設計、文化理解の不足といった“組織の盲点”が浮かび上がってきます。
「分かってるフリ」に始まり、「SNSの無断投稿」「宗教的制限」「無断欠勤」「短期離職」など、どの事例も“誰かのミス”ではなく、現場全体が育つべき課題としてとらえることが重要です。
そして、最も大切なのは、トラブルをそのままにしないこと。
記録し、見直し、共有し、教育に活かす。
それによって、「辞めない」「育つ」「活躍する」外国人職人が増え、企業にとっても現場にとっても、大きな“人財”へと成長していきます。
外国人職人との共生は、面倒でも難しくもありません。
必要なのは、“仕組み”と“姿勢”を整えること。
そうすれば、“トラブル”は必ず“信頼”へと変わっていきます。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。