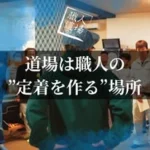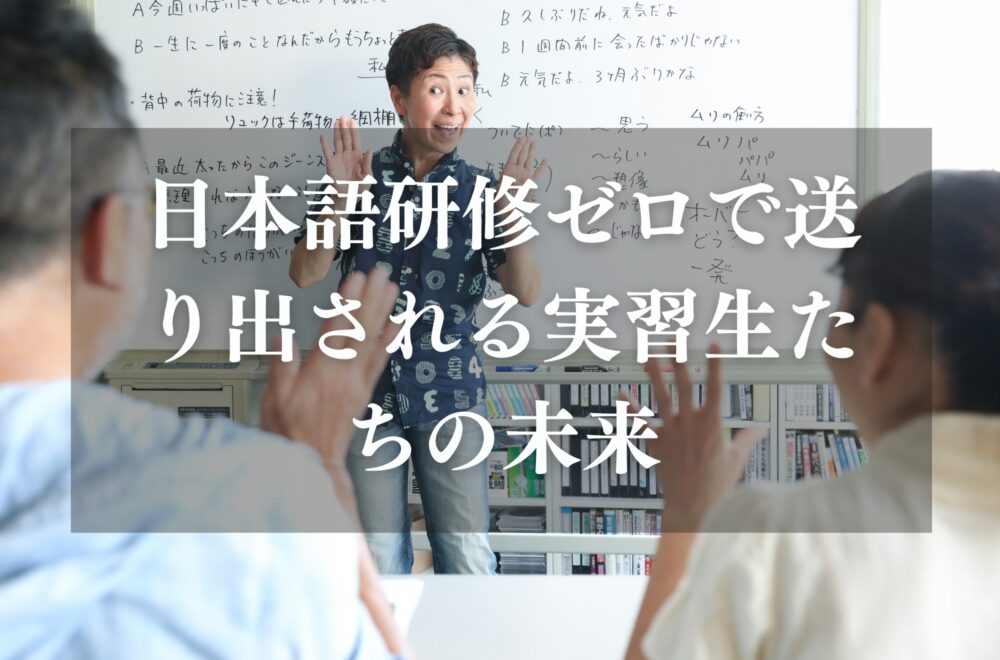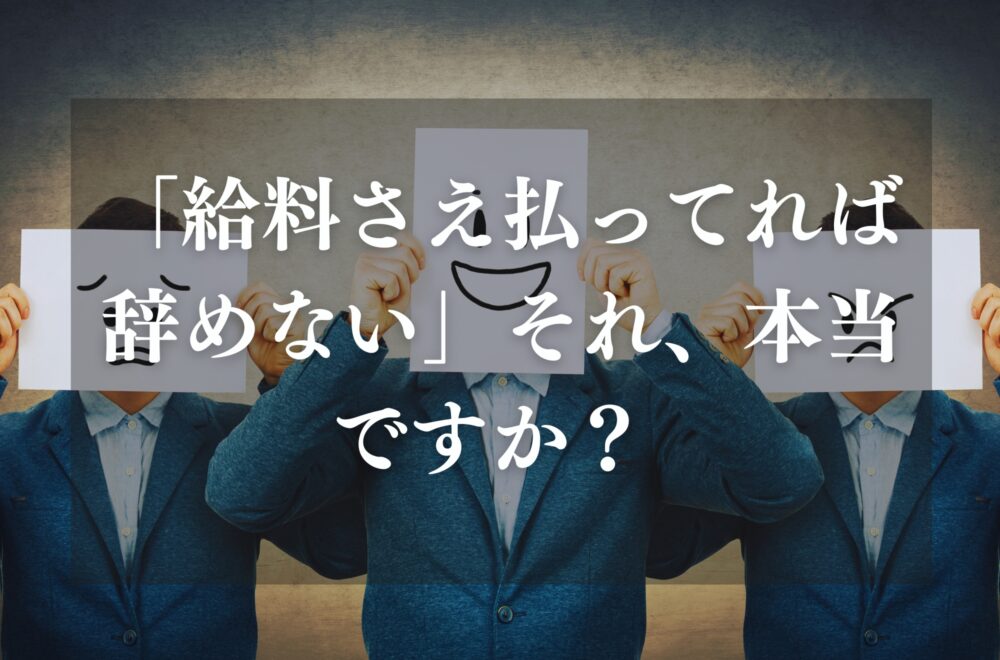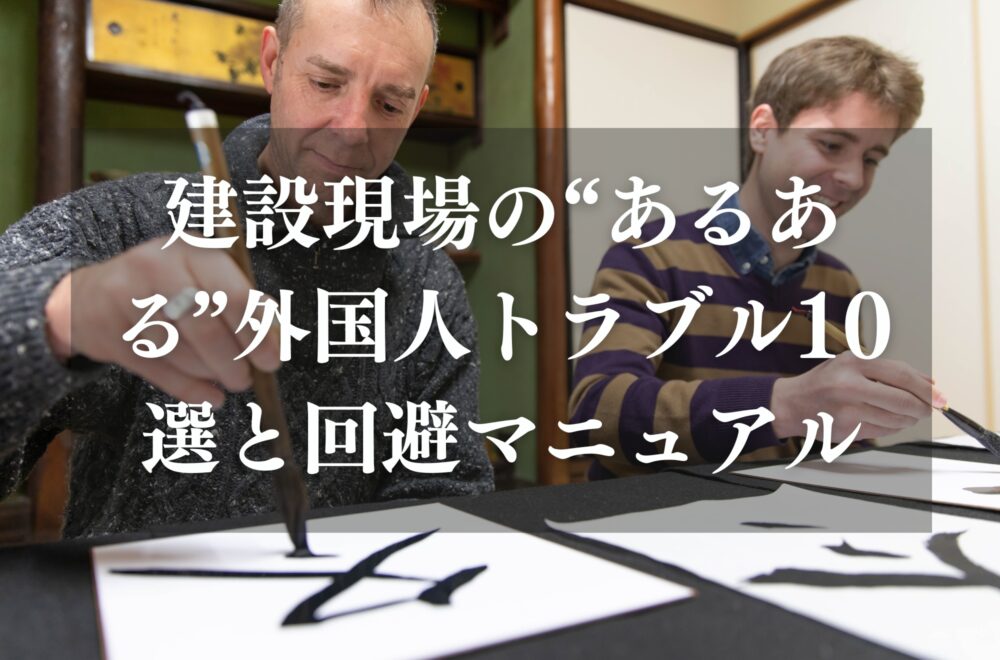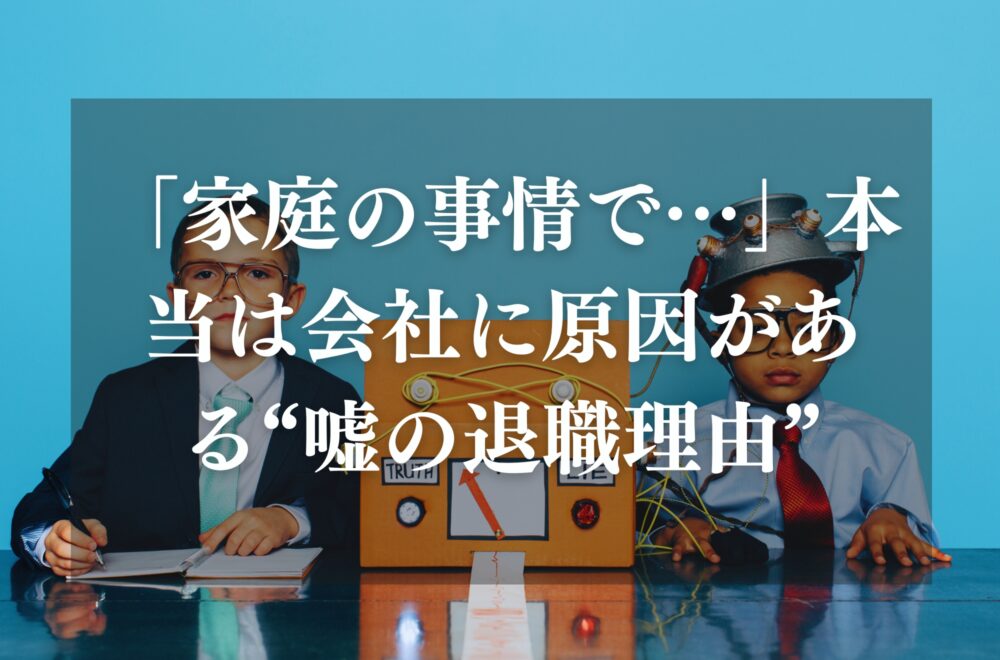日本語研修ゼロで送り出される実習生たちの未来
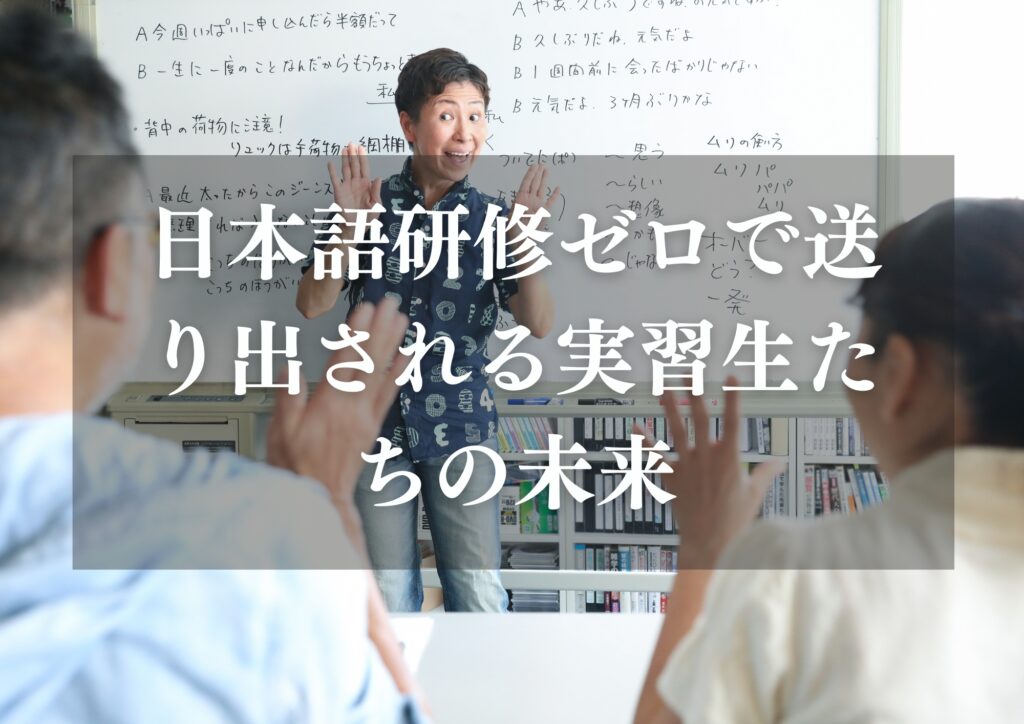
>目次(気になる記事のリンクをクリック下さい)
- ①日本語研修ゼロで送り出される実習生たちの未来
- ② 作業以前に会話が成立しない——日本語教育の欠落が引き起こす安全リスク
- ③ なぜ“送り出し機関任せ”ではダメなのか?制度の穴と責任の所在
- ④ “分かったフリ”が常態化する現場で育たない外国人職人たち
- ⑤ 通訳任せの限界——“言語の壁”は誰の責任か
- ⑥ 「教える側が疲弊する」——日本語力不足がもたらす教育コストの増大
- ⑦ 外国人職人本人が抱える“話せないストレス”と孤立のリアル
- ⑧ 企業が実践する“現場内日本語教育”とは?成功事例に学ぶ取り組み
- ⑨ “わかる日本語”を育てる仕組み——技能実習制度に足りない視点
- ⑩ “通じる言葉”が職人を変える——定着と育成の鍵は言語にある
- 【まとめ】“通じない言葉”が未来を閉ざす、“通じる言葉”が未来を開く
- この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武
- 多能工職人育成学校・技術研修所「職人道場紹介動画」
①日本語研修ゼロで送り出される実習生たちの未来

近年、建設業界における人手不足の深刻化を背景に、外国人技能実習生の受け入れは急速に拡大しています。
現場の即戦力として期待を集める一方で、実際に配属された実習生たちの“日本語力”に、多くの企業が衝撃を受けています。
「おはよう」と挨拶しても返事がない。
「こっち持って」と声をかけても反応しない。
「それ、片付けて」と言っても立ち尽くしたまま。
これは、本人がやる気がないわけでも、無視しているわけでもありません。
そもそも、何を言われているのか分かっていないのです。
その背景には、送り出し機関から現場に実習生が配属されるまでの日本語教育の不在、もしくは著しく不十分な実態があります。
「日本語研修あり」のはずが、実態は“名ばかり”
技能実習制度上、送り出し機関は実習生に対して一定の日本語研修を行うことが義務づけられています。
しかし、その実態を精査すると、
・1日1時間のビデオ学習だけ
・先生がいない自己学習形式
・「ひらがな」と「カタカナ」を“見せるだけ”の指導
など、実践的な日本語力を育むには到底及ばない内容であることが多く報告されています。
ある企業では、実習生3名が配属された初日に「こんにちは」が通じず、「おつかれさまです」を聞いても反応がなかったといいます。
言語レベルとしては、「日本語能力試験N5未満」。
日常会話どころか、指示語すら理解できない状態で送り込まれてきたのです。
このような“ゼロに等しい言語力”で実習が始まると、当然、現場では混乱が生じます。
実例:言語ミスが引き起こした作業事故
神奈川県内のある建設会社では、鉄筋組み立て中に「ここを締めて」と指示したつもりが、実習生は“取り外す”と誤解し、
すでに設置済みだった部材を解体してしまったケースがありました。
確認したところ、本人は“締める”という単語の意味を知らなかっただけでなく、
そもそも「ここ」という指示語の対象が分かっていなかったのです。
結果、半日分の作業がやり直しとなり、工程は1日遅れ。
現場責任者は「言葉が通じないことの怖さを初めて実感した」と語っています。
なぜ“言語力ゼロ”で現場に送り出されるのか?
理由は大きく3つあります。
送り出し機関の指導レベルのばらつき
海外の送り出し機関は玉石混交で、教育に熱心な機関もあれば、形式的に修了証を発行するだけのところも存在します。
企業側の“見えない期待”
「ある程度話せるだろう」「簡単な会話くらいは通じるはず」と思い込んでおり、実際の語学力を確認せず受け入れてしまう。
配属までの期間の短縮化
実習生の受け入れニーズが高まる中で、早期配属を優先する企業が増加。その結果、教育時間が圧縮される傾向にある。
このように、制度と実態のギャップの中で、言語力ゼロのまま現場に送り込まれる実習生が後を絶たないのです。
誰が困るのか?——“全員”が疲弊する現場構造
言葉が通じない現場で最初に疲弊するのは、当然ながら現場で直接指導をする職長・先輩職人たちです。
何度も言い直し、ジェスチャーで説明し、イラストを描いて伝える。
にもかかわらず、作業は思うように進まず、精神的な負担が増す一方。
「もう何も教えたくない」
「日本人だけで現場を回したい」
そう感じる指導者が現れた瞬間、職場全体の育成機能は失われます。
一方で、外国人職人本人も同じくらい苦しんでいます。
「何を言われているか分からない」
「注意されても、どう直せばいいのか理解できない」
「でも質問すると怒られそう」
——この繰り返しによって、自信を失い、孤立し、離職へとつながっていくのです。
現場に必要なのは“事前確認”と“自社内対策”
言語力の問題を解決する第一歩は、「来日前の日本語教育がどのように行われていたのか」を企業側がしっかりと把握することです。
・日本語の研修期間は何時間か?
・講師は日本人か、ネイティブか?
・どのような教材が使われていたか?
・日常会話と現場用語の区別はなされていたか?
これらを監理団体・送り出し機関に確認するだけでも、現場の混乱を未然に防ぐヒントが見えてきます。
さらに、自社で独自に「現場で必要な日本語リスト」「簡単な会話フレーズ集」を作成し、
配属初日から繰り返し教育することで、言語理解を実戦レベルに引き上げていく仕組みも整えていく必要があります。
最後に:言葉の壁は“準備不足”であり、“意識の壁”でもある
「こんにちは」が通じない職場で、果たして信頼関係が築けるでしょうか?
作業の指示どころか、挨拶さえ通じない現場は、職人を“共に働く仲間”ではなく、“ただの労働力”として扱う構造の象徴でもあります。
だからこそ、今企業に求められているのは、
「通じないから仕方ない」で済ませるのではなく、
「通じるようにするには、どんな仕組みが必要か?」を本気で考える姿勢です。
言葉は道具ではありません。
それは、人と人をつなぐ命綱なのです。
② 作業以前に会話が成立しない——日本語教育の欠落が引き起こす安全リスク

建設現場において「安全」は、すべての作業に優先される最重要事項です。
重機や高所作業、電動工具の使用など、日々の業務が常に事故と隣り合わせであるこの業界では、「声が届くか」「意味が伝わるか」という基本的なコミュニケーションが、命を守る防波堤となります。
しかし近年、外国人技能実習生が増加する中で、この“防波堤”が驚くほどもろくなっている現実があります。
その最大の理由が、日本語教育の欠落です。
「気をつけて」
「そこ、入らないで!」
「止まれ!」
こうした緊急性の高い言葉が、外国人職人に“その場で即座に伝わらない”という現実が、あらゆる現場で問題となっています。
日本語が通じなかったことで生まれた“ヒヤリ・ハット”
ある建設現場では、高所作業をしていた日本人職人の足元で外国人実習生が資材を運搬していました。
職長が「危ないから、そこどいて!」と声をかけたものの、実習生は反応せず、荷物を持ったままその場にとどまりました。
結果、上から落ちた工具がかすめる形となり、大きな事故には至らなかったものの、あと数センチずれていれば命に関わる事故だったといいます。
調査の結果、実習生は「“どいて”という言葉の意味が分からなかった」と説明。
また、声をかけられたことには気づいていたが、「叱られているのか、何か伝えられているのか分からなかったので、動けなかった」とも述べました。
このようなトラブルは決して一例ではなく、日常的に多くの現場で発生しています。
つまり、作業そのもの以前に、“日本語での会話が成立していない”ということが、安全の根幹を揺るがしているのです。
なぜ会話が成立しないのか?——根本にある「教育の設計ミス」
問題の根本は、「日本語を学ばせてから配属する」という発想が、制度として形骸化している点にあります。
送り出し国では、日本語教育が不十分なまま実習生が出国し、
受け入れ企業は「会話くらいできるだろう」と期待しながら、確認すらせずに現場に配属。
この“期待と現実のズレ”が、安全管理のブラインドスポットを生んでいるのです。
さらに、多くの企業が「日本語教育は監理団体や送り出し機関の仕事」と思い込んでおり、
自社で教育を設計するという発想すら持たないまま、現場に任せきりにしてしまう。
その結果、実習生は「見よう見まねで動く」ことしかできず、
その場しのぎの“作業”はできても、“安全に関する理解”にはまったく至らないまま時が過ぎていくのです。
実習生自身も“怖さ”を感じている
誤解してはならないのは、「言葉が分からなくても平気」と思っているのは現場側だけであり、
実習生本人たちはむしろ、日々の業務に強い不安を抱えながら働いているという点です。
「言われたことが分からなくて、怖い」
「危ないと思っても、どう伝えればいいか分からない」
「叱られても何を直せばいいか分からない」
これらの声は、職人道場が実施する現場ヒアリングでもたびたび寄せられます。
つまり、言語の壁は実習生本人の安心・安全にも直結しており、
事故の被害者・加害者になるリスクを常に背負っている状態だということです。
安全を守るために、今すぐできる「言語の整備」
安全管理の中に“日本語理解”を組み込むことは、もはやオプションではなく義務に近いものとなっています。
企業として今すぐ実践できる対応策としては、以下のようなものがあります。
現場で使うキーワードの“音声+イラストマニュアル”を配布
例:「とまれ」「あぶない」「さがって」「さわるな」など、現場で使う20語を厳選し、図解と音声で記憶させる。
毎朝の朝礼で“日本語クイズ”を実施
作業前に1単語だけでも復習させることで、言葉の記憶と理解を定着させる。
“言ってはいけないあいまい語”を現場で共有
例:「それ」「あれ」「ちょっと」「まあまあ」「大丈夫」など、日本人には通じるが外国人には意味不明な表現を廃止する。
緊急時の“ゼスチャー指示”を統一する
音声が聞こえないときや通じないときのために、手のひらを出してストップを示すなど、緊急時の合図を事前に共有。
こうした“伝える努力”が、安全な職場環境を構築するための第一歩です。
言語の壁を放置することは、“危機管理の放棄”である
建設現場において、日本語の通じない外国人職人が存在することはすでに前提であり、
それに対応できない組織は、人材受け入れに対する責任を果たしていないと言っても過言ではありません。
「安全第一」とは単なるスローガンではなく、
言葉で命を守れる体制が整っていてこそ、初めて成立する概念です。
作業は会話のうえに成り立つ。
会話が成立しないならば、作業もまた未完成なのです。
③ なぜ“送り出し機関任せ”ではダメなのか?制度の穴と責任の所在
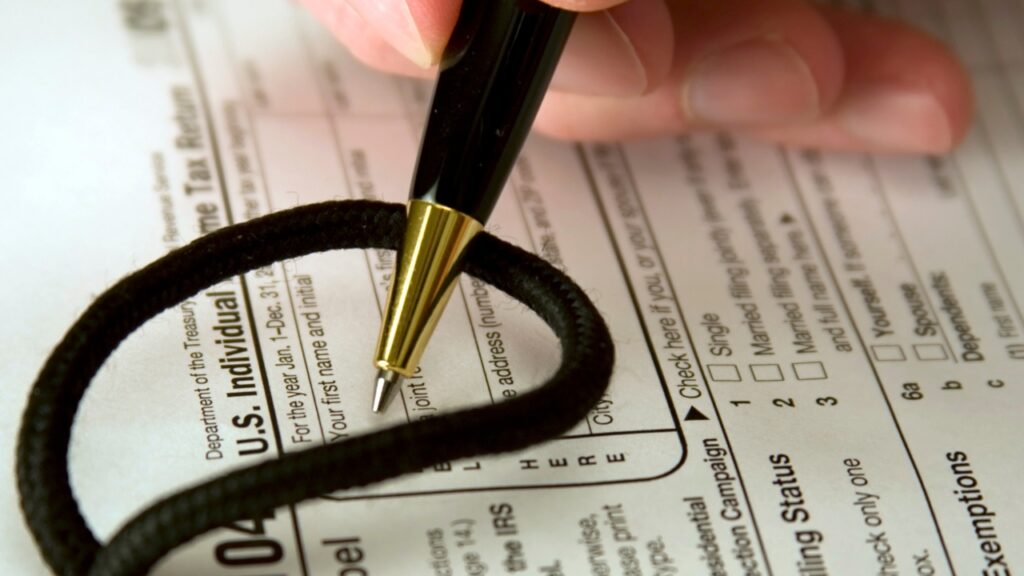
外国人技能実習生の受け入れにおいて、建設会社の多くが陥りやすい最大の落とし穴——それが、「送り出し機関がちゃんと教育してくれているはず」という前提で動いてしまうことです。
受け入れ企業としては、監理団体や仲介業者を通じて「研修済み」「日本語レベルN4相当」などと説明を受けることで、安心感を得てしまいがちです。しかし、いざ実習生が現場に配属されると、「あいさつができない」「工具の名前が分からない」「指示がまったく通じない」という現実に直面し、現場が混乱と疲弊に包まれる——この流れは全国各地で繰り返されています。
この原因は、制度自体の構造にあります。
制度の構造的な“責任の分散”がもたらす現場の迷走
現在、外国人技能実習制度の中では、
・送り出し機関(主に海外側の教育・人材供給)
・監理団体(日本国内の受け入れ支援・監督)
・受け入れ企業(現場での実習指導)
という三者が関わる形になっています。
表面上は役割が明確に見えますが、実際には責任の所在が曖昧です。
たとえば、
「言葉が通じない」→送り出し機関の責任?
「教育に時間がかかる」→監理団体の責任?
「指導が進まない」→受け入れ企業の責任?
このように、何か問題が起きたときに、「どこに改善を求めればいいのか」が不明確なのです。
その結果、受け入れ企業は「これは仕方がない」と諦め、現場任せにし、トラブルの火種がくすぶり続ける状況が常態化しています。
送り出し機関の教育内容は“見えないブラックボックス”
現場で実習生を受け入れる企業にとって、最も重要な情報の一つが「この人が、どのような教育を受けてきたか?」という点です。
しかし、送り出し機関の教育プログラムは、
・時間数が不明確
・講師の質や指導方法が不明
・どんな教材を使っていたかも分からない
という状態が多く、「実質ゼロ教育」のまま“教育済み”として送り込まれてくるケースも少なくありません。
ある企業では、「日本語初級の修了証あり」という触れ込みで配属された実習生が、「おはようございます」すら発音できず、
実際には“ひらがなを見たことがある程度”だったという衝撃の事例が報告されています。
「言語」も「文化」も教えずに“即戦力”を期待する矛盾
送り出し機関の目的は、実習生を送り出すことで収益を上げることにあります。
つまり、“送り出したら終わり”という構造が組み込まれてしまっているのです。
その結果、教育の質よりもスピードと数が重視され、
「3か月の研修」と言いながら、実態は週に数時間の自習形式だったり、
現地語と片言の日本語だけで授業を進める“研修ごっこ”が横行しているケースもあります。
これでは、実習生本人にとっても“日本で働く心構え”が整わないまま来日することになり、
現場とのギャップに直面してすぐに離職、あるいは失踪という最悪の結果を招きかねません。
結局、最後に責任を負うのは“受け入れ企業”
制度上、送り出し機関や監理団体が関わっているとはいえ、
実習生が現場で問題を起こした場合、責任を問われるのは受け入れ企業側です。
・安全管理上の不備
・指導記録の欠如
・教育体制の未整備
これらは労働基準監督署や出入国在留管理庁の調査対象となり、最悪の場合は実習生の受け入れ停止処分や企業の指導・勧告に至ることもあります。
つまり、「任せていた」「知らなかった」では通用しない時代に突入しているのです。
企業が主導権を持つために今すぐやるべきこと
このような状況の中で、受け入れ企業が取るべきスタンスは明確です。
「自社で教育の主導権を握ること」。
つまり、送り出し機関任せにするのではなく、以下のような“自社目線でのチェック体制”を整えることが求められます。
来日前の面談で日本語レベルを直接確認
教育カリキュラムの開示を送り出し機関に求める
「実技+会話」の模擬チェックを配属前に実施
配属後の教育マニュアルを自社で整備し、言語教育も含めて継続的に実施
教育実績をデータ化して管理(改善・再教育にも活用可能)
これらを行うだけで、「教えていないのに期待する」状態から脱却し、実習生との信頼関係も安定的に築けるようになります。
最後に:制度の穴は“意識”と“仕組み”で埋められる
外国人技能実習制度は、国際貢献という名目のもとに導入された制度ですが、
実態としては企業の労働力補填手段として機能している側面が大きく、
その中で“育成”を実現するためには、受け入れ企業自身が制度の限界を知り、補完する責任を持つ必要があるのです。
送り出し機関は選べても、送り出し機関の中身までは変えられない。
だからこそ、企業ができるのは、“見抜く力”と“補う力”を育てること。
「送り出された人材がどう育つか」は、制度の問題ではありません。
それは、受け入れる側の姿勢そのものにかかっているのです。
④ “分かったフリ”が常態化する現場で育たない外国人職人たち
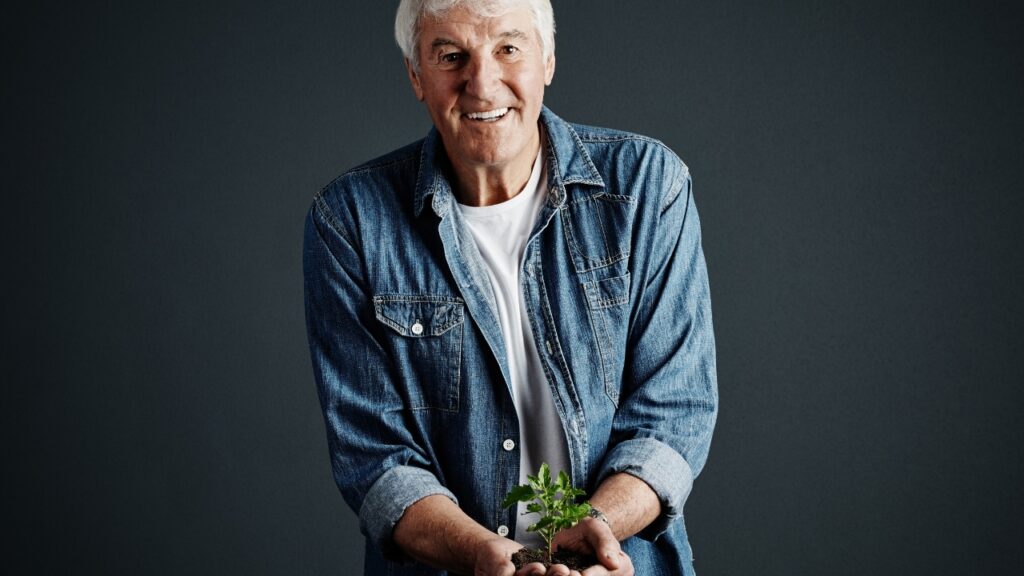
「はい、分かりました」
「OK、だいじょうぶ」
現場で外国人職人がそう答えてくれると、一見スムーズなコミュニケーションが成立しているように思えます。
しかしその裏では、“本当は理解していない”という現実が隠れていることが少なくありません。
この“分かったフリ”が常態化している現場では、作業ミス、再施工、事故、教育遅延といった問題が多発します。
そして何より深刻なのは、本人が成長しないまま現場に居続け、数ヶ月、数年と“わからないまま働き続ける”構造が固定化してしまうことです。
なぜ“分かったフリ”をしてしまうのか?
その理由のほとんどは、「分からない」と言えない心理状態にあります。
外国人職人たちは、こんな思いを抱えています。
何度も聞いたら迷惑がられるのではないか
怒られるのが怖い
“できないやつ”と思われたくない
自分の日本語が通じなかったら恥ずかしい
つまり、「理解していないこと」よりも、「理解していないとバレること」の方が怖いのです。
その結果、本人は“聞いていないフリ”よりも“聞こえたフリ”を選び、
“知らない”よりも“知っているフリ”を選び、やがてそれが日常のクセになっていきます。
現場ではどうなるか?——小さな誤解が“大きな損失”に
この“分かったフリ”は、日常的なコミュニケーションの中に潜んでいます。
「この材料、明日までに運んでおいて」
「はい(分かっていない)」
→ 材料が別の場所に放置され、翌朝の作業が滞る
「今日の作業はこっちじゃなくて向こうね」
「OK(向こうがどこか分からない)」
→ 違うエリアで作業を始め、誤って未着工区域を破壊
「危ないから、そこ立たないで!」
「はい(“危ない”の意味を正確に理解していない)」
→ 危険区域に入り、ヒヤリハットが発生
このように、“分かったフリ”は一見スムーズなやり取りに見えて、実は危険とトラブルの温床になっているのです。
“教えた”と“伝わった”は違う——育たない原因の正体
企業や指導者の多くが抱える悩みのひとつが、
「ちゃんと教えているのに、全然成長しない」というものです。
しかし、ここには大きな誤解があります。
それは、「教えたから伝わっているはずだ」「返事をしたから分かっているだろう」という確認の怠慢です。
外国人職人に対して、教える側は
・難しい日本語を使っていないか?
・専門用語や略語を前提にしていないか?
・主語が曖昧な話し方になっていないか?
・ジェスチャーや図解を使って補足しているか?
・「理解できたかどうか」の確認をしているか?
こうしたチェックを常に行っていなければ、“教えたつもり”は何の意味も持ちません。
“分かったフリ”を防ぐには?——3つの即効対策
リピートバックを標準化する
指示後に「今、何をするか説明して」と必ず確認。
これを徹底するだけで、理解度が可視化される。
チェックリストで見える化する
作業工程や注意事項を簡単な日本語+イラストで示し、本人がチェックできるようにする。
理解不足が自己認識できるようになれば、質問も増える。
間違えたときに怒らない文化をつくる
「分からない」と言える環境がなければ、フリはなくならない。
失敗したら、「どこが分からなかったか」を一緒に振り返る習慣をつける。
これらの工夫によって、“分かったフリ”は徐々に減少し、“自分から聞く”文化が現場に根づいていきます。
“できるようになる”には、“分からない”を大事にすること
外国人職人が本当に育つ現場とは、
「できる人間しか評価されない現場」ではなく、
「分からないことを放置しない現場」です。
人は、“分からない”と言えたときに初めて学びが始まります。
だからこそ、「分からない」と言える空気をどう現場に作るかが、実習生の成長スピードと定着率を左右します。
“分かったフリ”は、現場の見えない敵です。
それを放置するということは、将来の事故・離職・信頼喪失を容認することと同じです。
まずは、返事ではなく“理解”を見る。
それが、外国人職人を本気で育てる企業が実践している、共通のマネジメントなのです。
⑤ 通訳任せの限界——“言語の壁”は誰の責任か
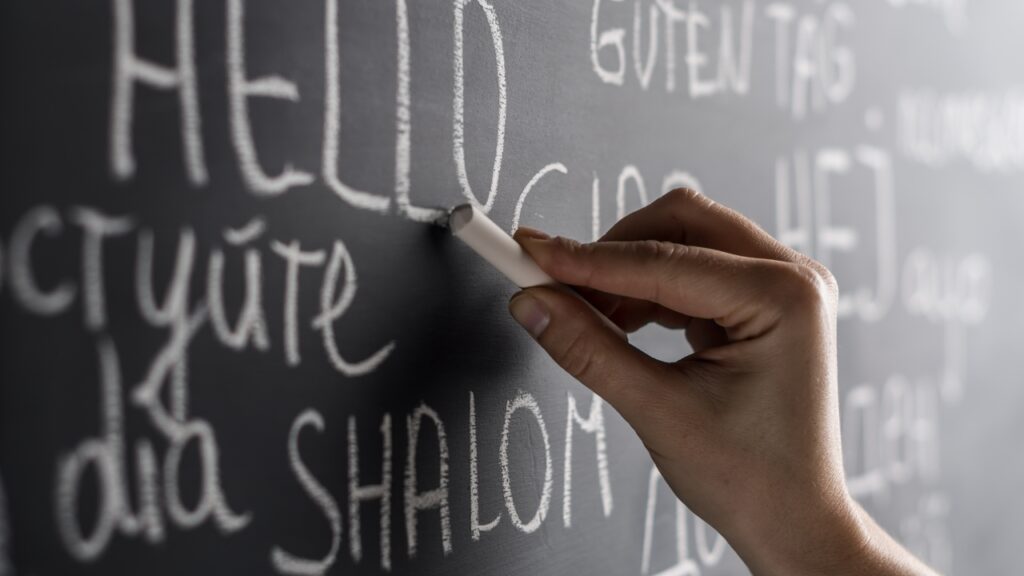
外国人技能実習生を現場に受け入れる際、多くの企業がまず頼るのが「通訳」の存在です。
特に配属初期やトラブル時には、「通訳がいれば安心」「通訳を通じて伝えれば大丈夫」と思っている管理者も少なくありません。
しかし現実には、“通訳任せ”の体制には重大な限界があることに、徐々に気づく企業が増えています。
通訳は万能ではありません。そして、言語の壁を通訳だけに任せることは、育成と安全、そして職場定着の根幹を揺るがす危険な依存構造を生むことにつながるのです。
通訳が常駐していない時間帯に何が起きるか
多くの現場で起きているのは、「通訳がいない時間は、現場が止まる」「会話が成立せず、職人も指導者もフリーズする」といった問題です。
たとえば、作業の変更を現場監督が口頭で伝えたが、通訳が昼食で不在だったため、実習生が指示を受けられず作業を進めてしまい、翌日には“なぜ勝手な判断をしたのか”と叱責される——このような齟齬は日常的に発生しています。
この状況では、実習生本人はもちろん、指導側も「伝えたいのに伝えられない」ストレスを抱え、
結果的に「通訳がいなきゃ何もできない」「だったら最初から採用しなければよかった」という空気が職場全体に広がってしまうのです。
通訳の“質”にもバラつきがある
さらに問題を複雑にしているのは、通訳者の言語力や建設現場への理解度がまちまちである点です。
たとえば、送り出し機関が紹介する通訳者の中には、
・母国語と日常日本語はできるが、建設業の専門用語が分からない
・文法的には正しく訳せるが、ニュアンスや安全の緊急性を表現できない
・実務経験がなく、職人の感覚や手順を理解していない
というケースが少なくありません。
その結果、「危ないから触るな」を「それ、ダメ」と軽く訳してしまったり、
「今日は段取りが変わったから、午後からB工程に移るよ」という複雑な工程説明を丸ごと省略してしまうなど、
“誤訳”や“説明不足”が新たな誤解を生む原因になっています。
通訳に頼り切る企業の“危うさ”とは
本来、通訳は「補助」であって「代行」ではありません。
しかし、現場でよく見られるのは、「全て通訳に伝えさせる」「会話の間に通訳を挟まないと不安」という依存的な使い方です。
これでは、外国人職人自身の言語能力も伸びず、
・自分で日本語を使ってみようとする意欲がなくなる
・通訳に頼ることが当たり前になる
・現場に主体性が生まれず、ただの“指示待ち労働力”になってしまう
という悪循環に陥ります。
つまり、通訳に頼るほど、自社の教育能力と職人本人の成長機会を奪っているという皮肉な構図ができてしまうのです。
言語の壁は“全員で越えるべき現場課題”
ここで改めて問いたいのは、「言葉が通じないのは誰の責任か?」ということです。
送り出し機関?
通訳者?
外国人本人?
いいえ、最終的には受け入れ企業の“教育設計力”に帰結します。
言語の壁は個人の努力で超えるものではなく、
現場全体が「通じ合う努力を仕組みにする」ことで、はじめて乗り越えられる課題なのです。
企業がやるべき「脱・通訳任せ」4つの実践
現場で使う日本語を標準化する
→ 指示語や曖昧語を減らし、「工具名」「行動指示」「安全用語」を統一。
→ 翻訳や指導がブレない“現場語辞典”を作成。
指導者が“伝えるスキル”を持つ
→ 教え方研修・やさしい日本語研修を導入し、通訳がいなくても伝えられる自信を持たせる。
通訳は“育成支援者”に位置付ける
→ 通訳者も現場教育の一員として、単なる翻訳者で終わらない立場にする。
外国人本人の“使える日本語”を育てる
→ 日常会話+現場用語を週単位で繰り返し習得させ、“受け身の通訳依存”から“自発的な理解”へ導く。
通訳に頼らなくても“通じ合える現場”は作れる
実際、職人道場では「通訳がいない環境で現場会話力を育てる」カリキュラムを導入し、
半年以内に約8割の実習生が「日常業務は自力でこなせるレベル」に到達しています。
通訳の不在が“困難”ではなく“成長機会”になる。
この感覚を持つ企業ほど、実習生の定着率も高く、職場に活気が戻っているのが事実です。
言葉の壁は、通訳に任せて超えるものではない。
全員で橋を架けるものだという視点が、今、企業に強く求められています。
⑥ 「教える側が疲弊する」——日本語力不足がもたらす教育コストの増大

外国人技能実習生の育成がうまくいかない理由として、現場から最も多く寄せられる声が、「教える側が疲れる」「何度言っても通じない」「結局、自分がやった方が早い」といった“教育の疲弊”です。
そしてその原因の多くは、実習生側の日本語力不足に起因する“伝わらない指導”にあります。
この疲弊は精神的なストレスにとどまらず、作業効率の低下、教育コストの増大、ひいては人材育成そのものの放棄へとつながり、企業にとって極めて深刻な悪循環をもたらします。
なぜ教える側が疲れてしまうのか?
一見、「伝えれば分かるはず」「簡単なことなのに」と思える作業指示が、外国人職人にはまったく通じない。
そのたびに言い直し、図で説明し、場合によっては実演までしてやっと理解してもらえる——
このサイクルが一日に何度も繰り返されるのが現場の実情です。
あるベテラン職長はこう語ります。
「日本人の新人に教えるときは、1回説明して、あとは見て覚えろで済む。外国人には、3回説明しても動けない。怒っちゃいけないって分かってても、つい声を荒げてしまう。自分のストレスも溜まるし、現場もピリつく。」
このように、指導の生産性が著しく低下し、現場の雰囲気が悪化することが、教育の継続を困難にしていくのです。
教育疲れは現場の“教えない文化”を生む
「教えても無駄だ」「通じないから自分でやった方が早い」
こうした思考が現場に蔓延し始めると、外国人職人への指導そのものが放棄されていきます。
本来であれば、
・安全管理の徹底
・道具の正しい使い方
・工程ごとの意味や理由
を丁寧に教えなければならないはずが、いつの間にか“作業を与えるだけの現場”に変貌してしまう。
結果、
・意味を理解しないまま動く
・応用が利かず、応急対応できない
・事故やミスの再発が止まらない
といった問題が連鎖的に発生し、実習生が“作業者”にとどまり、“職人”に成長しないという本末転倒な結果を招いてしまいます。
日本語力不足がもたらす“見えないコスト”
このような現場の停滞と指導者の疲弊は、企業にとって「人件費」や「再教育費」といった形で明確なコストとして跳ね返ってきます。
具体的には、
同じ作業を何度も教える時間=熟練職人の作業工数が削られる
言葉が通じないことで発生するミスの手直し=追加の人件費
教育係のモチベーション低下=離職率の上昇
トラブル回避のために通訳を常駐=月数万円〜数十万円のコスト発生
つまり、日本語力を補完する取り組みがなされていないことが、中長期的に“金銭的損失”と“人材損失”を増幅させているのです。
解決のカギは“教える側”の負担を軽減する仕組みづくり
この問題を解決するには、「教える人間の忍耐に頼る」のではなく、教育そのものの“設計”を変える必要があります。
具体的には、以下のようなアプローチが有効です。
視覚情報を徹底活用する
→ マニュアルは“読ませる”のではなく、“見せる”。
→ 写真・動画・イラストを多用した教材で、言語依存を減らす。
“伝え方教育”を職長にも実施する
→ 現場での指導に“やさしい日本語”や“非言語コミュニケーション”のスキルを導入。
→ 教える技術の可視化・標準化で属人化を回避。
週1回の言語フォロー研修を導入
→ 現場作業とは別に、言語トレーニングの時間を確保し、少しずつ“理解できる語彙”を増やす。
チェックリストによる反復と確認
→ 指示した内容が“理解されたかどうか”を視覚的に確認するフローを業務に組み込む。
このように、“教える人間の負荷”ではなく“仕組みとして教える環境”を作ることが、疲弊を防ぎ、持続可能な教育を実現する鍵なのです。
教育が回らなくなった現場は、人も定着しない
現場での教育がストップすると、最終的に被害を受けるのは外国人職人本人です。
「分からないけど、誰も教えてくれない」
「ミスして怒られるだけ。理由は分からない」
こうした状態が続けば、やがて心が折れ、離職や失踪といった結果を招きます。
逆に、“教わる土壌”があり、“伝え方が工夫された現場”では、職人たちは自然と定着していきます。
彼らにとって、“伝わった成功体験”は、“働く理由”そのものになるからです。
最後に:育てるとは、伝える環境を整えること
外国人職人を育てるうえで、「教える側の技術」はもちろん大切です。
しかしそれ以上に必要なのは、「教えられる状態を、現場全体でどう作るか」という視点です。
日本語力が不十分な人材を育てるには、忍耐ではなく設計が必要です。
そしてその設計は、決して一人の熱意ではなく、組織的に行う“仕組みづくり”によって成立するのです。
教育の疲弊を、“人の問題”で終わらせてはいけません。
それは、現場の未来を見据えたとき、“避けられる投資”であり、“回避可能なコスト”なのです。
⑦ 外国人職人本人が抱える“話せないストレス”と孤立のリアル

日本語が通じない現場で、最も深く傷つき、悩み、苦しんでいるのは、実は外国人職人本人です。
表面的には笑顔を見せ、指示には「はい」と答え、黙々と作業に取り組んでいるように見える彼ら。
しかしその内側には、“言葉が通じない”ことによって生まれる、強烈なストレスと孤独が静かに蓄積されています。
多くの日本人現場関係者は、「外国人は明るい」「前向き」「我慢強い」という印象を持っています。
それは一面では事実かもしれません。
しかし、その“明るさ”の裏には、「分からない」と言えない葛藤、「分かっていない」と思われたくない不安が隠れていることに、どれほどの人が気づいているでしょうか。
「日本語が話せない=意思を伝えられない」苦しさ
技能実習制度のもとで日本に来る実習生の多くは、20代前半の若者たちです。
中には、初めて海外に出たという人も少なくありません。
母国ではリーダー的存在だった人材が、日本に来た瞬間、“言葉の通じない赤ん坊のような存在”になってしまう。
このギャップは、本人にとって非常に大きな精神的ダメージになります。
・体調が悪くても伝えられない
・ミスをした理由を説明できない
・困っていることを相談できない
・現場で起きていることが分からず、ただ笑ってごまかす
こうした日常が続く中で、本人の中には「自分は役に立っていない」「ここにいる意味がない」という感覚が芽生え始めます。
これは、技能や技術以前の、“存在価値の否定”に近いレベルの孤独です。
孤立のサインは、日々の小さな変化に現れる
職人道場で行った現場観察では、離職や失踪をした実習生の多くに共通して見られた“孤立の兆候”がありました。
・休憩中は一人でスマホを見ている
・日本人職人との会話がほぼない
・会話しても一語で終わる
・目を合わせようとしない
・「大丈夫です」としか言わない
こうしたサインは、決して突然現れるわけではありません。
最初は小さなすれ違いから始まり、「伝わらない」経験が積み重なり、「どうせ言っても無駄」というあきらめに変わり、やがては心を閉ざす——このサイクルが、職場の中に“見えない失踪”を生み出しているのです。
“話せない”のは、能力の問題ではない
実習生の中には、「母国では成績優秀」「大学卒業」「英語はできる」という人材も多くいます。
にもかかわらず、日本語となると意思疎通がままならない。
これは、能力や努力の問題ではありません。
むしろ、“話せない”のではなく、“話す環境が整っていない”という構造的な問題が背景にあるのです。
・誰も話しかけてくれない
・聞き返すと嫌な顔をされる
・伝えようとしても、すぐ遮られる
・間違えると笑われる
こうした経験が積み重なると、本人は「黙っていれば怒られない」「何も言わなければミスしない」と考え、“沈黙することが身を守る術”になってしまいます。
孤立を防ぐのは、“会話”ではなく“関心”
外国人職人の孤立を防ぐ方法は、決して難しいことではありません。
高い日本語力も、特別なスキルも必要ありません。
必要なのは、「関心を持って接する」こと。
・「昨日、眠れた?」と聞いてあげる
・「寒くない?」と気遣う
・「この仕事、どうだった?」と感想を求める
・笑顔で目を見て、うなずくだけでも良い
こうした小さなやり取りが、彼らにとっては「ここにいてもいいんだ」と思える大きな支えになります。
実際、ある企業では「一日一声運動」として、全職人が外国人実習生に毎日一つ話しかけるルールを導入。
これだけで離職率が激減し、実習生本人の表情や作業効率にも明らかな変化が見られたといいます。
“話せるようにする”より、“話してもいいと思える”職場づくりを
日本語が話せるようになるには、時間がかかります。
しかし、「話してもいい」と思えるには、環境次第で明日からでも変えられます。
・ミスしても笑わない
・言葉に詰まっても待ってあげる
・分からないことを責めない
・聞き返されたら、丁寧に言い直す
こうした行動を積み重ねることで、外国人職人は少しずつ心を開き、言葉を発するようになります。
それは同時に、“職場に定着する第一歩”でもあるのです。
言葉はスキルではなく、“つながる手段”
最後に強調したいのは、言葉は単なる道具ではないということです。
それは、職場の中で「信頼」「関係」「安心」をつくるための、もっとも根源的な接着剤なのです。
「話せないから仕方ない」ではなく、
「話させない空気があるかもしれない」と、まずは現場自身が問い直すこと。
それこそが、外国人職人の孤立を防ぎ、本当の意味で“働ける職場”をつくる出発点になるのです。
⑧ 企業が実践する“現場内日本語教育”とは?成功事例に学ぶ取り組み

日本語を話せないまま現場に入る外国人職人が増加する中、多くの建設会社が直面するのが「誰が、いつ、どうやって日本語を教えるのか」という問題です。
送り出し機関任せにも限界があり、通訳の常駐はコスト負担が大きい。
「教育する時間も人手もない」という声が現場からは聞こえます。
しかし、そんな厳しい現実の中でも、“現場内日本語教育”をうまく組み込み、成功している企業が確かに存在するのです。
ここでは、教育の負担を最小限に抑えながら、実習生の日本語能力を確実に伸ばしている企業の実践例を紹介しつつ、その工夫とポイントを解説していきます。
成功事例①:「やさしい日本語」を使った現場指導(東京都・土木工事業)
この企業では、技能実習生が初めて配属される現場で、すべての指導者に対して「やさしい日本語研修」を実施しています。
内容は、「短く、簡単に」「主語を入れる」「専門用語は避ける」という基本ルールを徹底するもので、たとえば以下のような変換が奨励されます。
「これ、片付けといて」→「〇〇さん、この道具を元の場所に戻して」
「そっち持ってって」→「その木の板を、トラックの後ろに運んで」
指導者が“伝えやすい”ようにするのではなく、相手が“理解しやすい”ように伝えることを目的としたマインドセットが導入されている点がポイントです。
この取り組みにより、実習生の理解度と反応スピードが飛躍的に向上し、現場のストレスも激減。結果的に、指導者の離職も減り、教育文化の好循環が生まれました。
成功事例②:「現場ことば辞典」を配布(愛知県・設備会社)
この企業では、現場で使う用語をイラスト付きでまとめた『現場ことば辞典』を独自に作成し、全実習生に配布しています。
たとえば「脚立」「インパクト」「ボルト締め」「マスキング」など、作業時によく使う100語を厳選し、
・日本語(ひらがな+カタカナ)
・ふりがな付き漢字
・ベトナム語訳
・現場写真やイラスト
を組み合わせて、実際の使用場面が一目で分かるようにしています。
この辞典を作るにあたっては、現場のベテラン職人と通訳がタッグを組み、
“何をどう伝えれば通じるか”という観点から、言葉と現実を一致させる工夫が凝らされています。
この取り組みにより、「言葉の習得速度が早くなる」「復習が自分でできる」と実習生からも好評です。
成功事例③:週1回の“日本語ラウンド”制度(大阪府・建築会社)
この企業では、毎週金曜日の午後1時間を「日本語ラウンド」として設定。
現場を回りながら、その週に出た日本語の疑問や、よく使われた言葉を実習生と一緒に確認し、会話形式で復習する時間を設けています。
ここで重視されているのは、「現場で実際に使った言葉」をそのまま教材にするという点です。
教室で学ぶのではなく、「今週の業務」で実際に聞いたり言ったりした言葉を再確認することで、定着率が非常に高くなります。
また、指導者側もこの時間に「どの言葉が通じていなかったか」を振り返ることができ、
次週の指導に活かすPDCAの一環として位置づけられています。
共通点:無理をしない、でも継続する
これらの企業の取り組みに共通するのは、“特別な教育者”を置かなくても回せる設計になっているという点です。
・日常業務の中に無理なく組み込む
・資料や表現を工夫して負担を減らす
・職人と実習生が“学び合える関係”をつくる
・形式よりも“通じること”を重視する
つまり、「学校のような日本語教育」ではなく、「現場で使える言葉を、現場で育てる」スタンスこそが、成功のカギになっているのです。
教育コストではなく、“投資”として捉える視点
現場内日本語教育にかかる時間や工数を、「余計な手間」と感じる企業もあるかもしれません。
しかし、以下のような成果を考慮すれば、それはコストではなく明確な投資だと分かります。
作業効率の向上
指導ストレスの軽減
ミス・事故の減少
実習生の定着率向上
自社への愛着とブランド信頼の向上
そして何よりも、言葉が通じるようになった実習生は、自信を持って動き始め、次第に“考えて動ける戦力”へと進化していきます。
それは、人手不足に悩む企業にとって、最も確かな成果ではないでしょうか。
最後に:教える現場は、育つ現場
“教えられる文化”がある企業には、職人も、実習生も、自然と人が集まってきます。
なぜなら、人は「理解されること」「通じ合えること」に、安心を感じ、力を発揮できるからです。
現場内日本語教育は、実は“言葉を教える”こと以上に、“働く環境を整える”ための土台です。
それを整備できる企業こそが、外国人職人時代を勝ち抜く本物の受け入れ体制を持っている企業なのです。
⑨ “わかる日本語”を育てる仕組み——技能実習制度に足りない視点

外国人技能実習制度では、「日本語教育を行うこと」が定められており、送り出し機関でも一定時間の日本語研修が設けられています。
しかし、多くの建設会社が感じているのは、「来日してくる実習生の日本語力が、現場でまったく使い物にならない」という現実です。
「挨拶はできるが、作業指示は理解できない」
「教科書の日本語はわかっても、現場の会話にはついてこられない」
——このようなギャップが生じるのは、制度の中に“使える日本語”ではなく、“試験に合格する日本語”を重視する構造があるからです。
今、求められているのは、「話せる日本語」や「知っている日本語」ではなく、“わかる日本語”を育てる仕組みです。
その視点こそが、技能実習制度に足りない、そして現場で本当に必要とされている要素なのです。
“話せる日本語”と“わかる日本語”は別物
多くの実習生は、来日前に「日本語能力試験(JLPT)」でN4やN5といったレベルの資格を取得しています。
しかし、試験で問われるのは、文法や語彙、読解能力が中心であり、「現場で使う言葉」「作業の中で飛び交う指示語」「方言や略語」にはほとんど対応していません。
例を挙げると、
「それ、こっち持って」
「一回バラして、あとで戻して」
「段取り変わったから、明日は手元に入って」
こうした日本語は、ネイティブ同士なら感覚で理解できますが、実習生にとっては意味不明の“音の塊”です。
ここに、試験で評価された“話せる日本語”と、現場で求められる“わかる日本語”の決定的な断絶があるのです。
制度が想定していない“現場での言語ギャップ”
技能実習制度は、制度設計上「実習生が学びながら成長していく」ことを前提としています。
そのため、配属時点で完璧な日本語力を求めていません。
しかし一方で、現場は即戦力を求め、日々変わる工程や段取りに柔軟に対応できる人材を必要としています。
この制度の理想と現場の現実とのギャップが、「言葉が通じない問題」の本質なのです。
そしてもう一つ、制度が見落としているのが、“教育の継続性”です。
日本語教育は、来日前に一度行えば終了という扱いであり、配属後は企業任せ。
つまり、「教育の主導権が制度内に存在していない」という、根本的な構造不備があるのです。
“わかる日本語”を育てるとはどういうことか?
“わかる日本語”とは、単に言葉の意味を知っているというだけではなく、
・相手の言いたいことを汲み取れる
・状況の中で意味を推測できる
・似た言葉でもニュアンスを感じ取れる
といった、“実用的な理解力”を伴った言語能力です。
これを育てるには、以下のような取り組みが効果的です。
現場語を事前に習得させる
→ インパクト、養生、墨出し、番線、打設…など、専門用語リストを事前学習。
動画で場面別会話を習得
→ 現場の映像とともに、「どんな場面で」「どんな言葉が使われるか」を実践的に学ぶ。
指示語に反応する訓練
→ これ、それ、あれ、こっち、あっち、といった日本語特有の“指示語反応トレーニング”を行う。
“聞く力”を評価する教育制度に変える
→ 話す能力ばかりでなく、「聞き取れる力」に重点を置いた教育とテスト設計。
成功している企業は“わかる仕組み”を持っている
職人道場の導入企業の中には、“言語理解力の底上げ”に成功した事例が多数存在します。
ある企業では、「現場用語×イラスト×母国語訳」をまとめたオリジナル教材を配布し、毎週朝礼で復習。
また、指示語トレーニングを繰り返すことで、1年で“段取り変更”や“緊急対応”に柔軟に対応できる職人へと育て上げています。
この企業が大切にしているのは、「わかっていないことが悪いのではない。わかる仕組みがないことが問題」という考え方です。
この視点の転換が、実習生の自信、現場の安定、企業の教育効率を一気に引き上げているのです。
技能実習制度に本当に必要なのは“現場視点の言語設計”
今後、制度として取り組むべきは、「日本語能力試験の導入」よりも、
“現場で必要な言葉が何か”を明確にし、それを習得する仕組みを制度化することです。
・現場会話モデルを定義する
・用語リストを国家レベルで標準化する
・配属後の語学教育時間を義務化する
・“伝わる指導法”のガイドラインを整備する
こうした取り組みがなければ、現場は今後も“通じない日本語”に苦しみ続けることになります。
最後に:言葉は“教えるもの”ではなく、“育てるもの”
日本語を教えるというと、どうしても“教室”や“先生”のイメージが先行しがちですが、
“わかる日本語”は、現場での経験と支援の積み重ねによって、自然と育っていくものです。
だからこそ、企業に求められているのは、「言語教育の担い手になる」ということではなく、
“わかるようになる環境を、どう設計するか”という視点なのです。
制度が追いつかないのであれば、先に現場が変わればいい。
そして現場で実績が生まれれば、制度もまた、それに合わせて進化していく。
“わかる言葉”がある現場に、人は定着する。
それは、これからの技能実習制度に必要不可欠な、最も本質的な視点なのです。
⑩ “通じる言葉”が職人を変える——定着と育成の鍵は言語にある

外国人技能実習生が現場に配属されたとき、最初にぶつかる壁——それは「作業」ではなく、「言葉」です。
そしてこの“言葉の壁”こそが、育成の成否、そして企業との信頼関係、さらには離職率の高低を決定づける最も重要な要因であるということは、現場経験を持つ指導者なら誰もが痛感していることでしょう。
「通じる言葉」がある現場では、人が定着します。
「伝わらない言葉」に囲まれた現場では、人は不安を抱え、やがて去っていきます。
つまり、言葉とは“作業を回す道具”ではなく、“人を育て、繋ぎ、定着させる力”そのものなのです。
「通じる瞬間」が職人を変える
職人道場では、配属初期の外国人職人に対して「一つの言葉が通じる体験を作る」ことを重視しています。
たとえば、ある実習生は「インパクト取ってきて」という日本語が初めて理解できたとき、まるで試験に合格したような表情で走り出し、工具を持ってきました。
指導者は思わず「ありがとう!」と返し、そのとき実習生は“言葉が通じたこと”の達成感で笑顔を浮かべたそうです。
このたった一回の成功体験が、実習生のモチベーションを一変させたのです。
「もっと分かるようになりたい」
「もっと役に立ちたい」
そう思えるようになると、言葉に対する関心が高まり、自発的に学ぶ姿勢が育ちます。
そして何より、「ここにいていいんだ」「自分はこの職場で受け入れられている」という安心感が生まれるのです。
通じない現場では“何も始まらない”
一方で、言葉が通じないまま放置された職場では、どうなるでしょうか。
・作業指示が理解できない
・注意された内容が分からない
・冗談や雑談に参加できない
・報連相が成り立たない
・仕事への達成感もない
こうした状況が続くと、実習生は次第に無表情になり、指示を待つだけの“作業マシン”になってしまいます。
そして、心の中では「何のために働いているのか分からない」「いつまでこんな毎日が続くのか」と疑問を抱くようになります。
やがてその疑問は、「ここでは成長できない」という結論に変わり、離職、失踪、転職といった負の連鎖を招くのです。
「定着」とは、言葉による信頼の積み重ね
外国人職人の定着率を高めるために、企業ができる最大の工夫——
それは、“言葉で信頼関係を築くこと”に全力を注ぐことです。
・仕事の目的を伝える
・できたことを褒める
・困ったときは声をかける
・未来の期待を言葉にする
・日々の雑談にも言葉を使う
こうした言葉の積み重ねが、「信頼」を生み、「安心」を育み、やがて「定着」へとつながっていきます。
“わかってもらえた”という感覚こそが、人をその場に留まらせる最大の理由なのです。
言葉が通じれば、人は“育つ”ことができる
育成とは、教えることではありません。
相手が理解し、自分の言葉で返せるようになることです。
・「これはどうする?」と聞かれ、「こうします」と答えられる
・「昨日の作業はどうだった?」に対して、「難しかったけどできました」と返せる
・ミスをした理由を説明し、次の対策を自分で考えられる
こうした“言葉のキャッチボール”ができるようになることで、外国人職人は初めて“作業者”から“職人”へと成長します。
それは、スキルや経験を積むこと以上に、自ら考え、自ら伝える力を育てることによって実現するのです。
最後に:言葉は、未来への投資
外国人職人との共生は、単なる人手不足解消の手段ではありません。
それは、企業の多様性を高め、現場の文化を進化させ、日本の建設業全体を未来につなげるための重要な選択肢です。
そのために必要なのは、制度の整備や通訳の配置だけではありません。
現場で、一人ひとりが“伝えようとする努力”と、“わかろうとする姿勢”を持つこと。
そして、言葉を“作業指示のための道具”から、“育成と信頼を築く手段”へと再定義することです。
通じる言葉は、職人の心を開き、
通じる言葉は、職人を育て、
通じる言葉は、職人を定着させる。
そう信じて、今日もまた一つ、言葉を交わす。
それが、未来の職人と企業をつなぐ、最も確かな“架け橋”になるのです。
【まとめ】“通じない言葉”が未来を閉ざす、“通じる言葉”が未来を開く

日本語研修ゼロの状態で送り出される外国人技能実習生たちは、現場に立ったその瞬間から孤立と不安の中に放り込まれます。
「こんにちは」が通じない。「危ない」が理解されない。「わかりました」が“分かったフリ”かもしれない——
これらの現実は、企業や現場、そして実習生本人すべてにとって、大きなリスクであり障害です。
本ブログでは、制度の構造的な課題、送り出し機関の教育の限界、通訳依存の危うさ、教える側の疲弊、そして何よりも「通じないことで育たない現場」の実態を深掘りしました。
その中で浮かび上がったのは、「言葉」という存在の大きさ。
伝わる言葉があれば人は育ち、信頼が生まれ、未来へ進んでいける。
逆に、それがなければ、技能も心も現場に根を張ることはできません。
しかし、希望もあります。
すでに現場の中には、「やさしい日本語」「視覚教材」「朝礼トレーニング」「現場内語学研修」など、創意工夫によって“通じる仕組み”を作り、成果を上げている企業が増えています。
大切なのは、“完璧に教える”ことではなく、“通じるように育てる”という視点です。
制度任せにせず、教育を現場で設計し、定着と成長を見据える——
それこそが、これからの建設業界に求められる“言葉のマネジメント”です。
そしてその第一歩は、「今、目の前の職人に、伝わっているか?」という問いを持ち続けることなのです。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。