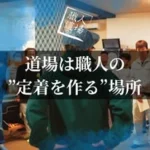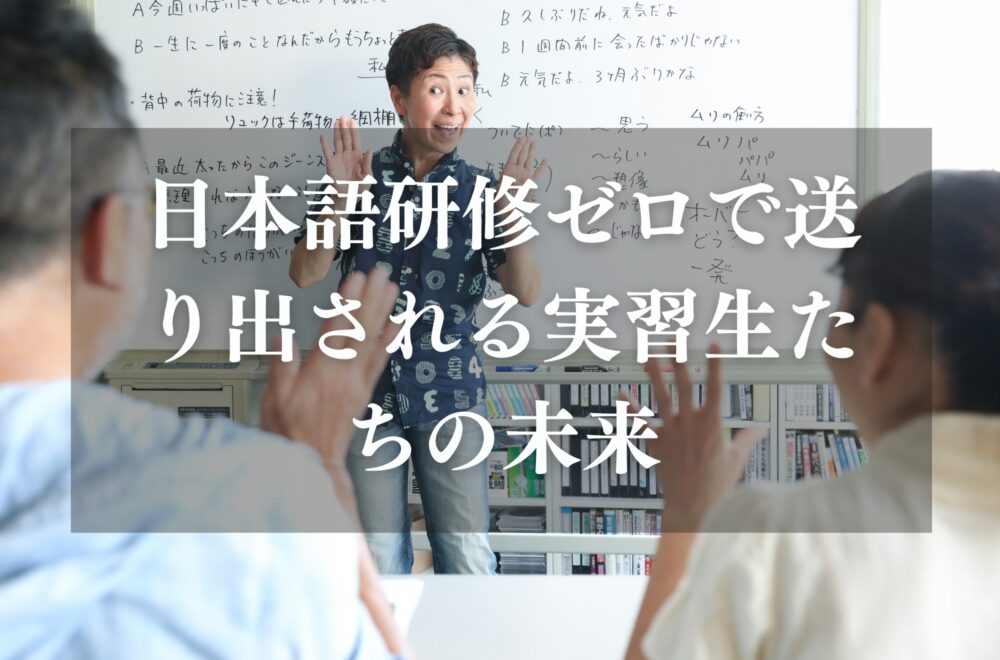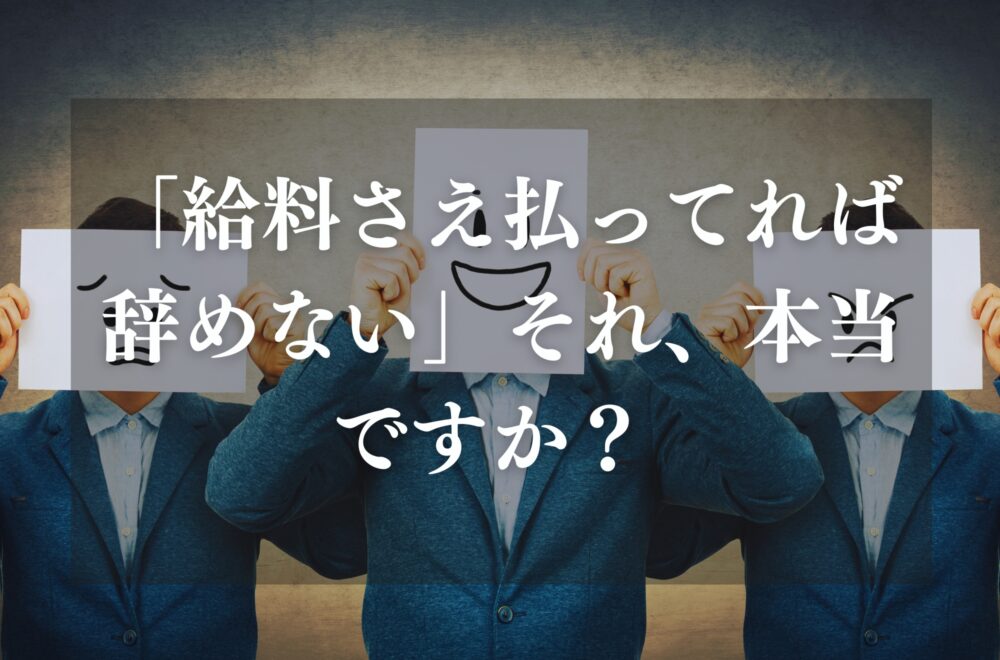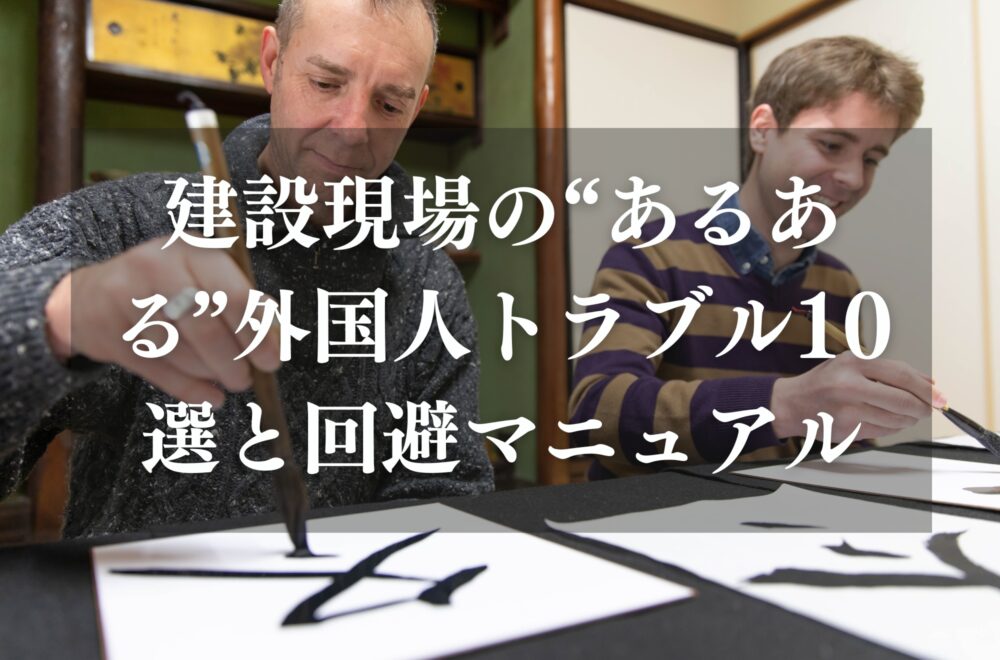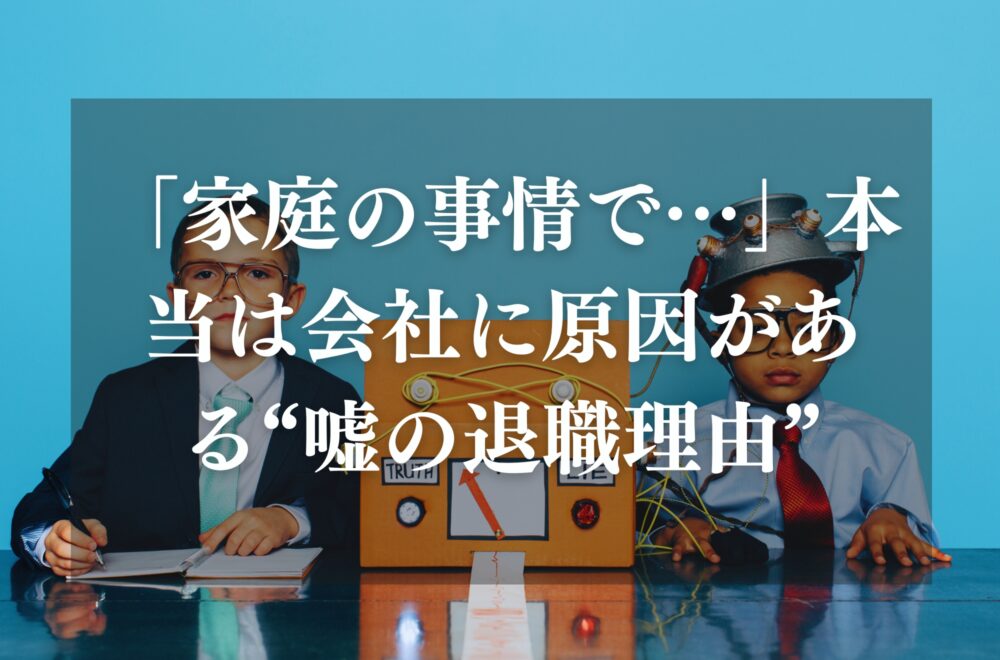外国人職人とともに未来を創る~「労働力」ではなく「仲間」として迎えるために~
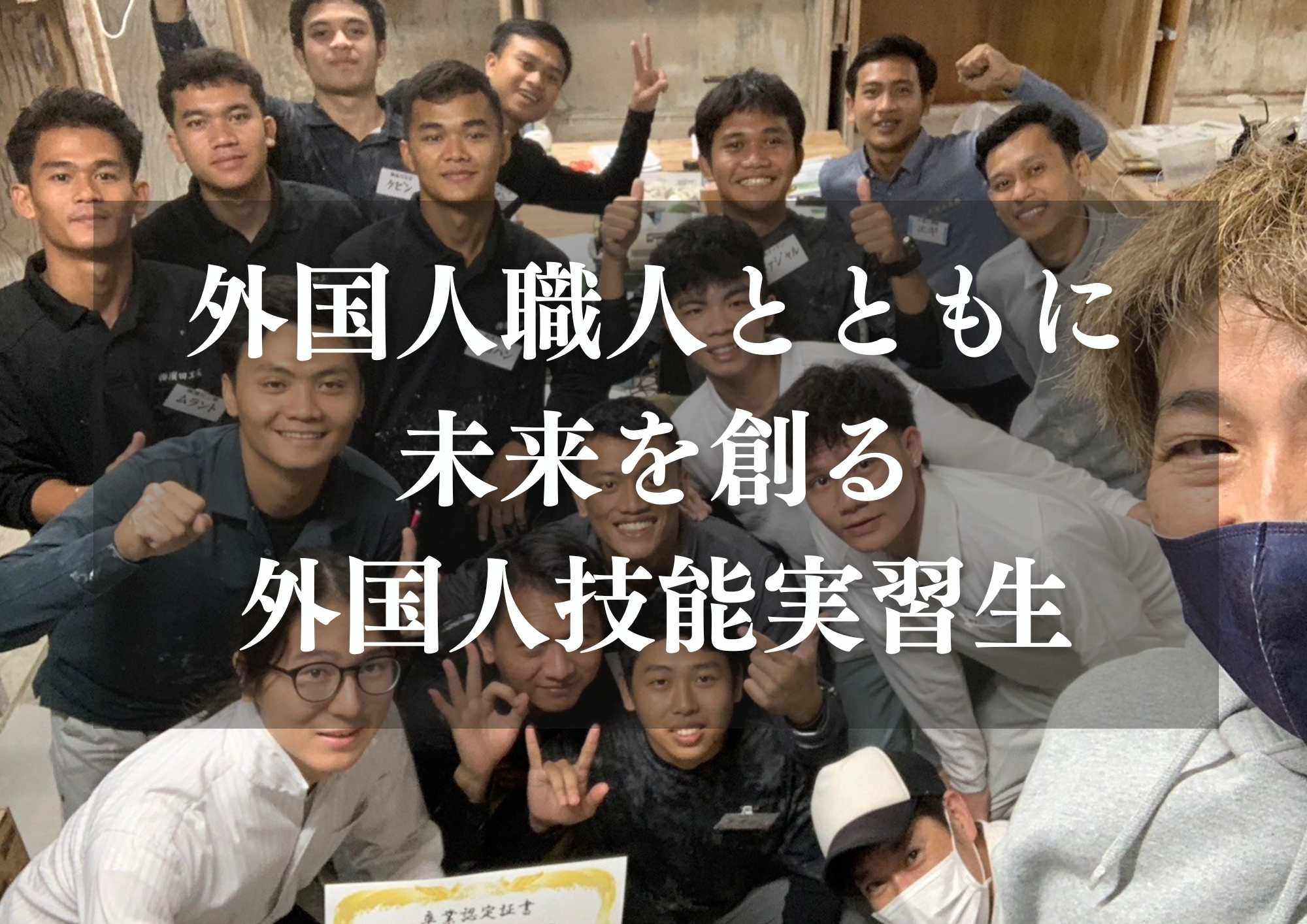
>目次
1. なぜ外国人職人は“労働力”として見られてしまうのか?

日本の建設業界において、外国人職人の存在はすでに珍しいものではなくなっている。特定技能制度や技能実習制度を活用し、アジア諸国を中心とした多くの外国人が建設現場で働いている。彼らは、過酷な環境の中でも努力を重ね、現場の一員として懸命に汗を流している。
しかし、現場のリアルな声を聞くと、「外国人職人はすぐに辞める」「結局、戦力にならない」「言葉が通じなくて指示が伝わらない」など、否定的な意見が少なくない。なぜこうした声が後を絶たないのか? それは、日本の建設業界に根付く「外国人職人=単なる労働力」という固定観念が原因ではないだろうか。
外国人職人は、本当に「労働力」なのか?
そもそも、日本の建設業界が外国人職人を受け入れる背景には、「慢性的な人手不足」がある。少子高齢化が進む日本では、建設業に従事する日本人の数が減少し続けており、55歳以上の職人の割合が全体の35%を超えている。このままでは、10年後には現場を支える職人が激減し、インフラ整備や都市開発が立ち行かなくなる可能性すらある。
こうした状況の中、多くの企業が「とにかく人手がほしい」という理由で外国人職人を採用する。しかし、この時に重要なのは、単に数を増やせば問題が解決するわけではないということだ。人手不足は単なる「頭数の問題」ではなく、職人の育成と定着の問題でもある。
外国人職人を「足りない労働力を補うための一時的な存在」として捉えてしまうと、結局、彼らは定着せず、戦力にもならず、企業側の負担ばかりが増えてしまう。つまり、最初から「労働力」として見てしまうこと自体が、外国人職人が活躍できない要因を生んでいるのだ。
日本の職人文化と外国人職人のギャップ
日本の建設業界には、長年培われてきた**「職人気質」が根付いている。特に、「見て学べ」「技術は盗め」**といった文化が強く、職人は長い年月をかけて仕事を覚え、ようやく一人前と認められる。
しかし、このような文化は、外国人職人にとっては大きな障壁となる。多くの外国人は、自国で体系的な教育を受け、日本に来てからも明確な指導やトレーニングを期待している。しかし、日本の現場では、
✅ 言葉での説明が少ない
✅ 感覚的な指導が多い
✅ 「見て覚える」ことが前提になっている
といった状況があり、外国人職人がスムーズに仕事を覚えるのが難しい。
また、日本では当たり前とされている「上下関係の厳しさ」や「時間厳守の文化」も、外国人にとっては適応しづらいポイントだ。例えば、日本の現場では5分前行動が基本だが、外国では「時間通りに到着すれば問題ない」と考える文化もある。こうしたズレが誤解や摩擦を生み、「使えない」「仕事の覚えが遅い」といった評価に繋がってしまう。
「労働力」ではなく「仲間」として迎える視点
では、どうすれば外国人職人が現場で真の戦力になり、長く活躍できるのか? その答えは、「労働力」ではなく、「仲間」として迎え入れる視点を持つことだ。
外国人職人は、ただ単に「安い労働力」ではない。彼らもまた、日本で技術を学び、自分のキャリアを築こうと真剣に考えている。日本の現場で働くことを誇りに思い、「良い仕事をしたい」「日本の技術を身につけたい」と願う人も多い。
そのためには、企業側が次のような視点を持つことが大切だ。
✅ 「仕事を教える」のではなく、「共に学ぶ」意識を持つ
外国人職人に対して、一方的に「教え込む」のではなく、日本人職人も彼らから学ぶ姿勢を持つことで、相互の理解が深まる。例えば、外国人職人の母国では「合理的な作業手順」が確立されていることもあり、日本の現場でも役立つアイデアを持っている可能性がある。
✅ 文化の違いを理解し、適応をサポートする
外国人職人が日本の職場に馴染むには時間がかかる。例えば、日本の「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」の概念は、外国人にとってはなじみがないことが多い。そのため、「なぜこのルールがあるのか」を説明することが重要になる。
✅ 技術だけでなく、「働き方の違い」を受け入れる
例えば、日本人は「何か問題が起きた時にはすぐに報告する」ことが当たり前だが、外国では「自分で解決できるなら報告しない」という文化もある。この違いを理解し、適切なルールを共有することが、現場のスムーズな運営につながる。
外国人職人を活かせる企業、活かせない企業
外国人職人を「戦力」として活用できる企業と、できない企業の違いは明確だ。
❌ 失敗する企業の特徴
- 「とにかく人手がほしい」という理由だけで雇う
- 言葉の壁や文化の違いを考慮せず、教育の仕組みを整えない
- 仕事を押し付けるだけで、フォローアップをしない
⭕ 成功する企業の特徴
- 「外国人職人を育てる」ではなく、「共に成長する」という考えを持っている
- 明確な教育プログラムを用意し、段階的にスキルアップを支援する
- 文化の違いを受け入れ、日本人職人との相互理解を深める努力をする
こうした取り組みが、外国人職人の定着率を高め、結果的に企業の生産性向上にもつながっていく。
2. 日本の建設業界に欠けている「共育」の視点
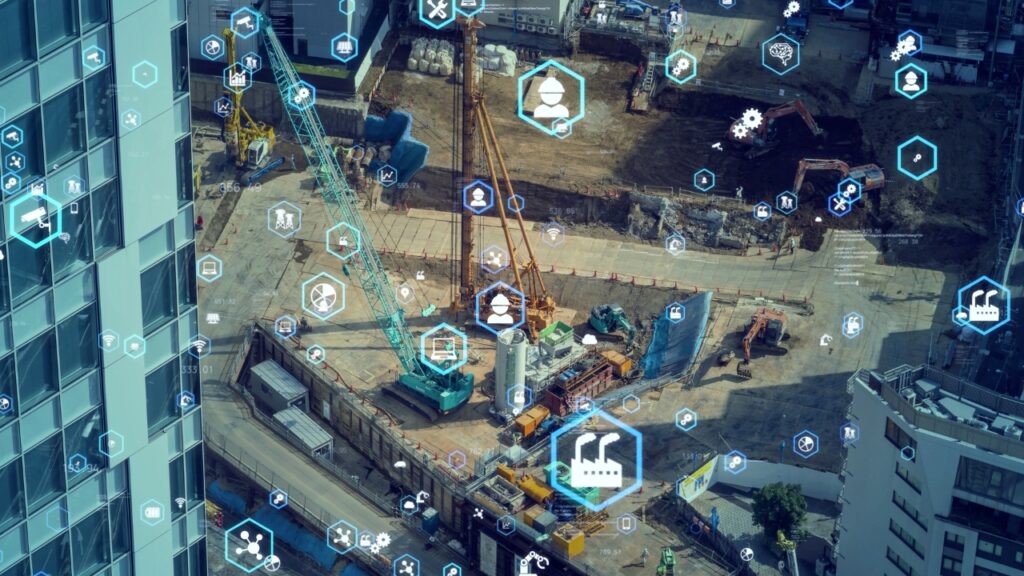
日本の建設業界には、長年にわたり培われてきた「職人文化」がある。その特徴的な要素の一つが、**「見て学べ」「技術は盗め」**という教育スタイルだ。これは、先輩職人が手取り足取り指導するのではなく、現場の空気を読み、仕事の流れを察し、自ら技術を習得していくことを前提とした育成方法である。
このスタイルは、日本の職人社会では効果を発揮してきた。なぜなら、日本の若手職人は、現場で先輩の動きを見ながら、「これは自分で学ぶべきものだ」という意識を持ち、長年かけて技術を磨く文化に慣れているからだ。しかし、外国人職人にとって、この方式は大きな壁となる。
彼らの多くは、日本とは異なる教育環境で育っており、明確な指示と体系的な学習を通じて技術を習得するスタイルに慣れている。日本の職人が当たり前のように行っている「察して動く」「暗黙のルールを理解する」といった行動は、彼らにとっては未知の領域だ。そのため、企業側が適切な教育方法を提供しなければ、外国人職人は学びたくても学べない状況に陥ってしまう。
こうした背景を踏まえ、日本の建設業界に求められるのは、「教える」「育てる」という従来の発想を超えた、「共に学ぶ」=共育の視点である。
「共育」の視点を持たないと何が起こるのか?
共育の視点を持たず、従来の「見て学べ」方式を外国人職人に押し付けた場合、現場ではどのような問題が発生するのか?
① 理解不足によるミスが増える
外国人職人は、日本語の微妙なニュアンスや現場の空気を読むことが苦手な場合が多い。そのため、「見て覚えろ」と言われても、どこに注目すればよいのかがわからず、結果的に誤った方法で作業を進めてしまうことがある。
例えば、ある企業では、外国人職人がコンクリートを均す作業を行った際、日本人職人が求める仕上がりの基準が伝わらず、全く違う仕上がりになってしまったという事例があった。これは、「仕上がりの感覚」を言葉ではなく経験で学ばせる日本の職人文化に原因がある。しかし、外国人職人にとっては「どうすれば正しいのか」を明確に示してもらわなければ、正解がわからないのだ。
② コミュニケーション不足で現場の雰囲気が悪くなる
「技術が身につかない」ことが原因で、日本人職人との関係が悪化することも少なくない。
例えば、日本人職人の立場からすれば、「何度言ってもできない」「一回教えたら理解するのが当たり前」と考えるかもしれない。しかし、外国人職人からすれば、「言葉の意味が分からない」「説明が曖昧で何をすればいいのか分からない」という状況であり、双方の意識に大きなギャップが生じる。
このような状況が続くと、日本人職人の側は「使えない外国人職人だ」と感じるようになり、外国人職人の側は「理不尽に怒られる職場だ」と思うようになり、結果的に辞めてしまう。企業がせっかく外国人を採用しても、教育の仕組みが整っていないと、短期間で離職するという悪循環に陥るのだ。
外国人職人を「育てる」のではなく「一緒に成長する」
では、どうすればこの問題を解決できるのか? そのカギは、外国人職人を「育てる」という一方的な視点ではなく、「共に成長する」という考え方を持つことにある。
以下のような取り組みが、外国人職人を戦力として活かす上で重要なポイントとなる。
① 外国人が理解しやすい指導方法の導入
日本の建設現場では、「口頭での指示」が多い。しかし、外国人職人にとっては、言葉だけでは理解が難しいことがある。そこで、以下のような工夫を取り入れると効果的だ。
✅ 動画マニュアルを活用する
スマートフォンやタブレットで作業手順を動画化し、何度でも見返せるようにする。これにより、言葉の壁を超えて学ぶことができる。
✅ 翻訳アプリを活用する
作業の説明をする際に、Google翻訳や翻訳デバイスを活用し、より分かりやすい形で伝える。
✅ チェックリストの作成
作業工程を簡単な日本語と母国語で書いたチェックリストにまとめ、作業完了ごとに確認できるようにする。
② 言語に頼らない視覚的指示の活用
言葉の壁を乗り越えるために、視覚的な指示を増やすことも有効だ。
✅ カラーコードの使用
作業に使う道具やエリアを色分けし、視覚的に作業の流れを把握できるようにする。
✅ アイコン化
文字だけではなく、図やアイコンを使って手順を示す。例えば、「手袋着用」「ヘルメット着用」といった指示を、アイコンで示せば直感的に理解しやすい。
③ メンター制度の導入
外国人職人が現場に定着しやすくなるように、日本人職人とペアを組ませ、互いに学び合う環境を作る。
✅ ベテラン職人と外国人職人をペアにする
指導役となるベテラン職人が1対1でサポートしながら作業を進めることで、安心して学べる環境を提供する。
✅ 外国人職人同士のネットワークを作る
同じ国の出身者同士でグループを作り、お互いに助け合える環境を整える。
3. 現場で起きている「文化摩擦」問題をどう乗り越えるか?

日本の建設現場では、外国人職人の受け入れが進んでいるが、それに伴い「文化摩擦」が発生するケースが増えている。言葉の壁だけでなく、価値観や習慣の違いが原因となり、現場のコミュニケーションがスムーズにいかないという問題が生じているのだ。
例えば、「なぜこんな簡単なことが伝わらないのか?」「どうしてルールを守らないのか?」といった不満が、日本人職人側から聞こえることがある。一方で、外国人職人の側からは、「なぜそんなに厳しく怒られるのか?」「理不尽なことを押し付けられている」といった声が上がることも少なくない。
こうした文化摩擦が放置されると、現場の雰囲気が悪化し、外国人職人の離職率が上がるだけでなく、日本人職人のストレスも増大することになる。では、どのようにしてこの問題を解決できるのだろうか?
3-1. 指示に対する考え方の違い:なぜ「生意気」と思われるのか?
日本の職場では、**「上司の指示にはすぐ従う」**という文化が根付いている。特に建設業のような上下関係の厳しい職場では、「指示されたことは黙ってやる」のが基本だと考えられている。
しかし、東南アジアや南米の国々では、指示を受けた際に「なぜその方法でやるのか?」と質問をする文化がある。これは「反抗」や「疑い」ではなく、「理解を深めるための行動」であり、彼らの教育や仕事のスタイルに基づいたものである。
この違いを知らない日本人職人が、「指示に従わずに質問ばかりするのは生意気だ」と感じ、衝突が生じることが多い。
✅ 解決策:「なぜ?」を歓迎する文化をつくる
外国人職人が「なぜこの作業が必要なのか?」と質問した場合、それを否定するのではなく、**「理由を理解すれば作業の質が向上する」**と考えるべきだ。むしろ、質問することで作業の意義を理解しやすくなり、ミスを減らすことができる。
✅ 例:説明の工夫
- 「なぜこうするのか?」と聞かれたら、「この方法が安全だから」「この手順でやると仕上がりが良くなる」などの背景を簡単に説明する。
- 日本人職人の側も、「こういう文化なんだ」と理解し、質問に対して適切に対応する姿勢を持つ。
3-2. 時間の概念の違い:「5分前行動」は本当に必要か?
日本では「5分前行動」が常識とされている。会議や現場作業でも、「集合時間の5分前には準備を終え、すぐに作業に取りかかれる状態にしておく」ことが求められる。これは日本の社会全体に浸透している価値観であり、「時間を守る=信頼できる人間」という考え方があるからだ。
しかし、外国人職人にとっては、「時間通りに到着すれば問題ない」と考えることが一般的だ。例えば、欧米や東南アジアでは「指定された時間に来るのが当たり前」であり、**「早く来る必要はない」**と考える人が多い。
この認識の違いが原因で、「時間を守らない外国人職人は信用できない」と日本人職人が感じてしまうことがある。
✅ 解決策:「時間を守ることの意義」を説明する
外国人職人に対して、「なぜ5分前行動が求められるのか?」を明確に伝えることが重要だ。
例えば、
- 「建設現場では、準備が遅れると全体の作業が遅れる」
- 「時間に余裕を持つことで、安全確認ができる」
といった合理的な理由を説明することで、納得感を持たせることができる。
また、企業によっては、「5分前行動は求めるが、そこまで厳格にしない」という柔軟な対応をすることも一つの方法である。大切なのは、「文化の違いを理解しつつ、仕事に支障が出ない範囲でルールを統一する」ことだ。
3-3. コミュニケーションの壁:「YES」と言われても安心できない?
日本人の職人は、「作業の指示を出したときに、相手が『はい!』と言えば、理解している」と考えることが多い。しかし、外国人職人の中には、「YES」と言ったものの、実際には内容を完全に理解していないことがある。
これは、文化の違いによるものである。特に東南アジアでは、「上司や先輩に対して『NO』と言うのは失礼」と考えられている。そのため、たとえ内容が理解できていなくても、とりあえず「YES」と答えてしまうことがある。
この結果、「言ったことをやっていない」「何度説明しても理解していない」といった誤解が生じる。
✅ 解決策:確認の仕組みを作る
- 「YES」と言った後に、**「じゃあ、今の説明を簡単に言ってみて」**と確認する。
- 言葉で説明するのが難しい場合は、**「ジェスチャーや図を使って確認する」**方法を取り入れる。
- 簡単なチェックリストを作成し、本人が理解したかどうかを自己確認できるようにする。
3-4. 外国人職人の文化を尊重し、柔軟に対応する
外国人職人を受け入れる企業の中には、「日本のやり方に完全に合わせてもらうべきだ」と考えるところもある。しかし、これは一方的な考え方であり、外国人職人が働きづらい環境を作る原因となる。
✅ 「文化の違い」を障害ではなく、強みとして捉える
例えば、東南アジア出身の職人は、チームワークを大切にする文化を持っている。彼らは「助け合いながら仕事を進める」ことに慣れており、日本人職人が個人作業をする場面でも、積極的に声をかけ、協力しようとすることがある。
このような行動を「おせっかい」と捉えるのではなく、「協力的な姿勢」として活かすことができれば、より良い現場環境を築くことができる。
4. なぜ外国人職人はすぐ辞めるのか?

日本の建設業界において、外国人職人の定着率の低さは企業の大きな課題となっている。多くの企業が外国人職人を採用し、現場での戦力として期待しているものの、「すぐに辞めてしまう」「長く続かない」といった悩みを抱えているのが現状だ。
では、なぜ外国人職人は短期間で辞めてしまうのか?その理由を深く掘り下げ、どうすれば彼らが長く働き続けられるのかを考えていく。
4-1. 外国人職人が辞める主な要因とは?
① 言葉の壁による孤立
外国人職人の多くが最も苦しむのが言葉の壁である。
日本語が十分に話せない、理解できない状態では、現場での指示がうまく伝わらず、ミスをして怒られることが増える。
特に、建設業の現場では「指示が一瞬で伝わること」が求められるため、日本語が苦手な外国人職人にとっては、大きなプレッシャーになる。
また、同僚の日本人職人とも十分なコミュニケーションが取れず、現場の雰囲気に馴染めないことも孤立を招く。結果として、**「自分はこの職場に必要とされていない」「居場所がない」**と感じ、辞めてしまうのだ。
✅ 解決策
- 日本語学習のサポートを強化
- 仕事でよく使う日本語をリスト化し、簡単な単語から覚えられるようにする。
- 仕事の合間に短時間の日本語レッスンを行う。
- スマートフォンの翻訳アプリを活用し、最低限のコミュニケーションをとれるようにする。
- 現場で使う用語をアイコンや画像で説明し、視覚的に理解できる仕組みを作る。
- 外国人職人同士の交流の場を設ける(例:月に1回、簡単なミーティングを開催し、悩みを共有する場を作る)。
② 給与が低く、将来性が見えない
外国人職人の多くは、母国で家族を養うために日本で働いている。そのため、給与は非常に重要な要素である。しかし、彼らの多くが「日本での労働は思ったよりも厳しい割に、給与が低い」と感じている。
特に、技能実習生として来日している外国人職人は、最低賃金ギリギリの給与で働いていることが多い。また、日本で長く働き続けても、昇給の機会が少なく、「このまま頑張っても報われないのではないか?」と将来への不安を感じてしまう。
✅ 解決策
- 成果に応じた評価制度を導入する
- 「仕事のスピードが向上したら〇円アップ」など、目に見える形で昇給のチャンスを提供する。
- 外国人職人にも「昇進の可能性」を示し、長期的に働くモチベーションを高める。
- **「この仕事を続ければ、○年後には○○円の給与がもらえる」**と、キャリアパスを明確に示す。
- 住宅手当・生活補助を検討する
- 給与を大幅に上げるのが難しい場合は、住宅手当を支給することで、実質的な収入を増やすことができる。
③ 過酷な労働環境
日本の建設現場は、長時間労働・厳しい作業環境が当たり前とされている。しかし、外国人職人の中には「こんなに厳しいとは思わなかった」とギャップを感じる人も多い。
特に、日本の現場では「休憩が少ない」「夏の暑さの中でも長時間働かされる」など、母国とは異なる労働環境に適応できず、心身ともに疲弊してしまうケースがある。
✅ 解決策
- 労働環境の見直し
- 炎天下での作業時間を短縮する工夫をする。
- 外国人職人専用の休憩スペースを設ける(文化的に慣れ親しんだ環境を作ることで、ストレスを軽減)。
- 仕事の合間に短い休憩を設け、リフレッシュできる時間を確保する。
- 「日本の労働文化」と「外国人職人の労働習慣」をすり合わせる
- 日本の建設現場では「限界まで頑張るのが当たり前」という文化があるが、外国人職人には無理に押し付けず、効率的な作業を優先する柔軟な考え方を取り入れる。
④ 日本人職人との関係が悪化
外国人職人が辞める大きな理由の一つが、日本人職人との関係がうまくいかないことだ。
建設業界には、「昔ながらの職人気質」が根強く残っており、厳しい指導を受けることも珍しくない。日本人職人の側からすると、「仕事を覚えるためには厳しくするのが当たり前」という感覚があるが、外国人職人にとっては、**「怒鳴られるのは理不尽」「なぜ怒られているのかわからない」**と感じることがある。
また、日本の職人社会では「先輩のやり方に従うのが常識」とされるが、外国人職人は**「もっと効率的なやり方があるのでは?」**と考えることがあり、それが「生意気だ」と誤解されることもある。
✅ 解決策
- 「外国人職人の教育」だけでなく、「日本人職人の意識改革」も必要
- 「外国人職人に対する適切な指導方法」を日本人職人に学んでもらう機会を作る(例えば、研修を行い、言葉の壁や文化の違いを理解してもらう)。
- 「日本のやり方を押し付ける」のではなく、外国人職人の視点も取り入れ、「新しいやり方を受け入れる姿勢」を持つ。
- メンター制度を導入
- 外国人職人と日本人職人のペアを作り、お互いに学び合う環境を整える。
5. 外国人職人と共に未来を創るために

日本の建設業界は今、大きな変革期を迎えている。高齢化が進み、日本人職人の数は年々減少している一方で、インフラ整備や都市開発の需要は依然として高く、人手不足が深刻な課題となっている。
この状況を打破するため、多くの企業が外国人職人を採用し始めた。しかし、単に「労働力の補填」として外国人職人を受け入れるだけでは、問題の根本的な解決にはならない。むしろ、適切な受け入れ体制が整っていなければ、すぐに辞めてしまう、現場で摩擦が生じる、といった新たな課題を生み出すだけになってしまう。
では、どのようにすれば外国人職人と共に未来を築いていけるのか? それを考えるには、まず「外国人職人とはどのような存在か?」を根本から見直す必要がある。
5-1. 外国人職人は「労働力」ではなく、「共に成長する仲間」
これまで、日本の建設業界では外国人職人を**「労働力の補充」**と見なす傾向が強かった。特に、技能実習制度を利用した外国人労働者は、「一定期間働いたら帰国する」という前提で雇われるため、長期的な視点での育成やキャリア形成が考慮されることは少なかった。
しかし、本当に持続可能な建設業界を築くためには、外国人職人を「一時的な労働者」ではなく、「共に成長し、未来を創るパートナー」として受け入れる視点が不可欠だ。
✅ 外国人職人の成長が、企業の成長につながる
彼らがスキルを身につけ、安心して働ける環境が整えば、企業にとっても大きな戦力となる。短期間で辞められるよりも、長く働いてくれる職人を育てる方が、結果的に企業の生産性向上や技術の継承につながる。
✅ 「共に成長する」という意識が、職場の雰囲気を変える
外国人職人をただの作業員として扱うのではなく、「一緒に学び、成長していこう」という意識を持つことで、日本人職人との関係性も改善される。結果として、職場の雰囲気がよくなり、定着率も向上するのだ。
5-2. 文化の違いを学び、相互理解を深める
外国人職人を受け入れる際に最も重要なのは、文化の違いを理解し、相互に歩み寄ることである。
① 価値観や働き方の違いを理解する
日本では、「上司の指示には即座に従う」「時間厳守は絶対」といった文化が根付いている。しかし、外国人職人の多くは、指示に対して「なぜそうするのか?」と質問する文化を持っている。
これは決して反抗的な態度ではなく、作業の意味を理解し、より良い方法を模索するための行動なのだ。しかし、日本の職人社会では、「指示通りにやるのが当たり前」という考えが強いため、「生意気だ」と誤解されてしまうことがある。
✅ 解決策:文化の違いを学ぶ機会を設ける
- 日本人職人向けに、「外国人職人の文化・価値観」を学ぶ研修を実施する。
- 外国人職人にも、日本の仕事文化やマナーについて教育を行い、スムーズに馴染めるようにする。
- お互いの文化を尊重する姿勢を持つことが、円滑なコミュニケーションの第一歩となる。
② 日本語の壁を乗り越える工夫をする
外国人職人の多くは、日本語に不慣れなため、指示がうまく伝わらないことがストレスの原因になる。
✅ 解決策:言葉の壁を克服するための工夫
- 視覚的な指示を増やす(作業工程をイラストや写真で説明する)
- 簡単な日本語リストを用意し、仕事でよく使う言葉を学べるようにする
- スマートフォンの翻訳アプリを活用し、リアルタイムで意思疎通を図る
こうした取り組みを通じて、言葉の壁を少しずつ低くしていくことが重要だ。
5-3. 外国人職人が「長く活躍できる環境」を整える
外国人職人を受け入れるだけではなく、「どうすれば長く働き続けてもらえるか?」を考えることが、企業にとっての大きな課題となる。
① 生活面でのサポートを充実させる
外国人職人が定着しない原因の一つに、生活環境の問題がある。
日本での生活に慣れることができなければ、いくら仕事が楽しくても長く続けるのは難しい。
✅ 解決策
- 住居の手配をサポートし、安心して生活できる環境を整える。
- 銀行口座の開設・健康保険の加入など、生活に必要な手続きを手伝う。
- メンタルケアの場を提供し、孤立を防ぐ。
② キャリアパスを示し、将来のビジョンを持たせる
外国人職人の多くは、「この仕事を続けたらどうなるのか?」という不安を抱えている。
「今の給与で一生働くのか?」「昇給の機会はあるのか?」といった将来の展望が見えなければ、モチベーションを維持するのは難しい。
✅ 解決策
- 「〇年後には〇〇のポジションに昇格できる」「技術が身につけば給与が上がる」といったキャリアパスを明確に示す。
- 資格取得支援制度を導入し、スキルアップの機会を提供する。
- 「この仕事を続ければ、自分の生活が向上する」という確信を持たせる。
まとめ~外国人職人と共に未来を築くために
~「労働力」ではなく「仲間」として迎える重要性~

1. なぜ外国人職人は“労働力”として見られてしまうのか?
日本の建設業界では、外国人職人が「人手不足を補うための労働力」として見られがちだ。しかし、彼らを単なる作業員として扱うだけでは、現場での定着は難しく、せっかくの人材が活かされないまま辞めてしまうケースが後を絶たない。外国人職人を真の戦力にするためには、「一緒に働く仲間」として迎え入れる視点が不可欠だ。
2. 日本の建設業界に欠けている「共育」の視点
日本の職人文化は、「見て学べ」「技術は盗め」というスタイルが一般的だ。しかし、この教育法は外国人職人には馴染みにくく、適応が難しい。必要なのは、「一方的に教える」だけでなく、「共に学び、成長する」=共育の考え方だ。日本人職人と外国人職人が互いに学び合う環境を作ることで、現場の活性化にもつながる。
3. 現場で起きている「文化摩擦」問題をどう乗り越えるか?
言葉の壁に加えて、仕事の進め方や価値観の違いが摩擦を生む原因となることが多い。例えば、日本では「上司の指示には即座に従う」のが基本だが、外国では「指示の理由を確認するのが当たり前」という文化もある。この違いが、日本人職人からすると「生意気だ」と捉えられることもある。こうした文化の違いを理解し、歩み寄る姿勢を持つことが、円滑な現場づくりには欠かせない。
4. なぜ外国人職人はすぐ辞めるのか?
外国人職人の離職率が高い理由には、言葉の壁による孤立、給与の低さ、過酷な労働環境、日本人職人との関係悪化がある。特に、日本の職人社会の厳しい上下関係に馴染めず、精神的に追い詰められてしまうケースが多い。こうした課題を解決するためには、外国人職人が安心して働ける環境を整え、努力が正当に評価される仕組みを作ることが重要だ。
5. 外国人職人と共に未来を創るために
これからの建設業界では、外国人職人の存在が不可欠になる。しかし、受け入れの方法を間違えれば、単なる「短期的な労働力の確保」に終わってしまう。本当に求められるのは、「外国人職人と共に成長し、未来を築く」という意識だ。
✅ 外国人職人を「労働力」ではなく、「仲間」として迎える
✅ 文化の違いを学び、相互理解を深める
✅ 働きやすい環境を整え、長期的に活躍できる仕組みを作る
これらの視点を持つ企業こそが、建設業界の未来を担い、長く成長を続けることができるだろう。外国人職人と共に働くことは、日本の建設業界にとっての新たな可能性を切り拓く第一歩なのだ。
この記事の作成者 職人道場運営責任者 本井 武

「職人不足の時代に、技術を未来へ繋ぐために」
建設業界は今、深刻な人材不足に直面しています。このままでは、長年受け継がれてきた職人の技術や、業界を支えてきた技術会社が消えてしまうかもしれません。私たちは、職人不足の課題に正面から向き合い、企業の未来を守るために職人道場を広める活動を続けています。単なる研修ではなく、職人の魂を継承し、企業の経営を支えるための取り組みです。
日々の営業活動の中で、社長の皆様が抱える不安や悩みに寄り添い、最適な提案をお届けしたい。そして、ただ職人を育てるのではなく、会社の未来を創る力を共に育みたい。日本の建設業を支えてきた技術を、次の世代へ。共にこの業界の未来を守り、職人不足を乗り越えていきませんか?私たちは、建設業の未来のために、共に戦い続けます。
>職人道場紹介MOVIE